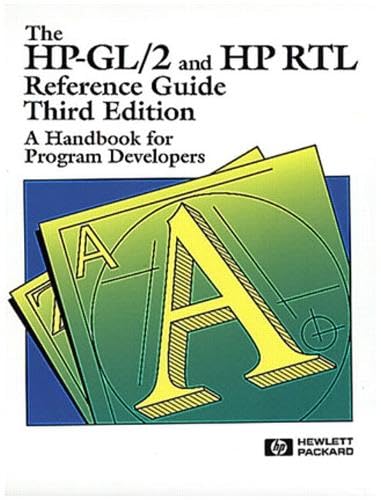1 0 0 0 OA 宗達草花粉本
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1800
1 0 0 0 現代に生きる宗教者の証言
- 著者
- 日本宗教者平和協議会編
- 出版者
- 新日本出版社
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 日本中が私の戦場 : 平和を求める宗教者の手記
1 0 0 0 OA 市中取締續類集
- 巻号頁・発行日
- vol.[113] 山王祭礼之部, 1000
- 著者
- 塩原 彩加 尾藤 三佳 服部 佐代子 坂元 花景 小西 啓介
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.63-67, 2016 (Released:2016-06-02)
- 参考文献数
- 13
40歳代,女性。SLE のためプレドニゾロン 13mg を内服中であった。臀部の小水疱を主訴に当科を受診した。帯状疱疹の診断で入院し,アシクロビル 250mg×3回/day 点滴を開始した。自覚はないが残尿 750ml があり,尿検査では膿尿を認めた。セフジニルの内服および導尿を開始したが,入院12日目,38度台の発熱,血圧低下を生じ,尿路感染による敗血症性ショックと診断した。尿培養で緑膿菌を認めたため,セフタジジム投与を開始し,感染は落ち着いたが尿バルーンは留置したまま退院となった。腰仙髄領域の帯状疱疹では残尿の有無に注意し,経時的に残尿測定を行う必要がある。そして残尿量が多い場合には尿路感染への注意が必要である。(皮膚の科学,15: 63-67, 2016)
- 著者
- 松本 啓太 善方 日出夫
- 出版者
- 日本人間工学会 ; 1965-
- 雑誌
- 人間工学 = The Japanese journal of ergonomics (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.46-50, 2017
1 0 0 0 OA 資治通鑑綱目集説59卷前編2卷
- 著者
- 明扶安撰
- 巻号頁・発行日
- vol.[16], 1000
1 0 0 0 OA 自動車運転時のヒヤリ・ハット体験と報酬の遅延価値割引との関連
- 著者
- 松本 明生 平岡 恭一
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.288-293, 2017 (Released:2017-08-25)
- 参考文献数
- 26
Impulsivity has been linked to traffic safety problems in many prior studies. However, it is not clear whether impulsivity, defined by the rate of discounting delayed monetary rewards, relates to drivers’ problematic behavior. We investigated the relationship between the discounting of hypothetical monetary outcomes and near accident (i.e. hiyari-hatto) experiences during driving among occupational drivers. A total of 189 occupational drivers (160 men) completed the delay discounting questionnaire and hiyari-hatto experiences scale. In completing the delay discounting questionnaire, participants were asked to perform the two delay-discounting tasks, in which they chose between ¥100,000 or ¥5,000 available after some delay (from 1 month to 5 years) or a lesser amount of money available immediately. Subjective equivalence points were obtained from participants’ choices on delay discounting questionnaires, from which the areas under the curve (AUC; Myerson et al., 2001) were calculated. The results indicated that the rate of discounting (AUC) was negatively correlated to near accident experiences. We discuss the need for future research on impulsivity, delay discounting, and traffic safety.
- 著者
- Hewlett-Packard
- 出版者
- Addison-Wesley
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA [源氏物語] 54巻
- 著者
- [紫式部] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.[47], 1623
1 0 0 0 OA 自己反すうと自己内省が社交不安に及ぼす影響─4週間の間隔を空けた縦断的検討─
- 著者
- 小澤 崇将 長谷川 晃
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.17-25, 2017-10-31 (Released:2018-03-16)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3
Possible effects of two forms of self-focus driven by different motives, self-rumination and self-reflection, on symptoms of social anxiety, were investigated. Undergraduates (N=200) completed the Rumination–Reflection Questionnaire, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), Short Fear of Negative Evaluation Scale (SFNE), and Interpersonal Stress Event Scale on two occasions with an interval of four weeks. Results indicated that self-rumination in the first session significantly predicted the subsequent increase in fear of negative evaluation assessed with the SFNE, even after controlling for the intensity of initial symptoms. This finding is consistent with previous studies showing that self-focus is a major factor in maintaining social anxiety. On the other hand, self-reflection in the first session predicted a decrease in subsequent avoidance behaviors from social situations assessed with the LSAS. These findings indicate that self-focus motivated by curiosity or an epistemic interest in the self might enable people to reconsider tendencies of avoiding social situations, which may prevent behavioral tendencies of avoidance. These findings suggested that motivations driving self-focus could determine its effects on the symptoms of social anxiety.
1 0 0 0 OA 高等諸学校一覧
- 著者
- 文部省専門学務局 編
- 出版者
- 文部省専門学務局
- 巻号頁・発行日
- vol.大正11年, 1926
1 0 0 0 大教院の制度と初期の活動(国際教養学科専任教員)
- 著者
- 小川原 正道
- 出版者
- 武蔵野短期大学
- 雑誌
- 武蔵野短期大学研究紀要 (ISSN:02888025)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.125-136, 2002-06-25
1 0 0 0 OA 本朝名異女図鑑 二代の尾上
1 0 0 0 OA 「化粧学」とは何か : その学術的意義について再考
- 著者
- 川野 佐江子 カワノ サエコ Saeko KAWANO
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 = Research Bulletin of Osaka Shoin Women's University
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.137-144, 2018-01-31
「化粧学」とは何か。本論の目的は、 大阪樟蔭女子大学にて化粧が明確にカリキュラムかされて 10 年目にあた り、 新学問領域として提唱してきた「化粧学」について、 改めてその意義を確認してみようというものである。まず、 化粧を学問の俎上に挙げるために研究者はどのようなプランニングをしたのかを明らかにする。つぎに、 そのプラン の実践としての大阪樟蔭女子大学における化粧に関連するカリキュラムを時系列で追うことで、 化粧学設置までにど のような経緯があったのかを調査する。そして、 改めて化粧学が包括する学問領域についてその可能性を探る。最後 に、 化粧学が学問としてその根底に何を含んでいるのか、 近代知への疑義とともにあるポストモダンの思想について 依拠しながら論じる。また、 美が持つイデオロギー性に着目しつつ、人が美に翻弄されそれを求め続ける存在である ことを理解し、美が人々の生活といかに関連しているか、豊かににしているかを既存の学問領域を縦断横断しながら 検討していく必要性について述べる。