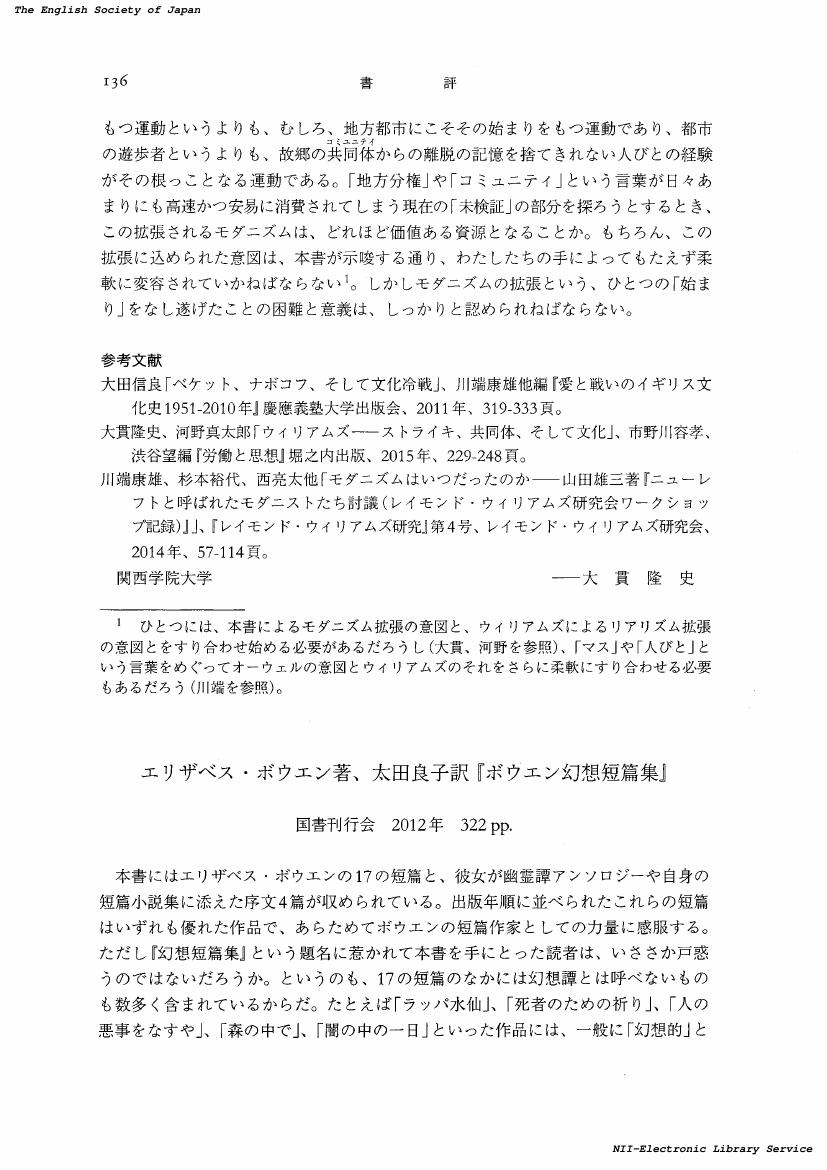1 0 0 0 西鶴文芸史の研究 : 受容理論を基底とした分析
- 著者
- 永塚 公彬 田中 宏宜 肖 伯律 土谷 敦岐 中田 一博
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会論文集 (ISSN:02884771)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.317-325, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 6 23
Dissimilar materials joining of an A5052 plate and a carbon fiber reinforced thermoplastic (CFRTP), which consisted of polyamide 6 (PA6) with 20 wt% carbon fiber addition, was performed using friction lap joining (FLJ) with the Al alloy plate as a top and the CFRTP plate as a bottom. The joint characteristics were evaluated to investigate effects of the surface treatment by the silane coupling treatment for A5052 and the joining speed on the joining properties. The joint strength was increased by inducing the silane coupling treatment for the A5052 plate surface. The tensile shear fracture load of the silane coupling treated FLJ joint increased with increasing the joining speed up to 6.67mm/s, and then decreased. The maximum tensile shear fracture load of 5.0kN was obtained at the joining speed of 6.67mm/s, and the fracture occurred at the CFRTP base plate with the joint efficiency of 97%. The shear strength of the joint interface of the joint formed at the joining speed of 1.67mm/s, which fractured at the joining interface by the tensile shear test, was estimated about 19MPa. The covalent bondings between the A5052 plate and the silane coupling layer, and the silane coupling layer and the CFRTP plate were indicated by inducing the silane coupling treatment.
1 0 0 0 OA 創薬応用を目指した脂肪酸受容体の機能解析
- 著者
- 木村 郁夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.9, pp.867-871, 2014 (Released:2016-09-17)
- 参考文献数
- 27
創薬ターゲットの大半を占めるGタンパク質共役型受容体(G protein-coupled receptor:GPCR)はこれまで広く注目されてきた.その中でも特に,その重要な生理機能から脂肪酸受容体の研究は,近年大きく進展している.例えば最近,この脂肪酸受容体のうちのGPR120がヒトの肥満の原因遺伝子であり,その一塩基変異が肥満と密接に結びつくことが明らかになっている.このことを含め,現在,機能解析が行われている各種脂肪酸受容体について,我々の研究成果を含めた最近の知見と糖尿病や肥満などに代表される生活習慣病の創薬ターゲットとしての展望も含めて概説する.
1 0 0 0 OA 軽犯罪法詳解 : 警察犯処罰令対照
1 0 0 0 OA 瓢軍談五十四場 第十一 此下宗吉郎稲葉山の搦手を襲ふ
1 0 0 0 OA 中山忠能履歴資料
- 著者
- 大塚武松, 藤井甚太郎 共編
- 出版者
- 日本史籍協会
- 巻号頁・発行日
- vol.第四, 1935
1 0 0 0 OA 潜在連合テストがもたらした社会的認知研究の進展
- 著者
- 小野 弘
- 出版者
- 常葉大学
- 雑誌
- 常葉大学保健医療学部紀要 (ISSN:21882800)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.11-22, 2017-03
1 0 0 0 OA 太平御覽 1000卷目録15卷
- 著者
- (宋) 李昉 等奉敕撰
- 出版者
- 饒世仁等銅活字印
- 巻号頁・発行日
- vol.[3], 1574
1 0 0 0 OA 泰西本草名疏 2巻付録2巻
- 著者
- 春別爾孤 著
- 巻号頁・発行日
- vol.附録上下完共二本, 1829
1 0 0 0 OA おからオンチョムの調製法と成分特性
- 著者
- 松尾 真砂子
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.9, pp.632-639, 1997-09-15 (Released:2009-05-26)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 11
おから(豆腐粕)を食糧資源として活用するため,おからオンチョム(オンチョム,Neurospora intermediaでおからを発酵させたインドネシアの伝統食品)の科学的調製方法と成分特性を調べた.オンチョムはスポンジのように多孔質なブロックに固められており,その表面はN.internzediaのオレンジ色の胞子によって覆われていた.菌糸はおからの組織内まで浸透・繁茂し,大豆の細胞壁成分の一部を資化していた.オンチョムの基本的調製法は次のようであった.水分を60%含むおからを1.1g/cm2で加圧して厚さを2.5cmにし,121℃で20分間滅菌した後,N.intermediaの胞子を含むオンチョムスターターを均一に散布し,30℃で18時間保った.菌糸が発生したら培養容器の蓋を二重のナイロンガーゼ(30 denier,105×99/inch2)と交換し,湿度65%,25℃で約11時間培養した.胞子が発生したら培地の上下を反転し,新しい上面が淡いオレンジ色になってから更に12時間培養した.おからのオンチョム化による成分変化は次のようであった.タンパク質は22%から27%へ増加し,かっ低分子化していた.脂肪は15%から9%へ減少し,難水溶性食物繊維も減少していた.オンチョムは大豆臭が無く,口当たりが滑らかで,油で揚げると鶏肉の唐揚げのような味がした.オンチョムは新たな風味を持った低エネルギー食品素材として有用であろう.
1 0 0 0 OA インドネシアの伝統的発酵食品
- 著者
- イングリッド・S・ スノロ 細野 明義
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- 酪農科学・食品の研究 (ISSN:03850218)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.A-91-A-98, 1995 (Released:2015-10-31)
- 参考文献数
- 20
インドネシアは世界最大の群島であり,多くの伝統的発酵食品が存在する。それら発酵食品には微生物としてカビ,酵母,細菌が関与しているが,構成微生物菌叢や製造過程での成分変化について明らかにされているものは極く一部に過ぎない。本稿ではカビを用いて製造するオンチョム,テンペ,タウチョ, ケチャップ,酵母を用いて製造するタペシンコン,タペクタン,ブルムケーキ,ブルムバリ,そして細菌を用いて製造するダディヒ,ミニャクサミン,テラシ,ケチャップイカン,イカンペダ,テルルアシン,テムポヤについて新しい知見と併せ紹介する。
1 0 0 0 直腸癌に対する機能温存 : 自律神経温存術
- 著者
- 大木 繁男 池 秀之 杉田 昭 山口 茂樹 市川 靖史 嶋田 紘
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.123-127, 2000-01-01
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 北川 依子
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, pp.136-139, 2015-12-01 (Released:2017-04-10)
- 著者
- 及川 和夫
- 出版者
- イギリス・ロマン派学会
- 雑誌
- イギリス・ロマン派研究 (ISSN:13419676)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.81-92, 2009-03-20 (Released:2017-01-17)