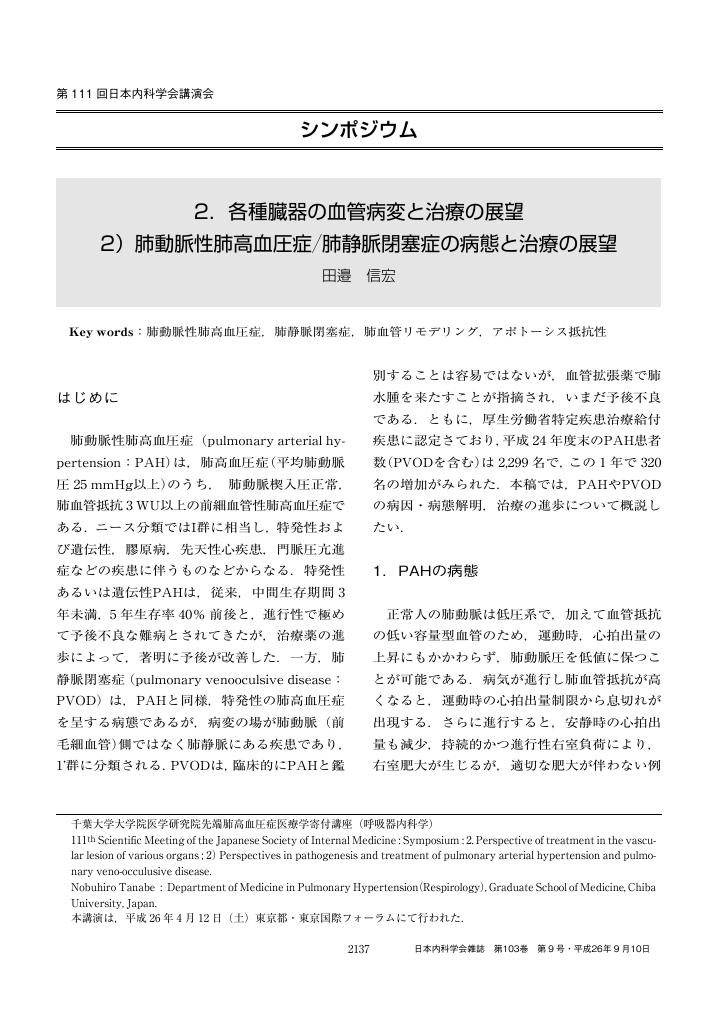1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎と粘膜治癒
- 著者
- 藤谷 幹浩 高後 裕
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.11, pp.1900-1908, 2013 (Released:2013-11-05)
- 参考文献数
- 48
潰瘍性大腸炎では臨床所見を指標として活動性が評価される.しかし,臨床症状が改善しても,内視鏡的,組織学的に炎症が残存している例が多く,このような例では長期の寛解が得られない.そこで,粘膜に炎症所見が認められない状態,いわゆる粘膜治癒を治療エンドポイントとすることが提唱されている.これまでの研究から,粘膜治癒症例では,長期の寛解が維持され,腸管切除の頻度も低いことが明らかにされた.しかし現状では,粘膜治癒の定義や判定時期が明確ではなく,粘膜治癒が得られない例への対応も確立されていない.今後,粘膜治癒の定義を統一し,治療法別に経時的な粘膜治癒達成率を明らかにしていくと同時に,粘膜治癒が得られない例に対する新規治療法の開発が期待される.
1 0 0 0 IR 『平家物語』における秩序の形成 : 後白河院と源頼朝の関係に着目して
- 著者
- 于 楽
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 文化 = Culture (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.1-19, 2017
1 0 0 0 OA 不定詞節における動詞句省略
- 著者
- 島 越郎
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 文化 = BUNKA(Culture) (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1,2, pp.20-34, 2017-09-25
1 0 0 0 OA KYコーパスを使用した計量的分析法の現状と課題
- 著者
- 森 秀明
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 文化 = BUNKA(Culture) (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1,2, pp.75-95, 2017-09-25
1 0 0 0 OA 語構成と節構成の関わりからみた字音形式「式・風」
- 著者
- 曽 睿
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 文化 = BUNKA(Culture) (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1,2, pp.113-134, 2017-09-25
1 0 0 0 IR 言語変化と文法化についての一考察
- 著者
- 高橋 光子 タカハシ ミツコ
- 出版者
- 流通経済大学社会学部
- 雑誌
- 流通経済大学社会学部論叢 = Journal of the Faculty of Sociology, Ryutsu Keizai University (ISSN:0917222X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.45-65, 2016-10
1 0 0 0 OA 防海録
- 著者
- [小宮山楓軒] [抄録]
- 巻号頁・発行日
- vol.[5], 1000
1 0 0 0 OA 白骨死体大腿骨頭内からのハエ幼虫検出事例
- 著者
- 桐木 雅史 一杉 正仁 千種 雄一 黒須 明 徳留 省悟
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.115-119, 2010-06-15 (Released:2011-01-07)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 5
某年12月下旬に栃木県中部の山林内で白骨化した遺体が発見された.法医解剖において,右大腿骨の大腿骨頭内から数十匹の虫体を検出した.採取した虫体は活発に動き,しばしば跳躍した.本虫はチーズバエ科(Diptera: Piophilidae)の3齢幼虫と同定された.本科は広く世界に分布し,日本には5種が報告されている.幼虫は動物の腐肉などの動物性蛋白質を好む種が多く,動物の死骸や骨に発生することが観察されている.本虫の骨内への侵入経路としては脈管孔が考えられる.孔径1 mm以上の脈管孔も多数あり,本科の幼虫のみならず,微小な生物であれば容易に侵入できると考えられる.遺体から検出される生物を解析することで死後時間の推定などの有用な情報が得られることがある.本事例から,体表や軟部組織のみならず,骨の内部も法医昆虫学的な検索の対象となり得ることが示唆された.
1 0 0 0 OA 志州布施田村小平治舟唐ヘ流レ行ク次第
- 出版者
- 写
- 巻号頁・発行日
- 1782
1 0 0 0 OA 2)肺動脈性肺高血圧症/肺静脈閉塞症の病態と治療の展望
- 著者
- 田邉 信宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.9, pp.2137-2143, 2014-09-10 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 現象学は外在主義から何を学べるか
- 著者
- 富山 豊
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.68, pp.155-168, 2017
<p>The internalism/externalism debate is one of the most important issues discussed in such areas of contemporary philosophy as philosophy of language, philosophy of mind (philosophy of thought), and epistemology. Husserl's phenomenology might also be regarded as a kind of internalism since it emphasizes its methodological reduction into the internal sphere of experiences ("phenomenological reduction"). Externalist criticisms against some naive forms of internalist prejudice, however, seem to contain some important insights concerning the concepts of meaning, knowledge, and mental content (or propositional attitudes). Therefore I would like to try to defend Husserl's basic insight concerning the concept of meaning, by adjusting it to accommodate this externalist insight. This "adjusting", however, is not a distortion of Husserl's original philosophy. I believe that it is just a precise explication of Husserl's own insight as it really is.</p><p>In order to show this, I will try to survey the early Husserl's theory of meaning first, bringing out its internalistic features. Secondly, I introduce a kind of externalist criticism relevant to the theory. Thirdly, I would like to try to reconcile them, focusing on the contextuality of experience. Then, finally, I will consider the objectivity of scientific knowledge. I will argue that Husserl can accept the contextualityof meaning from the viewpoint of the contextuality of experience, in a way which does not destroy the objectivity of scientific knowledge.</p>
本研究プロジェクトは、「環オホーツク海圏交流」を促進するため、環境科学的学術交流に的を絞り、持続的可能な経済発展交流の研究を追求することを目的とした。研究計画及び研究成果については研究分担者が所属する5大学の、1995年以来の各種の地域とのコンソーシアム開催事業によって、その課題を絞り込んで環境科学研究のテーマを設定してきた。そこで具体的な対象地域を設定し、社会科学的アプローチ、人文科学的アプローチ、自然科学的アプローチといった多種多様の切り口から分析を行ってきた。主な研究実績は下記の通りである。1.分析視点を深めるとともに、調査研究方法の検討会議を開催した。具体的には、これまでに先駆的に海圏交流研究を行なっている研究者に講演して頂き、研究手法・論理展開を参考としつつ、国際的見地からの環境問題への視座や、伝統的地域圏交流の再確立、広域圏交流へむけた新たな研究の視座を盛り込む研究手法を検討した。2.環オホーツク海圏における環境科学研究に関する基礎資料及び比較のための環日本海圏域における基礎資料の収集及び国内調査を実施した。3.「環オホーツク海圏広域交流」形成の課題を明らかにするため、北東アジア(モンゴル、ロシア・サハリン、中国東北部)を対象に、環オホーツク海圏における農畜産業の展開や環境汚染の状況、国際交流に向けての取り組みなどについて、各国の関係機関を中心に聞き取り調査を実施し、また関係機関からの提供資料や広域交流関連の文献などを用いながら、研究を深化させてきた。本研究の主な研究実績としては、「越境広域経営」や「環境ガバナンス論」を土台に、環オホーツク海圏の持続的な資源の利用と管理のための環境ガバナンスの構築を目指して、学術的なグランドデザイン「(仮称)OSERIEG(The Okhotsk Sea Rim for Environmental Governance)ビジョン」のモデルを検討し、「環オホーツク海圏」の位置づけを明らかにしたことがあげられる。
1 0 0 0 OA 音註五經
- 著者
- 林羅山點
- 出版者
- 吉野屋仁兵衞刊 (再刻)
- 巻号頁・発行日
- vol.[6], 1840
1 0 0 0 OA 金融制度の発展と貨幣の受領性
- 著者
- 守山 昭男 モリヤマ アキオ Akio Moriyama
- 雑誌
- 経済科学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.1-15, 2008-09-30
1 0 0 0 OA 中国都市部児童の身体状況と食生活実態及び保護者の食意識との関連
- 著者
- 邱 昱 中山 玲子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.6-19, 2018 (Released:2018-03-12)
- 参考文献数
- 49
【目的】本研究は,中国都市部児童の身体状況と食習慣,食意識・食行動等及び,保護者の食知識・食意識等との関係を,主として肥満について明らかにすることを目的とする。【方法】中国広州市立小学校全学年の児童の保護者1,020人を対象に無記名自己記入式でアンケート調査し,有効回答814人のデータを用い,解析を行った。【結果】児童の身体状況について,肥満・過体重は約20%,軽度やせ・高度やせは約17%であり,女子はやせ傾向児,男子は肥満傾向児が有意に高かった。保護者は子どもの身体状況を適正に認識していなかった。また,身体状況と食生活との関連を検討した結果,児童の肥満と朝食欠食,夕食の不規則性,間食・清涼飲料水・ファストフードの摂取頻度の多さと有意な関連が見られた。身体状況と共食状況との関連を検討した結果,夕食孤食の児童は肥満の割合が有意に高かった。望ましくない食行動を持つ児童は肥満の割合が有意に高かった。また,排便習慣,運動習慣が良くない児童は,肥満の割合が有意に高かった。一方,保護者の食知識について,認知度は20%未満であり,父親より母親は有意に知識が高かった。保護者の食知識と食意識(料理中の注意点)とは有意な関連が見られた。食意識が低い母親より,食意識が高い母親の子どもは肥満の割合が有意に低かった。【結論】中国児童の肥満を予防するため,児童及び保護者に対する飲食・栄養教育を行う必要性が示唆された。