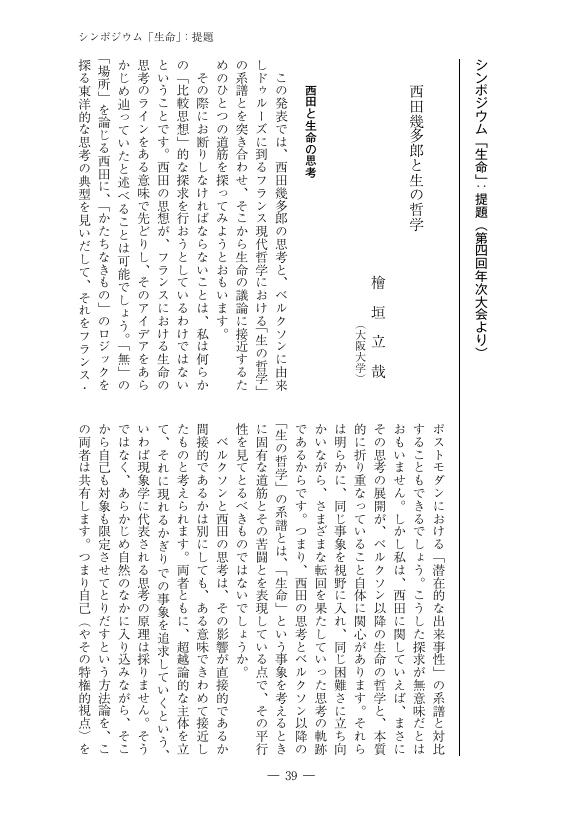3 0 0 0 OA 電子状態理論の初歩
- 著者
- 志賀 基之
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.102-105, 2012-04-30 (Released:2013-04-30)
- 参考文献数
- 15
近年の大型並列計算機の発展とともに分子シミュレーションと電子状態計算を統合した第一原理シミュレーションが普及し,国際標準になりつつある.これを用いて,従来では扱えなかった複雑な化学反応動力学や,光吸収や電磁場応答のような電子状態由来の物性などを対象に,さまざまな応用研究が広まっている.本稿では,電子状態理論の基礎をなす Hartree-Fock 法について,分子シミュレーションとの接点を少し意識しながら再考したい.
3 0 0 0 OA 西田幾多郎と生の哲学
- 著者
- 檜垣 立哉
- 出版者
- 西田哲学会
- 雑誌
- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.39-54, 2007 (Released:2020-03-24)
3 0 0 0 OA 日本の子どもを対象とした学級単位の社会的スキル訓練の効果 : メタ分析による展望(展望)
- 著者
- 高橋 史 小関 俊祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.183-194, 2011-09-30 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 9
本研究の目的は、14編の論文を用いたメタ分析によって、日本の子どもを対象とした学級単位の社会的スキル訓練(SST)の効果について検討することであった。本研究から得られた結果は、以下のとおりである。(1)学級単位のSSTによる社会的スキル向上効果は大きい。(2)小学1〜3年生の児童に対して最も効果を示しやすい。(3)セッション数(5セッション以下、6セッション以上)による効果サイズの差異は見られない。(4)担任教師がSSTを実施することの明確な優位性は見られない。(5)セッション時間外の介入を行うことでSSTの効果が高まると明確には結論づけられない。(6)教師評定や仲間指名法においてSSTの効果が示されやすい。これらの結果を踏まえて、学級単位のSSTにおける今後の研究動向について展望が行われた。
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年05月27日, 1916-05-27
3 0 0 0 OA 人工社会における循環型流行現象のシミュレーション実験
- 著者
- 中井 豊
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.345-358, 2000-10-30 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
流行には、1960年以降3回あったスカートの流行や、幕末以降4回あった新宗教ブームなど、「ほぼ同一の様式がある程度周期的に普及と沈滞を繰り返す循環型」の流行現象が存在する。 このような循環型流行現象の原因としては、従来いくつかのメカニズムが提案されていたが、本研究では「社会の気質」が周期的に変化している可能性に注目し、石井モデルを拡張したモデルを立てて、気質の周期的な変化が自律的に生じることがあるかどうかを検討した。 具体的には、石井モデルにおける流行採否戦略の社会的分布を社会の気質と解釈し、それを学習によって変化させるモデルを立ててシミュレーションを行った。その結果、あるパラメーターにおいて、採否戦略の周期的な変動と、それに伴うアイテムの流行の周期的な変化が見出された。 更に、採用に敏感な者同士のクラスターの発生と消滅が、この変動を駆動していることが分かった。
3 0 0 0 OA 尾張名所図会
- 著者
- 岡田啓 (文園) , 野口道直 (梅居) 著
- 出版者
- 片野東四郎
- 巻号頁・発行日
- vol.巻7 海東・海西郡, 1880
3 0 0 0 OA 東京案内
- 著者
- 東京市市史編纂係 編
- 出版者
- 裳華房
- 巻号頁・発行日
- vol.下巻, 1907
3 0 0 0 OA 大衆人事録
- 著者
- 帝国秘密探偵社 編
- 出版者
- 帝国秘密探偵社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和3年版, 1927
3 0 0 0 OA 昭和公論創刊拾周年記念号
3 0 0 0 OA 栄える彦島 : 郷土読本
3 0 0 0 OA 大衆人事録
- 著者
- 帝国秘密探偵社 編
- 出版者
- 帝国秘密探偵社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.第5(昭和7年)版 ア-ソ之部, 1932
- 著者
- 山中 咲耶 吉田 俊和
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.21-31, 2011 (Released:2011-08-30)
- 参考文献数
- 33
他者の面前や重要な場面において,思ったように能力を発揮できないことは,しばしば“あがり”と表現される。本研究では,“あがり”を緩和する状況要因として,面前の他者からのフィードバックと,個人差を示すパーソナリティ要因として特性的共感性に着目し,これらの要因が主観的感情体験と課題遂行に与える影響について検討した。その結果,課題遂行時に面前の他者からポジティブなフィードバックを知覚した遂行者は,ネガティブなフィードバックを知覚した遂行者よりも,主観的な“あがり”意識が低くなった。さらに,特性的共感性が高い人の方が低い人と比較して,ネガティブなフィードバックを知覚した際,主観的“あがり”意識がより高くなった。また,主観的な“あがり”意識の高低とパフォーマンス中の失敗数には,中程度の相関が示された。以上より,他者からのポジティブなフィードバックは,“あがり”の緩和効果を持つ可能性があることが示された。また,“あがり”が他者からの評価への意識と関連すること,さらに他者への意識だけでなく,他者からどれだけ影響をうけるかという個人特性,すなわち特性的共感性と深く関連した現象であることが示唆された。
3 0 0 0 OA 兵庫県会社一覧
- 著者
- 兵庫県総務部調査課 編
- 出版者
- 兵庫県総務部調査課
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和13年12月末日現在, 1939
3 0 0 0 OA 保育所長の職員採用に係る意識に関する研究
- 著者
- 石川 昭義 西村 重稀 矢藤 誠慈郎 森 俊之 青井 夕貴
- 出版者
- 仁愛大学
- 雑誌
- 仁愛大学研究紀要. 人間生活学部篇 (ISSN:21853363)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.30-38, 2013-03-31
平成23 年8 月に,A市(政令指令都市)の保育所289 園とB県の保育所278 園の所長を対象に調査を依頼した(保育所長の保育所運営に係る意識に関する調査).本稿では,調査質問項目の中から,四大卒及び男性保育士の採用に係る調査結果と併せて,新たに実施したヒアリング調査の結果を報告する.保育所長は,四大卒保育士の採用については,「どちらともいえない」という回答が最も多く(56.1%),ついで「ややそう思う」(24.1%)という回答が多かった.四大卒の保育士に期待する領域としては,「子どもの発達過程の理解」,「ソーシャルワークの知識・技能」,「保護者からの相談対応」が高かった.今後の男性保育士の採用については,「どちらともいえない」(38.4%),「ややそう思う」(30.0%)という回答が多かった.男性保育士の採用をめぐる自由記述では,採用に積極的な意見から消極的な意見まで,多様な見解があることが判明した.同時に,保育士の給与のベースとなる運営費の在り方という課題も浮かび上がった.
3 0 0 0 大洗町史
- 著者
- 大洗町史編さん委員会 編
- 出版者
- 大洗町
- 巻号頁・発行日
- vol.通史編, 1986
3 0 0 0 OA 「満洲」化学工業の開発と新中国への継承
- 著者
- 峰 毅
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.19-43, 2006-01-31 (Released:2014-09-30)
- 参考文献数
- 105
The North East Region of China, also known as Manchuria, became the chemical production base of the newly formed socialist China up to the time of the ‘open door’ policy. This chemical production base was originally developed by Japan prior to World War II. Only recently has Japan began to undertake academic research on this region; this hesitation is at least partly a reflection of Japanese attitudes to their invasion of China. However, US researchers had long held a high opinion of the industrial development of this region. Edwin Pauley, the first Westerner to visit Manchuria after the end of World War II, reported in 1946 to US President Truman concerning the Japanese assets in Manchuria, which he evaluated highly, to his surprise, as a war indemnity. Since then many researchers on China have written in the United States about the industrial development of this region as part of China, but not in Japan. However, more recently, researchers have begun to make studies on the industrial development of Japan-era Manchuria. Some remarkable research works have been published, especially concerning the steel and iron industry. Regarding the chemical industry, however, little research work has so far been done. This paper therefore starts with a description of how the Manchurian chemical industry was incubated and developed by Japan.First, this paper outlines the chemical production base developed by Japan in Manchuria. It then describes how Japan needed to develop and construct a chemical production base inManchuria, where natural resources, including coal are abundant, in order to put its economy on to a war footing. The construction of the highly organized industrial production base in Manchuria was only possible with the strong support of the Japanese Army. As a result the industrial structure of Manchuria was highly dependent on heavy industry, including the chemical industry. This paper also analyzes the characteristics of the economy of Manchuria and makes comparisons between the Republic of China and Japan based on GNP/CDP and on some data on three major representative chemical products: sulfuric acid, soda ash and am monia. The analysis shows clearly that the economy of Manchuria was oriented towards the war economy.This paper also analyzes the early days of the newly formed socialist China, when the production base in the North East Region played a key role in the national economy. After the defeat of Japan in 1945, Manchuria was invaded by Soviet soldiers and much of the production facilities were destroyed. Soon after socialist China was formed in 1949, the new government made recovery of the North East Region a top priority. This urgency was caused partly by the Korean War, which broke out in 1950, the year after the formation of socialist China, and partly by the existence of the highly organized modern heavy industry which was indis pensable to the construction of the national economy. Since then this region has contributed a great deal to the development of China’s chemical industry not only as a production base but also as an R&D and technical center. Some examples of the economic heritage of the industry from the days of Manchuria are introduced by referring to the Chinese literature as well as to papers written by the Japanese engineers and technicians who remained in China after World War II in order to help the recovery and reconstruction of China’s economy.