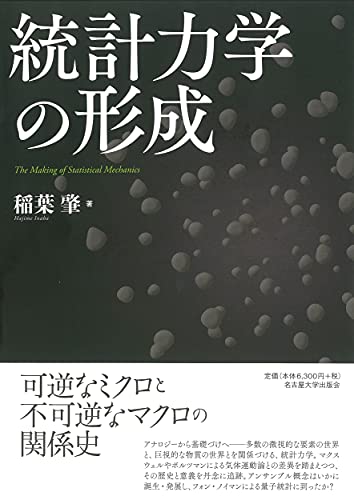2 0 0 0 OA A Giant Infected Coronary Artery Aneurysm
- 著者
- Yasutaka Tsujimoto Yohei Kanzawa Naoto Ishimaru Saori Kinami
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.7948-21, (Released:2021-10-19)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 電子透かしとしてのQR コードの検出
- 著者
- 古川 翔 永登 健太 荒木 智行 前田 俊二
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会大会講演論文集 30 (ISSN:13451510)
- 巻号頁・発行日
- pp.203-206, 2017-11-25 (Released:2021-02-01)
By embedding electronic watermarks (ex. QR codes) in advertisement such as digital signage, we can get additional information through the Internet by translating the electronic watermark into URL. Usually digital images in digital signage are composed of JPEG images. It is well known that electric watermarks deteriorate deeply if we embed them into JPEG images. It results in algorithm of JPEG compression. In this study, we try two methods as follows; (1) masking effect, and (2) embedding plural electric watermarks. Then, estimation and remained problems are shown.
2 0 0 0 IR 『儒教実義』の思想
- 著者
- 堀池 信夫
- 出版者
- 中国文化学会(筑波大学文芸言語学系内)
- 雑誌
- 中国文化 (ISSN:02896648)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.40-52, 1998
2 0 0 0 OA Identification of a novel filovirus in a common lancehead (Bothrops atrox (Linnaeus, 1758))
- 著者
- Masayuki HORIE
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.9, pp.1485-1488, 2021 (Released:2021-09-27)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 8
I performed metaviromic analysis of publicly available RNA-seq data from reptiles to understand the diversity of filoviruses (family Filoviridae). I identified a coding-complete sequence of a filovirus from the common lancehead (Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)), tentatively named Tapajós virus (TAPV). Although the genome organization of TAPV is similar to mammalian filoviruses, our phylogenetic analysis showed that TAPV forms a cluster with a fish filovirus. However, TAPV is still distantly related to all the known filoviruses, suggesting that TAPV can be assigned as a species of a novel genus in Filoviridae. To our knowledge, this is the first report identifying a filovirus in reptiles, and thus contributes to a deeper understanding of the diversity and evolution of filoviruses.
2 0 0 0 OA 現存するわが国最初の鉄道用鉄桁
- 著者
- 西野 保行 小西 純一
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 日本土木史研究発表会論文集 (ISSN:09134107)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.193-198, 1987-06-20 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 8
わが国最初の鉄道用鉄桁である70ft3主構ポニーワーレントラスが, 道路橋に転用されて今なお現存しているのが発見された.3主構が揃った姿ではないが, 1873年製の桁を含んでいるのは確実と思われ, これまで最古の鉄道用鉄楠として保存されている1875年製の100ft複線ポニーワーレントラス以前の, 文字通り「わが国最初で最占」の鉄道用鉄桁である, 発見の経緯, 転用状況, 現存の浜中津橋の調査結果などを述べる.
2 0 0 0 OA ジンメル近代文化論の射程
- 著者
- 菅野 仁
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.26-40, 1990-06-30 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 37
本稿の課題は、「生」と「分業」という二つの概念の統一的把握を通して、G・ジンメルの「近代文化論」がもつ独自な意義を明らかにすることにある。これまでジンメルの近代文化論については、その中心的概念が「生」であるとし、その概念的、形而上学的性格を批判する見解や、「生」と「分業」との統一的把握のもとに近代文化の問題の核心に迫った意義深い文化論であると積極的評価を下す見解などがあった。本稿は基本的に後者の立場に依拠しており、ここではジンメルの近代文化論がどのような意味で積極的に評価しうるのかを、『貨幣の哲学』の近代文化論の検討を通じて明らかにしたいと考える。すなわちジンメルは、「生」と「分業」という二つの概念を主軸に近代文化がはらむ問題状況を、「主体の文化と客体の文化との齟齬的関係」としてとらえ直すことによって、ネガティヴな現象形態をとりつつ進展する近代文化の在り方のなかに「可能性」として蓄積されているポジティヴ性をみる、という複眼的視座からの近代文化論を展開したのである。本稿では、彼の近代文化論における「生」概念と「分業」概念との関係の在り方を明らかにすることを通して、近代文化をとらえるジンメルの複眼的視座がもつ独自な意義に迫りたい。
2 0 0 0 OA 近代日本における肉食受容過程の分析 : 辻売,牛鍋と西洋料理
- 著者
- 野間 万里子
- 出版者
- 日本農業史学会
- 雑誌
- 農業史研究 (ISSN:13475614)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.77-88, 2006 (Released:2017-03-23)
In civilization and enlightenment period, gyunabe became popular, and for common people meat practically meant for gyunabe. Gyunabe inherited the way of cooking and the style of eating of kusurigui, most typical form of eating meat before the Restoration. But it became a symbol of civilization and enlightenment. The new government was encouraging eating meat, at that time. The Emperor Meiji first ate meat in 1872. He ate meat as Western food, not gyunabe, and the government regarded meat as beef and mutton. That is to say, the government considered that eating meat was a variety of Western civilization. I must add that besides gyunabe and Western food, there was another style of eating meat, a stewed meat stand. That was regarded as the food for the poor. Some reasons made it possible that eating meat was accepted as gyunabe. In the first place, people associated eating meat with civilization. The civilization included both Westernization and rationalities. The former couldn't have effect on people had ill feeling for Western. But the later was accepted more generally. In early modern times, to eat meat was thought disgusting conduct. Rational explanations were worked out to deny such a thought as superstition. Nutritional thinking also supported gyunabe boom. And, appetite was suppressed before Meiji, but after the Restoration, people could enjoy eating delicious things. This is also an important change. At that time, ranking formed among meat. The meat of wild animals seemed the lowest. Among the meat of livestock, beef was thought more refined than pork. Because pig was resemble to wild boar, eaten as kusurigui, and pork was associated with Ryukyu or Asia in spite of beef was associated with Western. As stated above, gyunabe was ranked higher than stewed meat stands. One of the reasons was rationalities, that was made valid by Western civilization. So Western food came higher rank.
2 0 0 0 OA 浜名湖に淡水の時代はなかった
- 著者
- 加茂 豊策
- 出版者
- 静岡県地学会
- 雑誌
- 静岡地学 (ISSN:02850753)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.19-29, 2007-11-18
2 0 0 0 OA サリドマイドのらい性結節性紅斑に対する保険適用に向けて
- 著者
- 石井 則久
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- 日本ハンセン病学会雑誌 (ISSN:13423681)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.275-279, 2010-09-01 (Released:2012-02-02)
- 参考文献数
- 22
- 著者
- Naoki SUZUKI Sohei KANEKO Naoki ISOBE
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.325-329, 2022 (Released:2022-03-03)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
This study aimed to determine whether causative pathogens in mastitic milk can be determined by Gram staining after the centrifugation of milk. Gram staining was performed using unconcentrated and concentrated milk cells. Using this method, we found that the background of microscopic image of unconcentrated milk cells was complex and bacteria were difficult to detect. In contrast, the background of the smears in the concentrated milk cells was translucent, and bacterial and somatic cells were clearly visible. The sensitivity and specificity of the Gram staining of concentrated milk cells were 84.4% and 86.0% and 50.0% and 94.5% for the detection of gram-positive and gram-negative bacteria, respectively. The presented method provides a simple and inexpensive means of determining mastitis-causing pathogens.
2 0 0 0 OA 「業務としての自殺援助」という新しい構成要件に関する一考察
- 著者
- 佐瀬 恵子 Keiko Sase
- 出版者
- 創価大学法科大学院
- 雑誌
- 創価ロージャーナル
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.163-169, 2020-03-25
2 0 0 0 OA ドイツ 業としての自殺幇助の禁止
- 著者
- 渡辺富久子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 266-1), 2016-01
2 0 0 0 OA 私が経験した抜管の修羅場─医学教育学的視点からの省察─
- 著者
- 髙田 真二
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.203-211, 2018-03-15 (Released:2018-04-07)
安全な抜管ができるためには,気道管理に関する専門的な知識や技術に加え,状況認識や意思決定などのノンテクニカルスキル(認知スキル)が不可欠である.抜管の失敗の多くは認知バイアスに由来する判断の誤り(認知のエラー)である.認知スキルを高めるには自分の行動や思考の自発的,客観的な振り返りが欠かせない.他者からのフィードバックを受けながら自分の経験を振り返り,教訓を概念化して次の経験へ活かすという経験学修サイクルを繰り返すことで,医療者は患者安全の実践能力やプロフェッショナリズムを修得していく.本稿では認知バイアスのため抜管の判断を誤った自験例を提示し,具体的な振り返りの方法を紹介した.
2 0 0 0 OA 近代教育制度と大正新教育運動 ―教育学における諸概念の検討を中心に―
- 著者
- 鈴木 和正
- 巻号頁・発行日
- 2017
教員採用試験における教育史関係の問題は,教育哲学・思想関係の問題と同様に,思想家の名前や著作,法令名などの細かい知識を暗記して問うものが目立つ。採用試験にまったく関知しない教職専門科目を維持することは,多くの大学(特に教員養成を重要視する大学)において容易なことではない。今,教育史は,実践的指導力を育成する「大学における教員養成」原則の下で,いかに教育されるべきか問われている。本稿では,筆者が教育史講義で使用している教材を紹介し,講義内容の一端を知ってもらえるようにした。筆者の研究領域である大正新教育運動は,1910年代から30年代前半にかけて展開された,主として初等教育における児童中心主義的な思想と実践である。従来の画一的・形式的な一斉教授法に対して,児童の個々の特性や主体性,活動性に配慮した教授・学習方法を導入した点に特徴がある。本稿においては,大正新教育運動の拠点となった新学校の教育実践を明らかにするとともに,綴方教育や芸術教育運動についても考察している。
2 0 0 0 OA 宮崎滔天のア・ジア主義 : 大陸浪人の一類型
- 著者
- 山口 光朔 Kosaku Yamaguchi
- 雑誌
- 桃山学院大学紀要 = JOURNAL OF ST. ANDREW'S UNIVERSITY
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.59-119, 1963-11-25
2 0 0 0 OA OCDの行動療法と薬物療法─機能的脳画像による効果の検証
- 著者
- 中尾 智博
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.193-199, 2012 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 16
強迫性障害(OCD)に対して,行動療法とSSRIによる薬物療法が有効であることが知られているが,これらの治療がどのような機序で症状の改善をもたらすのかについてはまだ不明な点が多い。しかし近年PET や SPECT,fMRIを用いた脳画像研究の進歩によってこれらの治療法による脳の機能的変化を調べることが可能となり,薬物療法,行動療法はともに脳の活動に影響を与え,前頭眼窩面,尾状核といった部位の過剰な賦活が症状改善後に正常化することがわかってきた。両治療法の脳機能修復プロセスの差異についてはなお不明な点が多く,今後の研究が待たれる。脳画像研究の結果はOCDの病態に関与する脳部位の神経連絡を考慮に入れたOCD─ loop仮説へと結実し,現在は当初考えられた前頭葉─皮質下領域に加え,辺縁系,頭頂後頭葉,小脳などを加えた広範な神経ネットワークの異常がOCDの情動,認知の障害に関与すると推測されている。さらに今後は疾患内における病態の多様性を考慮した神経ネットワークモデルの構築が必要となってくると思われ,OCDの病態理解と治療戦略構築のために画像研究が果たす役割は大きい