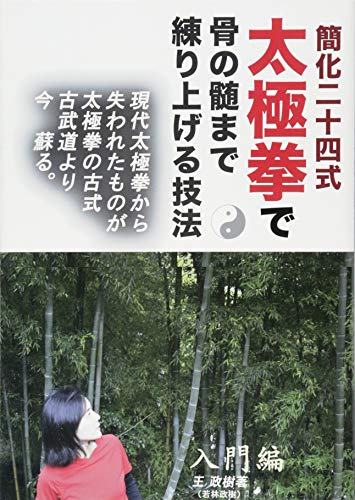2 0 0 0 OA 片山正樹教授年譜 ; 片山正樹教授業績
- 雑誌
- 年報・フランス研究 (ISSN:09109757)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.v-x, 1996-12-25
- 著者
- Gen Nakaji Maroka Shinchi Yurika Ohba Akihiro Koike
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF BIORHEOLOGY
- 雑誌
- Journal of Biorheology (ISSN:18670466)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.23-30, 2022 (Released:2022-07-29)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
Percutaneous coronary intervention (PCI) using balloon technology and stent implantation has revolutionized the interventional cardiology since the late 1970s. The plane old balloon angioplasty (POBA) was first proposed in the late 1970s as an alternative to coronary artery bypass grafting (CABG) for the treatment of coronary artery disease (CAD) such as angina pectoris and acute myocardial infarction (AMI). Thereafter, bare metal stent (BMS) was designed to overcome the problems proposed by POBA such as acute occlusion and restenosis of coronary target lesion. However, a new problem of BMS-induced in-stent restenosis (ISR) has appeared, and drug-eluting stent (DES) was introduced to resolve the problem of ISR. DES has improved the clinical outcome of patients undergoing PCI. Contemporary stent technology shows remarkable progress, and further effort continues to improve the design, structure, and materials of DES. However, DES has proposed a new problem of very late stent thrombosis. To overcome this late complication, non-stent strategy is introduced into the PCI. This article aims to review the historical development and future perspective of the PCI especially focusing on the evolution of DES.
2 0 0 0 OA Strategies of endovascular intervention for patients with symptomatic lower extremity artery disease
- 著者
- Eiji Karashima Masahiko Fujihara
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF BIORHEOLOGY
- 雑誌
- Journal of Biorheology (ISSN:18670466)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.3-11, 2022 (Released:2022-07-29)
- 参考文献数
- 58
Peripheral artery disease (PAD) is an obstructive arterial disease of the lower extremities. Due to the aging society and improved diagnostic techniques, the number of patients identified with PAD is increasing. Endovascular treatment (EVT) is a widely accepted interventional management method for diseased lower extremity arteries. Anatomically, the arteries of the lower extremities are divided into three segments: aortoiliac, femoropopliteal, and below-the-knee. The strategies of EVT recommended in the relevant guidelines are different for each segment. During the past 20 years, the indications and strategies of EVT have been evolving owing to the development of devices and improvement of clinical outcomes of EVT. Although it might be challenging to catch up with the evolving EVT strategies, we should develop an optimal EVT strategy for each PAD patient, considering that patient and lesion characteristics would also affect clinical outcomes. In this review, we describe the current knowledge of EVT strategies for each segment. We selected the EVT strategies that are currently performed for a majority of symptomatic PAD patients.
2 0 0 0 OA VII.NASHに対する薬物治療のエビデンス
- 著者
- 米田 政志
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.1, pp.56-63, 2020-01-10 (Released:2021-01-10)
- 参考文献数
- 23
非アルコール性脂肪肝炎(non-alcoholic steatohepatitis:NASH)の治療は,内臓肥満を是正するための運動及び食事等の習慣の改善が第一であるが,遂行・持続することが困難である.現在,NASHに対する確立された特異的な治療薬はないが,背景にあるメタボリックシンドロームに合わせた治療薬の効果が確認されており,ガイドラインで推奨されている.本稿では,日本における「NAFLD/NASH診療ガイドライン2014」(日本消化器病学会,2014年)を中心にエビデンスがある程度確認されているNASHに対する薬物治療を概説する.
2 0 0 0 船の科学
- 著者
- 国土交通省海事局 監修
- 出版者
- 船舶技術協会
- 巻号頁・発行日
- vol.18(5), no.199, 1965-05
2 0 0 0 OA 生物的自律分散システムの設計原理
- 著者
- 矢野 雅文
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.468-473, 1992-08-15 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 憲政五十年史 : 画譜
- 著者
- 画譜憲政五十年史刊行会 編
- 出版者
- 大日本皇道奉賛会
- 巻号頁・発行日
- 1942
2 0 0 0 OA フランスにおける同性婚法の成立と保守的家族主義への回帰
- 著者
- 北原 零未
- 出版者
- 中央大学経済研究所
- 雑誌
- 中央大学経済研究所年報 (ISSN:02859718)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.13-37, 2014-09-25
2013年5月,フランスにおいてようやく同性婚法が成立した。一般には,1999年末に成立したパックス(PaCS)をもってフランスは同性カップルを国家的に認知し,法的裏付けを与えたということになっているが,男女のみに許可されている既存の婚姻制度を批判し,婚姻法そのものの改正を求めていた同性愛者たちにとっては,パックスの成立は前進ではなく,むしろフランス国家からの否定的回答であったと言える。 今回の同性婚法成立は,そのこと自体は多様な家族生活,ライフスタイルを認めるという観点からすれば前進と言えるが,しかしその成立直後には,パックス成立時の時以上の反対運動が行われた。そして,そこでは,同性愛のみならず,伝統的家族以外の家族形態すべてが批判され,保守主義・家父長主義回帰が見られたのである。もはや同性婚以前の問題であり,保守的な男女の規範が賛美された。
- 著者
- SATO Kazutoshi KAMEDA Takao SHIRAKAWA Tatsuo
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-045, (Released:2022-07-22)
Iwamizawa on the Sea of Japan side of Hokkaido is one of the cities in Japan that experience frequent heavy snowfall events. Warm surface-layer ocean anomalies over the Sea of Japan can induce heavy snowfall over the Sea of Japan side of Japan; however, the relationship between ocean temperature over the northern Sea of Japan and snowfall events at Iwamizawa remains uncertain. This study used reanalysis data to investigate atmospheric and oceanic circulation anomalies associated with each anomalous heavy snowfall winter month at Iwamizawa. During all anomalous snowfall winter months at Iwamizawa, a cold air anomaly with northwesterly winds existed over the Far East that was associated with a dipole pattern with anticyclone anomalies over the north coast of the Eurasian Continent and cyclonic anomalies extending zonally over the Far East and northern Pacific Ocean. The surface cold air temperature and strong wind speed anomalies are major factor for anomalous upward turbulent heat flux over the northern Sea of Japan during all anomalous snowfall winter months at Iwamizawa. Additionally, during anomalous snowfall January, warm surface-layer ocean anomaly over the northern Sea of Japan, which preceded the heavy snowfall events at Iwamizawa by two months, has an important role in upward turbulent heat flux anomaly. This preceding warm ocean temperature anomaly was associated with a strong Tsushima Warm Current anomaly. Results showed that warm surface-layer ocean anomaly over the northern Sea of Japan that precedes anomalous cold advection from the Eurasian Continent has also large impact on producing heavy snowfall events over western Hokkaido coastal regions near Iwamizawa in January.
2 0 0 0 簡化二十四式太極拳で骨の髄まで練り上げる技法
2 0 0 0 OA ショパンの生涯と手紙
- 著者
- モーリッツ・カラソフスキー 著
- 出版者
- 新生社
- 巻号頁・発行日
- 1923
2 0 0 0 OA 陥入爪・巻き爪の違いと治療 -この似て非なるもの-
- 著者
- 青木 文彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本フットケア学会
- 雑誌
- 日本フットケア学会雑誌 (ISSN:21877505)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.200-207, 2018-12-25 (Released:2018-12-25)
- 参考文献数
- 24
【要旨】陥入爪と巻き爪は一般診療所においても診察の機会の多い疾患であり,それを扱う診療科も多岐にわたる.しかしながら,これらの疾患が異なる病態であることは,充分に理解されているとはいえない.陥入爪は男女ともに若年者に多く,陥入爪準備状態の爪に対して様々な外因によって引き起こされる一過性の病態といえる.一方,巻き爪は中・高年齢の女性に多く,爪そのものが様々な原因により変形していく継続的な病態と考えられる.
2 0 0 0 巻き爪と陥入爪の治療法
- 著者
- 原田 和俊 山口 美由紀 島田 眞路
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.11, pp.2069-2076, 2013-10-20 (Released:2014-10-30)
陥入爪とは爪甲が側爪郭を損傷し,炎症を引き起こした状態である.巻き爪とは遺伝的素因,生活環境などにより,爪甲が過度に彎曲した状態である.陥入爪の治療にはポリ塩化ビニル製チューブで陥入した爪甲を覆う方法や,アクリル樹脂を用いて側爪郭への陥入を除去する治療法などがある.疼痛を伴う巻き爪は,弾性ワイヤーなどを用いて過度の彎曲を矯正することが有効である.陥入爪と巻き爪の対応には,正確な診断を行い,各々の病態を理解し,正しい治療法を選択することが必要である.
2 0 0 0 OA 横浜の「シウマイ弁当」
- 著者
- 河野 一世
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.193-194, 2014 (Released:2014-07-04)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 下五島の持続可能な発展に向けたライフサイクル思考に基づく取り組み ―現状と今後の研究展望
- 著者
- 重富 陽介 種田 あずさ
- 出版者
- 日本LCA学会
- 雑誌
- 日本LCA学会誌 (ISSN:18802761)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.135-141, 2022 (Released:2022-08-05)
- 参考文献数
- 62
離島は多様性のホットスポットであるとともに様々な脆弱性を抱えており、その閉じられた境界の中で持続可能な発展の道筋を示すための先行研究が数多く実施されてきた。本稿では、長崎県にある約 600 の離島の中で最も人口が多い五島列島に焦点を当てる。五島列島の中で、五島市を行政の中心に据える下五島では、かねてより洋上風力発電や潮汐発電の日本初の実証地として再生可能エネルギーの利活用を軸とする地域活性化に力が入れられている。本稿では、下五島における持続可能な発展に向けた知見を得るための、同島の肉牛やうどん等の食の特産品に注目したライフサイクル分析のフレームワークと研究展望について紹介する。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1892年08月09日, 1892-08-09
2 0 0 0 OA 3 step model for the emergence of first life
- 著者
- 丸山 茂徳 戎崎 俊一 大島 拓
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2016年大会
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-10
生命の起源は、おそらく生物学者だけでは解けない問題だろう。この問題は、生物学のみならず、天文学、地球物理学、化学、地質学などを総動員した超学際研究によってのみ解明できるはずである。われわれは、地球史研究を通して、生命を育んだ器としての地球の歴史を、横軸46億年研究と特異点研究の2つの手法を利用して解明してきた。そこから導かれる生命誕生場はどのようなものであり、最初の生命はどのようなものだったのかをまとめたのが、地球生命誕生の3段階モデルである。本モデルでは、生命は、第一次生命体、第二次生命体を経て第三次生命体(原核生物)が誕生したことを提唱する。以下に、各段階における生命体について詳述する。第一次生命体は、それぞれの個体そのものだけでは生存できなかったが、多数が外部共生することによって生き延びることが可能であった生物群だと考える。第一次生命体が持っていたワンセットの遺伝子をミニマム遺伝子と考える。おそらく、ミニマム遺伝子は約100個の遺伝子からなっており、「膜+代謝+自己複製」を可能にした。しかし、生存するためには細胞外共生をする必要があった。当時、ミニマム遺伝子の周囲には、この微小生態系の100倍以上の量のオルガネラ(現代のウイルスに酷似の状態)が存在していたが、これらの微小生態系が活動するためには、連続してエネルギーを供給することが必要で、当時の冥王代地球表層では太陽エネルギーが利用できなかった。その代わりに、地下の自然原子炉から供給される強力なエネルギーによって地表と間欠泉内部をつなぐ環境でのみ存在が可能だった。自然原子炉間欠泉は、熱湯が周期的に噴出するため、内部の温度は100℃が上限がとなる。従って、高温によるRNAの損傷を受けることは少なかった。 間欠泉から地表に投げ出される第一次生命体は、地表に降り注ぐ原始太陽風(現在の1000倍の放射線)によって分解され死滅する。それによって、これらはタールと化す。冥王代表層環境の厚い大気(CO2100気圧)が薄くなり、次第に太陽が顔を出し始めると、可視光(太陽エネルギー)を利用することができるようになった新しい生命(第2次生命体)が生まれる。これは地下の自然原子炉間欠泉で生まれた第一次生命体を基本とし、太陽からの弱い電磁エネルギーを利用するために、半導体(FeSなど)を利用した反応システムを創り出した。第一次生命体に引き続き、第二次生命体も無限に近い種類のアミノ酸の高次有機物からできるので、第二次生命体の多様性はさらに増加し、種類は無数にあったと考えられる。第二次生命体も細胞外共生していた。原始海洋は猛毒(pH<1、超富重金属元素濃度、塩分濃度は現在の5-10倍)である。したがって、淡水をたたえる湖沼環境で生まれた第二生命体は、原始海洋に遭遇すると大量絶滅する。大陸内部のリフト帯の湖沼環境で生まれた生命体は、リフトが割けて海洋が浸入することによって大量絶滅を起こすことになる。このプロセスが何度も繰り返され、幾度となく第二次生命体は大量絶滅を経験する。一方、プレート運動によって、海洋の重金属は鉱床として硫黄とともに固定され、マントルへプレートと共に沈み込むことによって海洋から取り除かれていった。更に、陸地の風化浸食運搬作用によって、細かく砕かれた大陸の岩石と海洋が反応することによって、海洋の中性化が進む。このように浄化されていった海洋にやがて適応した生命体は遺伝子の数を桁違いに増加して、細胞壁を作り、耐性強化した。これが真正細菌でシアノバクテリアの起源だと考えられる。 こうして、原始生物は、生き延びるための防御構造を、次々と発明して、遺伝子数を急増させた。理論的に可能なアミノ酸の種類はほぼ無限(1020)に近いが、現代地球の生物は20種類のアミノ酸だけを使う。これは、第二次生命体が、無限に近い種類のアミノ酸を組み合わせたものであったが、猛毒海洋への適応戦略で淘汰された結果であろう。これが地球型生命体の起源である。
2 0 0 0 OA マレーシア 人身取引及び移民の不法入国防止に係る法改正
- 著者
- 日野智豪
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 292-2), 2022-08
2 0 0 0 OA 韓国 水上レジャー機具の登録等に関する法律の制定
- 著者
- 中村穂佳
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 292-2), 2022-08
2 0 0 0 OA 中国 騒音汚染防止法の制定
- 著者
- 湯野基生
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 292-2), 2022-08