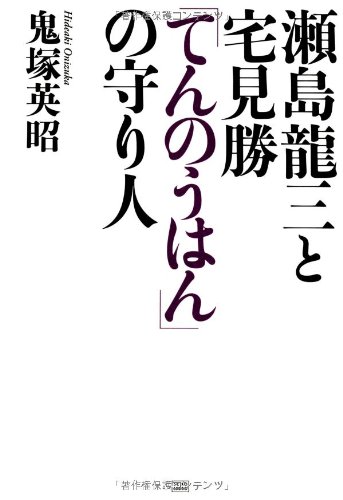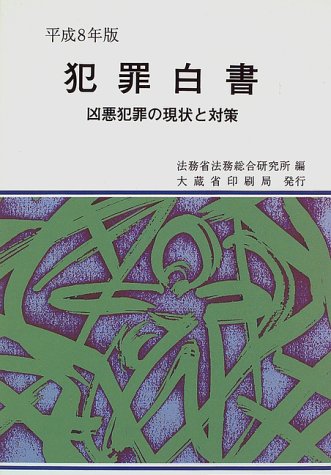2 0 0 0 OA 皮膚血管腫の統計的観察
- 著者
- 北村 弥 飯岡 昭子 森田 美智子 坂本 邦樹 桐山 保夫 伊藤 和男
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.726-731, 1982 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 11
加齢とともに発生頻度が増加する老人性血管腫について統計的観察をおこない, 次の結論を得た。1. Ruby spotの最少発症年令は9歳であり, 加齢とともにその発症頻度は増加した。2. Venous lakeは30歳代より発生しはじめ, 加齢とともにその発症頻度は増加した。Venous lakeを有した54人中53人が下口唇に発症していた。本症と消化管性潰瘍や肝疾患との関連は明らかではなかった。3. Angiokeratoma scroti Fordyceは30歳代以上の者の16.8%に認められた。
2 0 0 0 OA 血管腫に対する色素レーザー治療の限界と問題点
- 著者
- 岩崎 泰政
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.Supplement, pp.97-100, 1997 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 8
Selective photothermolysis with a long-pulse flashlamp dye laser with 585 nm is becoming widely accepted as a treatment for cutaneous vascular lesions because of high efficacy with a very low risk of scarring. The light of dye laser penetrated into 1,400 μAm depth of the human skin and induces selective intravascular and perivascular coagulation necrosis. However, the numbers and diameters of blood vessels were significantly decreased only in tissues down to a depth of 600 μm 3 months after the laser irradiation. Fifty two out of 550 patients (9.5%) with port-wine stains (PWS) showed an excellent clinical improvement after single treatment and up to 4 times additional irradiation further improved clinical responses in as much as 115 patients with excellent improvement. The degrees of clinical responses are dependent on histological type, age, anatomic location and color of PWS lesions. Treatments of strawberry mark are usually begun in a thin flat stage or at initial presentation with some success especially for their superficial lesions. However, they hardly affect the size of tumor and often leave atrophic and redundant skin surface with scarring. Finally practical problems in dye laser treatment of hemangioma were discussed.
- 著者
- 小谷 真理
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.24-34, 2008-04-10 (Released:2017-08-01)
飛浩隆「ラギッド・ガール」(<SFマガジン>二〇〇四年二月号に掲載)は、ある事情で放置されている仮想現実世界を扱った<廃園の天使シリーズ>の中編である。仮想現実世界は、<数値海岸(コスタ・デル・ヌメロ)>といい、<廃園の天使シリーズ>は、その創造と放棄と内部変化を描いている。もちろん仮想現実世界といっても、現実世界はあまりにも膨大なデータであるために、現実をそっくり写しとれるわけではなく、いわば仮設の情報集積所となっており、人間の似姿と人工知能が混在する世界として想定されており、インターネットに近い感触を持つ。「ラギッド・ガール」の「ラギッド」とは「ざらざらの」という意味。主要登場人物である安形渓の身体の異形を指している。物語は、体験や記憶がすべて体内に蓄えられながら生きる情報集積体たる渓の身体論を中心に、アガサとキャリバン、安奈と渓の関係を読み解きながら、現実世界、仮想現実世界、さらに仮想現実世界に内蔵されたサイバースペースという三つの空間にまたがって、性差とセクシュアリティの諸問題を投げかけ、人と人とのコミュニケーションについての問題を探求していく。この作品における女性の身体と性差の設定は、アメリカのSF作家ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの「接続された女」を彷彿とさせ、共通点が多い。特筆すべき要素は、女性身体をめぐる話題、「身体の醜さ」、「暴力」、「レズビアン・セクシュアリティ」である。そこで、本稿では、電脳空間を素材にしたサイバーパンク小説の先駆けと評される「接続された女」と、ポスト・サイバーパンク小説「ラギッド・ガール」を比較検討し、女性性、身体性、情報集積体としての性差について再考する。
2 0 0 0 OA 行動の自由に対する侵害犯としての公務員職権濫用罪
- 著者
- 江藤 隆之
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.1-34, 2017-11-06
2 0 0 0 OA マルクス国際価値論の復権-「賃金の国民的相違」と世界市場の独自的機構-
- 著者
- 前畑 雪彦
- 雑誌
- 桜美林大学研究紀要.社会科学研究 = J. F. Oberlin University Journal of Advanced Research. Social Sciences (ISSN:24362697)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.313-330, 2022-03-25
2 0 0 0 OA 思春期における吃音児指導に関する研究 : 小学校通級指導教室を終了した中学生を中心に
- 著者
- 長澤 泰子 太田 真紀
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.3-13, 2006-03-30 (Released:2018-02-07)
障害児・者は,障害そのものへの支援と心理面の支援を必要としている。吃音を持つ子ども達も例外ではなく,一般に,公立小学校の通級指導教室,通称ことばの教室において言語と心理の両面からの支援を受けている。しかし,言語の通級指導教室が殆どない中学校へ入学した時点で,この特別の支援は中断してしまう。我々は三論文を通して,ことばの教室における教師と子どもの相互交渉を分析し,よりよい関係を確立するための教師の留意点を報告した。障害の有無にかかわらず,思春期は自己をみつけ悩みながら,自己概念や自尊感情を築き上げる時期である。たとえ,小学校でよい関係を培ったとしても,中学校において吃音を持つ人としての支援がなければ,吃音のある中学生は一人で吃音について悩み,ネガティブな自己概念を作り上げる危険性を抱えている。本研究は,思春期の吃音児の実態や支援に対する要望を把握することを目的とし,2つの調査を実施し,その結果を報告するものである。調査1は,通級指導教室を持つ公立小学校657校に対して行われた。そのうち,小学校の通級指導教室の指導を終了し,自己概念尺度および吃音指導,直面している問題,相談する相手などに関する質問紙に回答することに同意した吃音のある中学生12名と彼らを指導した小学校通級指導教室の教師が本研究の対象である。生徒はみな卒業時に,「指導を受けなくても,もう大丈夫」と言っていた。生徒が記入した調査結果に対して,教師のコメントや分析を求めた。結果は以下の通りである。1) 対象者は全て小学校時代に「もう大丈夫」と言った生徒たちであったが,約半数の生徒は再び吃音を気にして,中学校でも支援を受けたいと思っていた。2) 対象児の中には,吃音に対し十分な指導を受けられなかったと不満を感じている者がいた。調査2は,調査1の参加者である一名の生徒を対象に,小学校4年生からの約3年間の追跡調査である。結果次の通りである。1) 彼の自己評価に影響を及ぼしていた要因は,学級の雰囲気,学校における経験,教師や親からの支援であった。2) 彼の中学校の全生徒は同じ小学校出身であったため,彼は良好な友人関係の中で中学生活をおくっていた。しかし,中学校にことばの教室があるならば,そこで支援を受けたいと感じていた。
- 著者
- 兼村 星志 柴田 昌三
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.473-478, 2018
<p>This research investigates the technique for cherry trees maintenance in the early 20th century by literature, especially articles of "Sakura- Japanese Cherry Blossoms (Journal)" (1918-1943) which was published by Society of Cherry Tress. As a result, the total number of articles was 444, and these included 47 articles about technique for cherry tree maintenance. These 47 articles mainly revealed the following 5 categories: "Pruning", "Fertilizing", "Planting", "Conservation", and "Pests Management". In addition, the contents of descriptions in 47 articles were fundamentally equivalent to the present recognition. However, some technique had been evolving from the early 20th century to present with diversifications of machinery and materials. The results and considerations in this research are important for keep improving the technique of cherry trees maintenance in the future.</p>
2 0 0 0 瀬島龍三と宅見勝「てんのうはん」の守り人
- 著者
- Ahmad H. Alghadir Sami A. Gabr Farag A. Aly
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.7, pp.2029-2033, 2015 (Released:2015-07-22)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 24 30
[Purpose] The purpose of this study was to evaluate the effect of 4 weeks moderate aerobic exercise on outcome measures of saliva stress hormones and lactate levels in healthy adult volunteers. [Subjects and Methods] Sixteen healthy students with an age range of 15–25 years participated in this study. The participants performed an exercise test of moderate intensity for 4 weeks, three times per week. The exercise was treadmill walking. Saliva concentrations of cortisol, testosterone and lactate dehydrogenase (LDH) were measured before and after the 4 weeks of moderate aerobic training using immunoassay techniques. [Results] After 4 weeks of exercise, there were significant increases in cortisol, free testosterone levels, and LDH activity along with a significant decrease in the ratios between testosterone and cortisol levels. No significant correlations were found among the studied parameters in the resting stage, a result which supports the positive effect of exercise on stress hormones following 4 weeks of training. [Conclusion] The results suggest that four weeks exercise of moderate intensity significantly affects the salivary stress hormones of young healthy volunteers. The data support the importance of salivary stress hormones as potential biological markers especially for older ages. However, more research is required to validate these biological markers which determine the host response to physical activity.
2 0 0 0 OA デューイ「心理学における反射弧の概念」 : この古い論文の再評価
- 著者
- 石原 岩太郎 Iwataro Ishihara
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.12-25, 1965-01-10
2 0 0 0 OA 新修シェークスピヤ全集
2 0 0 0 OA 犬鳴村のうわさ考 : 「負」の自然を「仰ぎ見る行為」としての犬鳴村のうわさ
- 著者
- 鳥飼 かおる トリカイ カオル Kaoru Torikai
- 雑誌
- 異文化コミュニケーション論集 = Intercultural communication review
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.81-90, 2016
2 0 0 0 OA 高校野球におけるサイン盗みに関する調査報告
- 著者
- 谷所 慶
- 出版者
- 日本生涯スポーツ学会
- 雑誌
- 生涯スポーツ学研究 (ISSN:13488619)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.77-84, 2021 (Released:2022-01-29)
The sign steeling in baseball is the observing and relaying of signs given by the opposing catcher to the pitcher, and this illegal action is reported frequently. The purpose of this study was to research the existing situations in Japanese high school baseball, and to investigate the coaches and players attitude to sign steeling. A questionnaire survey was conducted on 258 university male students who belonged to baseball club when they were high school students. The main contents of survey were following; highest competitive result, presence or absence of experience of sign steeling, effectiveness of sign steeling, and attitude to sign steeling of coaches and players. As a result, 85 out of 258 students carried out sign stealing (32.9%), and 74 out of 85 students answered that it was effective (87.0%). There is no significant relationship between competitive result and experience of sign steeling, therefore sign steeling was carried out at any competitive level. We conducted a Chi-square test and the results revealed significant relationship between the attitude to sign steeling of coaches and the experiences of sign steeling (p<0.01). These results indicated that the sign steeling in Japanese high school baseball can be reduced by coaches’ attitude to prohibition against sign steeling.
2 0 0 0 OA 昭和初期の和洋折衷華族住宅に関する考察 細川護立邸を通して
- 著者
- 奥冨 利幸 富松 幸恵 林 真由子 山口 明日香 山田 裕樹
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校
- 雑誌
- 小山工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02882825)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.177-186, 2004-03-05 (Released:2021-01-21)
2 0 0 0 凶悪犯罪の現状と対策
- 著者
- 法務省法務総合研究所編
- 出版者
- 大蔵省印刷局
- 巻号頁・発行日
- 1996