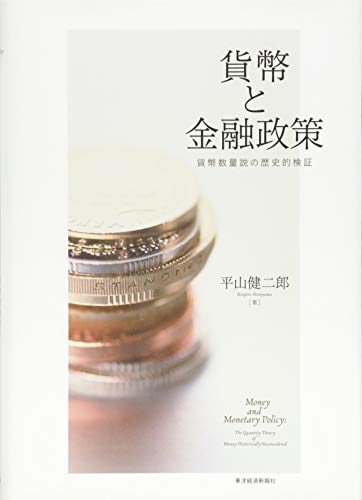2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1950年07月31日, 1950-07-31
2 0 0 0 貨幣と金融政策 : 貨幣数量説の歴史的検証
2 0 0 0 OA 「スタンダード化」時代における教育統制レジーム
- 著者
- 仲田 康一
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.9-26, 2018 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 29
The concept of ‘Standards’ has been featuring more and more in recent education policy in Japan. Many kinds of ‘standards’ are being set to control educational processes and reframe teachers’ professional expertise.‘Standards’ in Japan usually comprise lists, matrixes, and rubrics as official documents that are prescribed by governments and/or schools. They, for instance, tell teachers how to structure every lesson, dictate how to discipline students’ behaviour, or define the teachers’ standard competences required for each age group. As they tend to cover the relationships between teachers, students, and parents, it seems to be the case that they even regulate accordingly how students and families should be.This trend has to do with the growing effect of a PDCA cycle that has prevailed throughout the country. Under the New Public Management regime, the central government is supposed to be legitimated to set national objectives for education, to delegate their implementation to local governments, schools and teachers, and to hold them accountable for producing appropriate outcomes. The celebrated technology in this regime is the PDCA cycle. It requires each local government and school to create their ‘Plans’ reflecting on the higher-level government / institution, and to make their educational processes more effective. Because the ‘Plan’ is unquestionable in this regime, PDCA allows local governments and schools only to ask students and teachers to perform in a ‘Planned’ i.e. a predicted and predetermined way. We can understand the rapid rise of ‘standards’ as a representation of the desire for more predictability, shaped by the threat of PDCA.Meanwhile, standardisation has also had a considerable effect on the Anglo American education systems. This trend covers a range of education reforms such as the following -- i) more emphasis on the learning outcomes assessed by testing ; ii) endogenous privatisation that is forcing schools to act more like businesses with discrete dichotomy of failing or successful schools and/or teachers ; iii) exogenous privatisation from outsourcing teaching materials, selling/buying school improvement strategies, through to inviting private bodies to operate schools ; and iv) de-professionalisation that remakes the teaching expertise as a production process of appropriate data.As we can see, there are divergences and parallels between Japan and Anglo-American countries. I characterised the Japanese version of standardisation as ‘governing by templates’, compared with the Anglo-American version of standardisation as ‘governing by data’ with more emphasis on evidence and corporatisation. At the same time, mutual undermining of professionalism and democracy has been replicated, placing far more importance on external standards. I also added a caveat that ‘governing by templates’ and ‘governing by data’ are not mutually exclusive. With more emphasis being put upon ‘evidence-based policy making’ in Japan, I asserted that we need rather to focus on the complicated nature of the interactive effect of them.
2 0 0 0 OA 合併以降の都市計画の変遷と都市の変容
- 著者
- 片柳 勉
- 出版者
- The Tohoku Geographical Association
- 雑誌
- 季刊地理学 (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.1-16, 2000-03-01 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 21
吉原市, 旧富士市, 鷹岡町の2市1町による対等合併が行われた静岡県富士市を事例として, 合併以降の都市空間の変容と都市計画との関係を明らかにした。合併交渉の過程で最も大きな障害となったのは吉原市と旧富士市の確執であった。この両市の確執は, 合併後の都市計画の方針に大きく影響を与えることになった。新富士市では, 工業整備特別地域の指定のもとで工業開発が優先されるなか, 合併後の多極構造を解消することを目的として, 吉原, 富士の両既成市街地間における新都心の建設計画が策定された。これは, 吉原, 富士旧両市のバランスを考慮した結果であり, その後の富士市の都市形成に大きく関わっていくものであった。吉原, 富士の両市街地間では, 行政主導により土地区画整理事業が進められ, 各種公共施設が重点的に設置されていった。これにより行政・文化機能を有する新市街地が形成され, 当初分離していた吉原, 富士の両人口集中地区も連接した。一方で, 既成市街地の再開発が継続して行われていった。富士市では合併以降に公共事業の地域的分散が進み, 市街地の形態や中心性の面でより分散した様相を呈するようになったといってよい。
2 0 0 0 OA ビタミンCは尿路結石のリスク因子か?
- 著者
- 山本 憲朗 石神 昭人
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.10, pp.575-578, 2013-10-25 (Released:2017-08-10)
2 0 0 0 OA 電気機械工業における1企業グループの生産工場の展開と機能変化
- 著者
- 北川 博史
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.12, pp.858-881, 1994-12-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 2 2
電気機械工業における複数立地企業の事業所展開について1企業グループを単位とした生産工場の展開を分析し,生産工場の機能的な変化を考察した.国内生産工場の設立は1960年代後半から1970年代前半と1980年代の2時期に集中し,海外においては国内生産工場の設立時期直後に集中する.国内生産工場は製品別に事業グループをなし,企業内分業が行なわれている。本社を中心とした首都圏とその周辺には各事業グループの統括工場や最終組立工場の集積がみられる一方で,国土縁辺地域においては,相対的に労働集約度の高い部門に特化する.R&D機能のなかで開発・設計機能は首都圏とその周辺に限定されるが,最終組立工場へ開発・設計機能の一部が移管される傾向にある.一方,国土縁辺地域においては,生産技術開発部門の移管が積極的に行なわれているが,企業内組織のなかでは依然として分工場としての位置にある.
2 0 0 0 OA RFプラズマCVD法により作製したDLC薄膜の熱電性能評価
- 著者
- 中村 雅史 原口 忠男 内山 賢
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.325, 2010-04-01 (Released:2010-11-11)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 2
This paper presents an investigation of the thermoelectric performance of DLC films deposited on glass substrates using RF plasma CVD method. The respective thermoelectric performances of Si-doped DLC film and non-Si doped DLC film were evaluated and compared. The DLC films showed a Seebeck effect, and they had p-type semiconductor characteristics.The values of DLC films’ Seebeck coefficients were 1/5 - 1/100 compared to those of the conventional thermoelectric materials. At temperatures of 80-200°C, the Seebeck coefficients of Si-doped DLC and non-doped DLC were almost identical. The resistivity value of DLC films decreased exponentially with increasing temperature. Furthermore, the DLC film values were much larger than those of conventional thermoelectric materials: 105 to 1010 times larger. The thermal conductivity of DLC films was about one-half that of conventional thermoelectric materials at room temperature. The results presented above suggest that reducing DLC film resistivity through control of deposition conditions, doped element composition, and other means must be examined to raise the thermoelectric performance of DLC film.
2 0 0 0 OA 橈側皮静脈穿刺時の橈骨神経損傷リスクについてのボランティア研究
- 著者
- 小高 光晴 後藤 沙彩 田畑 春奈 岡村 圭子 安藤 一義 小森 万希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.340-342, 2020-10-25 (Released:2020-10-28)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 出羽 寛
- 出版者
- 北海道大学農学部演習林
- 雑誌
- 北海道大學農學部 演習林研究報告 (ISSN:03676129)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.105-119, 1975-11
2 0 0 0 渋川市誌
- 著者
- 渋川市市誌編さん委員会 編
- 出版者
- 渋川市
- 巻号頁・発行日
- vol.第3巻 (通史編 下 近代・現代), 1991
2 0 0 0 OA 明治四十二年栃木県特別大演習紀念写真帖
2 0 0 0 OA 日本野球史
- 著者
- 国民新聞社運動部 編
- 出版者
- 厚生閣書店
- 巻号頁・発行日
- 1929
- 著者
- 作田 妙子 守谷 恵未 大野 友久 山田 広子 岩田 美緒 角 保徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.323-330, 2019-07-25 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 15
目的:化粧療法は要介護高齢者や認知症患者に対して実施されているが,現場のニーズについての報告はない.本研究では医療従事者を対象に,高齢者の化粧療法に関する現状を把握することを目的とし質問紙を用いて調査を実施した.方法:A県下高齢者専門医療機関(職員数548名)に勤務する化粧が業務に影響すると考えられる医療従事者190名を対象に自記式質問紙法による調査を実施した.職種,性別,年齢について調査し,看護師は病棟勤務看護師を対象とし配属病棟の調査も実施した.高齢者における化粧療法の認識と容認できる化粧内容について質問した.対象者全体での検討以外に,看護師と療法士間,看護師の従事病棟別,性別ごとにも検討を加えた.結果:質問紙は121名から回収した(平均年齢33.3±9.4歳 男性42名 回収率63.7%).看護師55名,理学療法士25名などの職種となった.化粧は気分を良くし生活の質が向上すると考えている者がほとんどだが,化粧療法を初めて知った者が多かった.化粧療法をやってみたい者は全体の半数で看護師や女性はやや多かった.外来患者はほとんどの化粧内容が容認でき,入院患者はスキンケア以外の容認率が低かった.看護師,療法士間で比較したところ,入院患者のファンデーション,アイメイク,頬紅で看護師の容認率が低かった.女性で化粧療法をやってみたいと考える者が有意に多く,入院患者のファンデーションおよび頬紅の容認率が有意に低かった.従事する病棟別では,回復期リハビリテーション病棟では化粧療法をやってみたいと思う者が多く,各化粧内容の容認率が全体的に高い傾向があったが,有意差は認めなかった.結論:化粧療法は生活の質改善に効果があると考えながらも,実施したいという者は半数であった.また,化粧内容により容認率に差があった.化粧療法の現状を把握でき,その普及に資するデータが得られた.
2 0 0 0 OA 小麦農林10号育成の真相と作物育成者の業績評価
- 著者
- 松本 武夫
- 出版者
- 農業技術協會
- 雑誌
- 農業技術 (ISSN:03888479)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.12, pp.533-536, 1973-12 (Released:2011-03-04)
2 0 0 0 OA 日本民話やグリムおよびアンデルセン童話に登場する果実や野菜をはじめとする食物について
- 著者
- 平 智 川野 美保 山崎 雪恵 小岩井 優 宮沢 喜一
- 出版者
- 養賢堂
- 雑誌
- 農業および園芸 = Agriculture and horticulture (ISSN:03695247)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.7, pp.715-722, 2009-07 (Released:2011-04-05)