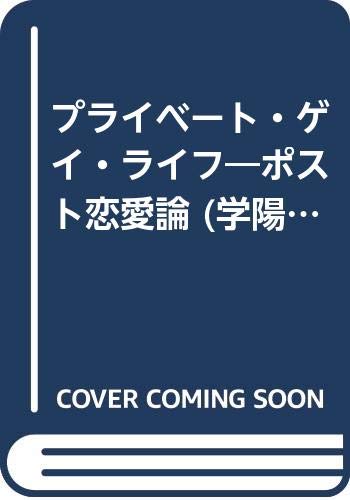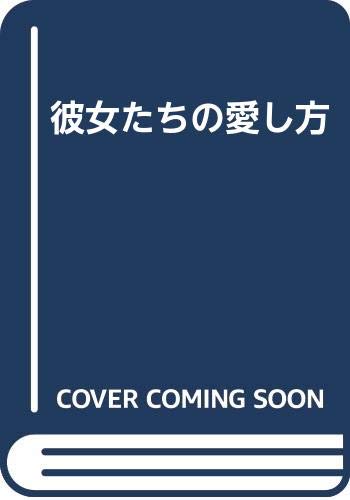2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1923年07月23日, 1923-07-23
2 0 0 0 OA 蛋白分解酵素を調理に利用する研究 (第1報)
- 著者
- 宮井 ふみ 石塚 盈代
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.6, pp.413-417, 1968-12-20 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 4
1. 実験範囲内において酵素濃度の対数と肉の硬度はある範囲内において直線的な関係にあり、硬度4~5を与えるロース肉程度の軟化には肉片10gについて酵素量2,500 P. U./ 10mlが適当である。2. 室温 (16~28℃) における酵素作用時間の影響は、作用時間2時間までは急激に肉軟化が増大し、作用時間3時間以降変化がみられない。実際の調理にあたっては、30分~1時間が適当と考えられる。3. 酵素作用は溶液として浸漬する方法と、乳糖を賦形剤として粉体をまぶす方法との間に差異は認め難く、実用面では粉体の使用が有利と考える。4. 可溶性蛋白、ペプタイドの生成量値は、使用酵素量増加と共に増加し、官能検査で得られた測定値と一致するため、肉軟化は肉蛋白の分解によるものと考える。5. 調味料のみによる肉の硬度は、調理至適濃度範囲においていずれも7以上で硬く、充分でない。常用食塩量ではパパインの活性低下を起さない。他の調味料も酵素の肉軟化に殆んど影響を与えない。6. 煮物、スキヤキ調理において酵素量250 P. U./10ml作用後、調味料を用いることにより、良好な風味と、硬度4.5~5.0のロース肉と変らない軟らかい肉を得ることができた。本研究は第16回日本家政学会に報告したが、その後、別所のくもの巣かびの産出する酸性プロテアーゼの肉軟化作用および旨味生成作用が、植物酵素に比較して良いとの報告を知った。調味添加剤として有害作用をもつ物質の混入の危険性ならびに使用上の簡易化などを考慮しながら、日本食における肉調理に酵素剤を広く実用化する目的で、更に私共は研究を続けている。
2 0 0 0 OA 顎関節症に対する葛根湯の使用経験
- 著者
- 佐野 和生 荒木 正弘 小川 晶子 簔田 雄二 寺崎 宏 村上 秀樹 二宮 秀則 弘中 亮治 伊東 弦 北村 晃 井口 次夫
- 出版者
- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.1684-1690, 1987-08-20 (Released:2011-07-25)
- 参考文献数
- 17
Thirty patients with the temporomandibular disorders were treated with “Kakkonto”, one of the most famous traditional drugs for chronic diseases with pain.“Kakkon-to” was given orally in a dosage of 7.5g 3 times daily before meals for two weeks. Clinical evaluation was carried out at seventh and fourteenth day after administration about spontaneous pain, pain with jaw movement, muscular tenderness, complications, and side effects. These symptoms were rated on a scale of 0 to 3 (0=no symptom and 3=severe). Two cases were dropped because of further administration of another analgesic for severe temporomandibular joint pain. 22 of 28 (78.6%) patients were improved at the therapy completion. 6 cases (21.4%) showed significant improvement, most of those had complications such as stiff shoulder and headache. Side effects were observed in 5 cases, such as slight nausea, vomiting and so on. It is suggested that “Kakkon-to” is a useful drug for temporomandibular disorders.
2 0 0 0 OA 「悪」の脱存在論化 : カントの宗教論を再構成する一試論
- 著者
- 箭内 任
- 出版者
- 尚絅学院大学
- 雑誌
- 尚絅学院大学紀要 (ISSN:13496883)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.1-15, 2012-07
The purpose of this paper is to reconsider Kant's philosophy of religion, and reconstruct it in the context of the modern secular society. In particular, I would like to consider this problem referring to "Religion within the Limits of Reason Alone"(1793). The first point that requires clarification is Kant's thought of "radical evil." The second argument concerns the theory of religion , especially of the concept of "evil" in reference to the secular society. So, it is concluded that it should be characterized from the point of the postmetaphysical thinking and the secular stage of modern age.
2 0 0 0 OA 季節を祝う食べ物 : (3) 新年を祝う十二種若菜
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学生活科学 = DWCLA human life and science (ISSN:13451391)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.78-89, 2012-02-20
資料
2 0 0 0 OA 地震の長期予測と東北地方太平洋沖地震
- 著者
- 遠田 晋次
- 出版者
- 日本混相流学会
- 雑誌
- 混相流 (ISSN:09142843)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.4-10, 2012-03-15 (Released:2012-06-20)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
The 2011 M9.0 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (Tohoku-oki earthquake) brought a great impact on the long-term forecasting of subduction earthquakes around the Japanese islands. Short historic data together with dogmas of modern seismology, such as conventional asperity model, characteristic earthquake model, and earthquake scaling law prevented us to have anticipated the size of M9 earthquake offshore Pacific coast of Tohoku. It may suggest that longer than 1000-year earthquake occurrence history is required to properly evaluate the size and frequency of mega-thrust events, same as the M~7 destructive earthquakes associated with inland active faults. The Tohoku-oki earthquake has significantly changed the state of crustal stress in northeast Honshu island from EW compression to EW extension, in which numerous widespread triggered earthquakes have been occurring. Here I introduce the coseismic stress transfer due to the Tohoku-oki earthquake onto the major active faults, and then demonstrate the importance of the transient changes of state of stress on the faults for long-term earthquake forecasting during the next few decades.
2 0 0 0 OA 2型糖尿病患者における教育入院後の外来通院状況
- 著者
- 本田 佳子 上月 正博 村勢 敏郎 佐藤 徳太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.355-361, 2004-05-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
糖尿病管理の問題点を明らかにすることを目的に, 糖尿病教育入院患者について, インスリン治療者および臨床データが不充分な患者を除いた, 男性360名 (年齢49±10歳) を対象に, 退院後の外来通院状況について追跡調査した. 24カ月の追跡期間中に通院を中断しその後1年以上にわたって通院していない通院中断例は1796, 追跡期間中に通院を中断しその後再び通院している中断後継続例は1896, 他院で治療を続けている継続通院例は2296, 継続通院例は4396であった, 通院中断者のHbAlc値は, 通院中断直前まで, 継続通院者に比して差はなくコントロールされていたが, 一旦中断した後はHbA1c値は有意に上昇していた. 通院中断の理由については, 転勤, 待ち時間が長い, 仕事が忙しくなった, 自覚症状がないので, 生活環境の変化, 医療側の対応の問題, 糖尿病療養への教育の問題等が混在していた.
2 0 0 0 ジェンダーで読む愛・性・家族
- 著者
- 岩淵宏子 長谷川啓編
- 出版者
- 東京堂出版
- 巻号頁・発行日
- 2006
- 著者
- 鳥居 洋祐 大西 崇文 長友 忠相 佐藤 元 中村 純子 鳥居 良貴 森井 英一 廣田 誠一
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.221-227, 2018-03-25 (Released:2018-03-27)
- 参考文献数
- 8
グロコット染色は一般に,銀液の温度や反応時間の設定が難しく,施行者間での染色性に差が生じやすい。特にメセナミン銀液を用いる従来法ではその傾向が強いことから,銀液の反応時間の許容範囲が大幅に広く,また塩化金液による菌体の染色性を調節することができるクロム酸アンモニア銀法を用いることで施行者間での相違が少なくなることが期待される。しかし,これまでには温熱下での銀液反応時間の設定や,真菌ごとの至適条件の検討は十分には行われていない。今回我々は,従来法とクロム酸アンモニア銀法における各種真菌での溶融器と温浴槽を用いた銀液の反応時間および塩化金液の反応時間を比較検討した。検討した真菌はアスペルギルス,クリプトコッカス,ニューモシスチス・イロベチーの3種類で,いずれの真菌でも溶融器を用いた場合に,良好な染色性を示す銀液の反応時間の幅が最も広いことが確認された。また,いずれの真菌においても塩化金液の反応時間を変えることで菌体の色の濃さが調節でき,いずれも1~5分で十分な染色が行えることが明らかになった。溶融器を用いたクロム酸アンモニア銀法によるグロコット染色は,塩化金液での染色時間を真菌ごとに調節することで,施行者間の差の少ない安定した結果が得られるものと考えられる。
2 0 0 0 OA 光合成による酸素発生のはじまりとそのメカニズム
- 著者
- 野口 巧
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.322-328, 2003-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 大熊 宏
- 出版者
- The Mining and Materials Processing Institute of Japan
- 雑誌
- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.1, pp.87-94, 2008-01-25 (Released:2011-01-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4 2
The simulator for geological CO2 sequestration was developed by adding to a commercial compositional oil reservoir simulator the functions of geochemical reactions and fracture occurrence/fault activation. The resulting simulator, GEM-GHG, was verified with a number of validation runs and is believed to be one of the most advanced and robust simulators of this kind today.The simulator was made use of for various purposes throughout the pilot CO2 injection test at Nagaoka, Japan. During the planning stage, the simulation studies were conducted repeatedly to confirm the technical feasibility of the test plan. Once CO2 injection began, the objectives of simulation were history matching and interpretation of the observed injection performances. Reasonable agreement of the bottom-hole pressures and the breakthrough times was attained by varying uncertain parameters such as relative permeability curves, areal changes in permeability, and vertical permeability.The final aquifer model of the history matching was employed to predict the long-term CO2 movement. The results implied that the CO2 movement would be very limited after the end of injection and the injected CO2 would essentially remain within the injection zone in the pilot test area.
2 0 0 0 プライベート・ゲイ・ライフ : ポスト恋愛論
- 著者
- 小西 信之
- 出版者
- 愛知県立芸術大学
- 雑誌
- 愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi University of the Arts (ISSN:03898369)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.177-189, 2016
2 0 0 0 OA 顔之推伝研究
- 著者
- 佐藤 一郎 佐藤 一郎
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.1-23, 1970-03-30
2 0 0 0 OA 戦国期における勅願寺由緒の形成と展開 : 美濃国立政寺を事例に
- 著者
- 桐田 貴史
- 出版者
- 皇学館大学人文学会
- 雑誌
- 皇学館論叢 = KOGAKKAN RONSO (ISSN:02870347)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.29-49, 2017-10
2 0 0 0 OA M&E編集委員長から
- 著者
- 高井 研
- 出版者
- 日本微生物生態学会
- 雑誌
- 日本微生物生態学会誌 (ISSN:24241989)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.78, 2019-09-01 (Released:2019-09-26)
2 0 0 0 彼女たちの愛し方 : Bye bye sexuality
2 0 0 0 OA 有限要素法の流体力学への応用
- 著者
- 川原 睦人
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 圧力技術 (ISSN:03870154)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.151-156, 1974-05-25 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 14