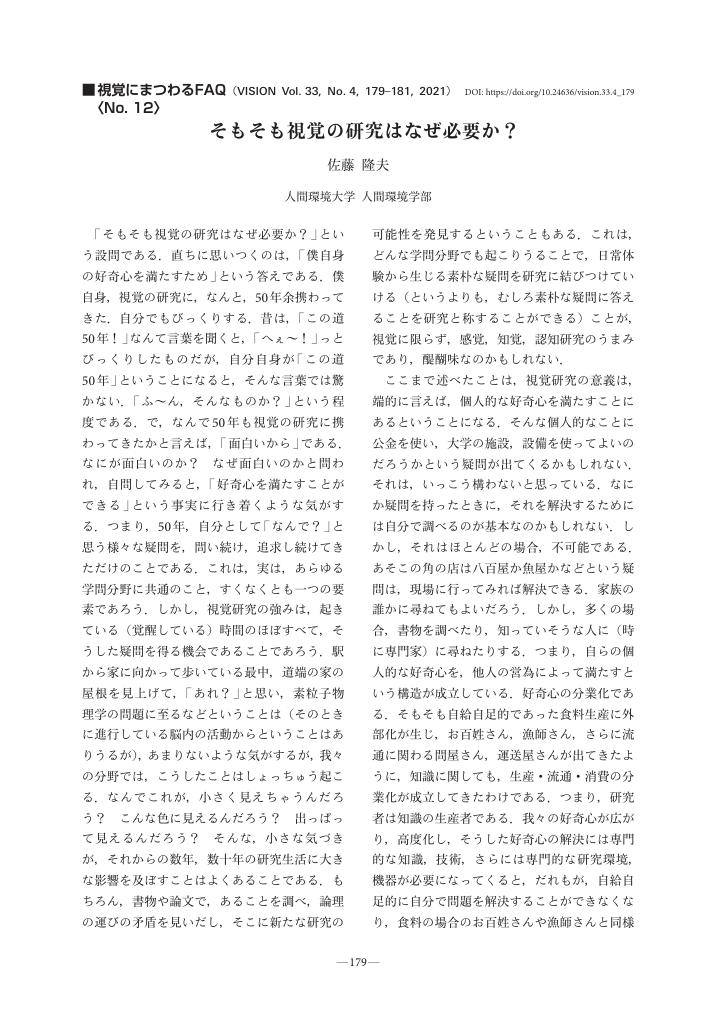38 0 0 0 OA No.12 そもそも視覚の研究はなぜ必要か?
- 著者
- 佐藤 隆夫
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.179-181, 2021-10-20 (Released:2021-10-29)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 佐藤 隆春 大和大峯研究グループ 奥田 尚 佐藤 浩一 竹内 靖夫 南浦 育弘 八尾 昭
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科學 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.403-413, 2006-09-25
- 被引用文献数
- 12
紀伊山地中央部の秩父帯は大峯-大台スラストで四万十帯の構造的上位にある.大峯-大台スラストは弧状および半円形断層で変位している.秩父帯は東西幅30km以上の弧状断層および直径15km以上の半円形断層の内側にみられる.両断層は同心円状の形状を示す.安山岩と安山岩-石英斑岩複合岩脈からなる弧状岩脈群が弧状断層の内側に貫入している.半円形断層の外側に並行して火砕岩岩脈群が貫入する.中生界(秩父・四万十帯)は両断層と火砕岩岩脈群の内側が数百m陥没する.これを大峯・大台コールドロンと命名する.前者は弧状断層で囲まれる.後者は半円形断層と火砕岩岩脈群で囲まれている.これらの特徴はコールドロンが連続して形成された二重のコールドロンであることを示す.コールドロンにともなわれる岩脈群の放射年代はこれらが中期中新世に形成されたことを示す.大峯・大台コールドロンの形成機構は大量の火砕岩の噴出によるピストンシリンダータイプの陥没と考えられ,特に大台コールドロンはトラップドアタイプの陥没と考えられる.紀伊山地中央部の秩父帯はこれらのコールドロンの内側に残存する中生界である.紀伊山地の隆起と侵食により,これらのコールドロンから噴出したカルデラ充填火砕岩層はコールドロンの周囲には残っておらず,カルデラ床を構成していた中生界が露出するにいたった.
20 0 0 0 OA ミニチュア効果 ―画像のぼけと距離と大きさの知覚―
- 著者
- 佐藤 隆夫 草野 勉
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.312-319, 2012-04-01 (Released:2012-04-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
ミニチュア効果とは,街の風景,建物,車など,ある程度の大きさを持つものを撮影した写真で,被写体が,まるでおもちゃを撮影したかのように小さく感じられる不思議な効果である.この効果の要因として最大のものは,中心から周辺に向かって大きくなるぼけである.通常の視覚においてもそうしたぼけは存在するが,ミニチュア効果が生じる写真ではそうしたぼけが誇張されている.誇張されたぼけによって,撮影距離が実際よりも短く知覚され,その結果被写体が小さく感じられる.ここでは,ぼけが視覚に対して,特に,距離知覚に対して持つ効果を視覚心理学的な見地から検討し,ミニチュア効果の生成の原理を考察する.
13 0 0 0 OA 刺激等価性の機能的分析:行動随伴性,関係枠,ネーミング
- 著者
- 佐藤 隆弘
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.333-346, 2008 (Released:2010-02-15)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 5
Three theories have been proposed in behavior analysis to explain the establishment of stimulus equivalence. Sidman's (1994) equivalence relation theory suggests that stimulus equivalence is a fundamental behavioral function caused by reinforcement contingencies, and asserts that learning is unnecessary for its establishment. In contrast, the relational frame theory (RFT) suggests that stimulus equivalence results from previous learning regarding many different stimulus-relationships. On the other hand, the naming theory focuses on the naming process, or the circular relationship between the behaviors of the speaker-listener. The latter two theories hold that verbal learning is necessary for the formation of stimulus equivalence. Moreover, naming theory suggests that equivalence relations are formed by verbal responses, whereas the other two theories suggest that naming is the same behavioral process as equivalence. In conclusion it is suggested that analysis of stimulus function is crucial to understand cognition and language.
10 0 0 0 OA 15パズルの変形とその最大の最短手数に関する研究
- 著者
- 佐藤 隆太郎
- 巻号頁・発行日
- 2021-03
Supervisor: 上原 隆平
- 著者
- 佐藤 隆
- 出版者
- エアワールド
- 雑誌
- Air world (ISSN:02885603)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.66-69, 2012-05
8 0 0 0 OA 胆汁酸受容体TGR5活性化による健康寿命の延伸
- 著者
- 佐藤 隆一郎
- 出版者
- 日本脂質栄養学会
- 雑誌
- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.35-42, 2016-03-31 (Released:2016-05-10)
- 参考文献数
- 9
Bile acids exert anti-obesity and anti-hyperglycemic effects through a G protein-coupled receptor TGR5. In L cells located in the lower small intestine TGR5 activation stimulates secretion of a peptide hormone GLP-1 that enhances insulin sensitivity. In brown adipose tissues and skeletal muscles its activation results in an increase in energy expenditure, leading to anti-obesity effects. Based on these findings, we searched for food factors that mimic bile acid functions, and identified a citrus limonoid nomilin as a powerful agonist for TGR5. Simulation analyses for TGR5-nomilin association and mutation analyses of human TGR5 revealed that TGR5 is capable of biding nomilin through three amino acid residues located in a transmembrane and extracellular domain. Further analyses using transgenic mice overexpressing human TGR5 in skeletal muscles showed that TGR5 activation results in an increase in muscle mass. Taken together, we believe that TGR5 is one of ideal targets for functional food factors to extend healthy life expectancy.
7 0 0 0 OA 公益社団法人日本農芸化学会の取り組み
- 著者
- 佐藤 隆一郎
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.8, pp.8_84-8_85, 2018-08-01 (Released:2018-12-14)
6 0 0 0 OA 少年戦車兵 : 若き鉄獅子
5 0 0 0 OA 中新世の室生火砕流堆積物
- 著者
- 佐藤 隆春 中条 武司 和田 穣隆 鈴木 桂子
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.Supplement, pp.S53-S69, 2012-08-15 (Released:2013-02-21)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 1 6
室生火砕流堆積物は1960年代以降,大規模な珪長質火山活動の噴出物としてとらえられてきた (志井田ほか, 1960など).ここ十数年の間に,火山地質,地質構造,古地磁気方位,化学組成,構成鉱物の特徴など,多面的な研究が進められてきた.これらのデータの多くから室生火砕流堆積物は,熊野酸性火成岩類や中奥 (なかおく) 火砕岩岩脈群などと共通する特徴を示し,紀伊半島中軸部〜東部に形成されたカルデラ火山群が給源火山であることが明らかになった.室生火砕流堆積物の遠方相に対比される石仏凝灰岩層は給源カルデラ群北端から50 km以上流走したと推定される.本巡検では高温で大規模な火砕流堆積物(high-grade ignimbrite)の岩相と縁辺部における岩相を中心に観察し,大規模火砕流噴火の推移を体感してもらいたい.
5 0 0 0 OA 群発地震発生域直上における地殻応力測定
- 著者
- 佐藤 隆司 楠瀬 勤一郎 長 秋雄 木山 保 山田 文孝 相澤 隆生
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.57-65, 1997-05-28 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 22
Crustal stress measurements by the hydraulic fracturing method were carried out using a 1000m- and a 100m-deep boreholes drilled at Inagawa town, Hyogo prefecture, where earthquake swarm activities with very shallow hypocenters have intermittently occurred since July 1994. On borehole televiewer record, borehole breakouts were clearly observed at a number of depth intervals of the 1000m-deep borehole. The borehole breakout data as well as the hydraulic fracturing data was used to estimate orientation of the maximum horizontal compressive stress.Magnitudes of the horizontal stress down to 700m in depth are comparable to the standard stress gradients with depth in western Japan derived by TANAKA (1986). On the other hand, the maximum and minimum horizontal compressive stresses at about 950m in depth are about 70MPa and 40MPa, respectively, which are about twice as large as the standard stress gradients with depth in western Japan. The maximum horizontal compressive stress below 600m in depth is generally oriented E-W to NW-SE.
- 著者
- 佐藤 隆春 大和大峯研究グループ
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.403-413, 2006-09-25 (Released:2017-07-14)
- 被引用文献数
- 13
紀伊山地中央部の秩父帯は大峯-大台スラストで四万十帯の構造的上位にある.大峯-大台スラストは弧状および半円形断層で変位している.秩父帯は東西幅30km以上の弧状断層および直径15km以上の半円形断層の内側にみられる.両断層は同心円状の形状を示す.安山岩と安山岩-石英斑岩複合岩脈からなる弧状岩脈群が弧状断層の内側に貫入している.半円形断層の外側に並行して火砕岩岩脈群が貫入する.中生界(秩父・四万十帯)は両断層と火砕岩岩脈群の内側が数百m陥没する.これを大峯・大台コールドロンと命名する.前者は弧状断層で囲まれる.後者は半円形断層と火砕岩岩脈群で囲まれている.これらの特徴はコールドロンが連続して形成された二重のコールドロンであることを示す.コールドロンにともなわれる岩脈群の放射年代はこれらが中期中新世に形成されたことを示す.大峯・大台コールドロンの形成機構は大量の火砕岩の噴出によるピストンシリンダータイプの陥没と考えられ,特に大台コールドロンはトラップドアタイプの陥没と考えられる.紀伊山地中央部の秩父帯はこれらのコールドロンの内側に残存する中生界である.紀伊山地の隆起と侵食により,これらのコールドロンから噴出したカルデラ充填火砕岩層はコールドロンの周囲には残っておらず,カルデラ床を構成していた中生界が露出するにいたった.
4 0 0 0 OA インドの農業問題再考
- 著者
- 佐藤 隆広 Sato Takahiro
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学商学論叢 = Fukuoka University Review of Commercial Sciences (ISSN:02852780)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2・3, pp.265-299, 2021-12
4 0 0 0 OA 自殺企図にてグラルギン300単位を自己注射したミトコンドリア病合併糖尿病の1例
- 著者
- 辻野 一三 林下 晶子 渡部 拓 山田 安寿香 佐藤 隆博 板谷 利 高階 知紗 大塚 吉則 清水 祐輔 西村 正治
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.722-728, 2014-09-30 (Released:2014-10-07)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
症例は35歳,男性.糖尿病,うつ病にて当院通院中の平成25年5月,自殺企図にてインスリングラルギン300単位を皮下注したところを家族に発見され,当科へ救急搬送となった.血糖値の頻回モニタリングと経口および静脈内グルコース投与にて,皮下注射から約50時間の経過で重篤な合併症や後遺症なく低血糖状態から脱した.入院中の精査にてミトコンドリア病の診断基準を満たし,うつ病および糖尿病は同疾患によるものと考えた.うつ病と糖尿病の合併は臨床的に重要な問題であり,本報告ではうつ病合併糖尿病の診療上の問題点,インスリン大量投与時の対処と病態,さらにミトコンドリア病の本症例における関与について若干の文献的考察を加え報告する.
4 0 0 0 秋田藩家蔵文書と「戦国時代の秋田」
- 著者
- 佐藤 隆
- 出版者
- 秋田県公文書館
- 雑誌
- 秋田県公文書館研究紀要 (ISSN:13411101)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.14-33, 2011-03
4 0 0 0 OA 健常成人男性における20秒間息こらえ後の呼気ガスと動脈血中酸素飽和度の変化について
- 著者
- 添田 哲平 佐藤 隆裕 角田 圭 長谷川 信 久留利 菜菜 土橋 邦生
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.D3P1517, 2009 (Released:2009-04-25)
【はじめに】近年COPD患者に対する身体への酸素の取り込みを総合的かつ簡便に評価できる20秒間息こらえテストが用いられるようになり、先行研究においては20秒間息こらえ開始後の動脈血酸素飽和度(以下SpO2)の変化についての報告はあるが、そのテストの方法論は確立されておらずメカニズムも解明されていない.今回健常成人男性において、息こらえ時の呼吸の止め方の違いによりSpO2や呼気ガスにどのような変化が起きるか、またその変化がどのような個人因子と関連があるのかについて調べ、20秒間息こらえテストの有用性を検討することを目的とした.【方法】対象者は本研究の目的および内容について説明を行い、紙面にて同意の得られた健常成人男性19名を対象とした.測定項目は、呼気ガス分析装置により、V(dot)E、V(dot)O2、V(dot)CO2、ガス交換比(以下R)、呼吸数、パルスオキシメータによりSpO2を測定した.測定は、端坐位にて、安静3分間、その後息こらえ20秒間、息こらえ終了後の安静3分間についてSpO2は5秒毎に記録し、呼気ガス分析の値は一呼吸毎の値とした.息こらえ時の呼吸の止め方は3条件とし、息をこらえる直前の呼吸を、条件1では最大吸気位、条件2では最大呼気位、条件3では安静吸気位で息こらえを開始することとした.また、アンケートにより身長、体重、運動習慣等を調査した.条件1と条件2の平均の比較にはWilcoxonの符号付順位検定を、条件3での群間比較にはMann-WhitneyのU検定を用い有意水準は5%未満とした.【結果】条件1と条件2の比較では、V(dot)Eの値が呼吸再開後の2回目と3回目の呼吸において、Rの値は呼吸再開後の3~10回目の呼吸において、条件1よりも条件2で有意に高値を示した.また、SpO2の値は、息こらえ開始後の25~50秒にかけて条件1よりも条件2で有意に低値を示し、条件2では一旦低下した後上昇し、息こらえ開始後の65~115秒にかけて安静時の平均値を上回った後、息こらえ前の値に近づいた.条件3については、息こらえ後のRの値が1を超えずに徐々に回復する群(以下A群、n=11)と、1を超えた後徐々に減少し回復が見られる群(以下B群、n=8)の2群に分けられ、V(dot)Eの値が呼吸再開後の2回目と4回目の呼吸において、またRについても3~12回目の呼吸においてA群よりもB群で有意に高値を示した.SpO2の値は、B群では値が低下後に上昇し息こらえ開始後の55~100秒にかけて安静時よりも高い値を示した.運動習慣については、A群よりもB群において有意に運動習慣が少なかった.その他のアンケート結果には2群間に差は認められなかった.【まとめ】安静吸気位での20秒間息こらえテストは、そのSpO2の値の変化が運動習慣の違いを反映し、本テストが運動習慣を評価する指標として有用である可能性が示唆された.
4 0 0 0 OA フラクタル画像解析の細胞診断への応用
- 著者
- 高安 秀樹 佐藤 隆 横山 俊朗
- 出版者
- 日本医用画像工学会
- 雑誌
- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.587, 1997 (Released:2016-03-16)
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 日浅 崇馬 佐藤 隆紀 風間 英気 明 愛国 下条 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2017 (ISSN:24243124)
- 巻号頁・発行日
- pp.2P1-K06, 2017 (Released:2017-11-25)
Within limbs of typical animals, there are bi-articular muscle-tendon complex crossing two joints. In particular, it is known that the bi-articular muscle-tendon complex between hip joint and knee joint contributes to the dynamic motion such as high jumping and fast running. This realizes transfer of the torque between the two joints and storage and reuse of the elastic energy. In this paper, we introduce the muscle-tendon complex between hip joint and knee joint to the hind legs of the quadruped robot. In the vertical jump simulation, we confirmed that the mechanism enabled the leg to transfer the torque between the two joints and the leg with the mechanism realized higher jump than the one without it. A prototype of the mechanism has been fabricated also.