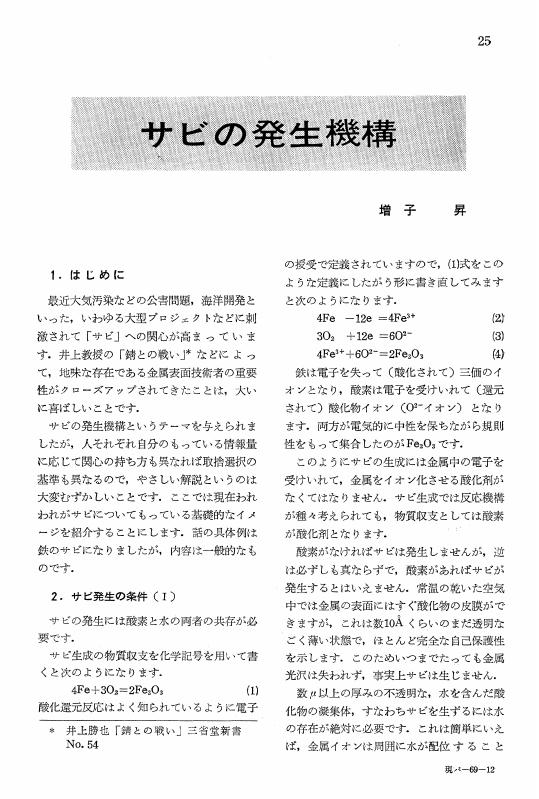53 0 0 0 OA 1945 年ルーズベルト呪詛説に関する一考察
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.43-48, 2019-07-07 (Released:2022-10-03)
- 参考文献数
- 1
26 0 0 0 OA 「とんかつ」の受容と変容に関する一考察 ‐先行研究の再検討を中心に‐ 1.はじめに
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.3-11, 2019-12-24 (Released:2019-12-24)
- 参考文献数
- 15
“Tonkatsu” is a dish in that pork loin and fillet are fried in cooking oil with flour, beaten egg and bread crumbs.This is one of the best “Yoshoku” In Japan .There are various theories about the origin of “Tonkatsu”.In this study, previous research on the origin of“Tonkatsu” is to be reviewed. . In addition, the study aims at considering the origin of the “Tonkatsu” as a street food which has not been discussed so far.
19 0 0 0 OA 苦学生よ!屋台をひこう! ―苦学ブームの中での屋台と大衆化―
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.78-83, 2021-07-11 (Released:2022-07-25)
16 0 0 0 OA 魚を喰うから日本は強い ―中村吉次郎『日本人と魚食』にみる魚食強兵と魚食報国―
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.84-88, 2021-07-11 (Released:2022-07-25)
14 0 0 0 OA 視点を変えた「謎の4世紀」 朝鮮側の資料から日本の「謎の4世紀」を探る
- 著者
- 増子 哲央
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.6, pp.1-9, 2017 (Released:2019-04-20)
- 参考文献数
- 9
14 0 0 0 OA 創られた戦争美談 -肉弾三勇士と戦争美談-
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.27-35, 2015-12-25 (Released:2015-12-30)
- 参考文献数
- 3
With the start of the “Fifteen-Year War” against China by the outbreak of the Manchurian Incident on September 18, 1931, the press reports of the period came to be focussed on military operations in mainland China. The nation-wide hurly-burly in wartime, brought about by dramatic changes of the social situation, prepared a way to the establishment of war footing. In this atmosphere “Sensou Bidan” or “amazing stories of self-sacrificing warriors” were fabricated to “applaud their valiance.” Was it the State Power that forced the press to invent such tales? Or was it the press which prepared the path to this propagation? In order to see that the state power and the press went hand in hand in each stage of the war, I will take up “Nikudan Sanyushi” ( “In Praise of the Three Suicide-Bombing Heroes”) which marked the summit of the campaign.
10 0 0 0 OA 変化するラーメン像 ‐ラーメンにおける「中華」と「和」のイメージの変遷‐
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.12-23, 2018-12-23 (Released:2018-12-25)
- 参考文献数
- 11
“Ramen” is now different from Chinese noodles originated in mainland China and develop itself into a Japanese food with diversity. On the other hand, back in 1980s, Japanese Ramen had little diversity – basically on the premise of Chinese elaboration - than that of today. Then 1990s showed a gradual change on it when a concept of “Wa” (=Japanese spirit of harmony) was brought into Ramen with more recreational value of food and in that process, it became something emphasizes “Japanese tradition” instead of Chinese elaboration.Here we take a look at this “Ramen transition” in Japan from a viewpoint of both “Chuka” (=Chinese) and “Wa”images with time series analysis.
9 0 0 0 OA マカオカジノ産業における構造変化 -転換点としての対外開放-
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.26-36, 2016-12-25 (Released:2016-12-26)
- 参考文献数
- 10
Macau overtook Las Vegas in sales of casinos in 2006. Up to the present day, many observers have attributed the remarkable success of the city to its open-door policy to capital investment from abroad. They assert that the revitalization and institutionalization of casino facilities effected by accepting foreign capital is the most important factor that has directly led to the success of Macau casino. By critically examining their views, this paper will concentrate on the structural changes of the Macau industry brought about by opening its doors to the outside world, and consider other factors that account for Macau' success.
8 0 0 0 OA 日本化する叉焼 -我が国における叉焼の受容と変容-
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- 国際情報研究 (ISSN:18842178)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.39-49, 2017-12-24 (Released:2017-12-24)
- 参考文献数
- 16
In many places of Canton, China, barbecued pork, Char sui, is greatly favored, and is loved much more deeply than Siu mei, that baked pork, goose, or duck which has been popular and prevalent in Guangzhou, Hong Kong, Macao and other cities of Canton. In Japan, Cha shu, also barbecued pork that came from China, is a side dish like boiled or grilled pork and yet is now much different from the Chinese original. By surveying Chinese cuisine books published in Japan, this study examines how the original pork cooking has been rearranged to meet the needs of Japanese palate.
8 0 0 0 OA 運動器疾患に対するストレッチングの効果
- 著者
- 森山 英樹 増子 潤 金村 尚彦 木藤 伸宏 小澤 淳也 今北 英高 高栁 清美 伊藤 俊一 磯崎 弘司 出家 正隆
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.1-9, 2011-02-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 5
【目的】本研究の目的は,理学療法分野での運動器疾患ならびに症状を対象としたストレッチング単独の有用性や効果を検証することである。【方法】関連する論文を文献データベースにて検索した。収集した論文の質的評価を行い,メタアナリシスあるいは効果量か95%信頼区間により検討した。【結果】研究選択の適格基準に合致した臨床試験25編が抽出された。足関節背屈制限,肩関節周囲炎,腰痛,変形性膝関節症,ハムストリングス損傷,足底筋膜炎,頸部痛,線維筋痛症に対するストレッチングの有効性が示され,膝関節屈曲拘縮と脳卒中後の上肢障害の改善効果は見出せなかった。【結論】現時点での運動器障害に対するストレッチングの適応のエビデンスを提供した。一方,本結果では理学療法分野でストレッチングの対象となる機能障害が十分に網羅されていない。ストレッチングは普遍的治療であるからこそ,その有用性や効果を今後実証する必要がある。
6 0 0 0 OA 「行為」としての賽銭
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.25-33, 2022-07-24 (Released:2022-07-26)
- 参考文献数
- 2
At the beginning of the year, Japanese people have an event to worship at shrines and temples called the “Hatumoude”. At the first visit, we give thanks for the year and pray for the safety and peace of the new year. One of the actions to be taken at the time of this first visit is the action of "throwing" money.This act is seen not only at the time of the first visit but also when asking God or Buddha to grant some wish.It can be inferred that the so-called offering is not compulsory and is one of the voluntary actions of each individual. Where does this motive come from? Why do people throw money in front of the money box?
5 0 0 0 OA マゴットセラピーを受けた患者の心理面における変化
- 著者
- 増子 寛子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.215, 2007 (Released:2007-12-01)
<はじめに>マゴットセラピーは治癒しにくい四肢潰瘍に対し無菌マゴット(ハエ幼虫・ウジ)を用い治癒を促す治療方法であり今回、当整形外科においてはじめてマゴットセラピーを受けた患者の心理面の変化を振り返り精神的援助のあり方を考える機会を得たので報告する。 <事例> 73歳 男性 職業:無職 一人暮らし。平成18年12月8日駅で転倒し左脛骨腓骨骨折で入院。平成9年より糖尿病の既往あり。12月14日非観血的骨接合術施行されるも、術後創感染見られ、下肢切断が必要な状態となった。 本人より「足は切りたくない」と要望あり、本人と息子の同意のもと、平成19年1月26日より1クール3週間のマゴットセラピーを2クール施行された。 <心理面での変化の過程>一1クール目、いざ治療が開始されると創部からの悪臭もあり、食欲低下・嘔吐・仮面様顔貌と無口・下肢に対する否定的な言葉・治療の部分を見ようとしない等の心身両面の変化を来たした。治療が終了してから一旦症状が消失したが、7週間後、再度治療を行うと告げられた時点で再び嘔吐、食欲低下等が現れた。 看護介入としては、患者と頻繁に接触して肯定的な態度で対応し、その治療の経過及び予後に対する感情を分かち合い、話し合うようにした。又、創状態が徐々に良くなっていることを細かく伝えるとともに励ますことに努めた。プライバシー保護の為、マゴット使用中は個室対応とした。臭気対策には、部屋の換気回数を多くし、芳香剤を使用した。2クール目にはリハビリ・車椅子散歩・入浴等の介助等積極的に行った。これらにより、2クール目の途中より、徐々に食事量が増加し否定的な言葉が聞かれなくなり表情も和らぎ、処置に対しても協力的になり治療部分に目を向けたり、脱走したマゴットを直視し、つまむ場面も見られるようになった。 <考察>今回の事例は、マゴットセラピーによりボディイメージの混乱を来たし一時的にショックを受け、否定、無関心、抑うつ状態を経て治療終了までに自己のボディイメージの修正が出来たと考える。その経過において看護師自身初めての経験であり、計画的に十分なケアが出来なかった部分もあったが、患者の感情や思いを受容し、認め、励まし、暖かく寄り添う看護の基本的な態度が適応過程での助けになったのではないかと考える。 マゴットセラピー施行患者の看護においては、このよう心理的な反応があることも予測し、感情の変化の過程を注意深く観察し、その過程に応じた有効な援助を行なう必要があることを学んだ。今後も安心して治療を行ってもらえるための有効な援助を追及していきたい。
5 0 0 0 過去50 年間の北浦における魚類相の変遷
- 著者
- 大森 健策 加納 光樹 碓井 星二 増子 勝男 篠原 現人 都築 隆禎 横井 謙一
- 出版者
- 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- pp.18-019, (Released:2018-08-20)
- 参考文献数
- 64
Large-scale Japanese lakes support many fish species and abundant fisheries resources. However, long-term changes in the fish fauna of such lakes have not been fully investigated, despite recent significant anthropogenic impacts on associated ecosystems. Accordingly, the extensive native and non-native fish fauna of Lake Kitaura, a typical large inland-sea lake (36 km2) in eastern Japan, was investigated based on specimens collected by the staff of Itako Hydrobiological Station, Ibaraki University from 1977 to 1997, plus data from previous studies conducted since the 1950s. In total, 83 species in 35 families have been recorded from the lake from the 1950s to the present decade. The analyses of long-term changes in fish species data since the 1960s demonstrated a sharp decrease in marine, estuarine and diadromous species due to an estuarine barrage (Hitachi River floodgate) established in 1973, the disappearance of nine red-list species (e.g., threatened and near threatened species) following various artificial environmental changes from the 1960s to 1980s, and an increase in introduced exotic and Japanese species after the 1980s.
4 0 0 0 OA 天津飯の起源 ―定説を疑う―
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.52-57, 2018-07-08 (Released:2022-10-04)
Tianjin Rice does not exist in China. Tianjin Rice is a dish arranged in Japan.It is unknown why the name Tianjin was named. Tianjin rice is just a thing that puts a crab meat with eggs on the rice. This paper aims to reexamine the theory so far.
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.JO47-52, 2023-07-23 (Released:2023-07-23)
3 0 0 0 AIによるESG情報分析と評価モデルに関する総合的研究
- 著者
- 中尾 悠利子 石野 亜耶 國部 克彦 田中 優希 西谷 公孝 岡田 華奈 奥田 真也 Weng Yiting 増子 和起 越智 信仁 牟禮 恵美子 大西 靖 北田 皓嗣
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2022-04-01
既存のAI(人工知能)を活用したESG(環境・社会・ガバナンス)評価研究では,ESG投資を既存の財務投資のパラダイムの下で発展させることは可能であっても,ESG投資の本来の目的である社会や環境への貢献を目指した投資の側面を発展させることには大いに限界がある。そこで,本研究では,ESG投資の本来の目的に立ち返り,どのようにすれば,AIによって,このようなESG投資のために情報開示における多様性をさらに発展させて,社会の改善につなげることができるのかを学術的問いとし,探求する。
3 0 0 0 OA コケ植物の絵画的考察
- 著者
- 増子 真有
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 蘚苔類研究 (ISSN:13430254)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.12, pp.310-315, 2023-07-10 (Released:2023-08-10)
コケ植物は植物の中でも特徴的な生態や外見を持ち合わせており,絵画や彫刻,あるいはインスタレーション作品においても主たるモチーフになり得る植物であると筆者は考える.種による形態や色彩の差はもちろん,同種でも視点を変えるたびに異なる側面をあらわす植物であり,マクロ・ミクロの両視点において違った魅力や印象を与えるため,表現に落とし込む際に作品や作家ごとに多様性が生まれるであろう.今後も美術作品におけるコケ植物の扱い方について考察を深めていきたい.
3 0 0 0 OA サビの発生機構
- 著者
- 増子 昇
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 金属表面技術 現場パンフレット (ISSN:03685527)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.12, pp.25-31, 1969-12-15 (Released:2009-10-07)
3 0 0 0 OA アルミニウム製錬技術の現状
- 著者
- 増子 曻 眞尾 紘一郎
- 出版者
- 一般社団法人 軽金属学会
- 雑誌
- 軽金属 (ISSN:04515994)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.66-71, 2015-02-28 (Released:2015-05-30)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 7 12
- 著者
- 大瀬戸 篤司 近野 敦 増子 弘二 小泉 卓也 内山 勝
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2012 (ISSN:24243124)
- 巻号頁・発行日
- pp._2A1-H10_1-_2A1-H10_4, 2012-05-27 (Released:2017-06-19)
- 被引用文献数
- 1 1
Quad rotor helicopters has simple mechanism and high stability. However, it is not easy for a quad rotor helicopter to fly long time and long distance, because most of the thrust is consumed to lift the body, and hence horizontal component of the thrust is small. In this paper, we present the experimental results of a quad rotor tail-sitter UAV (Unmanned Aerial Vehicle) which is composed of a quad rotors and fixed wing. Developed UAV can hover like a quad rotor helicopter, and can fly long distance like a fixed wing airplane. We designe attitude and altitude control system of the UAV for hovering. In order to verify the designed control systems, we conducted hovering control flight experiment. Additionally, we identified both the impact of propeller slipstream on yaw control and the solutions.