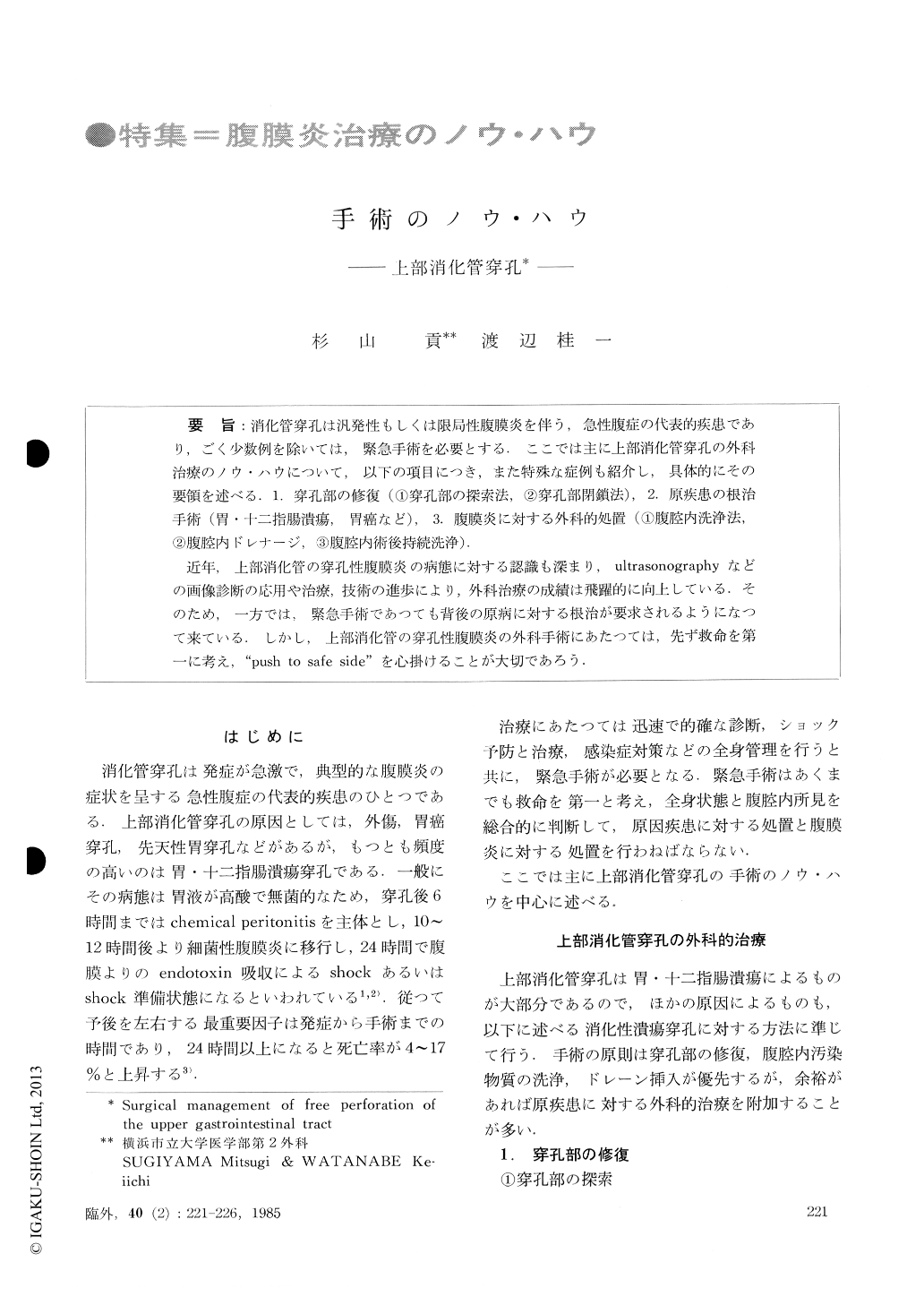615 0 0 0 直腸手術における排尿, 性機能障害の病態解明と骨盤内自律神経温存手術の開発
1.目的.直腸癌の手術後には排尿, 性機能障害が高率に発生するが癌の治療のためには不可避なものとされていた. 本研究は癌に対する治療効果を十分に得ながら手術に伴う機能障害を最小限にするため骨盤内自律神経を温存する手術術式を開発しその適応を明らかにすることを目的とする. 2.排尿及び男性性機能を支配する神経は下腹神経, 骨盤内臓神経と陰部神経である. われわれは下腹神経, 骨盤内臓神経, 骨盤神経叢及びこれからの分枝を直視下に確認して温存し直腸を切除する方法を工夫して開発した.1.直腸癌に対する自律神経温存手術の排尿機能検査. 自律神経温存手術を受けた直腸癌69例に尿力学的な検査を行った. その結果, 自律神経をすべて温存すると排尿障害はなかった. (0/29). また片側の第4前仙骨孔から出る骨盤内臓神経が温存されれば83.3%(5/6)に排尿機能が維持された.2.直腸癌に対する自律神経温存手術後の性機能. 65歳以下で術前に性機能障害のない53例に術後の性機能を調査した. 下腹神経, 骨盤内臓神経, 骨盤神経叢およびその分枝をすべて温存した症例では勃起障害11%, 射精障害21%であり拡大郭清例(n=29)の66%, 93%の障害と比較して明かに性機能の温存ができた.3.雑種成犬を用いた骨盤内自律神経温存及び損傷の程度と排尿機能との関係. 17頭の雄成犬を用いた. 神経非損傷時には尿管からCO_2を注入すると排尿反射がみられ, 完全排尿となった. 片側骨盤内臓神経切断時には不完全収縮ながら排尿反射がみられた. 両側切断時には排尿反射は認められなかった.4.直腸癌に対する自律神経温存手術症例の手術適応. 下腹神経, 骨盤内臓神経をすべて温存した104例の5年累積局所再発例は20.8%, 累積5年生存率は72.7%であり, 拡大郭清例より良好であった. 背景因子から分類して検討すると癌の占居部位, 深達度にかかわらずリンパ節転移のない症例には自律神経温存手術の適応としてよいと考えられた.
16 0 0 0 OA キックスケートで転倒し病院前心肺停止に至った小児肝破裂の1例
- 著者
- 森脇 義弘 伊達 康一郎 長谷川 聡 内田 敬二 山本 俊郎 杉山 貢
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.1701-1705, 2001-07-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 14
キックスケート(車輪付きデッキ,シャフト,ハンドルバーから構成される遊戯具)による肝損傷で病院前心肺停止状態(CPA-OA)となり救命しえなかった症例を経験した.症例は, 9歳,男児,同遊戯具で走行中転倒しハンドルバーで右側胸部を強打.救急隊現場到着時,不穏状態で呼名に反応せず,血圧測定不能,搬送途中呼吸状態,意識レベル悪化,受傷後約30分で当センター到着, CPA-OAであった.腹部は軽度膨隆,右肋弓に6mmの圧挫痕を認めた.急速輸液,開胸心臓マッサージにより蘇生に成功した.肝破裂と腹腔内出血の増加,血液凝固異常,著しいアシドーシスを認めた.胸部下行大動脈遮断し,救急通報後78分,搬送後46分で緊急手術を施行した.肝右葉の深在性の複雑な破裂損傷に対しperihepatic packing,右肝動脈,門脈右枝結紮術を施行,集中治療室へ入室したが受傷後約15時間で死亡した.
3 0 0 0 頸部から背部にかけての鍼治療後の両側気胸の一例
- 著者
- 森脇 義弘 杉山 貢
- 出版者
- 社団法人日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.287-290, 2008-03-20
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
鍼治療後の両側気胸症例を経験した。58歳の女性,体調不良に対し頸部から腰部にかけて約20箇所の鍼治療直後に胸部違和感,呼吸困難感自覚し,救急搬送された。意識清明,血圧200/110mmHg,脈拍数151回/分,呼吸数36回/分,苦悶様顔貌,発汗著明であったが,チアノーゼや気道狭窄音,呼吸音の左右差はなく,心臓超音波,心電図で異常なく,血液検査でも白血球上昇以外異常はなく,動脈血ガス分析(酸素101/分)はpH7.215,Pao_2118.7mmHg,Pco263.9mmHgであった。前医鍼灸院から情報を得て,胸部単純X線検査で両側気胸と診断,両側胸腔ドレナージを施行した。血液ガス分析はpH7.326,Pao_2181.6mmHg,Pco_242.8mmHgと改善,症状も消失し,第13病日退院となった。考察・結論:気胸など鍼治療の合併症が生じると鍼治療担当者とは別の医師が治療を行うことになるが,鍼治療合併症に対する対応体制は未発達である。今後は,鍼治療時のインフォームドコンセントの充実と合併症時の鍼灸治療者と救急医療機関との連携あるシステム構築が必要と思われた。
2 0 0 0 OA 痔瘻から発生したガス産生性壊疽性筋膜炎(Fournier's Gangrene)の1例
- 著者
- 若杉 純一 金 正文 簾田 康一郎 杉山 貢
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.480-484, 1992 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 2
症例は53歳の男性で,陰嚢の発赤腫張を主訴に来院した.腹部単純X線検査で陰嚢および骨盤内に散在する小ガス像を,CT検査で陰嚢から仙骨前面,膵後面まで広がる異常ガス像を認めた.直腸診で肛門管後壁に痔瘻の1次口を認め,注腸造影検査で1次口から仙骨前面に造影剤が逸脱し,痔瘻より発生した壊疽性筋膜炎と診断,ドレナージ術および人工肛門造設術を施行した.細菌培養検査の結果,好気性菌のE. coli,pseudomonas aeruginosaと嫌気性菌のbacteroides fragilisによる混合感染であった.肛門疾患から発生したガス壊疽の本邦報告例は自験例も含め29例で,糖尿病を合併しているものが多かった.抗生物質の発達した近年,壊疽性筋膜炎は比較的まれ疾な患であるが,痔瘻や肛門周囲膿瘍などの肛門疾患で,糖尿病などの基礎疾患がある場合は,広範な壊疽性筋膜炎に進展することもあるので,十分な経過観察が必要であると考えられた.
2 0 0 0 OA 酩酊症を呈した胃カンジダ症の1例
- 著者
- 施 清源 杉山 貢 衛藤 俊二 土屋 周二 長岡 英和
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.6, pp.1318-1321, 1982-06-05 (Released:2007-12-26)
- 参考文献数
- 19
2 0 0 0 キックスケートで転倒し病院前心肺停止に至った小児肝破裂の1例
- 著者
- 森脇 義弘 伊達 康一郎 長谷川 聡 内田 敬二 山本 俊郎 杉山 貢
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.1701-1705, 2001
キックスケート(車輪付きデッキ,シャフト,ハンドルバーから構成される遊戯具)による肝損傷で病院前心肺停止状態(CPA-OA)となり救命しえなかった症例を経験した.症例は, 9歳,男児,同遊戯具で走行中転倒しハンドルバーで右側胸部を強打.救急隊現場到着時,不穏状態で呼名に反応せず,血圧測定不能,搬送途中呼吸状態,意識レベル悪化,受傷後約30分で当センター到着, CPA-OAであった.腹部は軽度膨隆,右肋弓に6mmの圧挫痕を認めた.急速輸液,開胸心臓マッサージにより蘇生に成功した.肝破裂と腹腔内出血の増加,血液凝固異常,著しいアシドーシスを認めた.胸部下行大動脈遮断し,救急通報後78分,搬送後46分で緊急手術を施行した.肝右葉の深在性の複雑な破裂損傷に対しperihepatic packing,右肝動脈,門脈右枝結紮術を施行,集中治療室へ入室したが受傷後約15時間で死亡した.
1 0 0 0 OA 腹部外傷による出血性ショックに対する緊急O型未交差赤血球輸血の経験
- 著者
- 森脇 義弘 鈴木 範行 杉山 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.147-153, 2009-02-01 (Released:2011-12-23)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 3
はじめに:肝,脾,腸間膜損傷で出血性ショック合併の腹部外傷では,蘇生的緊急開腹術など外科手技の適応と緊急輸血の適応判断を迫られる.異型輸血を含む危険を内在する未交差赤血球製剤(uncrossmatched-red cell concentrate;以下,UCM RCC)緊急輸血の安全性と問題点を考案する.方法:過去5年間で,O型Rh+UCM RCCを含むUCM RCC緊急輸血を実施した腹部外傷を対象にUCM RCC輸血の実態と輸血関連インシデント・アクシデント回避の成否を検討した.結果:UCM RCC輸血は33例に54回,388単位実施され,準備UCM RCCは426単位で使用率は91.1%であった.出血源は肝臓13例,脾臓8例,腸間膜17例で,輸血前平均収縮期血圧は62.5 mmHg,脈拍数117回/分,ショック指数(脈拍数/収縮期血圧)1.97,base excessは−12.7 mEq/l,7日生存例は48.5%であった.血液型判定(blood typing test;以下,BTT)未判定でのO型UCM RCC輸血は17例(21回,168単位),うち非O型への輸血は11例(14回,120単位)であった.1回のBTT後のO型UCM RCC輸血は8例(12回,96単位),うち非O型への輸血は4例(7回,54単位)で,1回のBTTでの非O型症例への未確認同型UCM RCC輸血は15例(20回,120単位)であった.O型UCM RCC輸血全体に年度別増減はなかったが,1回のBTTでの非O型への未確認同型UCM RCC輸血は減少した.ABO型不適合輸血,輸血に関わるインシデントはなかった.考察:UCM RCC輸血では,院内マニュアルを整備したうえでのO型UCM RCCの使用は安全と考えられた.
1 0 0 0 OA 刺杭創(杙創)について
- 著者
- 杉山 貢 山下 俊紀 松田 好雄 小林 衛 竹村 浩 土屋 周二
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.369-372,406, 1974 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 6 1
平時比較的稀な会陰部の刺杭創(杙創)について,2例の自験例を中心に文献的考察を加えて述べる。症例1は8歳女児で校庭の植木の支柱による刺杭創であり,幸い直腸穿孔のみでことなきを得た.症例2は27歳男子で鉄製の椅子の脚による刺杭創で,膀胱・直腸瘻を形成した.刺杭創による腸管損傷について,本邦の報告例について検討すると,1927年に布目が報告して以来症例を加えると27例となり,好発年齢はほぼ外傷年齢である10代と20代に多く,性差は23:3と圧倒的に男性に多かつた.原因物体に関しては,竹による刺杭創が10例と目立った.損傷部位は直腸100%と膀胱88%と高率であり,手術時には特にこの両者への損傷の検索を怠ってはいけない.刺杭創に遭遇した場合には,受傷状況,程度をすばやく把握し,できる限り早期に対処し,むやみに保存療法により時を費すことはあってはならないと思う.
1 0 0 0 手術のノウ・ハウ—上部消化管穿孔
消化管穿孔は汎発性もしくは限局性腹膜炎を伴う,急性腹症の代表的疾患であり,ごく少数例を除いては,緊急手術を必要とする.ここでは主に上部消化管穿孔の外科治療のノウ・ハウについて,以下の項目につき,また特殊な症例も紹介し,具体的にその要領を述べる.1.穿孔部の修復(①穿孔部の探索法,②穿孔部閉鎖法),2.原疾患の根治手術(胃・十二指腸潰瘍,胃癌など),3.腹膜炎に対する外科的処置(①腹腔内洗浄法,②腹腔内ドレナージ,③腹腔内術後持続洗浄). 近年,上部消化管の穿孔性腹膜炎の病態に対する認識も深まり,ultrasonographyなどの画像診断の応用や治療,技術の進歩により,外科治療の成績は飛躍的に向上している.そのため,一方では,緊急手術であつても背後の原病に対する根治が要求されるようになつて来ている.しかし,上部消化管の穿孔性腹膜炎の外科手術にあたつては,先ず救命を第一に考え,"push to safe side"を心掛けることが大切であろう.
1 0 0 0 OA 第17回 心臓性急死研究会 病理解剖にて劇症型心筋炎と診断された院外心肺停止の1例
- 著者
- 外山 英志 田原 良雄 豊田 洋 小菅 宇之 荒田 慎寿 松崎 昇一 天野 静 下山 哲 中村 京太 岩下 眞之 森脇 義弘 鈴木 範行 杉山 貢 五味 淳 野沢 昭典 木村 一雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.Supplement3, pp.27-30, 2005-07-30 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 8
症例は64歳の男性,狭心症の既往はなし.冠危険因子は高脂血症と家族歴があった.2週間前から発熱,咳嗽などの感冒様症状が出現し内服薬を処方されていたが改善しなかった.突然の呼吸困難にて発症し救急隊を要請したが,現場到着時には心静止であった.当院搬送後,心肺蘇生処置を継続したが効果なく死亡確認となった.病理解剖を行ったところ,肉眼的には,漿液性の心嚢水が貯留,両心室腔・右房の拡張,左室壁の肥厚を認めた.左室壁はほぼ全周性に心筋の混濁が認められたが,心筋の梗塞巣や線維化は認められなかった.組織学的には両室心筋に全層性の炎症細胞浸潤,巣状壊死,変性,脱落を認めた.臨床経過と合わせて劇症型心筋炎と診断した.一般に「突然死」と呼ばれている死亡原因には,急性心筋梗塞,狭心症,不整脈,心筋疾患,弁膜症,心不全などの心臓病によるものが6割を占め,そのほかに脳血管障害,消化器疾患などがある.突然死の中でも心臓病に起因するものが「心臓突然死(SCD)」と呼ばれているが,現在米国では心臓突然死によって毎年40万人もの人が命を落としており,その数は肺がん,乳がん,エイズによる死亡者の合計数よりも多いとされている.心臓突然死における急性心筋炎の頻度は不明であるが,しばしば可逆的な病態であり,急性期の積極的な補助循環治療により,完全社会復帰された症例も散見されるので,鑑別診断として重要である.
1 0 0 0 OA 緊急手術が回避できず術前鑑別診断が十分できなかった腸結核出血・穿孔の1例
- 著者
- 森脇 義弘 豊田 洋 小菅 宇之 荒田 慎寿 岩下 眞之 鈴木 範行 杉山 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.5, pp.272-278, 2008-05-15 (Released:2009-07-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 1
出血性ショックを伴ったクローン病として転院搬送された腸結核の 1 例を報告する。患者は62歳,女性。透析導入のための近医入院中に下部消化管造影,内視鏡,生検でクローン病と診断され,ステロイド治療を開始された。感染徴候のない発熱と考え再入院となり,ステロイドと免疫抑制剤で治療されたが改善はなかった。下血と呼吸促迫を伴うショックとなり,人工呼吸管理,カテコラミン投与の後に,外科的処置を目的に当センターへ転院搬送となった。前医の下部消化管造影から必ずしも典型的クローン病とは考えにくかったが,出血性ショックのため緊急手術(右結腸切除)を余儀なくされた。術後はseptic shockから離脱できず第 6 病日に死亡した。患者の死後,切除標本の組織学的検査から,肺症状を伴わない活動性の腸結核と診断された。ステロイドを使用しているクローン病では,常時,腸結核との鑑別を念頭におくべきと思われた。また,情報に乏しい初診患者への緊急対応を余儀なくされる救急部門では,診療が終了してから結核であったと判明した場合に関係した職員の健康診断を行うなどの対策を考案しておくべきと考えられた。
1 0 0 0 OA 頸部から背部にかけての鍼治療後の両側気胸の一例
- 著者
- 森脇 義弘 杉山 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.287-290, 2008 (Released:2008-09-18)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 1
鍼治療後の両側気胸症例を経験した。58歳の女性,体調不良に対し頸部から腰部にかけて約20箇所の鍼治療直後に胸部違和感,呼吸困難感自覚し,救急搬送された。意識清明,血圧200/110mmHg,脈拍数151回/分,呼吸数36回/分,苦悶様顔貌,発汗著明であったが,チアノーゼや気道狭窄音,呼吸音の左右差はなく,心臓超音波,心電図で異常なく,血液検査でも白血球上昇以外異常はなく,動脈血ガス分析(酸素10l/分)はpH7.215,Pao2118.7mmHg,Pco263.9mmHgであった。前医鍼灸院から情報を得て,胸部単純X線検査で両側気胸と診断,両側胸腔ドレナージを施行した。血液ガス分析はpH7.326,Pao2181.6mmHg,Pco242.8mmHgと改善,症状も消失し,第13病日退院となった。考察・結論:気胸など鍼治療の合併症が生じると鍼治療担当者とは別の医師が治療を行うことになるが,鍼治療合併症に対する対応体制は未発達である。今後は,鍼治療時のインフォームドコンセントの充実と合併症時の鍼灸治療者と救急医療機関との連携あるシステム構築が必要と思われた。
1 0 0 0 OA 胃切除後骨代謝異常の発生と病態
- 著者
- 杉山 貢 徐張 嘉源 山中 研 Keiichi WATANABE 施 清源 山本 俊郎 門口 幸彦 片村 宏 佐藤 芳樹 土屋 周二
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.10, pp.2129-2133, 1986 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 22
胃切除後の107例に対して無選択的にmicrodensitometry法による骨塩量の測定を行い, 胃切除後骨障害の発生頻度をまたCa infusion試験によりその病態を研究した.胃切除後骨障害の発生率は38%であり, 術後5年以上経過すると, 胃全摘後では62%に, 胃部分切除後では55%に骨代謝異常を認めた.胃切除後, 骨障害度の初期になるのにかかる期間は胃全摘後で1年6ヵ月, 胃部分切除後では5年であった.Ca infusion試験によると, 胃切除後の骨障害例とくに重症例の多くは, Nordinの基準による28%以下で骨軟化症を呈していた.
- 著者
- 中山 尚貴 尾崎 弘幸 海老名 俊明 小菅 雅美 日比 潔 塚原 健吾 奥田 純 岩橋 徳明 矢野 英人 仲地 達哉 遠藤 光明 三橋 孝之 大塚 文之 草間 郁好 小村 直弘 木村 一雄 羽柴 克孝 田原 良雄 小菅 宇之 杉山 貢
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.54-57, 2007
症例は30歳,男性.2006年6月,スポーツジムのランニングマシンで運動中に突然,心窩部不快感が出現し,運動を中止したが痙攣を伴う意識消失をきたし倒れた.スポーツジムのトレーナーがただちに心肺停止を確認し,施設内の自動体外式除細動器(AED)を装着した.AEDの音声に従い除細動ボタンを1回押し,すみやかに自己心拍が再開したが,AED使用後にリセットボタンを押したため,メモリーが消去され,心肺停止の原因として致死性不整脈の関与は確認できなかった.<BR>入院後,トレッドミル運動負荷心電図検査で広範囲の誘導でST低下を認め,冠動脈造影検査を施行し冠動脈瘤を伴う重症多枝病変を認めた.心肺停止の原因は心筋虚血による心室細動もしくは無脈性心室頻拍と推定し,冠動脈バイパス術を施行した.<BR>AEDの普及に伴い非医療従事者によるAEDを使用した救命例が本邦でも徐々に報告されており,本症例は現場にあったAEDをただちに使用したことが社会復帰に大きく貢献したと考えられる.ただし,本症例で使用したAEDのように,一部機種ではリセットボタンを押すことによりメモリーが消去され,事後検証が困難になることは注意すべき点であり改善を要する.