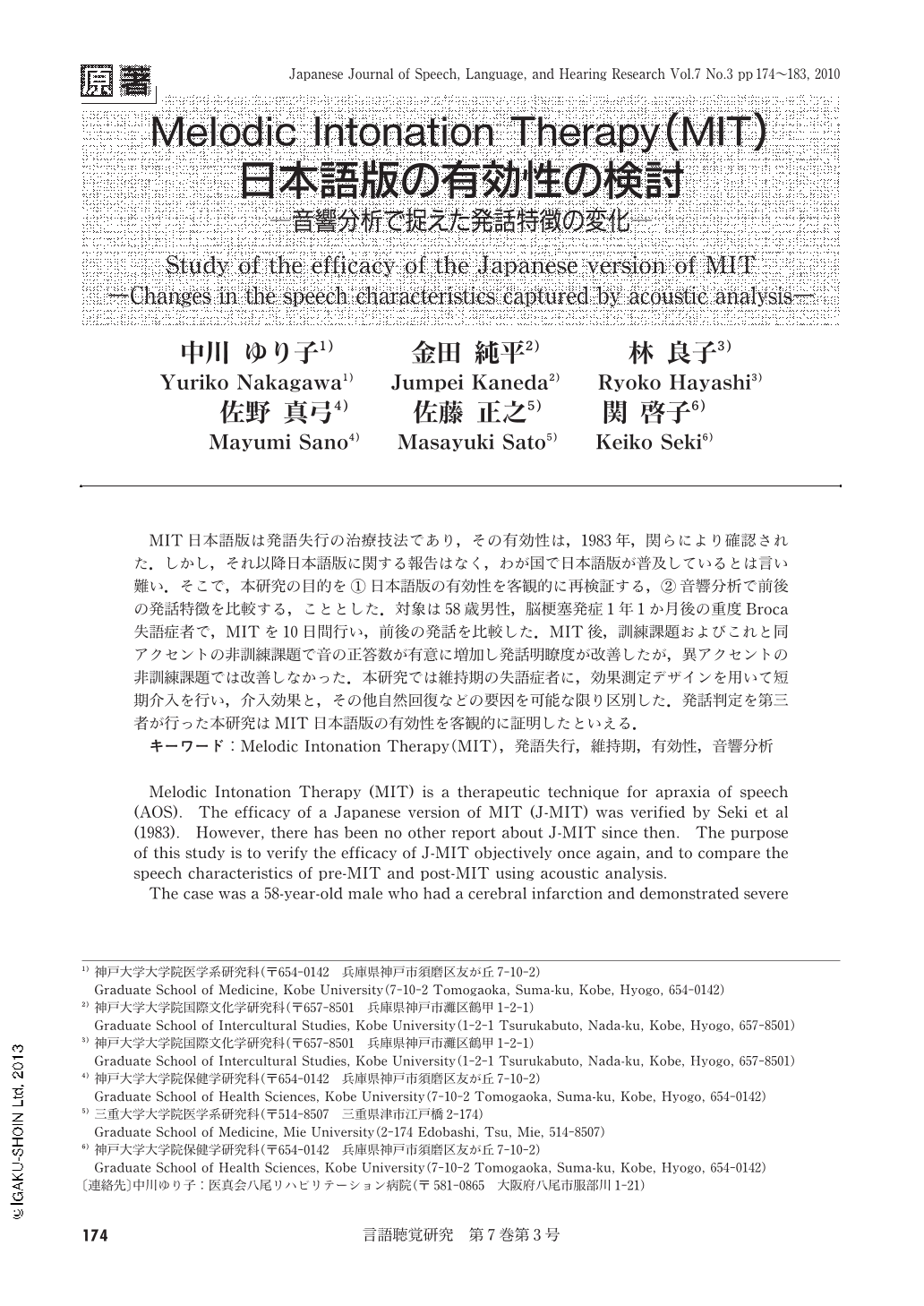1 0 0 0 OA Attenuated Ventilatory Responses to Hypercapnia and Hypoxia in Assisted Breath-hold Divers (Funado)
- 著者
- 升田 吉雄 吉田 明夫 林 文明 佐々木 健 本田 良行
- 出版者
- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.327-336, 1982 (Released:2011-06-07)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 14 19
The steady-state ventilatory responses to hypercapnia and hypoxia in 7 assisted breath-hold divers (Funado) were compared with those in 7 normal sedentary controls.Ventilatory response to hypercapnia was measured from the slope of the hyperoxic VN-PETCO2 line, where VN was normalized minute ventilation using the allometric coefficient and PETCO2 end-tidal PCO2. The slope of this line in the Funado (1.48±0.54 liters·min-1·Torr-1) was significantly less than in the control (2.70±1.08 liters·min-1·Torr-1)(p<0.025). On the other hand, hypoxic sensitivity estimated by hyperbolic and exponential mathematical equations was not found to be significantly different between the two groups, although estimated increments in ventilation using the hyperbolic equation exhibited significantly lower response in the Funado than in the control only when PETO2 decreased lower than 50 Torr (p<0.05).These findings in the Funado were different from our previous observations obtained in unassisted breath-hold divers (Kachido), in whom no obvious attenuations in CO2sensitivity were seen. This difference was assumed to be derived from more hypercapnic and hypoxic conditions produced in the Funado than in the Kachido during diving activities.
- 著者
- 升田 吉雄 吉田 明夫 林 文明 佐々木 健 本田 良行
- 出版者
- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.187-197, 1981 (Released:2011-06-07)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 22 26
The ventilatory responses to hypoxia and hypercapnia of 5 Amas (Kachido) were compared with those of 5 controls of similar ages, physical characteristics and lung volumes. The responses to hypoxia and hypercapnia were analyzed by the equations originally proposed [a] by Lloyd et al. and [b] by Kronenberg et al. as follows:[a] VN=(PCO2-B')·D·(1+A/PO2-C) +VB'.[b] VN=(PCO2-B')·D·(1+R0·exp (-k·PO2)) +VB'.The CO2-response slope in hyperoxia, D, of the Ama (1.820±0.441 liters·min-1·Torr-1) was slightly higher than that of the control (1.148±0.586 liters·min-1·Torr-1), but the difference was not significant. However, the slope of CO2-response in hypoxia at PETO2=44 Torr, S44, was almost the same in the two groups (Ama, 1.822±0.689 liters·min-1·Torr-1; control, 1.742±0.902 liters·min-1·Torr-1). The ratio of S44 to D was significantly lower (p<0.05) in the Ama (1.039±0.377) than in the control (1.529±0.249). Comparing the hypoxic response in terms of the ventilation ratio (VR), the elevation of ventilation with augmentation of hypoxia in the Ama was exceeded by that in the control.Thus, it was suggested that the difference in the ventilatory response to hypoxia between the Ama (Kachido) and the control may have been derived from the respiratory adaptation of the Ama (Kachido) acquired by their daily diving activities.
- 著者
- 本田 良行 林 文明 吉田 明夫 升田 吉雄 佐々木 健
- 出版者
- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.181-186, 1981 (Released:2011-06-07)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 5
Relative contributions of chemical and non-chemical respiratory stimulations to breath-holding time (BHT) were examined in assisted (Funado) and unassisted (Kachido) breath-hold divers (Ama). In the Funado the magnitude of the chemical contribution was reduced, though statistically not significant. On the other hand, in the Kachido no difference in chemical contribution was seen from the control. This was considered to be due to the fact that ventilatory response to CO2 was reduced in the Funado, but not in the Kachido. Despite the decreased contribution of CO2 drive to BHT, absolute BHT in the Funado was not prolonged. This may be related to sensitization of the respiratory centers to non-chemical stimulation. Such adaptation would be effective for preventing the danger of losing consciousness in the Funado who face extreme hypoxia on returning to the surface from a dive.
- 著者
- 竹下 博之 加藤 博和 林 良嗣
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09131280)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.463-468, 2009-10-25
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
本研究は、鉄軌道線廃止後の代替交通網整備の検討方法について示唆を得ることを目的としている。2006年10月に廃止となった桃花台新交通桃花台線(愛知県小牧市)を対象として、その廃線前後の沿線における交通利便性変化を、土地利用を考慮した評価が可能なポテンシャル型アクセシビリティ指標を用いて評価した。その結果、代替公共交通網により名古屋市方面への交通利便性は維持されているものの、小牧市内へのそれは大きく低下していることが明らかとなった。この結果と、独自に実施した廃止に伴う住民の交通行動変化に関するアンケート調査結果とを比較したところ、おおむね合致していることがわかった。このことから、鉄軌道廃止後の公共交通網検討のための評価指標として、アクセシビリティ指標を用いることが可能であると考えられる。
- 著者
- 林 健太朗 粕谷 大智
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学系物理療法学会
- 雑誌
- 日本東洋医学系物理療法学会誌 (ISSN:21875316)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.105-113, 2018 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 32
【目的】末梢性顔面神経麻痺(以下 麻痺)患者の後遺症は、患者のQuality of Life(以下 QOL)を 著しく低下させる。そのため、後遺症の出現が予想される患者に対してはその予防や軽減を目的 に発症早期からリハビリテーション(以下 リハ)が行われている。リハの介入の中で表情筋に対 するマッサージは日々の臨床で多用されている。そこで、本研究では我が国の麻痺患者に対する マッサージの文献レビューを行い、目的・方法・効果に焦点を当て、現状と意義および課題につ いて検討した。 【方法】データベースは、医中誌Web Ver.5 を使用し、検索語はその統制語である「顔面麻痺」、 「Bell 麻痺」、「帯状疱疹- 耳性」の同義語のうち関連する検索語と「マッサージ」とした。調査日 は2018 年6 月20 日、調査対象期間は限定せずに行った。同時に、ハンドサーチも行った。対象 論文は、包含基準・除外基準に基づき選定した。 【結果】検索の結果、医中誌Web23 件、ハンドサーチ3 件、合計26 件が抽出された。そのうち対 象論文の条件を満たす11 件について検討した。マッサージの目的は、後遺症出現前は予防、出現 後は軽減を目的に行われていた。方法は、主に前頭筋・眼輪筋・頬骨筋・口輪筋・広頸筋などの表 情筋に対して、頻回の筋を伸張するマッサージが行われていた。マッサージは他の治療法と併用 されていた。評価は、柳原法、Sunnybrook 法、House-Brackmann 法、Facial Clinimetric Evaluation Scale などが用いられており、マッサージを含めたリハの効果として、後遺症の軽減、QOL の向上 が報告されていた。 【考察・結語】麻痺患者に対するマッサージは、病期に応じて後遺症の予防や軽減を目的に、他の 治療法と併用することにより後遺症の軽減、その結果としてQOL の向上に寄与できる可能性が示 唆された。特に麻痺患者のQOL を著しく低下させる要因である顔面のこわばり感などの違和感に 対してマッサージを行い一定の効果を挙げていることは、この領域における手技療法の意義が考 えられた。一方で、マッサージの方法、効果の検討に関する課題も明らかとなった。
1 0 0 0 IR 資料紹介 宮内庁書陵部蔵『琵琶銘并序』影印・翻刻
- 著者
- 小林 加代子
- 出版者
- 同志社大学国文学会
- 雑誌
- 同志社国文学 (ISSN:03898717)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.201-222, 2005-03
MIT日本語版は発語失行の治療技法であり,その有効性は,1983年,関らにより確認された.しかし,それ以降日本語版に関する報告はなく,わが国で日本語版が普及しているとは言い難い.そこで,本研究の目的を①日本語版の有効性を客観的に再検証する,②音響分析で前後の発話特徴を比較する,こととした.対象は58歳男性,脳梗塞発症1年1か月後の重度Broca失語症者で,MITを10日間行い,前後の発話を比較した.MIT後,訓練課題およびこれと同アクセントの非訓練課題で音の正答数が有意に増加し発話明瞭度が改善したが,異アクセントの非訓練課題では改善しなかった.本研究では維持期の失語症者に,効果測定デザインを用いて短期介入を行い,介入効果と,その他自然回復などの要因を可能な限り区別した.発話判定を第三者が行った本研究はMIT日本語版の有効性を客観的に証明したといえる.
1 0 0 0 OA 抗不安薬服用によって頸肩腕症状を消退させた1例
- 著者
- 小林 雅文
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.84-91, 1994-06-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 11
Cervico-omo-brachial syndrome consists of symptoms that include pain and paralysis extending from the neck, shoulders and arms to the fingers, muscle contracture or hypertonia of these parts and the inhibition of movement at the cervical vertebrae. Although the cause is complicated, it may be produced principally by compression and/or stimulation of the spinal cord and/or nerve root, plexis or periphery. Little literature describes psychogenic intervention in this syndrome. This study describes a case of the syndrome which exhibited psychosomatic influence.Patient: 40 years old housewife.First examination: August 8, 1993Chief complaint: Sensory disturbance of the neck, shoulders and arms together with pain in the mandibular joint produced by “close-bite malocclusion” of metal crowns set on the right and left mandibular molars several years previously.History of present illness: Patient complained of dry mouth, thoracic compression and cardiopalmus in addition to the above-described syndrome, although doctors told her that no abnormal state was found from clinical, physiological and biochemical examinations. Her sickness had changed from stiffness to paralysis after a miscarriage in the previous year, and the paralysis has extended to the arms. The syndrome was not improved during 30 days of taking (p. o.) of tizanidine hydrochloride prescribed by a plastic surgeon.Status praesens: The author advised her to stop taking tizanidine. Her complaint of maladaptation of metal crowns (765 567) was foud to have almost no physical basis when examined orally, including by x-ray. The result of CMI questioning was III.However, the author counseled the patient to accept and bear with her complaint on two occasions for one hour each and also devoted one hour to reassuring the patient that her sickness would heal, making a combined total of 3 hours during the 3 months' therapy. The author also adjusted the occlusion 65 567 65 567 and set the new metal crown at 7 after root canal treatment.Etizolam (0.5mg/tablet) was administered 3 times (1 tablet p. o. every time) per day for 5 days in the first month and 10 days in the second month, and then alprazolam (0.4mg/tablet) was administered twice (1 tablet p. o. every time) per day for 5 days during final week of the second month. Her sickness disappeared for the most part. Three weeks after stopping alprazolam, (0.5mg/tablet) was administered twice (1 tablet each time) per day for 5 days in the third month. Sleeplessness was also improved considerably.Her sickness has not recurred to date, i. e. 7 months since the final treatment.
1 0 0 0 OA 全国猟区案内
- 著者
- 川口屋林銃砲火薬店 編
- 出版者
- 川口屋林銃砲火薬店
- 巻号頁・発行日
- vol.大正11年調査, 1923
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.19-27, 2010-12
1 0 0 0 国際物流の発展と税関 (税関120周年記念特集)
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 日本関税協会
- 雑誌
- 貿易と関税 (ISSN:04064984)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.p58-64, 1992-12
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 日本海運経済学会
- 雑誌
- 海運経済研究 (ISSN:03865320)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.1-10, 2003
本研究の目的は、荷主企業の視点から鉄道コンテナ輸送に対する評価を把握し、荷主企業のグリーロジスティクス構築に鉄道コンテナ輸送が貢献する可能性を探ることにある。荷主企業に対するアンケート調査と先進的事例のインタビュー調査により、 (1) 荷主企業にとってモーダルシフトが重要な経営課題となっていること、 (2) 多くの荷主企業が戦術的レベルで、一部先進企業が企業戦略レベルでモーダルシフトに取り組んでいること、 (3) 通運事業者とJR貨物に対し専門家として重要な役割を果たすことを期待していることがわかった。今後、荷主企業の視点に立ったグリーンロジスティクスの構築に向けて、輸送事業者と荷主企業との間で連携を進め、それぞれの役割を果たしていくことが求められている。
1 0 0 0 長距離フェリーの発展段階と経営環境変化
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.9, pp.37-44, 2001-09
1 0 0 0 国際物流の現況と課題 (特集 進展する国際物流の効率化)
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 日通総合研究所
- 雑誌
- 季刊輸送展望 (ISSN:05134080)
- 巻号頁・発行日
- no.252, pp.11-20, 1999-11
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.9, pp.10-18, 2008-09
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.12, pp.19-25, 2013-12
1 0 0 0 ネット時代の物流革新 (特集 ネット通販時代の交通・物流)
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.33-37, 2016-06
1 0 0 0 EUの複合輸送政策
- 著者
- 林 克彦
- 出版者
- 運輸調査局
- 雑誌
- 運輸と経済 (ISSN:02878305)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.p32-43, 1995-11