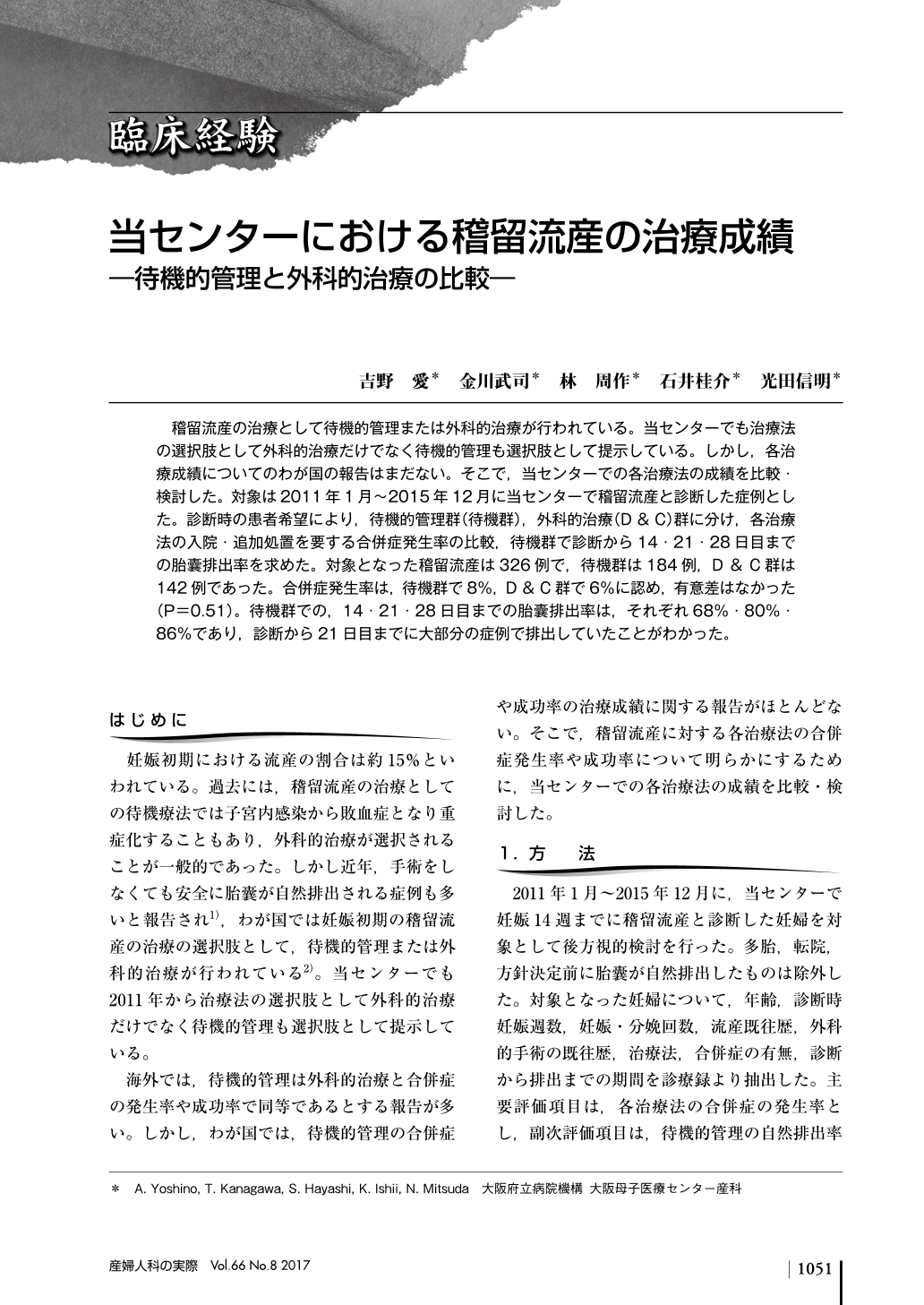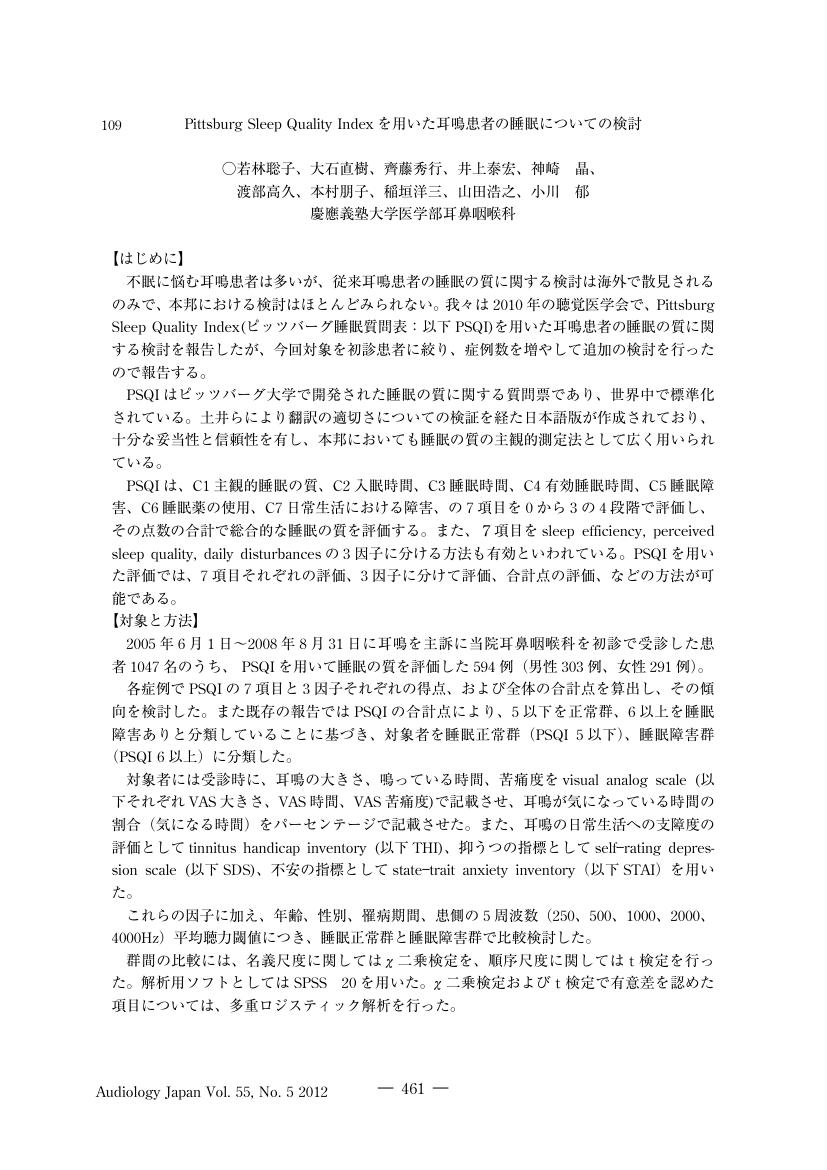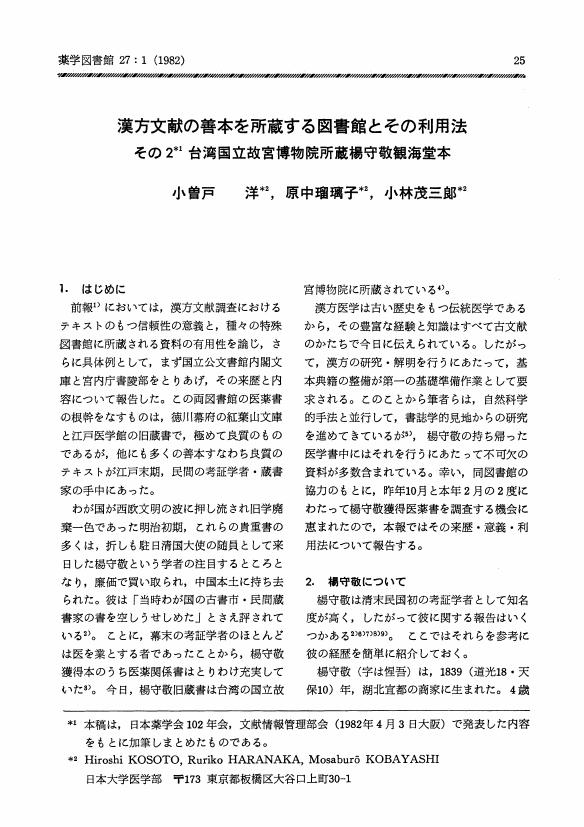1 0 0 0 OA 地域で在宅難病患者や重度障害者を支えるための世田谷区としての役割
- 著者
- 林 英治
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.S84, 2020 (Released:2020-10-05)
1 0 0 0 IR 近代中国におけるアヘン・麻薬問題と日本居留民
- 著者
- 小林 元裕
- 出版者
- 東海大学文化社会学部
- 雑誌
- 東海大学紀要文化社会学部 (ISSN:24344710)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.175-183, 2020-03
1 0 0 0 プラトンの『ヒッピアス(大)』における美しさの実質の探求
- 著者
- 栗林 広明
- 出版者
- 北海道哲学会
- 雑誌
- 哲学年報 (ISSN:1344929X)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-12, 2005
1 0 0 0 OA LIWCを用いたユーザー属性推定手法の検討とSNSデータへの応用
- 著者
- 冨平 準喜 山下 晃弘 松林 勝志
- 雑誌
- 第80回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.1, pp.539-540, 2018-03-13
近年SNSにおいてユーザーが爆発的に増えているため,それらのマーケティングへの活用が期待されている.様々な趣味,職業,性格を持つユーザーの中から,ターゲットとなるユーザーを絞り込むのは重要な課題となっている.しかし一般的にプロフィールの基準が厳格化されていないため,その情報だけでユーザーの属性を判断するのは困難である.語彙を抽象化してカテゴリ化するツールであるLIWC(Linguistic Inquiry and Word Count)はユーザーの属性推定に適しているとされている.LIWCの日本語版は公開されていないため,英語版を半自動翻訳し,日本語のLIWCを用いたユーザー属性推定の方法を提案する.
1 0 0 0 高校生における領域別援助要請スタイルと学校適応との関連
- 著者
- 林 亜希恵 中谷 素之
- 出版者
- 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 = The Japanese journal of developmental psychology (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.55-66, 2020-06
- 著者
- 伊澤 雅子 傳田 哲郎 玉城 歩 小林 峻
- 出版者
- Pro Natura Foundation Japan
- 雑誌
- 自然保護助成基金助成成果報告書 (ISSN:24320943)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.394-398, 2020 (Released:2020-09-29)
稽留流産の治療として待機的管理または外科的治療が行われている。当センターでも治療法の選択肢として外科的治療だけでなく待機的管理も選択肢として提示している。しかし,各治療成績についてのわが国の報告はまだない。そこで,当センターでの各治療法の成績を比較・検討した。対象は2011 年1 月〜2015 年12 月に当センターで稽留流産と診断した症例とした。診断時の患者希望により,待機的管理群(待機群),外科的治療(D & C)群に分け,各治療法の入院・追加処置を要する合併症発生率の比較,待機群で診断から14・21・28 日目までの胎囊排出率を求めた。対象となった稽留流産は326 例で,待機群は184 例,D & C 群は142 例であった。合併症発生率は,待機群で8%,D & C 群で6%に認め,有意差はなかった(P=0.51)。待機群での,14・21・28 日目までの胎囊排出率は,それぞれ68%・80%・86%であり,診断から21 日目までに大部分の症例で排出していたことがわかった。
1 0 0 0 IR <論文>視線パターンと選択行動との関連性-戦略形ゲームにおけるアイトラッカー実験-
- 著者
- 栗原 崇 小林 伸
- 出版者
- 早稻田大學政治經濟學會
- 雑誌
- 早稻田政治經濟學雜誌 (ISSN:02877007)
- 巻号頁・発行日
- no.389, pp.2-17, 2016-03-31
- 著者
- 若林 聡子 大石 直樹 齊藤 秀行 井上 泰宏 神崎 晶 渡部 高久 本村 朋子 稲垣 洋三 山田 浩之 小川 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.461-462, 2012 (Released:2013-12-05)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 大学キャンパスのバス待ち列の現況と各キャンパスの対策
- 著者
- 司 隆 佐藤 雅明 伊藤 昌毅 厳 網林
- 雑誌
- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017-ITS-71, no.18, pp.1-8, 2017-11-08
大学キャンパスへのバスが混雑している地域の分布とその対策について,11 の大学キャンパスにおいて調査した.都市郊外型の大学キャンパスにおいてバス待ちができるキャンパスが点在し,各々列を整備する人を配置して対応するキャンパスが相当数存在した.またバスの時刻表を調べるアプリケーションが実装されている大学も多かったが,バス待ち列に対応するアプリケーションはあまり製作されていない状況であることがわかった.
1 0 0 0 OA 風土論と地理学
- 著者
- 小林 茂
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.33-44, 1977-09-30 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 形容詞の連用形名詞法について
- 著者
- 林 謙太郎 ハヤシ ケンタロウ Kentarou Hayashi
- 雑誌
- 二松學舍大學論集
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.95-114, 1998-03-31
1 0 0 0 OA 藍染め染色布の消費性能
- 著者
- 杉本 奈那 鈴木 結花 岩﨑 潤子 小林 泰子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 68回大会(2016)
- 巻号頁・発行日
- pp.97, 2016 (Released:2016-08-04)
【目的】 藍染め布は、古くから衣服に使用され、消臭、細菌増殖抑制、虫除け等の効果もあるという。本研究では、衣服として必要な消費性能から、数種の物性と染色堅ろう性、消臭性、抗菌性を選び、検討を行った。【実験方法】 試料布は綿と麻ブロード、染料はインド藍液(田中直染料店)を用い、1回染めと5回染めにより、染色布を調製した。JIS法に基づき、物性は、引張り強度と引裂き強度試験、染色堅ろう度は、摩擦と耐光試験、その他機能性は、検知管法による消臭性とフードスタンプ法による抗菌性試験を行った。【結果と考察】 引裂き強度は、綿では1回染め布で20%、5回染め布で50%、麻では約2~3倍に増加した。摩擦堅ろう度は、5回染めにより乾燥試験のたて方向で4級から3級に減少した。湿潤試験では、1回染めと5回染めで変化はなく、3級だった。濃色化により色落ちが目立った。耐光試験では、濃色化により堅ろう性は増加した。アンモニアに対する消臭性は、藍染め布には認められなかったが、銅媒染により発現した。抗菌性は、未処理布に比較し、染色を重ねることによりコロニー数が減少した。これら結果より、物性、抗菌性では、十分な消費性能が得られ、消臭性も媒染を加えることにより期待できることがわかった。今後は、より染色堅ろう性の高い染色布の調製を行い、紫外線遮蔽性、数種の細菌を用いた抗菌性についても検討を行う。
1 0 0 0 OA pHメーターのわかりやすい説明
- 著者
- 林 久史 ハヤシ ヒサシ Hisashi Hayashi
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 理学部 = Journal of Japan Women's University. Faculty of science
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.43-48, 2012-03-31
1 0 0 0 OA 漢方文献の善本を所蔵する図書館とその利用法
- 著者
- 小曽戸 洋 原中 瑠璃子 小林 茂三郎
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.25-32, 1982-06-15 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 吃音のある学齢児の指導(訓練)・支援
- 著者
- 小林 宏明
- 出版者
- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
- 雑誌
- 子どものこころと脳の発達 (ISSN:21851417)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.48-54, 2020 (Released:2020-09-24)
- 参考文献数
- 24
近年,発達性吃音のある学齢児の指導(訓練)・支援方法として,子ども一人ひとりの吃音の言語症状,心理症状,周囲の環境などの要因に応じた指導・支援を行う多面的包括的アプローチが支持されている.そこで,本稿では,まず,吃音の症状,出現率,原因論及び,吃音のある学齢児が抱える困難と,多面的包括的アプローチを中心とした学齢期吃音の指導法に関する国内外の動向を概説した.そして,これらを踏まえた筆者の実践である,ことばの教室での実践を想定した「ICF(国際生活機能分類)に基づいた学齢期吃音のアセスメントプログラム」,アセスメント及び指導・支援の効果検証に用いる評価ツールである「吃音のある学齢児の学校生活における活動・環境質問紙」,小中学校における教員の吃音の理解と配慮・支援の普及を意図した「子どもの吃音サポートガイド」の概要と今後の課題を述べた.
1 0 0 0 OA 蘇我氏と外来文化に関する研究
- 著者
- 小林 幹男
- 出版者
- 長野女子短期大学出版会
- 雑誌
- 長野女子短期大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.57-76, 2000-12-20
蘇我氏の系譜は、『古事記』の孝元天皇、あるいはその孫にあたる武内宿禰を祖とする説、『上宮聖徳法王帝説』などの石河宿禰を祖とする説、あるいは満智を祖とし、満智が百済の木満致と同一人物であるとする説などがある。その本居地についても、大和国高市郡の蘇我の地、大和国葛城地方、河内国石川地方とする説がある。『日本書紀』の記事によると、百済・新羅・高句麗からの氏族の渡来、および仏教をはじめとする多く文化や技術を受容したのは、応神天皇から推古天皇の時代に目立って多い。この時期は、中国や朝鮮半島の諸国が、互いに抗争を繰り返した激動の時代であり、わが国も中国や半島諸国と通交して、積極的な外交政策を展開した時期である。その前段の時代、すなわち応神天皇から雄略天皇の時代は、中国の史書『宋書』などに記されている「倭の五王」の時代と対応する年代であり、欽明天皇から推古天皇の時代は、蘇我氏が渡来系氏族を配下において、大陸文化の受容と普及に努め、開明的な屯倉経営を推進して農民の名籍編成などを行い、積極的に農業生産力の増強を図って中央政界をリードした時期である。蘇我馬子が建立した飛鳥寺は、高句麗方式の伽藍配置を採用し、北魏様式の飛鳥大仏を造り、百済から渡来した僧侶や技術指導者たちを動員して完成した。蘇我氏の開明的性格を如実に物語る歴史的事実である。4~7世紀のわが国古代の文化は、「倭の五王」などの渉外関係史、蘇我氏と渡来系氏族の研究を基礎にしてこそ、その歴史の真実に迫ることができるものと考える。
1 0 0 0 OA 若年者にみられた原発性副鼻腔・気管気管支アミロイドーシスの1例
- 著者
- 小清水 直樹 井上 裕介 伊藤 靖弘 岩嶋 大介 菅沼 秀基 小林 淳 朝田 和博 須田 隆文 千田 金吾 田井 久量
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.25-30, 2009-01-25 (Released:2016-10-29)
- 参考文献数
- 15
背景.気管気管支アミロイドーシス(以下ア症)は中高年に多くみられる疾患であり若年者の報告はまれである.症例.15歳女性.2004年より嗅覚の低下があり,アレルギー性真菌性副鼻腔炎が疑われた.2006年8月鼻出血が続き,易出血性の副鼻腔ポリープがみとめられた.当院耳鼻科でポリープ切除術を施行し,鼻腔アミロイド(AL型)と診断された.全身検索目的および乾性咳嗽にて,当科に紹介となった.気管支鏡検査では,気管下部よりびまん性に粘膜の発赤・浮腫性の腫脹があり,易出血性で気道は狭小化していた.気管支粘膜生検でもアミロイドの沈着をみとめた.明らかな基礎疾患はなく,その他の臓器にはアミロイドの沈着はみられず,原発性と考えられた.呼吸器症状は軽微で,若年者でもあることから,吸入ステロイド剤投与にて経過観察をしている.4ヵ月後の胸部CTでは,気道病変に変化をみとめていない.検索した限りでは,原発性気管気管支ア症としては,本例が最年少であった.結論.基礎疾患のない若年者にも,気管気管支ア症がみられることがある.びまん性気管気管支ア症に対する副作用の少ない有効な治療法の開発が望まれる.
1 0 0 0 OA トピック情報を利用したユーザの知識推定
- 著者
- 片山 太一 小林 のぞみ 牧野 俊朗 松尾 義博
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第27回全国大会(2013)
- 巻号頁・発行日
- pp.1F44, 2013 (Released:2018-07-30)
ユーザに合わせたシステム構築のためには、ユーザの知識を理解することは重要である。既存の研究では、人手で単語に難易度を付与し、その情報を利用してユーザの知識推定を行ってきた。しかし、専門性が高くなるとあるトピックには詳しいが他のトピックには詳しくないといったユーザもいるため、一般的な難易度のみを利用して知識推定を行うことは難しい。本研究では、トピック情報を利用することで、上記の問題を解決する。