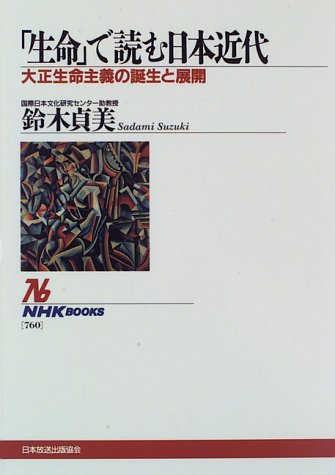1 0 0 0 OA 25pSC-1 重力発電「48」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 70.2 (ISSN:21890803)
- 巻号頁・発行日
- pp.7, 2015-09-16 (Released:2017-07-10)
1 0 0 0 OA 19aAG-1 重力発電「49」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- The Physical Society of Japan
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:21890803)
- 巻号頁・発行日
- pp.1, 2016-03-19 (Released:2017-07-10)
1 0 0 0 25pYL-8 重力発電「20」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, 2000-09-10
1 0 0 0 IR グローバリゼイション、文化ナショナリズム、多文化主義と日本近現代文芸
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.13-56, 2003-03-31
今日、日本の近現代文芸をめぐって、一部に、「文化研究」を標榜し、新しさを装いつつ、その実、むしろ単純な反権力主義的な姿勢によって、種々の文化現象を「国民国家」や「帝国主義」との関連に還元する議論が流行している。この傾向は、レーニンならば「左翼小児病」というところであり、当の権力とその政策の実態、その変化を分析しえないという致命的な欠陥をもっている。それらは、「新しい歴史教科書」問題に見られるような「日本の威信回復」運動の顕在化や、世界各国におけるナショナリズムの高揚に呼応するような雰囲気が呼び起こしたリアクションのひとつであろう。その両者とは、まったく無縁なところから、第二次大戦後の進歩的文化人が書いてきた日本の近代文学史・文化史を、その根本から――言い換えると、そのストラテジーを明確に転換して――書き換えることを提唱し、試行錯誤を繰り返しつつも、少しずつ、その再編成の作業を進めてきた立場から、今日の議論の混乱の原因になっていると思われる要点について整理し、私自身と私が組織した共同研究が明らかにしてきたことの要点をふくめて、今後の日本近現代文芸・文化史研究が探るべきと思われる方向、すなわち、ガイドラインを示してみたい。整理すべき要点とは、グローバリゼイション、ステイト・ナショナリズム(国民国家主義)、エスノ・ナショナリズム、アジア主義、帝国主義、文化ナショナリズム、文化相対主義、多文化主義、都市大衆社会(文化)などの諸概念であり、それらと日本文芸との関連である。全体を三部に分け、Ⅰ「今日のグローバリゼイションとそれに対するリアクションズ」、Ⅱ「日本における文化ナショナリズムとアジア主義の流れ」、Ⅲ「日本近現代文芸における文化相対主義と多文化主義」について考えてゆく。なお、本稿は、言語とりわけリテラシー、思想などの文化総体にわたる問題を扱い、かつ、これまでの日本近現代文学・文化についての通説を大幅に書き換えるところも多いため、できるだけわかりやすく図式化して議論を進めることにする。言い換えると、ここには、たとえば「国家神道」など、当然ふれるべき問題について捨象や裁断が多々生じており、あくまで方向付けのための議論であることをおことわりしておく。
1 0 0 0 「生命」で読む日本近代 : 大正生命主義の誕生と展開
1 0 0 0 OA <共同研究報告>江戸川乱歩、眼の戦慄 : 小説表現のヴィジュアリティーをめぐって
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.187-214, 2010-09-30
日本の一九二〇年代、三〇年代における(狭義の)モダニズム文藝のヴィジュアリティー(視覚性)は、絵画、写真、また演劇等の映像だけではなく、映画の動く映像技法と密接に関係する。江戸川乱歩の探偵小説は、視覚像の喚起力に富むこと、また視覚像のトリックを意識的に用いるなど視覚とのかかわりが強いことでも知られる。それゆえ、ここでは、江戸川乱歩の小説作品群のヴィジュアリティー、特に映画の表現技法との関係を考察するが、乱歩が探偵小説を書きはじめる時期に強く影響をうけた谷崎潤一郎の小説群には、映画的表現技法の導入が明確であり、それと比較することで、江戸川乱歩におけるヴィジュアリティーの特質を明らかにしたい。それによって、日本の文藝における「モダニズム」概念と「ヴィジュアリティー」概念、そして、その関係の再検討を試みたい。
1 0 0 0 OA 東アジア近現代の概念編制史研究の現在
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 東アジアにおける知的交流──キイ・コンセプトの再検討── = Intellectual Exchange in Modern East Asia: Rethinking Key Concepts (ISSN:09152822)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.9-22, 2013-11-29
1 0 0 0 OA インスリン抵抗性とメタボリックシンドロームに関する疫学研究
1 0 0 0 日本における生命観から見た性愛観:その学際的・通史的研究
日本における生命観についての学際的、総合的研究の一環として、性愛についての学際的・通史的研究を課題として取り組み、関連図書約500点余を購入し、国際日本文化研究センター図書室に入れた。最終年度の研究代表者、早川聞多は、絵画、とりわけ徳川時代の浮世絵春画を対象とし、そこに書かれた言葉と描かれた絵との関連を分析する新たな手法による研究を重ねて、徳川時代の性愛、とりわけ男色などに関する風俗全般の表象の研究を飛躍的に発展させた。前二年度にわたる研究代表者、鈴木貞美は、とくに明治後半期から大正期の生命観と性愛観の変容の過程を、進化論受容や大正生命主義などの思想史、「自然主義」などの文芸思想の展開、および文芸上の性愛の表現を探る論考を重ねた。井上章一は、風俗史の観点から、近・現代において性愛の営まれる場所の諸相の解明を中心に、未開拓の分野に成果をまとめた。小松和彦は、近親相姦の伝承に関して取り組み、その端緒をひらいた。全体としては、性愛学(セクソロジー)の隆盛の中で、手薄であったり、未開拓であったりした領域を開拓したものの、「生命観から見た性愛観」という角度に絞ったまとめがなし切れなかった。「生命観」という研究対象がアモルフなものなので、研究過程にあっては、いたしかたないともいえるが、今後は「生命観」の研究それ自体の確定とアプローチの角度の分節化など、方法の明確化が必要であるとの結論に達した。鈴木貞美がこれを今後の課題として分担することを確認し、終了した。
1 0 0 0 生命観の近代--進化論受容を中心に (特集 生命)
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 昭和堂
- 雑誌
- 日本の哲学 (ISSN:1346051X)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.52-70, 2002-12
1 0 0 0 1p-ZK-9 重力発電「V」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集. 年会
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, 1993-03-16
1 0 0 0 5p-J-9 重力発電「IV」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 秋の分科会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.1, 1992-09-14
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 年会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, 1985-03-31
1 0 0 0 21p-E-7 重力発電「14」
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, 1997-09-02
- 著者
- 鈴木 貞吉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, 2010-08-18
- 著者
- 鈴木 貞美
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.315-348, 2008-09
和辻哲郎(一八八九―一九六〇)の『ニイチェ研究』(一九一三)は、彼の哲学者としての出発点をなす書物であり、同時に、日本における初めてのまとまったフリードリッヒ・ウィルヘルム・ニーチェ(Friedrich Willhelm Nietzsche, 1844-1900)の研究書として知られている。また、そこに示された考え方は、その後の彼の歩みに、かなりの意味をもつものとなった。 本稿第一章では、『ニイチェ研究』の立場、方法、意図を分析し、「宇宙生命」を原理とする初期和辻哲郎の哲学観が大正生命主義の一典型であることを明らかにする。第二章「『ニイチェ研究』まで」では、和辻哲郎の最初期の著作にニーチェへの接近の跡をたどり、第三章では、内的経験、暗示象徴、永遠回帰、宇宙生命などのキイワードについて考察し、また同時代思潮との関連をさぐる。第二章、第三章をあわせて、初期和辻の哲学観、世界観(狭義の哲学観、表現観)の形成過程を明らかにする。「結語」では、各章の結論をまとめるとともに、和辻哲郎の初期哲学が、その後の歩みに、どのように働いているかを展望する。 なお、本稿は、和辻哲郎の「哲学」「芸術」観をめぐって、「修養」及び「人生論」との関係を探る点で、二十世紀初頭の学芸ジャンル概念編成の解明に資するものであり、同時に和辻哲郎の「宇宙生命」観念と、その形成過程を探る点において、二十世紀初頭の生命観、とりわけ大正生命主義研究を増補するものである。
1 0 0 0 九州西方における非島弧的マントルアップウェリング構造の検証
本研究実績は大きく分けて2つに分類される。第1は1999年9月末より10月上旬まで、九州西方海域で行われた地殻構造の大規模な調査であり、第2は自然地震の走時データを用いたトモグラフィーの研究である。第1の研究は本研究最大の実績ともいうべきもので、九州西方海域での地殻構造調査の成功とそのデータ解析結果である。平成11年度9月末より10月上旬まで、発破とエアガンを使った地殻構造の大規模な調査を行った。まず地殻構造調査においては,海底地震計で得られたデータは見かけ速度の変化に富んでいて、地殻上部の構造の複雑さを示していた。得られた地震波速度構造モデルでは、堆積層は二層に分けられ。上部層はP波速度1.7〜1.9km/sの垂直速度勾配が小さい厚さ200〜500mの層であり、下部層は2.0〜3.5km/sの垂直速度勾配がやや大きい層が800〜3500m存在する。上部地殻は二層に分けられ、第一層の上面のP波速度は3.0〜4.9km/sと水平方向に大きく変化している。この層の下面のP波速度は4.2〜5.3km/sである。第二層として、上面のP波速度は5.6〜5.9km/sの層が存在する。この層の下面のP波速度は6.0〜6.2km/sである。海面から上部地殻と下部地殻の境界までの深さは約10kmである。下部地殻の上面のP波速度は6.5〜6.7km/sのである。モホ面の深さは海面から約26kmと求められ、マントル最上部のP波速度は7.7〜7.8km/sと求められた。沖縄トラフで、モホの深さやマントル最上部のP波速度がこのように正確に求められたのは初めてのことである.第2の成果として、地震トモグラフィーの研究を上げられる。平成12年度はその結果を使って、特に背弧上部マントルの低速度異常領域について調べた、これはマントルのマントルアップウエリングとの関係で注目される。
1 0 0 0 近代中国東北部(旧満州)文化に関する総合研究
中国の東北部、つまり旧「満州」は日本の近代史においてきわめて重要な場所である。なぜならば、日清戦争はさることながら、その後の日露戦争、日中戦争、さらに日米戦争に至るまで、いわば日本の運命を決めた戦争という戦争は、究極のところ、全部この地域の権益をめぐって起こされたものであり、ある意味において、日本の近代はまさに「満州」を中心に展開されたとさえ認識できるからである。しかし、近代日本の進路を大きく左右したこの旧「満州」について、これまではけっして十分に研究したとは言い難い。むろん、旧「満州」、とりわけ「満鉄」に関する歴史学的なアプローチに長い蓄積があり、多くの課題においてかなりの成果を挙げている。だが、よく調べてみれば、そのほとんどがいずれも政治、経済、あるいは軍事史に偏っており、いわゆる当時の人々の精神活動、あるいは行動原理に深く影響を与えた社会や文化などについての考察が意外にも少数しか存在していない。本研究は、いわば従来あまり重視されなかった旧「満州」の社会や文化などの諸問題を取り上げ、関連史実等の追跡を行う一方、とりわけその成立と展開に大きく関わっていた「在満日本人」の活動を中心に、できるかぎりその全体像を整理、解明しようとした。そして三年間の研究を通して、主に以下のような成果を得ることができた。1.これまで重視されなかった旧「満州」の社会や文化などの問題について比較的総合かつ多角的に追及し、多く史実(都市空間、公娼制度、秘密結社、文芸活動など)を解明した。2.海外共同研究者の協力を得て、多くの史料、とりわけいわゆる在満日本人の発行した各分野の現地雑誌を発掘し、その一部(「満州浪曼」、「芸文」)を復刻、またはその関連作業に取り組み始めた。3.従来、難しかった現地研究者との交流を実現させ、三回の国際研究集会を通じて、多くの中国や韓国研究者とさまざまな問題について意見を交換した。以上のように、この三年間は、現地調査などを通して、多くの貴重な史料を入手したばかりでなく、現地研究者との間に比較的親密な協力関係も築いたため、今後もこれらの成果を生かすことにより、一層の研究上の進展が得られるだろうと思われる。
- 著者
- 吉野 浩一 大野 範夫 鈴木 貞興 藤井 杏美
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
【はじめに】<BR>立位バランスまたは歩行時の安定性に大きく関与していると考えられる足趾の機能を評価することは、下肢の疾患に対する理学療法を施行するうえで重要である。臨床上も立位バランス不良の症例において、足趾の開俳運動不全を呈していることをしばしば経験する。そこで今回、足趾開俳機能と足趾把持機能との関連性について検討したので報告する。<BR>【対象と方法】<BR>対象者は測定時に下肢に愁訴のない成人男性22名,44足を対象とした。平均年齢は29.2±4.5歳,平均身長172.3±5.3cm,平均体重66.5±6.6kgであった。足趾の開俳は足関節底背屈0°にて、自動運動で足趾の開俳が可能であるかを評価した。その際、代償運動排除のため足部のMP関節伸展に制限を加えた。可否の判定は足趾間の接触がなく開俳可能なものと定義した。その後、全被験者の足趾屈筋の筋力(把持力)を測定した。測定にはT.A.G.メディカル社製EZフォース(プロトタイプ)を使用し、自作の足趾把持用のバーを取り付け測定した。測定肢位は自然立位とし、片側に対し3回施行し両側の測定を行った。測定された数値(peak)は3回の平均値とし、体重で除し体重比で算出した。尚、測定された筋力は全足趾開俳可能群(以下開俳群)と非開俳可能群(以下非開俳群)に分け、開俳機能と足趾屈筋筋力との関係について比較検討した。統計処理にはマン・ホイットニ検定を用い危険率5%以下を有意とした。<BR>【結果】<BR>22名44足中、11名の両側22足に足趾の開排不全が認められた。開排不全の最も多かったのは4,5趾間で13足、ついで3,4趾間9足、2,3趾間5足、1,2趾間5足であった。尚、2趾間以上重複しての開排不全は10足であった。また、足趾把持筋力(体重比)の平均値は開排群0.146±0.03kg/BW、非開排群0.108±0.02kg/BWで(p<0.05)にて有意差を認めた。<BR>【考察】<BR>今回の実験において足趾開排の差における足趾把持筋力の有意差が確認できた。これは足趾同士が接触せず、足趾間が開排する事により屈筋がより収縮しやすい足趾の肢位に置かれたことによるものと思われる。この結果、足趾の把持能力改善には足趾の開排運動が有効であることが示唆された。また、足趾別の検討として、非開排群においては4,5趾間の開排不可が13足と多く、この影響も考えられたが、重複した開排不全が10足あり、足趾別の把持力貢献度は今回の実験では検討することはできない。今後、足趾固有の機能についても検討していきたい。<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>