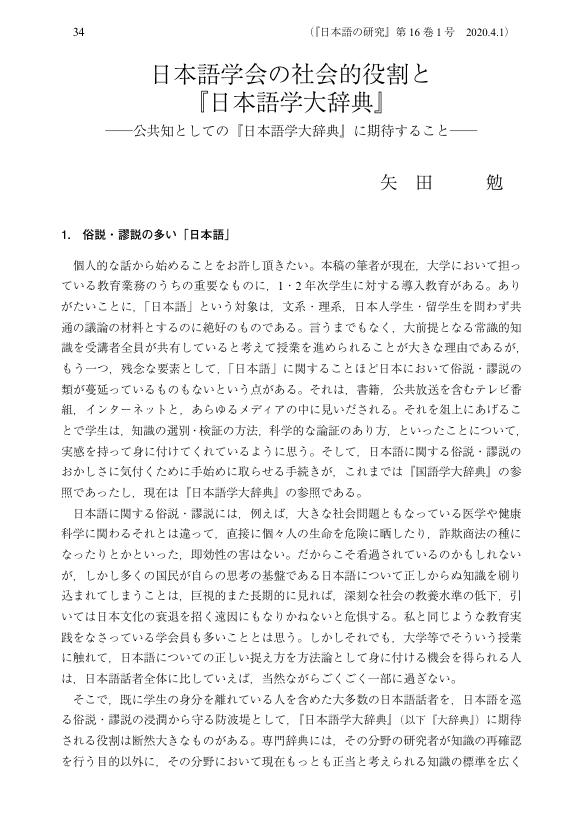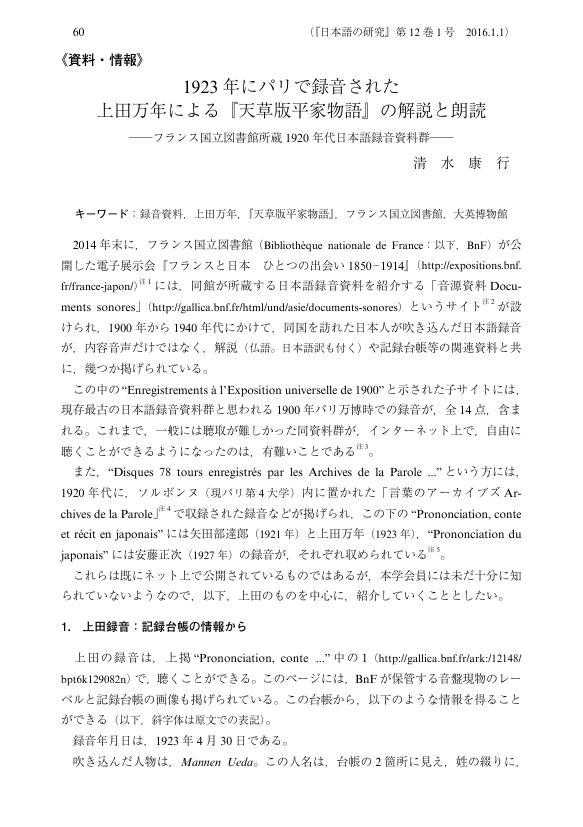921 0 0 0 OA 日本語学会の社会的役割と『日本語学大辞典』 ──公共知としての『日本語学大辞典』に期待すること──
- 著者
- 矢田 勉
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.34-41, 2020-04-01 (Released:2020-06-01)
35 0 0 0 意味変化の東西差 : 方言「エズイ」を例として
- 著者
- 櫛引 祐希子
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.31-46, 2009
エズイは中世の中央語として<対象を厭わしく感じる程度の恐怖感>を表していたが、各地に伝播して意味変化を起こした。関東に伝播したエズイは意味変化を重ね、関東で新しく生まれた意味が東北に伝播して二次的な意味変化を起こした。一方、西日本の各地域に伝播したエズイは個々の地域で独自の意味変化を起こした。このように中央語のエズイは関東を挟んだ東西の地域に伝播した結果、東では関東と東北で段階的な意味変化を遂げ、西では各地域で個別的な意味変化を遂げた。エズイが起こした意味変化の東西差は、東日本では関東が東北に対して求心力を持っていたこと、西日本では中央を除くと関東のような求心力を持った地域がなく複数の地域が拮抗状態にあったことを示唆する。
32 0 0 0 OA 語彙史・語構成史上の「よるごはん」
- 著者
- 橋本 行洋
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.33-48, 2007-10-01
<夕食>を意味する「よるごはん」は、現在若年層を中心に使用される新語と見なされているが、その成立は少なくとも第二次大戦前後にまで遡ると見られる。当初は児童が用いる稚拙な印象の語であったため、文字資料に残されることが少なかったが、近年では夕食時間帯の遅延や朝食の欠食という食環境の変化に伴い、これが妥当な表現という意識が生じて使用が拡大し、新聞記事や国会発言および小学校教材等でも使用されるという、《気づかない新語》としての性格をも有するに至っている。「よるごはん」の成立要因としては、<夕食>時間帯表現における「よる」の使用があげられるが、さらにその遠因に、二食時代の「あさ」-「ゆう」の対応に「ひる」が加わった結果、「ひる」-「よる」という対応意識の生じたことが存すると考えられる。「よるごはん」の出現は、食事時間帯語彙に「よる」が加わった点で新しいものであるが、旧くは存在しなかった「よる」を前項要素とする複合語という点においても特筆すべき存在で、語彙史・語構成史の両面から注目すべき語と言える。
23 0 0 0 OA 日本語学大辞典について
- 著者
- 下地 理則
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.42-50, 2020-04-01 (Released:2020-06-01)
- 参考文献数
- 11
20 0 0 0 OA 九州地方における「天国」の受容史 : 宗教差,地域差,場面差
- 著者
- 小川 俊輔
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.1-14, 2012-04-01
九州地方における「天国」の受容の程度を明らかにするため,九州地方全域300地点において現地調査を行った。調査によって得られた資料から言語地図を描き,考察を行ったところ,「天国」の受容には,宗教差,地域差,場面差のあることが分かった。宗教差については,カトリックと神道の信徒が「天国」を受容しているのに対し,浄土真宗の信徒は「天国」を受容しない傾向がある。彼らは仏教語である「浄土」を持つゆえに,「天国」を受容しない傾向をみせたと推測される。地域差については,宮崎・鹿児島では「天国」の受容が進んでいるのに対し,長崎では遅れている。場面差については,大人が子どもに話しかける場面では「天国」が使用されやすいのに対し,仏教色の強い場面では「天国」が使用されにくい。
18 0 0 0 OA 近世板本において併用された楷書体漢字と平仮名
- 著者
- 久田 行雄
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.101-86, 2019-08-01 (Released:2020-02-01)
現在、日本語の表記で使用される楷書体漢字平仮名交じり文という書記体は、近代以前においては一般的ではなく、活版印刷の導入を機に使用されるようになったと指摘されてきた。しかし、本稿の調査により、一八世紀初期に出版された医書に楷書体漢字平仮名交じり文の使用例が確認されること、この書記体は一八世紀中期には仏書へと広がり、一八世紀後期以降にさらに使用範囲が広がっていくことを明らかにした。楷書体漢字と平仮名が併用されるようになったのは、楷書体漢字との併用を許容する程に平仮名の役割が徐々に変化してきたからであろうと指摘した。このような表記意識の変化が、一八世紀を通して社会に広がっていったことを明らかにした。
15 0 0 0 OA 複合助詞「であれ」「にせよ」「にしろ」の変遷
- 著者
- 北﨑 勇帆
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.1-17, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 27
本稿では, 動詞「あり」「す(る)」の命令形を用いて逆接仮定的な構文を作る複合助詞「であれ」「にせよ」「にしろ」について, その形態の歴史的変遷を調査した。「であれ」相当形式は中古に「用言連用形+もあれ」「体言+にもあれ」として発生し, 中世以降, 体言が前接する場合に限って「にてもあれ」「でもあれ」へと姿を変える。「にせよ」「にしろ」相当形式は中世頃に「動詞連用形+もせよ」として発生し, 近世に「にもせよ」「にもしろ」が現れると, 次第に「であれ」相当形式の使用数を上回る。この移行の要因として, 動作についての逆接仮定を示すために補助動詞「す」が採用されたこと, 体言・用言のいずれに対しても同形態で接続できる「にもせよ」「にもしろ」に利便性があったことを論じた。
15 0 0 0 OA Exercises in the Yokohama Dialectと横浜ダイアレクト
- 著者
- カイザー シュテファン
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.35-50, 2005-01-01
本稿は、開港のころ横浜居留地で発生した横浜ダイアレクトの唯一まとまった資料であるExercises in the Yokohama Dialectについて、出版状況を当時の資料により検討し、初版が1873年に出たことなどを明らかにした。また、横浜ダイアレクトの使用者・使用場面について当時の資料を参考に考察し、少なくとも1861年以降の横浜で外国人と日本人の接触場面における商談などが双方向のピジン日本語で行われたこと、そのピジン語を記述した資料としてExercisesが信頼性のある文献であることを確認した。さらに、後世の日本語文献で取り上げられている「横浜言葉」とその資料として使われた「異国言」などの資料を検討し、開港当時の日本人が英語のピジンを話していた証拠とすることができないことを主張した。
14 0 0 0 OA 狭母音の無声化の全国的地域差と世代差
- 著者
- 邊 姫京
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.33-48, 2007-01-01 (Released:2017-07-28)
全国の母音の無声化生起にかかわる要因を探るため,1986〜1989年にかけて収集された音声資料「全国高校録音調査」の41府県の話者,老若608名の音声の音響分析を行なった。無声化生起と音環境,及び地域差との関係,世代差との関係について調べた。その結果,従来無声化が目立つとされる地域の無声化生起率はおよそ60%以上であること,ほとんどの府県において後続する子音の種類(破裂音,摩擦音,破擦音),無声化拍の後続拍の母音の種類(狭母音,非狭母音)により無声化生起率に有意差があることがわかった。また無声化の生起には地域差に加え,世代差があり,東北地方において特に世代差が著しいことが確認された。これらは語中の無声化について得られた結果であり,語末では地域にかかわらず全体として無声化生起率が非常に低く,一般的な無声化の生起環境でないことが明らかになった。
- 著者
- 文 昶允
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.18-34, 2017-07-01 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 23
本研究では,複合構造を持つ外来語から形成される短縮語を取り上げ,その語形成過程にみられる世代差の実態について,仮想語を用いた実験を通じて分析する。前部要素の2モーラ目に長音を含む複合外来語に基づいて短縮語が形成される際には,短縮語の出力形にその長音が保たれるタイプ(保持形)と,長音を組み込まず,長音の直後にある自立モーラで全体のモーラ数を補うタイプ(補完形)に加え,長音が短縮形に組み込まれず,かつ補完形も取らないタイプの3パターンが生じる。本研究で行った仮想短縮語実験を通じて得られた結果は以下の2点である。第一に,複合外来語に由来する短縮語形成過程においては,保持形が一般に選択されやすい傾向が観察される。第二に,中・高年齢層が専ら4モーラ短縮形を好む一方,若年齢層には3モーラ短縮形という変則形をも許容する傾向が指摘できる。これは,短縮語形成の方略が世代間で異なることを示唆している。
14 0 0 0 いわゆるパーフェクトの「シタ」について
- 著者
- 井上 優
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 國語學 (ISSN:04913337)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.94-95, 2001-09-29
(1)のような「シタ」は,対応する否定形式が「シナカッタ」でなく「シテイナイ」となることから,「完成相過去」ではなく,「パーフェクト相現在」を表すと言われる。(1)「もう昼飯を食べたか?」「いや,まだ食べていない(×食べなかった)。」しかし,(1)の現象は「シタ」がパーフェクト性を持つことを示すものではない。むしろ,(1)は次の(2)と同様,直接の対応関係にない肯定形式と否定形式が一定の文脈の中で対をなして用いられる(見かけ上対応するように見える)だけのケースである。(2)(ワイシャツについたシミを落としながら)a よし,落ちた。b なかなか落ちないなあ(×落ちてないなあ/×落ちなかったなあ)。(2)bの「落ちない」は「現在`落ちる'ことが実現される様子がない」ことを表す。これに直接対応するのは「現在`落ちる'ことが実現される様子がある」ことを表す「落ちる」であり,「落ちた」ではない。(1)もこれと同類の現象である。現代日本語の「シタ」は,「過去にこのようなことがあった」ということを表すだけでなく,「出来事全体を(その前後を含む)継起的な時間の流れの中に位置づける」という動的叙述性が顕著である。そして,それに呼応する形で,「シナカッタ」も「当該の出来事が実現されないまま終わった」ことを表し,単に「このようなことは過去にない」ということの叙述はパーフェクト相現在「シテイル」の否定形「シテイナイ」が担う。その結果,(1)のように当該の出来事が実現される可能性が残されている文脈では,「シナカッタ」ではなく,「シテイナイ」が用いられることになる。つまり,(1)の現象は,「シタ」の動的叙述性の強さ(ある意味では完成性の強さ)を示すものであり,「シタ」がパーフェクト性を持つことを示すものではない。
13 0 0 0 関西若年層の用いる同意要求の文末形式クナイについて
- 著者
- 高木 千恵
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.1-15, 2009-10
関西若年層が使用する文末形式クナイについて,自然傍受による用例収集と大学生対象のアンケート調査をもとに,韻律的・形態的・構文的特徴および文法的意味を中心に考察した。イ形容詞の否定疑問形式に由来するクナイは,疑問上昇調のイントネーションを伴い,主として動詞の基本形に後続することが多い。意味的には本来の<否定>としての機能を失っており,<同意要求>に特化したモダリティ形式である。関西におけるこのようなクナイの成立には,動詞述語の二重否定(疑問)形式であるンクナイ・ヘンクナイがすでに定着していたこと,および<同意要求>にコトナイという形式が使われていたことが関わっている。また,クナイを東京のことばと捉えている話者がおり,東京語化に対する抵抗感がクナイの浸透を阻む可能性もある。
13 0 0 0 OA 富山県呉西地方における尊敬形「〜テヤ」 : 意味・構造の地域差と成立・変化過程
- 著者
- 小西 いずみ 井上 優
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.33-47, 2013-07-01
富山県呉西地方には動詞尊敬形「〜テヤ」があり,南部の井波では継続相,北部の高岡では非継続相を表す。いわゆる「テ敬語」にあたる形とされてきたものだが,両方言とも基本終止形〜テヤが連体形・疑問形にもなり,このヤをコピュラとはみなせない。井波方言では,否定形が「〜テ(ン)+補助形容詞ナイ」であること,アクセントが「〜テ+補助用言」に準じることから,「〜テ+助動詞ヤ(コピュラとは別語)」と分析でき,高岡方言では,否定形が〜ンデヤとなること,アクセントが中止テ形やタ形に準じることから,テヤを一つの接尾辞だとみなせる。井波より南の五箇山には「〜テ+存在動詞アル」に由来する継続相尊敬形「〜テヤル」があり,井波のテヤはその変化形,高岡のテヤはさらにそれが変化したものと推測される。こうした呉西地方のテヤ形の成立・変化は,上方語や他の西日本方言の「テ敬語」の成立についても再考の余地があることを示唆する。
12 0 0 0 OA 1923年にパリで録音された上田万年による『天草版平家物語』の解説と朗読
- 著者
- 清水 康行
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.60-67, 2016 (Released:2017-01-24)
- 参考文献数
- 20
12 0 0 0 OA 「イラッシャル」に生じている意味領域の縮小
- 著者
- 水谷 美保
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.32-46, 2005-10-01 (Released:2017-07-28)
<行く><来る><いる>の尊敬語形式について,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県に生育し居住する20歳以上の146人を対象にしたアンケート調査と,東京出身作家76人(76冊)の小説を用いた調査を行い,「イラッシャル」は,表すとされてきた<行く><来る><いる>それぞれの意味で用いられるのではなく,<来る><いる>としては使用され続けているが,<行く>には用いられなくなりつつあることを明らかにした。この変化の主な要因としては,「イラッシャル」は敬意によって動作主の移動の方向を中和するよりも,話し手が自身の関わる移動を,優先して表すようになったことにあるとした。そのために,「イラッシャル」が表す移動は,話し手(の視点)の位置が動作主の到達点となる<来る>になり,移動を表すことを同じくしながら,話し手の関わりが大きくない<行く>は,「イラッシャル」の意味領域から排除されることになった。
- 著者
- 平子 達也
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.1-15, 2013-01-01
本稿は,観智院本『類聚名義抄』中にある平声軽点の粗雑な写しと見られるものを利用し,従来同じ下降調として再建されてきたものの中に現れ方の異なる二つのものがあったことを示すものである。まず,観智院本『類聚名義抄』の中で,従来下降調として再建されるものに差されている声点のうち平声点位置に見られるものを下降調を示す平声軽点の「粗雑な写し」であると認められることを示した。そして,下降調として再建される形容詞終止形接辞「シ」と二音節名詞5類の第二音節に差される声点の在り方が異なることを示し,同じ下降調でも現れ方の異なる二つのものがあることを明らかにした。最後に本稿での議論を踏まえ,従来から議論のある[HF]型の存否の問題について論じた。
- 著者
- 金 銀珠
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.123-137, 2006-04-01
近代文法学における「形容詞」は,江戸時代以来の伝統的な形容詞論をスタートラインにおけば,その規定が最初は名詞修飾機能中心へと移行し,次は叙述機能中心へと移行しながら,成立したものである。このような二度の移行に関わっていたのが西洋語のAdjective解釈である。本稿は,近代文法学における「形容詞」「連体詞」概念がどのように成立したのかを,西洋文法におけるAdjectiveとの関連から考察した。近代文法学の「形容詞」概念がAdjectiveを名詞修飾だけに極度に限定していきながら成立し,その結果として,今日の学校文法における「連体詞」が登場する過程を示した。
11 0 0 0 OA 恋愛用語「三角関係」と"三角恋愛"の成立と定着 : 1920年代の日中語彙交流の視点から
- 著者
- 清地 ゆき子
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.46-61, 2010-04-01 (Released:2017-07-28)
本稿は,日中語彙交流の視点から日本で訳語として成立した恋愛用語が,1920年代に中国語に借用されたことを明らかにすることを目的として,日中異形同義語「三角関係」と"三角恋愛"の成立及び定着過程を考察したものである。結論は次の4点てある。(1)「三角関係」は,1910年代後半に森鴎外や島村民蔵により訳語として成立した可能性が高い。(2)"三角関係"は1920年代初め,日本語借用語彙として中国人留学生らの創作作品などを介して中国語にもたらされた。(3)中国語では"三角関係"ではなく,1920年代前半に日本でも一時期使用された"三角恋愛"が定着した。(4)中国語において"三角恋愛"が定着した背景には,1920年代前半に,《婦女雑誌》を中心として,恋愛が頻繁に議論された社会状況があった。
11 0 0 0 OA 「変体漢文」の研究史と「倭(やまと)文体」
- 著者
- 毛利 正守
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.1-15, 2014-01-01
現在,古事記などの文章は,「変体漢文」であると一般に把握されている。「変体漢文」という呼称は,橋本進吉によって提唱され,漢文を記すことを志向しながらもその用法を誤って「変則な書き方」になったもの,それを「変体漢文」と命名した。一方,橋本は,古事記などの文章については,漢字を用い慣れるに従って日本語をも漢字で書くようになり,その文章は「変体漢文」ではなく「和文」であると把握した。それ以降の研究史を辿ってみると,橋本の道理に適った「変体漢文」という捉え方が正確に継承されず,橋本の主要な発言を見過ごし,また誤解したまま今に至っているというのが現状である。が,その捉え方がすでに長く行われているのだからそれでよしとするのではなく,もう一度,理に適った論に立ち返り,考え直すべきであると筆者は考える。本稿は,研究史の実態を炙り出すところにその主眼をおき,あわせて研究史と関わらせつつ倭(やまと)文体についてとり挙げることにする。