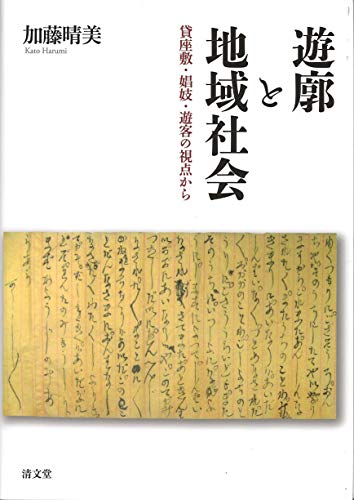1 0 0 0 IR <図書紹介>『映像学原論』 植条則夫著 ミネルヴァ書房,1990年
- 著者
- 伊藤 弘
- 出版者
- 関西意匠学会
- 雑誌
- デザイン理論 (ISSN:09101578)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.143-144, 1991-11-15
1 0 0 0 最高裁判所民事判例集
- 著者
- 最高裁判所事務総局編
- 出版者
- 最高裁判所判例調査会
- 巻号頁・発行日
- 1947
- 著者
- 大石 岳史 池内 克史
- 出版者
- 情報処理学会 ; 1960-
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.1235-1240, 2014-10-15
本章では,東京オリンピック招致の際に利用されたVR/AR・MR技術について概説する.前回,2016年招致の際には,晴海ふ頭に建設予定のスタジアムをVR/MR技術によって再現し,未来の競技を体験できるシステムによって国際オリンピック 委員会(IOC)委員へのプレゼンテーションが行われた.また今回2020年の招致 活動においてもAR技術によって競技をより魅力的に観戦できるアイディアが紹介映像の中で用いられ,日本の技術力をアピールするとともに招致に大きく貢献した.本章ではこれらの技術について紹介し,さらに2020年東京オリンピックにおける映像処理技術への期待について述べる.
1 0 0 0 OA BERTで獲得する各場面の分散表現を用いたコサイン類似度に基づく小説の挿絵推薦
- 著者
- 下窪 聖人
- 出版者
- 法政大学大学院情報科学研究科
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要. 情報科学研究科編 (ISSN:24321192)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.1-6, 2021-03-24
In recent years, E-book provides many opportunities that people read books during a commute or break time. Though an E-book reader provides some useful functions for reading the books. This system enables a new function of recommending illustrations during one is reading. This is achieved by calculating cosine similarity which uses the BERT based distributed representation of each scene. There are mainly 4 steps: (1) this system divides texts into some scenes by TopicTiling; (2) the important sentences are extracted by using BERT for each scene; (3) subjects, verbs, and objects are extracted using MeCab and CaboCha; and (4) the system recommends appropriate illustrations by calculating similarity between the sentences by using the analysis results and image titles. As expected, this system can recommend illustrations for a reader to form the image when he is difficult to understand E-book in only text content. These recommended illustrations are original from the illustrations of the web site “irasutoya”. As a result of the experiment, the accuracy of the illustration’s recommendation was about 72.0 percent. This result was obtained by using CNN to convert the image style of both the original and the recommended illustrations, and then evaluating them by SSIM.
1 0 0 0 OA 「山家学生式」について
- 著者
- 古田 榮作 Eisaku FURUTA
- 出版者
- 大手前女子大学
- 雑誌
- 大手前女子大学論集 = The Journal of Otemae Women's University (ISSN:02859785)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.061-089, 1999-02-20
1 0 0 0 OA 「山家学生式」創出の思想的根拠――最澄の提示した“速成的方法”――
- 著者
- 上原 雅文
- 出版者
- 国士舘大学哲学会
- 雑誌
- 国士舘哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, 1999-03
1 0 0 0 さまよえるキリスト教 : 21世紀に生き残れるのか
- 著者
- 河合 吉彦 住吉 英樹 八木 伸行
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム一般講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.185-186, 2007-08-22
1 0 0 0 OA 深海底タービダイトを用いた南海トラフ東部における地震発生間隔の推定
- 著者
- 池原 研
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.4, pp.471-478, 2001-08-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 12 14
Deep-sea turbidite has potential for paleoseismicity analysis. Many deep-sea turbidites were intercalated in two sediment cores collected from two slope basins off Tokai area along the eastern Nankai Trough. Geological and topographic setting of the basins suggests that these turbidites were of earthquake origin. Depositional age of each turbidite layer was determined by radiocarbon dating using planktonic foraminifera in hemipelagic mud. The results indicated that large earthquakes along the eastern Nankai Trough might have occur periodically every 100-150 years during the last 3000 years.
1 0 0 0 OA 日本における発達障害児に対する学校適応支援を目的とした作業療法の評価
- 著者
- 助川 文子 伊藤 祐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.663-673, 2019-12-15 (Released:2019-12-15)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
本研究は,日本の小学校通常学級に在籍し特別支援教育の対象となる発達障害児に対し,平成29(2017)年度に行われた学校適応支援のための作業療法評価の実態を調査することを目的とした.日本作業療法士協会に,職域を「発達障害」の「臨床」と登録した1,594名の作業療法士を対象に質問紙による全数調査を行った.有効回答は324件で有効回答率は20.3%であった.結果より,日本の発達障害児に対する作業療法は,医療法関連施設,および児童福祉法関連施設の双方で実施され,多くの評価は,感覚統合理論を基盤とする評価とDTVP視知覚発達検査を組み合わせて実施していた.また最も利用されている評価は臨床観察で,標準化した評価の活用は少なかった.
1 0 0 0 OA 白居易の茶詩 ―――茶詩の新しい姿
- 著者
- 馮 艶
- 雑誌
- 摂大人文科学 = The Setsudai Review of Humanities and Social Sciences (ISSN:13419315)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.143-156, 2014-01
1 0 0 0 IR ふなっしーの魅力はどこまでグローバルになれるか
- 著者
- Papia Daniel
- 出版者
- 武蔵野大学グローバルスタディーズ研究所
- 雑誌
- Global studies (ISSN:24327476)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.93-100, 2017-03-01
1 0 0 0 小麦新奨励品種'ネバリゴシ'粉による製めん
- 著者
- 関村 照吉 笹島 正彦
- 出版者
- 岩手県工業技術センター
- 雑誌
- 岩手県工業技術センタ-研究報告 (ISSN:13410776)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.69-72, 2001-09
岩手県は、平成12年に低アミロース小麦で製めん適性が優れているとされている小麦の新品種'ネバリゴシ'(旧東北206号)を奨励品種とした。当センターでは、ネバリゴシ粉を用い既存のめんには無い特徴のあるめんができることを既に報告している。本年度は、温めて食べるうどんと冷たいまま食べるうどん、中華めん及び中華まんじゅうを製造して官能試験を実施した。また、製めん条件を検討した。その結果、温かいうどんではゆで伸びしやすく、色の評価は良くなかった。中華めんと中華まんじゅうでは評価の良否が分かれた。また、従来の製めん試験法はそのままでは適応することができないことが判った。
1 0 0 0 OA 京都を中心とせる校外教育
- 著者
- 京都市小学校教員会 編
- 出版者
- 京都市小学校教員会研究部
- 巻号頁・発行日
- 1938
1 0 0 0 遊廓と地域社会 : 貸座敷・娼妓・遊客の視点から
1 0 0 0 OA H-IIロケット 宇宙への挑戦
- 著者
- 柴籐 洋二
- 出版者
- 日本宇宙生物科学会
- 雑誌
- Biological Sciences in Space (ISSN:09149201)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.95-105, 1995 (Released:2006-02-01)
The development program of the H-II rocket has been initiated in 1985. The H-II rocket is a new expendable launch vehicle to meet a demand of space activities in the 1990's. With the successful development if the N rocket family,, Japan has established the technology for launching satellite into Geostationary Earth Orbit (GEO). The National Space Development Agency of Japan(NASDA) has made a major effort to obtain a heavier launch vehicle, capable of meeting the increasing needs of GEO mission. Following the II 1 rocket capable of carrying a 550 kilogram satellite into GEO and ready for a first launch in August 1986, a new launch vehicle called the H-II rocket is being planned to carry a 2 ton satellite into GEO and to be most cost effective per payload ton into GEO. This launch vehicle is of 100 percent domestic design and Japan will be able to have an independent and competitive capability in the field of space transportation systems. First launch of the H-II rocket was performed successfully in February 1994. After that, second and third H-II rocket were launched in august 1994 and march 1995.
1 0 0 0 北里大学一般教育紀要
- 著者
- 北里大学一般教育組織 [編]
- 出版者
- 北里大学一般教育組織
- 巻号頁・発行日
- 1999
- 著者
- 星野 敦 仁田坂 英二 JAYAKUMAR Vasanthan 榊原 康文
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.39-46, 2017
1 0 0 0 OA 当院通所リハビリテーション利用者における高齢者の社会参加と生きがいとの関連について
- 著者
- 大浦 洋一 小西 隆洋 井手 満雄 森田 正治
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会 九州ブロック会
- 雑誌
- 九州理学療法士学術大会誌 九州理学療法士学術大会2021 (ISSN:24343889)
- 巻号頁・発行日
- pp.16, 2021 (Released:2022-02-03)
【はじめに】今後さらに高齢化が進むわが国において健康寿命を延ばすことが課題となっており、その一つとして高齢者の社会参加が注目されている。社会参加には健康増進活動、ボランティア活動、地域活動など様々あるが、地域高齢住民を対象とした先行研究において、社会参加の機会を有する高齢者は、そうでない高齢者に比べ認知機能が高く、フレイル(虚弱)の割合が低いことが報告されている。しかし、生きがいとの関連については十分に明らかにされておらず、過去に科学的根拠を整理した研究はほとんどない。筆者らが行った研究では健康増進活動を主とした社会参加活動について生きがいは有益な効果があると結論付けたが、具体的な要因は何であるのか、生きがいの構成4 因子(生活充実感・存在感・自己実現意欲・生きる意欲)と社会参加活動との関連を言及するまでには至っていない。本研究では当院通所リハビリテーション利用者を対象とした質問紙調査の結果をもとに、社会参加と生きがいの主要因について関連を検討する。【方法】本研究は2020 年11 月から2021 年2 月までの当院通所リハビリテーションを利用する65 歳以上の要支援者24 名(男性10 名、女性14 名)とし、対象者に質問紙調査を実施した。生きがい評価として、生きがい感スケール(16項目4 因子(1)自己実現と意欲(2)生活充実感(3)生きる意欲(4)存在感)を使用した。満点は32 点、カットオフ値を17 点とし、統計解析はWindows 版SPSS24 を用い、Mann-WhitneyU 検定により、生きがい感との関連を確認した。また、社会参加項目(年齢、性別、配偶者、家族形態、健康状態、暮らしぶり、外出頻度、外出手段)についても比較検討を行なった。なお、有意水準は5%とした。【結果】対象は生きがい高い群(A 群)が15 名、生きがい低い群(B 群)が9 名で、参加者の多くが81 歳から90 歳の後期高齢者であった。A 群は男性3名、女性12 名であり、B 群は男性7 名、女性2 名であった。2 群間の男女割合としてA 群は女性が有意に高く、B 群は男性が有意に高かった。生きがい感は、自己実現因子にける「心のよりどころ(P=0.001)」、「向上したと思える(P=0.002)」、「他人から評価されている(P=0.014)」、「何か成し遂げた(P=0.034)」、存在感因子における「私がいなければだめだ(P=0.047)」、「世の中や家族のために役に立っている(P=0.025)」、「家族や他人から期待されている(P=0.025)」の因子において生きがい感との間に有意な関連性を認めたが、他の生活充実感と生きる意欲との間には関連を認めなかった。【考察】地域で生活している虚弱高齢者の生きがい要因を確認することは地域包括ケアシステムを機能させる上で意義があると考える。本研究の結果から、A 群では多くが女性に日常生活活動を向上・維持したいという意欲が受動的に見られ、特にその要因として自己実現因子と存在感因子を主としていた。高齢者の老年期は生きがい感を喪失しやすい危機に直面するものの、新たな生きがい感の源泉や対象を見出すことで再獲得できる力を持つと考えられている。本研究では家庭内役割の中で、生きがい感を獲得することで、自律した社会参加能力を得ることが可能であると考える。【まとめ】生きがい感が高い対象者は家庭内役割を獲得し、自律して活動する社会参加能力が高いことが認められた。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は所属施設の倫理審査委員会の承認(渡整第2020-1101 号)後、対象者に書面及び口頭にて十分な説明を行い、同意を得た上で実施した。また、本研究において開示すべき利益相反はない。