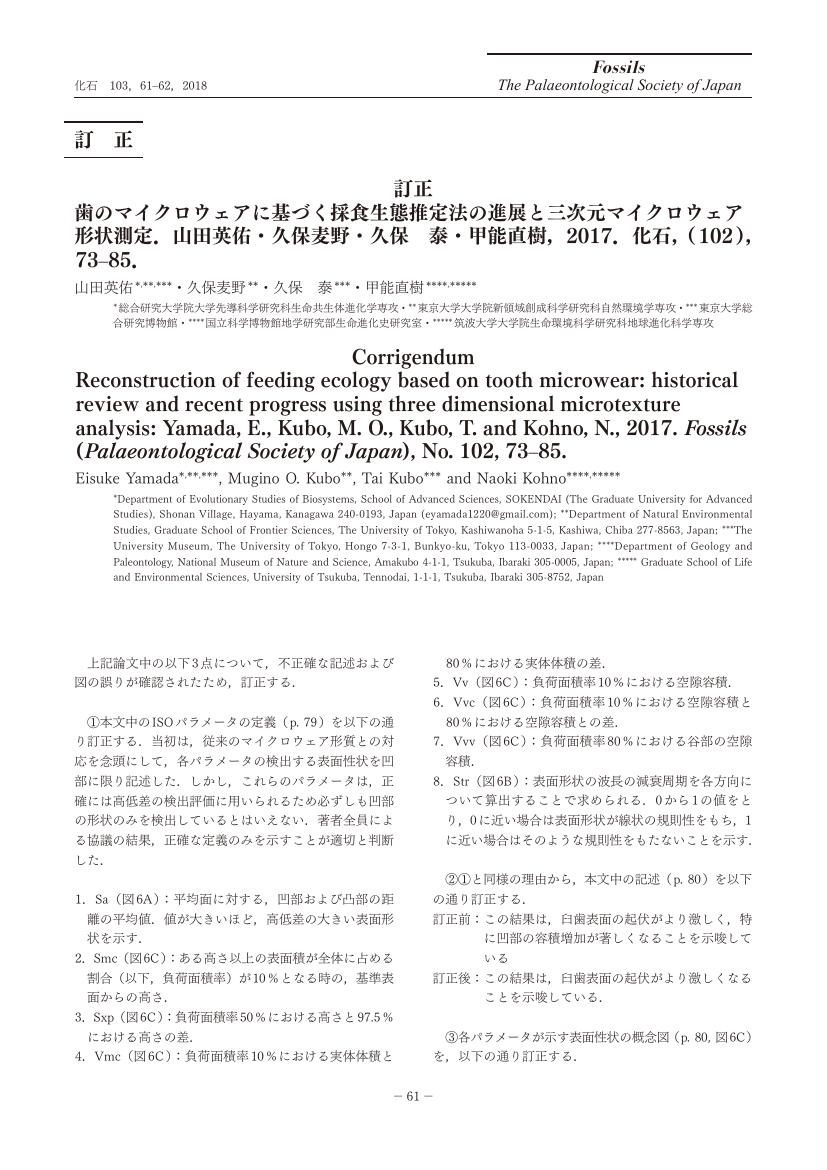1 0 0 0 OA 既存ステーションを考慮した Pメディアンモデルによる水素ステーション配置に関する研究
- 著者
- 板岡 健之 木村 誠一郎 広瀬 雄彦 吉田 謙太郎
- 出版者
- 一般社団法人 エネルギー・資源学会
- 雑誌
- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.242-249, 2019 (Released:2019-11-11)
- 参考文献数
- 10
In response to the introduction of fuel cell vehicles (FCVs) to the commercial market hydrogen station deployment needs to be progressed. Since resources allocated for deployment are limited for either private companies who wish to install stations and governments who provide subsidies, efficient station allocation should be cognizant of the service of potential customers. Based on a literature review, the results of a social survey and data analysis, p-median is chosen to find optimum locations for hydrogen stations. Location and the amount on potential demand for FCV’s in the early stage of deployment is estimated by a regression model. The result of GIS analysis for short mid-term perspective using p-median implies the importance of covering regional hub cities (such as prefectural capital cities) as well as metropolises and the result of GIS analysis for long-term perspective implies the ultimate necessary deployment of hydrogen stations. The locations suggested by the analysis were examined through coverage analysis on existing gasoline stations. The geographical tendency of station locations allocated by the developed methodology provides guidance for hydrogen station location practice.
1 0 0 0 IR 「皇孫御誕生記念こども博覧会」についての考察
- 著者
- 川口 仁志 Hitoshi Kawaguchi 松山大学経営学部 Matsuyama University College of Business Administration
- 出版者
- 松山大学
- 雑誌
- 松山大学論集 (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.6, pp.81-101, 2006-02
1 0 0 0 山下清の文章
- 著者
- 西京大学文芸学科国語国文研究室 [著]
- 出版者
- 西京大学文家政学部
- 巻号頁・発行日
- 1958
1 0 0 0 OA 性・暴力・ネーション-フェミニズムの主張4
- 著者
- 多賀 太
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.93, 2000-07-31 (Released:2010-01-22)
本書は、「女性兵士問題」「国家と『性暴力』問題」「女性性器手術問題」という、フェミニズムにおいて近年クローズアップされてきた問題を論じた、9人の執筆陣からなる論文集である。第I部から第III部のそれぞれに男性の執筆者が1人ずつ含まれることで、議論により一層の広がりが与えられているように思える。まず第I部で、軍隊内で男女にまったく対等な処遇を行うかどうかという「女性兵士問題」を題材として、フェミニズムが「暴力」とどのような関わりをもつべきかが議論される。続いて第II部では、「従軍慰安婦問題」と「夫婦間強姦」を題材として、近代国民国家においては十分保障されてこなかった「性暴力を受けない権利」をめぐる議論が展開される。さらに第III部で、「女性性器手術問題」を題材として、「第一世界」のフェミニストたちが「第三世界」の女性の経験を「性暴力」の被害として規定すること自体の「暴力」性についての議論が行われる。最後に第IV部で、編者による議論の総括が行われる。一見しただけでは無関係にも思えるこれらの問題の背後には、共通するより大きな問いが存在している。すなわち、グローバル化が進行しつつある現代において、フェミニズムは、「性」の違いによって「暴力」に関する異なる経験を強いてきた近代国民国家 (=「ネーション」) とどう関わっていくべきかという問いである。しかし、これに答えるのはそうたやすいことではない。もし、フェミニズムが国民国家の枠を越えて「性」と「暴力」の問題に取り組むべきであるとするならば、他国に暴力を行使する軍隊の存在を前提としてそこでの男女の機会均等を主張することは慎まねばならないし、たとえ国家によって合法化・正当化された営みであっても女性の人権侵害と見なされるならば「国家批判」や異文化への「介入」も必要となってくる。しかし他方で、国家を越えた問題設定は国内での性差別を不可視化させる危険性を伴うし、女性の人権のうち国民国家の枠によってこそ保障されうる側面や、異文化への「介入」にともなう「暴力」性をどう考えるのかという問題も起こってくる。本書には、この問いに対する明確な回答は記されていない。編者がわれわれ読者に求めているのは、本書から唯一の正答を見つけだすことではなく、むしろ本書が提供してくれる議論を足がかりとして、女性あるいは男性として今後国家とどのように関わっていくべきなのかを1人1人が考えていくことなのであろう。
1 0 0 0 OA 津軽屏風山砂丘地帯の地形について
- 著者
- 角田 清美
- 出版者
- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
- 雑誌
- 東北地理 (ISSN:03872777)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.15-23, 1978 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 28
In this paper, the writer attempts to make clear both the history of the formation and the morphological features of the Byóbusan sand dune region in the northernmost part of the Honshu Island.The following results are obtained.The Byobusan region consists of two terraces, about 10 meters and 20 meters higher than the present sea level. The latter is called the Yamadano terrace, which was formed during the stage of the higher sea level in the Shimosueyoshi transgression (in the Monanstrian age), and the former is called the Dekishima terrace (in Holocene age). On certain parts of the Yamadano terrace, the Old dune was formed in Pleistocene, and covered by the Iwaki volcanic ash layer. At that time, the prevailing winds were blowing from the west, just as at the present time.The Younger dune in Holocene, covers about two-thirds the area of the Byobusan region. Most of it was formed since the Yayoi period. Some parts of it were formed since 1948, when strong prevailing winds blew sand grains to creep up the cliffs or gullies, and formed transverse dune, on both Yamadano and Dekishima terraces.To the lee of transverse dunes, U-shaped dune and parabolic blowout dunes were developed and migrated downwind. Longitudial dune ridgs were developed finally by the erosion of parabolic blowout dunes. Sand dunes are commonly arranged in chains extending downwind from the source drifts. Thus the developement of sand dunes is related to the shifting speeds of sand dunes and the supply of sand grains.
1 0 0 0 OA アイヌの髯揚箆と日本の刀劒
- 著者
- 杉山 壽榮男
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.10, pp.444-456_1, 1940 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 IR 応仁・文明の乱期室町幕府の政務体制をめぐる一考察
- 著者
- 木下 昌規
- 出版者
- 大正大学
- 雑誌
- 大正大学大学院研究論集 = Journal of the Graduate School, Taisho University (ISSN:03857816)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.103-110, 2009
1 0 0 0 OA 『君の名は。』大ヒットの要因:日本的悲恋物の系譜における位置づけ
- 著者
- 打田 素之
- 出版者
- 神戸松蔭女子学院大学学術研究委員会
- 雑誌
- 神戸松蔭女子学院大学研究紀要. 文学部篇 = Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin Women's University : JOL (ISSN:21863830)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.13-22, 2018-03-05
『君の名は。』ヒットの要因はいろいろと分析されているが、この作品が日本的悲恋物の系譜に属する作品であったことが大きいと考えられる。日本人は近松浄瑠璃の昔から、共同体の制度や倫理に阻まれて、死に行く恋人たちの物語を好んで消費してきたが、こうした障害は社会の発展・民主化とともに、1960 年代は〈難病〉へと姿を変え、80 年以降、新しい要素として〈時間〉が現れた(『時をかける少女』)。『君の名は。』も、「時の隔たり」が恋人達を引き裂いているという点において、この伝統に連なる作品だと言える。 また、彼らの恋愛成就とヒロインの住む町の運命が一体となっていることは(=セカイ系)、それまで恋人達の敵であった共同体が、彼らの恋愛成就を助ける側となったことを意味し、日本的悲恋が新しい物語形態(=共同体との和解)を採用するに至ったことを示している。『君の名は。』のラストは、「歴史の流れ不変の原則」に基づいた「忘却のルール」が破られる展開となっており、これは旧来の共同体が力をもてなくなった現代の日本社会において、00 年代以降の大衆の嗜好に合致するものとなっている。 このように、『君の名は。』は日本的悲恋の伝統を受け継ぐ形で、「時間」という障害を採用しながらも、そのルールを変える新しい結末を用意したことが、全世代的なヒットに繋がったと考えられる。
1 0 0 0 OA 介護殺人の行動パターン把握の試み : 37件の判例をもとに
- 著者
- 宮元 預羽 三橋 真人 永嶋 昌樹
- 雑誌
- 人間関係学研究 : 社会学社会心理学人間福祉学 : 大妻女子大学人間関係学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.91-99, 2013
- 著者
- ツィマーマン ラインハルト 山田 到史子 Reinhard Zimmermann Toshiko Yamada
- 雑誌
- 法と政治 (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.213(1832)-276(1769), 2012-01-20
1 0 0 0 IR 講演 平等取扱と契約自由
- 著者
- Coester-Waltjen Dagmar 釜谷 真史 角松 生史
- 出版者
- 九州大学法政学会
- 雑誌
- 法政研究 (ISSN:03872882)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.1123-1139, 2006-03
1 0 0 0 OA 舌骨上筋群表面筋電図と甲状舌骨筋およびオトガイ舌骨筋筋電図との比較
- 著者
- 林 伊吹 林 与志子 宇野 功 藤原 裕樹 高橋 宏明
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.666-672, 1997-09-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
嚥下を観察する際, 嚥下開始の指標を決定するために, 舌骨上筋群表面筋電図を用いることが多い. これは, 被験者に非侵襲的であるため, 有用な方法とされている. しかし, 舌骨上筋群表面筋電図と実際の筋の活動とが, どのように関わつているかを確認する必要がある. 著者らは甲状舌骨筋とオトガイ舌骨筋に電極を刺入して得た筋電図と, 舌骨上筋群表面筋電図を同時記録し比較検討した.嚥下の際に, 舌骨上筋群表面筋電図波形上, 2つの波形変化を認めた. 最初におこる小さい振れと, それに続く大きい振れである. 前者をEMG1, 後者をEMG2とした. 筋電図の比較により, EMG1はオトガイ舌骨筋の活動開始点と, EMG2は甲状舌骨筋の活動開始点と強い相関を認めた.この結果より, 舌骨上筋群表面筋電図は嚥下開始の指標を決定でき, EMG1は嚥下第一期の開始を, EMG2は嚥下第二期の開始の指標を表すものと考えられた.
1 0 0 0 OA アナログ実験によるつむじ風の発生・消滅条件の探求
- 著者
- 鈴木 大介 赤池 優斗
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-07-04
1.背景本研究の目的はつむじ風が発達・消滅する条件をアナログ実験により明らかにすることである。そのため、人工的につむじ風様の鉛直渦を発生させる装置の製作を行った。つむじ風は晴れた日の日中に突発的に発生する強い鉛直渦であり、テントが飛ばされるなどの被害が時々報告される。私たちは、なぜそのような強い渦が突発的に発生し、そして消滅するのか疑問に思った。現在、つむじ風の発生メカニズムについての研究は数値シミュレーションにより行われている。しかし、数値シミュレーションは想定した条件下でのパラメータ探索が容易な一方で,地表面摩擦の影響や乱流といった微細な構造を取り入れることは難しい。そこで、私たちは、より細かな構造や擾乱を容易に入れられる、アナログ実験を行うことにした。環境条件をコントロールしながら人工的につむじ風を作り出し、つむじ風の構成パラメータを定量的に評価することで、数値シミュレーションでは知りえなかった性質を発見できることを期待して本研究を開始した。2.研究の手法 つむじ風の発生メカニズムに関する先行研究を参考に、つむじ風が発生しやすいとされる環境を再現する、すなわち上昇気流に角運動量を与え、つむじ風のような鉛直渦を発生させる装置を製作する。ホットプレートで地表面(水)を加熱し上昇気流を発生させ、円筒状の網を回転させることで流入する気流に角運動量を与える装置を考案した。水を加熱するのは湯気を発生させてつむじ風を可視化するためである。さらにこの湯気にシート状のレーザー光を当てることで、任意の渦の断面を定量的に計測できるように工夫した。またビデオカメラを用いて、撮影した渦の画像から渦の大きさを求める方法を確立した。この装置を用いて与える角運動量を変化させたときの渦の直径の変化及び渦の内部の温度分布を計測した。3.結果と考察地表面温度を一定にしたまま、与える角運動量を大きくすると渦の直径は増加した。渦の内部は周辺部よりも高温となっており、渦直径が小さいときのほうが温度差は顕著であった。また中心部の鉛直方向の温度傾度は渦直径が大きい、つまり与える角運動量が大きいときのほうが顕著であった。このように、つむじ風は地表面の熱の効率的な輸送を担っているようである。中心部が周囲より高温になるのは、つむじ風の中心向きの気圧傾度力により地表面付近の高温の空気が集められるためであり、中心向きの大きな気圧傾度力は、中心付近が高温である結果であると考える。しかしながら、つむじ風の形成初期に、なぜ中心向きの大きな気圧傾度力が生まれるのかについて、明快な答えを得ることはできなかった。今後、地表面の温度分布や与える角運動量、微細な地表面構造などのコントロールを行いながらつむじ風を構成するパラメータを定量し、渦動粘性係数を用いた実際のつむじ風と実験装置のスケーリングを経ることで、つむじ風の発生消滅の条件を明らかにできるのではないかと考えている。4.謝辞 本研究をするにあたってご指導いただいた静岡大学理学部地球科学科の生田領野准教授、様々な支援をしていただいた静岡大学FSS事務局の皆様に感謝申し上げます。5.参考文献 ・伊藤純至、(平成29年)、塵旋風の発生・発達機構と強風、日本風工学会誌第42巻第1号 ・新野宏、(2009)、竜巻と塵旋風-大気の激しい渦の理解の現状と課題、第58回理論応用力学講演会 https://doi.org/10.11345/japannctam.58.0.2.0
1 0 0 0 OA ため池の「池干し」がリン循環に与える影響
【はじめに】ため池は雨水や河川水を貯め、稲作灌漑に利用されてきた。また、生物の生息場所の保全、地域の憩いの場を提供するなど多面的機能を果たしている。しかし、農家数の減少により灌漑用途としてのため池使用は減少し、管理が行き届いていないため池が増加している。このようにため池の管理が行き届かなくなると、水が長期間滞留することから水質悪化が懸念される。水質悪化を避けるため、多くのため池で伝統的におこなわれてきた「池干し」が見直されている。池干しとは、ため池において水利用の少ない冬期に一定期間水を抜き、底泥を乾燥させることである。そして、富栄養化した水の排出、底泥の洗い流し、栄養塩類の溶出抑制などにより水質改善が見込める。しかし、その水質改善についての詳細なメカニズムは不明な点が多い。これは、池干しによる有機物分解等の作用の違いを実験的に作り出すのが難しいからである。そこで私たちは、池干し下にある底泥を採取し、実態に即して検討することにした。具体的には、何十年も池干しをおこなっていない池と、毎年おこなっている池を選定し、リン循環の周年変化を比較し、違いを考察する。【実験結果】本研究では、加古川市東部の台地上にあり、市街地化も同程度と立地環境が似ている2つの池を選定した。池干しをおこなっていない池が源太池、おこなっている池が新川池である(図1)。まず、この 2 つの池において底泥の堆積構造を調べ、サンプリングをおこなった(図2・3)。 実験1では、サンプルを天日干しして水分を除いた後、電気炉を用いて強熱減量(有機物量)を求めた。その結果、有機物量は源太池で平均 15.7%、新川池では 13.0%となった(図4)。これは t 検定では有意差である。 実験2では、モリブデン青法を測定原理とする試薬と吸光光度計とを使って、全リンと溶存態リンの溶出濃度を測定した。全リンについてはオートクレーブを使用している。実験開始後 25 日目における溶出濃度をみると、新川池の方が全リン・溶存態リンともに溶出が抑制されている(抑制率は順に 82.1%、55.5%)ことから、池干しの効果が大きいと考えられる(図5・6)。 全リンは有機態リンも含んでおり、源太池に有機物が多く含まれているという実験1の結果と整合する。【考察】以上の結果に基づき、池干しをおこなう新川池のリン循環モデルを作成した(図7)。①池干し前の湛水期は、水中の有機態リンが溶存酸素用いた微生物の活動で異化され、無機態リンとなる。底泥に含まれている Fe2+イオンが溶出して、酸化・水酸化反応により水酸化鉄に、PO43-イオンは水酸化鉄との吸着反応により沈降する。嫌気状態で還元が起き、リン酸イオンが溶出する。このリン酸イオンが植物プランクトンの栄養分となり、有機態リンに変わる。② 池干しをおこない底泥が空気にさらされると、好気性微生物が活動し有機物が分解される。③その後、新たに溶存酸素を多く含む水が流入してくる。起こる反応は池干し前の湛水期と同じであるが、溶存酸素をより多く含むため有機態リンから無機態リンへの異化、リン酸イオンの水酸化鉄との 吸着・沈殿がより活発になる。また、新たな溶存酸素を多く含む水が流入してくることで水中の溶存酸素量が増えるだけでなく、池干し期間中に換気によって有機物の分解が既に起きているので、水中の溶存酸素消費量が減り溶存酸素量の低下が抑制される。溶存酸素量は池干しをおこなっていない池よりも多くなり、有機態リンから無機態リンへの異化が進みやすい。 このように、①から③を一年かけて繰り返す。池干しをおこなうことで溶存酸素量が増え、結果的にリンが多く流入しても富栄養化を防ぐ作用が働くため、水質改善の効果を示す。底泥は沈殿したリンを保持する役割を果たしている。【おわりに】池干しによる水質改善効果について、リンの周年的循環に注目し、その解明に取り組んだ結果、池干しによって単に溜まっていた水が酸素を多く含んだ水に入れ替わることで水質が改善されるだけではなく、換気により水質悪化の原因の一つである硫化水素の発生も抑制し、その後しばらくの間抑制効果が持続するということが分かった。
1 0 0 0 OA 東北日本沖合で発生した地震からのsP波とpP波の波動場
- 著者
- 小菅 正裕
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
sP phase is an S to P converted waves at the ocean bottom or sea surface. Some researchers have used this phase from the offshore earthquakes in northeastern Japan to improve the depth accuracy of the earthquakes. However, the wavefield and propagation characteristics of this phase have not been well studied. Here I examined the characteristics by applying some simple visualization techniques and 3D wave propagation simulation. One technique is the simulated broadening of seismograms from the Hi-net network by correcting for the characteristics of the short-period seismometers. This correction enables us to investigate seismogram's lower frequency components that are less sensitive to short-wavelength heterogeneities in the lithosphere. The other technique is the visualization of low-pass filtered and auto-gain-controlled seismograms as wiggle traces. Thus, we can easily trace some converted phases on the paste-up seismograms. A comparison of simulated and observed seismograms is also quite useful to investigate the origin of converted waves. I used OpenSWPC code and velocity and attenuation structure based on the JIVSM model. I applied these techniques to some inter-plate earthquakes that occurred offshore Miyagi prefecture in northeastern Japan. I could identify both pP and sP phases from almost all examined earthquakes. These phases appear as a continuous phase on paste-up seismograms as far as 400 km epicentral distance. The time difference between these waves and P-waves varies with the source location, reflecting the depth difference between the earthquake and ocean bottom. Since the converted waves appear as continuous wave packets crossing station network, picking of arrival times from limited time bands determined from the paste-up records can improve the data accuracy, and hence the location accuracy. The use of pP phase together with sP phase will provide a new method to improve the depth accuracy of offshore earthquakes, which is important to investigate the seismicity in the period before the operation of the S-net, the ocean-bottom seismometer network covering offshore from Hokkaido to Kanto district.
1 0 0 0 OA 放射温度計による様々な土質の比熱放射温度計による様々な土質の比熱と熱容量
- 著者
- 黒澤 駿斗 市川 大翔
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-07-04
地面は様々な物質で構成されている。同等の熱を加えたときに温度の上がり方・下がり方はそれぞれ異なる。温度を測るときには直接地面に刺して計測が難しいため放射温度計を用いて似た条件で複数回計測する必要がある。日差しが強い日になるとアスファルトと土の上では温度は大きく変わる。そのため同じ熱が当たっていても、土壌や地面の成分によって温度の上がり方は大きく異なる。このことから地面を構成している様々な物質にはそれぞれ比熱の違いがあると考えられるため放射温度計(SATO社SK-8940)を使い調査した。調べるための方法としては季節や時間を変えて、放射温度計で地面の温度を計測した。季節は昨年11月から今年4月にかけて、計測した時間帯は午前中の地温上昇がみられる時間帯に、約1日2回時間,30分から2時間ほどの間隔で行った。ここで注意すべき点としては、気温を下げる要因としての風の強さ、日陰の位置変化である。放射温度計は計測面積を十分にとるため地面から1m離して計測した。距離D:測定直径S=10:1の放射温度計を使用したためD=1mの場合、計測面積は78.5cm2と見積ることができる。土壌は、アスファルト、植生あり・なしでの地面の違いで計測した。熱容量の計算方法は受熱量Q(J)/上昇温度T(K)で考え,熱容量の比を比較したところ以下のようになった(比であるのは現在、厳密な測定面積の確定ができていないため)。【熱容量比】1例目 4月7日 草地:砂:レンガ≒0.714 :0.357:0.6672例目 4月9日 草地:砂:レンガ:土:アスファルト≒0.133:0.120:0.106:0.833:0.1123例目 4月11日 草地:砂:レンガ:土:アスファルト≒0.166:1.428:0.175:0.116:0.219データには考慮すべき誤差があるが全体の傾向として熱容量は 1例目 草地>レンガ>砂 2例目 土>草地>砂>アスファルト>レンガ 3例目 砂>レンガ>アスファルト>草地>土となった。ここからいえることとしては、アスファルトとレンガは熱容量の差が小さく外的要因による影響が少ないが、逆に草地、砂、土は熱容量の差が大きいため、風などの外的要因に影響されているのではないかと考えた。植生のある土壌の熱容量、ひいては比熱をもとめるにはさらに安定した条件で測定することが求められるであろう。この安定した測定には何が必要か、議論をしたい。
1 0 0 0 OA 視程観測の自動化
- 著者
- 田中 陽登 馬場 光希 浜島 悠哉
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-07-04
研究背景・目的本校天文気象部では、約70年前より百葉箱による気象観測(1日2回、気温・気圧・湿度・風速・雨量・視程観測等)が続けられてきた。1995年以降は欠測が増えたが、2007年には自動観測装置を導入し、視程以外の観測を再開させた。2018年には目視による視程観測を再開したが、毎日同じ時間に屋上に出て観測することが難しく、過去に比較して欠測が非常に増えた。本研究では、この問題を解決するために、コンピュータ制御したカメラで定時に対象を撮影することによる新たな観測方法を開発した。カメラを使うことで観測者の視力の影響を無くすことも可能となる。自動観測装置の製作・設置都心方面のより多くの目標物を見渡せる場所として5回の屋上を選択し、手すりに土台を取り付けて観測装置を固定した。容器は粉塵や風雨から機器を守るためにアルミシートで覆った密閉型のケースを作り、電源供給のため屋外用の電源コードとLANケーブルを室内から繋げるよう工作した。観測装置は、一眼レフカメラと、カメラを制御するためのRaspberry Piで構成した。プログラムは、定時に写真を撮影し、撮影画像を自動的にGoogleドライブにアップロードする命令をPythonで記述した。さらに、スマートフォンによる操作で撮影ができるようにし、その時の空の様子や視程の具合を確認できるよう、Slackを通じて観測装置をコントロールするプログラムも作成した。観測方法と結果観測を自動で行うために、カメラの適正な露出や感度など、撮影する際の設定をあらかじめ決める必要がある。同一のタイミングで撮影設定の異なる数枚の写真を撮り、露出が適正である写真を選ぶ作業を繰り返して、設定を決めた。焦点距離は150mmに固定し、1回の観測で3種類の撮影設定を定めた。36㎞先のスカイツリーや25㎞先の新宿のビル群について、同時刻の目視観測の結果とカメラの撮影画像の結果を比較したところ、目視観測で視認できたものは3種の撮影画像でも確認でき、目視とカメラで観測結果に差はないことがわかった。目視と画像にょる識別の差については更に観測を増やして検討する必要がある。考察今回の自動観測で得られたデータと先行研究の1950~60年代の同時期(冬)のデータと比較してみると、現在のほうが、格段に視程がよくなっている。かつては視程が4km未満の日が多くあり、先行研究では冬の朝もやや大気汚染が視程の悪さの要因となっていると言及していたが、現在は天気により視程が悪い時でも4km先まで見通せており、朝もやが出現することはほとんどなかった。今後は更に、視程と天候、及び季節、黄砂や大気汚染との関係をより詳しく調査していく。