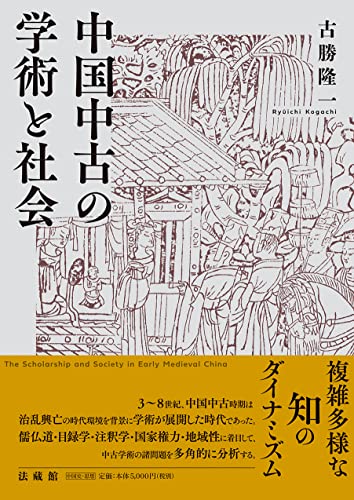9 0 0 0 OA 選択的夫婦別姓制度は何故実現しないのか : 「女性活躍推進」の陰で
- 著者
- 笹川 あゆみ
- 出版者
- 武蔵野大学教養教育リサーチセンター
- 雑誌
- The Basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 = The Basis : The annual bulletin of Research Center for Liberal Education, Musashino University (ISSN:21888337)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.185-200, 2019-03-01
9 0 0 0 OA GLIM基準を心不全診療に生かす
- 著者
- 木田 圭亮 鈴木 規雄
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.113-117, 2022-08-15 (Released:2022-09-15)
- 参考文献数
- 6
日本の循環器領域では,2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインでGlobal Leadership Initiative on Malnutrition(GLIM)は初めて取り上げられた.心不全患者においても,GLIM基準を活用し,早期診断,早期介入が求められている.そのためには,多職種でのチーム医療,心臓リハビリテーションが大いに活躍できる場と考える.そして,循環器領域ではまだ良く耳にする,「低アルブミン血症のため低栄養です.」というフレーズ,こちらについては,今回のガイドラインにおいても,血液中のアルブミン,すなわち内臓たんぱく質貯蔵量による栄養評価は,炎症,体液量増加による血液の希釈など,疾患重症度を反映し,単独では栄養状態を示す指標にならないと明記されていることを循環器内科医はもっと知っておくべきである.心不全領域での心臓リハビリテーションにおける運動療法の分野は,これまで多くのエビデンスが構築されてきたのに比べると,栄養の分野はまだ道半ばである.心不全患者に対して栄養補給なしの運動だけではより痩せるリスクもあり,ある意味“修行”になってしまうため,運動には十分な栄養補給が必要である.
9 0 0 0 OA ギリシア人の見た一九三五年の日本──ニコス・カザンザキスの眼差し
- 著者
- 村田 奈々子
- 出版者
- 東洋大学
- 雑誌
- 東洋大学文学部紀要. 史学科篇 = Bulletin of Toyo University, Department of History, the Faculty of Literature (ISSN:03859495)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.316(95)-263(148), 2022-03
9 0 0 0 OA ヘルペスウイルス感染と疲労
- 著者
- 近藤 一博
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.9-17, 2005 (Released:2005-11-22)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 10 11
疲労は,痛みや眠気と並んで非常に重要な生体シグナルであるが,疲労の原因や疲労を感じる機序は,全くと言っていいほど不明である.また,疲労・ストレスによるヘルペスウイルスの再活性化は,良く知られた現象であるが,これまでは短期的なストレスと再活性化の関係が研究されているだけであった.今回我々は,過労死などの原因もなる中・長期的疲労がhuman herpesvirus 6(HHV-6)の再活性化を誘導することを見出した.これは,HHV-6の再活性化誘導因子の解明に役立つだけでなく,疲労の客観的な定量や疲労の機序の研究にも役立つものと考えられた. また,HHV-6の潜伏感染特異的遺伝子の研究によって,HHV-6には潜伏感染と再活性化の間に,潜伏感染に特異的遺伝子および蛋白の発現亢進が見られるにもかかわらず,ウイルス産生の見られない中間状態が存在することを見出した.この中間状態に発現する潜伏感染蛋白に対する血清抗体は,病的な疲労状態である慢性疲労症候群患者の約4割で検出された.これらの結果は,HHV-6が疲労という生物学的現象に深く関わるウイルスであることを示していると考えられる.
9 0 0 0 OA 世阿弥十六部集 : 能楽古典
9 0 0 0 OA [北海道人造石油株式会社留萠研究所]研究実験成績報告
- 著者
- 北海道人造石油株式会社留萠研究所 編
- 出版者
- 北海道人造石油留萠研究所
- 巻号頁・発行日
- vol.第2号, 1942
9 0 0 0 OA ハクサイのゴマ症発生要因について
- 著者
- 谷本 俊明 上本 哲
- 出版者
- [広島県立農業試験場]
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.69-78, 1982 (Released:2011-03-05)
9 0 0 0 OA 戦時期の外米輸入 : 一九四〇~四三年の大量輸入と備蓄米
- 著者
- 大豆生田 稔
- 出版者
- 東洋大学
- 雑誌
- 東洋大学文学部紀要. 史学科篇 = Bulletin of Toyo University, Department of History, the Faculty of Literature (ISSN:03859495)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.77-121, 2013
9 0 0 0 OA 善導の在家弟子に見る臨終行儀――新出「念弥陀仏誦弥陀経行者」墓誌銘について――
- 著者
- 倉本 尚徳
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.67-73, 2021-12-20 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 7
This paper presents the original text and a modern Japanese translation of an epitaph for the Tang period lay person Bao Baoshou 包宝寿, and then examines connections between Shandaoʼs 善導 writings and the epitaphʼs portrayal of daily life practices for Pure Land rebirth and deathbed rites. The former consist of being mindful of Amitābha Buddha, reciting the Amituo jing, and maintaining the abstinential rules. The daily life practices for rebirth and the signs of the coming of the holy retinue to welcome him to the Pure Land experienced by Bao at the end of his life can be seen as the “highest of the high stage” (shangpin shangsheng 上品上生) as described in the Pure Land Contemplation Sūtra 観無量寿経, and also match the practice for the “highest of the high stage” in the Guannian famen 観念法門. Many lay practitioners were present at the end of Baoʼs life and Shandao also emphasized the existence of fellow practitioners.
9 0 0 0 OA 南大東島のノスリ新亜種について
- 著者
- 黒田 長久
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 鳥 (ISSN:00409480)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.89, pp.125-129, 1971-06-25 (Released:2008-12-24)
Type: Possibly male, a live specimen at examination on Oct. 22, 1970. Six years and fivemonths old. Collected on May 4, 1964 as new-born chick by Mr. K. Yonamine on Minamidaito I., Borodino Is. and has been reared and being kept alive by Mr. Masao Oshiro in Naha City, Oki-nawa I.Measurements: Total L. 470mm, Wing Exp. 1050mm, Wing 330mm (Natural), 340mm (Pres-sed), Tarsus 64mm, Culmen 31mm (Entire), 24mm (From cere). For comparison, the measurements in 10_??__??_, 6_??__??_ of japonicus (from Japan) are: Wing (Natural) _??__??_ 348-368 (Av. 354. 5)mm, _??__??_ 363-373 (Av. 367. 6)mm; Tail _??__??_ 187-210 (Av. 195.6)mm, _??__??_ 205-210 (Av. 207.5)mm (Measured by the author).Description: Similar to Bnteo buteo japonicus as a whole, but is generally more reddish, the tectrices and rectrices being almost chestnut color with distinct regular dark bands. The sides of head, supercilliaries and ear-coverts, as well as foreneck at crop region are distinctly tawny buff.The typical japonicus is buffy white in these regions, and wings and tail lack chestnut color(though there is a weak wash of this color on primaries) and with less regular dark bands, the tail being usually uniformly pale greyish brown. However, the flank pattern is of japonicus-type (Cf. Photos). There is no similarly reddish and so distinctly banded example among Japanese specimens preserved in Yamashina Institute, and is also different from larger-sized continental reddish and banded phase.Range: Minamidaito I., Borodino Is. (The first record).Remarks: Having examined only one bird, it is not clear whether its plumage pattern represents whole Minamidaito population. However, it is reasonable that a darker (redder) population has been established on this southern island. It is decidedly smaller in size than japonicus. Its subspecific name is dedicated to Mr. Oshiro who has reared it from chick. The nest was found by Mr. Yonamine with three eggs which soon hatched but a late hatched chick had disappeared when he examined the nest three hours later. The two chicks were taken by him and one of them was given to Mr. Oshiro.
9 0 0 0 OA 祭事を読む-諏訪上社物忌令之事-
- 著者
- 武井 正弘
- 出版者
- 飯田市美術博物館
- 雑誌
- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.121-144, 1999 (Released:2017-10-01)
9 0 0 0 OA [絶筆三句]
- 著者
- [正岡]子規 [著]
- 出版者
- [正岡子規]
- 巻号頁・発行日
- 1902
明治35年(1902)9月18日午前、紙をはりつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら俳句3句をしたためた。子規は翌19日午前1時ころ息をひきとり、これが絶筆となった。箱書は門下の長老内藤鳴雪(1847-1926)の筆。
- 著者
- 大西 寿明
- 雑誌
- 英米文學 = English & American literature
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.93-97, 2021
9 0 0 0 OA 日本軍の対ソ連情報思想戦 : 朝鮮軍、関東軍の事例とその含意
- 著者
- 金 仁洙 In-soo KIM
- 出版者
- 島根県立大学北東アジア地域研究センター
- 雑誌
- 北東アジア研究. 別冊 = Shimane journal of North East Asian research. [Special issue] : North East Asian region (ISSN:13463810)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.145-184, 2021-03-31
9 0 0 0 OA ソーラー電力セイルミッションの展望
- 著者
- 森 治 ソーラー電力セイル探査機プリプロジェクト候補チーム MORI Osamu Solar Power Sail Project Preparation
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)
- 雑誌
- 第20回宇宙科学シンポジウム 講演集 = Proceedings of the 20th Space Science Symposium
- 巻号頁・発行日
- 2020-01
第20回宇宙科学シンポジウム (2020年1月8日-9日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県
9 0 0 0 OA 下水汚泥からのリン回収プロセスの開発
- 著者
- 萩野 隆生 平島 剛
- 出版者
- 一般社団法人 環境資源工学会
- 雑誌
- 環境資源工学 (ISSN:13486012)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.172-182, 2005 (Released:2005-12-08)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 13 12
A novel process for effectively recovering phosphorus from waste has been developed. By this process, magnesium ammonium phosphate (hereinafter referred to as MAP) is recovered from anaerobic digestive sludge in sewage. The MAP recovery process involves recovering inorganic fine particles, which include the MAP particles, from digestive sludge through a successive line of separating devices such as, a vibrating screen, a hydro-cyclone, and a revolving-cylindrical type thin flow separator or multi-gravity separator. Continuous tests for MAP recovery carried out to study the performance of this process indicate that it was possible to recover about 90% of MAP.
- 著者
- 木村 邦博
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.31-41, 2009-07-19 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 23
本稿の目的は,科学としての社会学と歴史学(科学史)としての社会学史との双方にとって,どのような「学説研究」が実り多いものと考えられるかについて,論じることである.より具体的には,具体的な社会現象に対する「問い」を主題とした学説研究を実践することこそが,社会学・社会学史それぞれの分野における研究の発展を促すものであることを主張する.まず,科学としての社会学と歴史学(科学史)としての社会学史とを峻別する必要があることを述べるだけでなく,このふたつの違いをできるだけ明快な形で定式化する.その上で,社会現象の科学的探求としての社会学がどのような目標と方法をもつべきものであるかを,具体例を挙げつつ論じる.さらに,相対的剥奪に関するレイモン・ブードンの研究を模範例として取り上げ,そこにおいてブードンがとった研究戦略を検討することで,「問い」を主題とした学説研究の重要性を示すことにしたい.最後に,「問い」とそれに対応した仮説を主題とした学説研究が,学者(学派)・言説(主張)・概念・メタ理論を主題にした場合と比較して,科学としての社会学においては先行研究のレビューとして有効かつ不可欠なものであると同時に,社会学史の分野でも社会学的な営みを魅力的なものとして描くことにつながるものであると主張する.
9 0 0 0 OA 食卓風景に関する研究II 食器の属人性および共用への抵抗感に関する地域比較
- 著者
- 今井 悦子
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.183-191, 2002-12-25 (Released:2011-01-31)
- 参考文献数
- 15
宮城, 新潟, 京都, 広島および鹿児島を中心とした地域居住者に対し, 家庭内での属人器の実態および家族との共用に対する抵抗感をアンケート調査し, 前報の埼玉のデータを加えて地域比較を行った. その結果以下のことが明らかとなった.1. 回答者の属性ごとに食器の属人性を検討した結果, ほとんどのケースにおいて地域差が認められた. どの食器, どの属性においても埼玉は専用が特徴的に多く, 一方共用が多い地域としては飯碗と箸では鹿児島が, 汁椀では京都と広島が, 湯呑みでは広島が多く出現した. これらから食器の属人性には東高西低の傾向があると考えられた. また, 食器では湯呑みから, 年齢的には若い世代から, 地域差がなくなっていく可能性も示唆された.2. 食器の属人性に寄与する因子の検討を行った結果, 飯碗, 汁椀および箸では地域性が最も大きく寄与する因子であることが分かった. 湯呑みでは食事作りを担当している者の年齢の次に寄与する因子であった.3.食器共用への抵抗感について, 回答者の属性ごとに地域性を検討した結果, 湯呑みに対する抵抗感は一部のケースを除けば地域差がなかった. その他の食器は地域差が見られ, どの食器, どの属性においても鹿児島は抵抗感なしが特徴的に多かった. 京都, 広島も汁椀で抵抗感なしが多かった. 一方抵抗感ありは汁椀では埼玉が, 箸では新潟が, 飯碗では鹿児島を除く各地域が出現した. 抵抗感の高さも東高西低の傾向があると考えられた. また外食時の食器に対する抵抗感は地域差が全くなかった.4. 食器共用への抵抗感に寄与する因子を検討した結果, 箸および汁椀では地域性が最も大きく関与する因子であった. 飯碗では地域性は一部寄与する因子であり, 湯呑みおよび外食時の食器では地域性は全く寄与していなかった.5. 家族の中で配偶者と子どもとの共用に抵抗感があると答えたケースについて地域差を検討した結果, 子どもに対する抵抗感は配偶者に対する場合より地域差があるケースが少なかった. 地域差があったケースでは, 抵抗感なしは鹿児島が, 抵抗感ありは埼玉が特徴的に多かった.
- 著者
- George E. Williams
- 出版者
- The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan , The Geodetic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Physics of the Earth (ISSN:00223743)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.475-491, 1990 (Released:2009-04-30)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 18 35
The recent recognition of cyclically laminated tidal rhythmites provides a new approach to tracing the dynamic history of the Earth-Moon system. Late Proterozoic (-5650 Ma) elastic rhythmites in South Australia represent an unsurpassed palaeotidal record of -560 years' duration that provides numerous palaeorotational parameters. At -5650 Ma there were 13.1+-0.1 lunar months/year, 400+-7 solar days/year, and 30.5+-0.5 solar days/lunar month. The lunar apsides and lunar nodal cycles were then 9.7+-0.1 years and 19.5+-0.5 years, respectively. The indicated mean Earth-Moon distance of 58.28+-0.30 Earth radii at -5650 Ma gives a mean rate of lunar retreat of 1.95+-0.29 cm/year since that time, about half the present rate of lunar retreat of 3.7+-0.2 cm/year obtained by lunar laser ranging. The rhythmite data imply a substantial obliquity of the ecliptic at -5650 Ma, and indicate virtually no overall change in the Earth's moment of inertia, which militates against significant Earth expansion since -5650 Ma. Early Proterozoic (-52, 500 Ma) cyclic banded iron-formation in Western Australia, that may record submarine fumarolic activity triggered by earth tides, suggests -514.5+-0.5 lunar months/year and a mean Earth-Moon distance of -554.6 Earth radii at -52, 500 Ma. The combined rhythmite data suggest a mean rate of lunar retreat of -51.27 cm/year during the Proterozoic (-52, 500-650 Ma); the indicated increasing mean rate of lunar retreat since -52, 500 Ma is consistent with increasing oceanic tidal dissipation as the Earth's rotation slows. A close approach of the Moon during earlier time is uncertain. Continued study of tidal rhythmites promises to further illuminate the evolving dynamics of the Earth-Moon system.