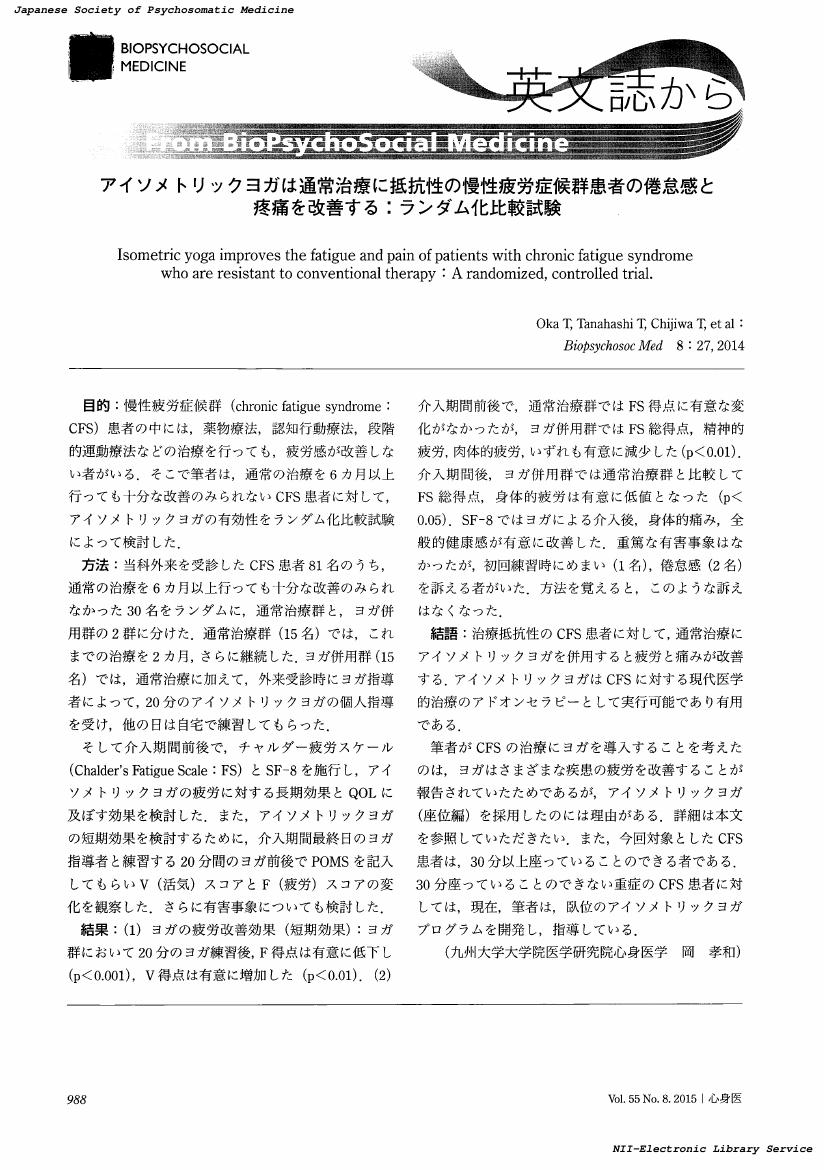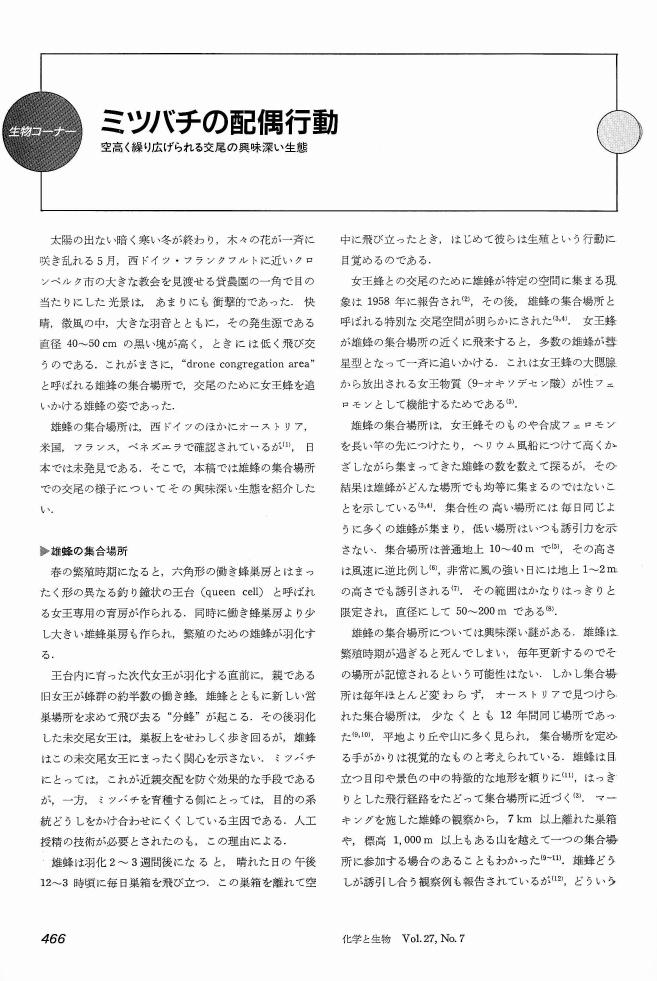9 0 0 0 2つの東大と民青同盟--激動の時代の東大生の生き方を考える
- 著者
- 日本民主青年同盟東大同盟委員会
- 出版者
- 日本共産党中央委員会
- 雑誌
- 前衛 (ISSN:13425013)
- 巻号頁・発行日
- no.643, pp.p91-105, 1994-02
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.8, pp.988, 2015-08-01 (Released:2017-08-01)
9 0 0 0 OA 量子現象によって開示される存在論的構造
- 著者
- 東南 裕美 安斎 勇樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.3_43-3_52, 2022-01-31 (Released:2022-02-05)
- 参考文献数
- 24
本研究の目的は, 三浦半島における事例研究を通じて, 観光まちづくりに有効なデザイン・ワークショップのモデルを提案することである. そこで, 一般的なデザインプロセスに基づいて「観光まちづくりにおけるデザイン・ワークショップの仮説モデル」を作成し,ワークショップを実施した. 一般的なデザインプロセスでは, 「ターゲット設定」が最初のステップになることが多い. しかし, 観光まちづくりの場合は,「地域の問題定義と資源の整理」というプロセスがターゲット設定に大きく影響する.観光まちづくりにデザイン・ワークショップを応用する際には, 「ターゲット設定」「地域の問題定義と資源の整理」「観光コンセプトの創造」を繰り返し, 最適な三位一体の関係を考えるという特徴的なプロセスをたどることが明らかになった. この特徴を踏まえて, 仮説モデルを一部修正し, 観光まちづくりに有効だと考えられるデザイン・ワークショップのモデルを提示した.
9 0 0 0 OA 百科全書
- 著者
- ウィルレム・チャンブル, ロベルト・チャンブル 編
- 出版者
- 丸善
- 巻号頁・発行日
- vol.上巻, 1885
9 0 0 0 ペルー国における日本人移住史
- 出版者
- 日本人ペルー移住史編纂委員会
- 巻号頁・発行日
- 1969
9 0 0 0 OA 日本語基本文型 : 日本語練習用
9 0 0 0 精巣上体尾部電気刺激法による精子の大量回収法に関する研究
電気刺激法によるラット(12週齢ウィスター系)精巣上体尾部からの精子回収では、ピーク電圧70V、パルス幅250μs、20Hz、30秒の刺激で回収精巣上体液量平均10.5±2.2μl、回収精子数46(±14)×10^6と効率的に精子を回収することが可能であった。この手法においては、回収精子に不純物が少なくF12に分散させるだけで運動精子が得られることが特徴である。電気刺激法では刺激時に精子に電位が加わるため、高電位では精子の運動性をそこなうことが予想される。そこで精子にたいする電位負荷がヒト精子の運動性に及ぼす影響を調べると、精子の運動性喪失の機序は大きく二つに分類され、一つは、低イオン強度下での高電位負荷時に見られる運動性喪失で、運動精子の50%が運動停止に要する電位勾配は160V/2mmであった。これにたいし高イオン強度下では電極周囲においてのみ認められて電極間では運動性喪失が起こりにくいことから、高イオン強度下での電気刺激のほうが運動精子回収法として適していることが明らかとなった。ヒトに対する応用では、症例数が少なく断定的な結論をうることができなかったが、少量の逆行性射精を伴う機能性閉塞症例で、本手法により高濃度、高運動率の精子回収が可能であることが多い傾向にあった。これにたいし、完全閉塞例では精巣上体管液が多量に回収されても、中に精子が存在しないことが多く、また非閉塞例では精巣上体管液の回収自体が困難な症例が多く認められた。したがって、現時点での本手法の適応は傍大動脈リンパ節廓清などによる機能的な閉塞にあるものと考えられた
9 0 0 0 OA 女性と経済 : フェミニスト経済学のあゆみ
- 著者
- 足立 眞理子
- 出版者
- 大阪府立大学女性学センター
- 雑誌
- 女性学講演会 (ISSN:18821162)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.51-81, 2013-03
9 0 0 0 応永初年ごろの耕雲(子晋明魏)について
- 著者
- 大橋 直義
- 出版者
- 実践国文学会
- 雑誌
- 實踐國文學 (ISSN:03899756)
- 巻号頁・発行日
- no.100, pp.42-47, 2021-10
9 0 0 0 OA 生類憐み政策の成立に関する一考察 : 近世日本の動物保護思想との関連で
- 著者
- 根崎 光男
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 人間環境論集 (ISSN:13453785)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.A1-A18, 2005-03-31
9 0 0 0 OA 東京における寄席定席興行の顔付け傾向分析 -芸術活動評価への統計的解析手法導入の序として
- 著者
- 坂部 裕美子
- 出版者
- 立命館大学アート・リサーチセンター
- 雑誌
- アート・リサーチ = アート・リサーチ (ISSN:13462601)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.64-54, 2011-03
9 0 0 0 OA 近年の所得税改革と残された課題
- 著者
- 三浦啓
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.1190, 2022-04-12
9 0 0 0 写真でみる大宮の昔と今
9 0 0 0 OA 豊岡盆地の水田におけるコウノトリ育む農法の生物多様性保全効果
- 著者
- 内藤 和明 福島 庸介 田和 康太 丸山 勇気 佐川 志朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.217, 2020 (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
兵庫県豊岡市を中心とする地域で行われている「コウノトリ育む農法」の実施圃場と慣行栽培圃場のそれぞれで植生および動物分類群の調査を行い、景観要素を含めて解析して、コウノトリ育む農法が植生および動物分類群に及ぼす影響を明らかにした。コウノトリ育む農法は水生動物の個体群密度よりも田面および畦畔の維管束植物の出現種数と被度に対してより直接的な正の影響を及ぼしていた。水生動物の個体群密度に対するコウノトリ育む農法の影響は、アシナガグモ属、ミズムシ科、コオイムシ科、タイコウチ科、ゲンゴロウ科(成虫および幼虫)、ガムシ科(成虫および幼虫)の個体群密度、カメムシ目およびコウチュウ目(成虫)の出現種数に対しては総じて正の影響で、この農法の生物多様性保全効果が確認された。一方で、分類群によって異なる景観要素の影響も検出された。トノサマガエル(成体)の個体群密度には農法による影響が確認されなかった。
- 著者
- 佐藤 広美
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報. 教育学 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.83-118, 1993-03-20
- 著者
- Karin Inoue Takuya Yahagi Taeko Kimura Yasunori Kano
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.66-75, 2022-02-22 (Released:2022-02-23)
- 参考文献数
- 71
- 被引用文献数
- 1
Ellobium chinense is a red-listed snail species of the family Ellobiidae with a geographic distribution from Vietnam and south coast of China to South Korea and mainland Japan. This species is restricted to specialized habitats in a narrow upper-intertidal to lower-supratidal zone of salt marshes and thus particularly sensitive to environmental degradation through land reclamation and other human activities. Here, we first report the genetic diversity and population structure of E. chinense in Japan to evaluate the connectivity and conservation value of its local populations. Specimens were collected from seven localities (Tsu, Okayama, Yamaguchi, Usa, Imari, Saga and Izumi) that cover the species’ present distribution in the country. Analyses of 612-bp sequences of the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene showed high genetic diversity within populations and a reasonable level of connectivity among populations. However, significant genetic differentiation was detected among distant geographic regions in Japan and South Korea, due potentially to the disjunct distribution of habitable salt marshes and a short pelagic larval period of the species. The population of the Ise–Mikawa Bay area, representing the eastern limit of the current distribution range, showed the highest level of genetic differentiation and deserve particular conservation efforts to avoid local extinction, which occurred in Tokyo Bay area in the last century.
- 著者
- 吉田邦輔
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.2, 1971-01-20
9 0 0 0 OA 極東国際軍事裁判所判決
- 著者
- [極東国際軍事裁判所 編]
- 出版者
- 極東国際軍事裁判所
- 巻号頁・発行日
- vol.〔第1冊-第13冊〕 印度代表パル判事判決書(第1頁-338頁), 1948
9 0 0 0 OA 生物コーナー
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.7, pp.466-470, 1989-07-25 (Released:2009-05-25)