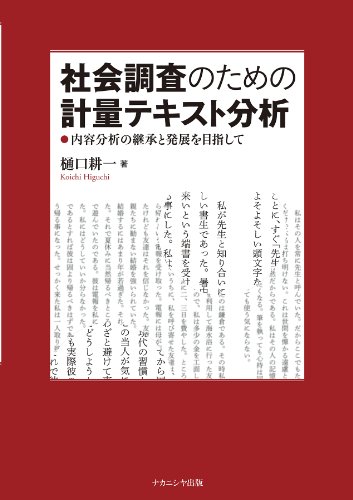7 0 0 0 OA 確率システム制御の最近の話題
- 著者
- 大住 晃
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.363-370, 1998-07-15 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 51
7 0 0 0 IR 抗日戦争期における日本人民の反戦運動
- 著者
- 伊原 沢周
- 出版者
- 追手門学院大学
- 雑誌
- 東洋文化学科年報 (ISSN:09132163)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.33-56, 1995-11
7 0 0 0 子どもの権利条約と子どもの性 : 特集
- 著者
- "人間と性"教育研究協議会企画編集
- 出版者
- エイデル研究所
- 巻号頁・発行日
- 2011
7 0 0 0 OA 労務統計
- 著者
- 鉄道大臣官房現業調査課 編
- 出版者
- 鉄道大臣官房現業調査課
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和7年10月10日現在 第5輯 年齡、配偶關係、敎育程度, 1935
7 0 0 0 OA 素人に出来る珍らしい料理十二ケ月
- 著者
- 東京料理献立研究会 著
- 出版者
- 啓文社
- 巻号頁・発行日
- 1937
- 著者
- 山下 奈緒子 清水 真央
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護教育 (ISSN:00471895)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.882-886, 2014-09
7 0 0 0 OA 天然変性タンパク質の動的構造解析
NMRや質量分析を用いて、天然変性タンパク質の動的構造を解析し、天然変性タンパク質を構造から理解し、分子認識機構の構造的な普遍性を解明することを目的として研究を展開した。その結果、ヒストン多量体および相同組換え補助因子 Swi5-Srf1複合体の構造、iPS細胞を誘導する転写因子Sox2およびOct3/4の動的構造、スプライシング関連因子PQBP1とスプライソソームU5-15kDの複合体およびPQBP1-U5-15kD-U5-52K複合体の立体構造を解析し、神経特異的抑制因子NRSFのN末天然変性領域とコリプレッサーSin3の相互作用を阻害する化合物を同定するなど、多くの成果が挙げられた。
7 0 0 0 OA 歴史哲学概論
- 著者
- オットオ・ブラウン 著
- 出版者
- 至上社
- 巻号頁・発行日
- 1924
- 著者
- 針間 克己
- 出版者
- 科学評論社
- 雑誌
- 精神科 (ISSN:13474790)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.246-250, 2006-09
7 0 0 0 OA 差異のドラマトゥルギー : 「障害者」に対する差別発言問題を考える
- 著者
- 高石 伸人
- 出版者
- 九州龍谷短期大学
- 雑誌
- 九州龍谷短期大学紀要 (ISSN:09116583)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.25-49, 2006-03-14
- 著者
- 小野 幸二
- 出版者
- 医学の世界社
- 雑誌
- 産婦人科の世界 (ISSN:03869873)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.295-297, 2006-03
7 0 0 0 サイバー空間に移行し始めた図書館 (田中功先生追悼特集号)
- 著者
- 神崎 秀嗣
- 出版者
- パーソナルコンピュータ利用技術学会論文誌編集委員会
- 雑誌
- パーソナルコンピュータ利用技術学会論文誌 = Journal of the Japan Personal Computer Application Technology Society (ISSN:18817998)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.5-8, 2015-03
- 著者
- 二宮 周平
- 出版者
- 判例タイムズ社
- 雑誌
- 判例タイムズ (ISSN:04385896)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.13, pp.47-53, 2006-05-10
7 0 0 0 OA 国立公文書館所蔵米国接収文書の概要
- 著者
- 広瀬順皓
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.37, 1990-03-05
7 0 0 0 クローゼットの認識論:セクシュアリティの20世紀
- 著者
- 志田 哲之
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.105-105, 2001
セジウィックによる本書は, 奇しくもバトラーの『ジェンダー・トラブル』と, その原著 (1990), 日本語訳 (1999) ともそれぞれ同年に出版された。バトラーが既存のジェンダー理解を構築主義的視点から批判的に問いかけたというならば, セジウィックは同様の視点から同様の問いかけを既存のセクシュアリティ理解に対して行なったといえ, 両書はジェンダー・セクシュアリティ研究に対し, 強いインパクトを与えた。<BR>「近代西洋文化の実質上どのような側面についての理解も, 近代のホモ/ヘテロセクシュアルの定義に関する批判的な分析を含まない限りは, 単に不完全というだけではなく, その本質的部分に欠陥を持つことになる」 (P.9) 。冒頭においてそう主張する著者は, その批判的分析を, 異性愛主義を内在化させている20世紀の西洋文化全体の側からではなく, 近代のゲイ理論および反同性愛嫌悪 (アンチ・ホモフォビア) の理論といった, 相対的に中心から外れた視点から始めることが適切であるとし, この視点から本書を著わした。このような問題関心から, 本書は二項対立化されている男性のホモ/ヘテロセクシュアルの定義が内包する矛盾や非一貫性に着目し, この矛盾や非一貫性に対して裁定を図るのではなく, むしろそれらの有するパフォーマティヴな効果を明らかにすることを企図した。<BR>序論では, ホモ/ヘテロセクシュアルの定義問題や二項対立について, またジェンダーとセクシュアリティを区分することによって生じる研究上の生産性についてなど, ホモセクシュアリティを研究していくうえでの諸議論に対し, 鋭い予備的考察が公理のスタイルをとって展開されている。序論としての役割を果たしながらも, この序論のみでホモセクシュアリティに関する今日的議論の概観を把握することが可能であり, まずはこの序論を一読することを勧めたい。<BR>第1章から第5章にかけては20世紀の欧米の文学作品を分析対象として, 本質主義対構築主義の拮抗, 二項対立, ホモセクシュアル・パニック, クローゼットという沈黙の発話状態などについて詳細に論じている。<BR>西洋文化圏において対照的な二項対立化された諸カテゴリーが, 実は暗黙のうちにダイナミックに存続しており, ホモ/ヘテロセクシュアルもその一部であるという筆者の主張は家族研究に連結する。なぜならこれら諸カテゴリーのリストとして筆者がとりあげた私的/公的, 男性的/女性的などは, 近代家族論の立脚点と相通じるからであり, 本書において筆者が行ったこれら二項対立の脱構築の試みは, 今後の家族研究のさらなる展開に対し示唆的であろう。また, 近代家族論以前の家族研究が, ホモセクシュアリティを研究の対象外とするか, あるいは病理として扱い, そして近代家族論においてはジェンダーを主要な軸のひとつに据えているものの, ホモセクシュアリティについては俎上に乗せられなかったという経緯をふまえるならば, 近代家族論以降の家族を論じる際にホモセクシュアリティという, あらたな軸を導入する意義や可能性について検討するヒントも本書から与えられるだろう。
7 0 0 0 IR 翻訳 李泰鎮「吉田松陰と徳富蘇峰」 : 近代日本による韓国侵略の思想的基底
- 著者
- 李 泰鎮 邊 英浩 小宮 秀陵 KOMIYA Hidetaka
- 出版者
- 都留文科大学
- 雑誌
- 都留文科大學研究紀要 (ISSN:02863774)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, pp.175-202, 2014
本稿は李泰鎭(イ・テジン ソウル大学名誉教授)が「韓日両国知識人共同声明記念第3 次学術会議」(2014 年1 月27 日)で行った報告を論文としたものである。直前に安倍首相が靖国神社を参拝し、韓国と中国、米国などからの批判をよびおこしていたが、靖国参拝の思想的背景の解明が必要とされていた。思想的源流はまず征韓論にあることは周知の通りであるが、被害当事国である韓国では、征韓論に対する研究は意外なほど少なく、本論文はその研究上の空白を埋めるものである。本論文では、韓国併合にいたる過程は、通説的な理解である近代的な帝国主義による膨張ではなく、吉田松陰が唱えた封建的な膨張主義である征韓論が実現していく過程であり、実際にも松陰の門下生たちがその後韓国併合をなしとげていったことが明かにされている。また併合過程で言論機関の統制を担ったのが徳富蘇峰であったが、徳富も吉田松陰の信奉者であり、徳富が吉田松陰のイメージをつくりあげていくうえで大きな役割を果たしたことも明かにされている。本論文が、現在悪化している日韓関係を巨視的にみていくにおいてもつ意義は決して小さくはない。 日本語への翻訳は小宮秀陵(こみや ひでたか 啓明大学校招聘助教授)が草案を作成し、邊英浩(ピョン ヨンホ 都留文科大学教授)が点検した。なお以前の本研究紀要では、邊英浩を辺英浩、BYEON Yeong-ho をPYON Yongho と表記した論説があることを付記しておく。
7 0 0 0 先天異常としての性同一性障害
- 著者
- 光嶋 勲
- 出版者
- 金原出版
- 雑誌
- 小児科 (ISSN:00374121)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.13, pp.2327-2330, 2004-12