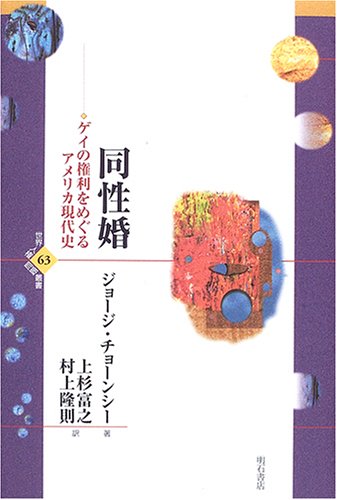7 0 0 0 性同一性障害の診断・治療とその問題点〔発表要旨〕
- 著者
- 山内 俊雄 加澤 鉄士 森 秀樹
- 雑誌
- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.1, pp.65-70, 1999-01-25
- 参考文献数
- 6
7 0 0 0 名医が勧める治療法(5)性同一性障害
- 著者
- 前田 健太郎
- 出版者
- 東京大学出版会
- 雑誌
- UP (ISSN:09133291)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.34-39, 2018-03
- 著者
- 辻 佐保子
- 出版者
- 早稲田大学演劇博物館
- 雑誌
- 演劇映像学
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.33-46, 2013-03-22
7 0 0 0 OA Timing of Australian flight attendant food and beverage while crewing: a preliminary investigation
- 著者
- Sally Lee PERRIN Jillian DORRIAN Charlotte GUPTA Stephanie CENTOFANTI Alison COATES Lyla MARX Karyn BEYNE Siobhan BANKS
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- pp.2018-0070, (Released:2018-10-19)
- 被引用文献数
- 13
Flight attendants experience circadian misalignment and disrupted sleep and eating patterns. This survey study examined working time, sleep, and eating frequency in a sample (n=21, 4 males, 17 females) of Australian flight attendants (mean age=41.8 y, SD=12.0 y, mean BMI=23.8 kg/m2, SD=4.1 kg/m2). Respondents indicated frequencies of snack, meal, and caffeine consumption during their last shift. Reported sleep duration on workdays (mean=4.6 h, SD=1.9 h) was significantly lower than on days off (M=7.2 h, SD=1.2 h, p<0.001), and significantly lower than perceived sleep need (M=8.1 h, SD=0.8 h, p<0.001). Food intake was distributed throughout shifts and across the 24 h period, with eating patterns incongruent with biological eating periods. Time available, food available, and work breaks were the most endorsed reasons for food consumption. Caffeine use and reports of gastrointestinal disturbance were common. Working time disrupts sleep and temporal eating patterns in flight attendants and further research into nutritional and dietary-related countermeasures may be beneficial to improving worker health and reducing circadian disruption.
7 0 0 0 OA 維新英雄詩人伝
- 著者
- 堀江秀雄 著
- 出版者
- 大日本百科全書刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1943
- 著者
- 野角 裕美子
- 出版者
- 国土社
- 雑誌
- 月刊社会教育 (ISSN:02872331)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.37-43, 2018-07
- 著者
- 金 利昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09131280)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.91-96, 2009-10-25
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
本研究は、自転車利用者の満足度を用いて自転車走行環境を評価し、自転車レーンのサービス水準を設定した。具体的な成果は第一に、自転車レーンにおける満足度評価の安定には10回程度の実走行が必要である。第二に、交通環境と満足度の関係を分析し、満足度モデルを構築した。第三に、構築した満足度モデルを用いてさまざまな道路状況における自転車レーン走行環境のサービス水準を設定した。これにより、利用者の満足度指標を用いた自転車レーンの評価を可能とした。
7 0 0 0 若年性線維筋痛症に対する集学的治療における理学療法
- 著者
- 松宮美奈 向山ゆう子 小林寿絵 中村大輔 髙木寛奈 上杉上 水落和也
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 第49回日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-29
【はじめに】線維筋痛症は原因不明の全身疼痛が主症状で,うつ病など精神神経症状・過敏性腸症候群など自律神経症状を随伴する疾患である。2013年の線維筋痛症診療ガイドラインによれば,有病率は人口の1.7%(日本推計200万人)であり,80%が女性で40~50代に多く,10歳前後に多い若年性線維筋痛症(Juvenile Fibromyalgia:JFM)は4.8%のみである。発症要因として外因性と内因性のエピソードがあり,治療はプレガパリンを中心とする疼痛制御分子の標的療法が中心で,運動療法は,成人例に対して長期間に渡り有酸素運動を行い疼痛が軽減した報告がある(エビデンスIIa)が,JFMでは,いまだ確立した治療法がない。JFMでは患児と母親の相互依存性や,まじめ・完璧主義・潔癖主義・柔軟性欠如などコミュニケーション障害を伴う性格特性が特徴であるとも言われており,当院では,小児リウマチセンターにおいてJFMの集学的治療を実践している。その内容は,生活環境からの一時的な隔離を意図した短期入院による母子分離,臨床心理士による心理評価と小児精神科によるカウンセリング,ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液(ノイロトロピン®)点滴静注を中心とした薬物療法,そしてリハビリテーション治療である。【目的】本研究の目的は,JFMに対する理学療法(PT)の実施状況と集学的治療による効果を明らかにし,JFMに対するPTの課題を明確にすることにある。【対象と方法】2007年4月から2012年12月までにJFMと診断され当院小児科に入院し,PTを行った症例を対象とし,患者属性,発症要因,入院期間,PT実施期間,PT内容,PT開始時及び退院時の運動機能と移動能力を診療録より抽出し後方視的に調査した。【倫理的配慮,説明と同意】当院では入院時に臨床研究と発表に対する同意を文書で得ている。【結果】調査期間に小児科に入院したJFM症例は33名であった。33名のうち6名は調査期間内に複数回の入院があり,これを別の入院例とみなして,対象を42例としたが,診療記録不十分のため調査項目の確認ができなかった3症例を除外し,39症例(30名)を対象とした。平均年齢は12.2歳(7~16歳),平均発症年齢12.1歳(7~15),性別は男児7例,女児32例であった。入院期間は中央値17日(7~164日),PT期間は中央値12日(1~149)だった。発症の誘因としては,内因性誘因では家族関係のストレス27例,学校関係のストレス22例であり,外因性誘因と内因性誘因の重複が11例にみられた。主症状は筋・関節痛39例,左上肢の慢性疼痛1例であり,ほぼ全例に睡眠障害や冷感,起立性調整障害など自律神経系合併症状を認めた。PT内容は,独歩可能な症例には歩行練習(屋外歩行やトレッドミル,水中歩行),自転車エルゴメーターなどを実施し,歩行困難な症例には下肢自動運動や座位・立位練習,車いす自走や歩行補助具を使用した段階的歩行練習を行っていた。また,キャッチボールやサッカーなどレクリエーショナルアクティビティも随時行われていた。PT中は疼痛が増強しない範囲で負荷を設定し,疼痛を意識させずに運動できるよう配慮し,受け入れのよい課題を選択し,目標を本人と相談しながら実施するなどの配慮がうかがえた。PT実施率は高く,疼痛や体調不良でPTを欠席したものは1症例,1日のみであった。入院中の疼痛の変化は改善28例,変化なし5例,悪化6例であり,移動能力は入院時に歩行(跛行なし)20例,歩行(跛行あり)9例,車いす移動10例が,退院時は歩行(跛行なし)28例,歩行(跛行あり)6例,車いす移動5例であった。【考察】成人の線維筋痛症では手術や感染などの外因が誘因となることがあるが,今回調査した小児では全例が内因性誘因を有していた。PTの介入は母子分離環境による心理社会的効果と薬物療法による疼痛軽減に合わせて,できる範囲の運動を導入することで,気晴らし的効果と身体機能維持改善の効果が期待できると思われた。PTの効果のメカニズムとして,JFMではセロトニン欠乏が睡眠障害や疼痛を引き起こすという知見が最近得られており,歩行などのリズム活動がセロトニン神経を賦活化し疼痛の悪循環を断ち切る可能性もある。疼痛で活動性が低下し,休学を余儀なくされている症例も多く,生活機能障害に対するPTの予防的・回復的・代償的な関わりはJFMの集学的治療に重要な役割を果たすと思われる。【理学療法学研究としての意義】線維筋痛症に対する運動療法の効果は成人では文献が散見されるが,小児では少ない。今回の調査は,JFMに対して症状の改善に運動療法が寄与した可能性を示唆している。
7 0 0 0 同性婚 : ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史
- 著者
- ジョージ・チョーンシー著 上杉富之 村上隆則訳
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2006
7 0 0 0 OA オランダの大学図書館におけるオープンアクセス支援
- 著者
- 尾城 友視
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, pp.2034, 2019-03-31 (Released:2019-04-25)
近年オランダでは,政策レベルでオープンアクセス (OA) が推進され,各大学図書館において現場レベルでの支援が行われている。本稿では,2018年11月にユトレヒト大学,ティルブルフ大学,オランダ大学協会 (VSNU) で実施したインタビュー調査に基づき,オランダの大学図書館におけるOA支援について報告する。ユトレヒト大学では,戦略プランにOA支援を位置づけ,OAファンドやジャーナル出版支援といった取組みを進めている。ティルブルフ大学では,オープンサイエンスに関するアクションプランの中で,ジャーナル出版支援やプレプリント発信等を目指す動きが見られる。VSNUでは,出版社交渉をはじめとする活動により,国内のOA活動を推進している。これらのオランダにおける取組みは,日本の大学図書館における研究支援のあり方を考える上でのモデルケースになると考える。
- 著者
- Ichiro Abe Hideyuki Fujii Hanako Ohishi Kaoru Sugimoto Midori Minezaki Midori Nakagawa Saori Takahara Tadachika Kudo Makiko Abe Kenji Ohe Toshihiko Yanase Kunihisa Kobayashi
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.187-192, 2019 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 12
Glucose intolerance is often observed in patients with pheochromocytoma. However, it remains controversial issue that glucose intolerance on pheochromocytoma is caused by impaired insulin secretion and/or by increased insulin resistance. We aimed to reveal the mechanism of glucose intolerance on pheochromocytoma with regard to the type and amount of catecholamines released. We evaluated 12 individuals diagnosed with pheochromocytoma and who underwent surgery to remove it. We examined glycemic parameters before and after surgery and investigated the association between the change of parameters of insulin secretion (homeostasis model assessment of β-cell function (HOMA-β)), insulin resistance (homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR)) and that of urinary levels of metanephrine/normetanephrine before and after surgery. Overall, fasting plasma glucose, glycated hemoglobin (HbA1c), HOMA-β, and HOMA-IR were improved significantly after surgery. Regression analysis showed that the improvement in HOMA-β from before to after surgery was significantly positively associated with an improvement in urinary levels of metanephrine from before to after surgery and showed a significantly negative association with improvement in urinary levels of normetanephrine from before to after surgery. The improvement in HOMA-IR from before to after surgery was significantly positively associated with an improvement in urinary levels of normetanephrine from before to after surgery. Our results showed that pheochromocytoma extirpation improved glycemic parameters. Furthermore, the different effects elicited by excess amounts of adrenaline and noradrenaline on glucose intolerance were demonstrated.
7 0 0 0 移民社会の形成と福祉国家財政
本研究の目的は、移民社会を抱えた先進福祉国家と移民を輩出する発展途上国との関係を、財政政策を媒介にして明らかにすることであった。先進国側では、移民社会の出現が、地方自治を通して福祉国家の縮小を促す。福祉的な社会サービスの受給者が移民であるのに対して、その税負担はもっぱら白人ミドル・クラスの財政課税に依存しているために、サービス受益者と税負担者が人種的の分裂してしまうからである。特に英米のようなアングロサクソン系諸国では、こうした傾向が強い。これに対して、南アジア諸国やフィリピンのような途上国では、移民達の送金が構造調整政策を支える役割を果している。1980年代以降貿易・為替政策の自由化や公的部門の縮小をはじめとする経済自由化政策を追求してきた。しかし脆弱な産業構造をもつ途上国では、さまざまな手段を講じて移民送金を引きつけようとするのである。また中国では華僑の投資が経済成長を先導している。このように移民社会の出現は、互いに経済自由化政策を支え合うという関係を作り出すのである。つまり、それは先進国の福祉国家を解体し、途上国では構造調整政策の実行を支える役割を果すのである。しかし、このことは、先進国・途上国の双方で、経済自由化政策に問題がないということを意味していない。先進国側では、マネタリスト的政策の一貫性は失われている。他方、途上国側では、経済自由化政策が外国投資の増加をもたらす反面、地域間格差や貧困問題を悪化させる側面をもっている。特に、地方財政分野では、税構造の歪み・インフラ事業の赤字や資金不足問題が生じており、教育・衛生・社会保障などの支出低下が生じているために、貧困問題の中長期的解決を遅らせているのである。
7 0 0 0 OA 高柳昌行とアクション・ダイレクト : “前衛”の終焉
- 著者
- 小野 貴史
- 出版者
- 信州大学教育学部
- 雑誌
- 信州大学教育学部研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.9-25, 2016-03-31
7 0 0 0 4次元的な断層破砕帯の解析と断層活動性の評価
- 著者
- 和田 実
- 雑誌
- 思春期学 = ADOLESCENTOLOGY (ISSN:0287637X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.139-148, 2007-03-25
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 綾部 慈子 金指 努 肘井 直樹 竹中 千里
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第124回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.399, 2013 (Released:2013-08-20)
2011年3月の福島第一原子力発電所爆発事故により放出され、その後森林地域に降下した放射性物質の食物連鎖を通じての濃縮・拡散過程を明らかにするため、林内、林縁部に生息する捕食性節足動物の造網性クモを対象として、その虫体に含まれる放射性セシウムの濃度を測定した。調査は2012年10月下旬に、発電所から北西30~35 kmにある福島県伊達郡川俣町内の渓流沿いおよび高台の二次林と、西65 kmの郡山市にある福島県林業試験場構内において行なった。地表から1~2 m高の網上のジョロウグモを採集し、持ち帰って個体湿重を測定した。各採集地では、地上高1 mの空間線量も併せて測定した。クモ個体は乾燥重量測定後に粉砕し、高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーにより1.6万~35万秒測定し、Cs-137, 134の個体重当たり濃度を算出した。その結果、30 km地点の渓流沿いで採集されたクモのCs-137濃度は2000~6800 [Bq/kg d.wt]、35 km地点の高台の二次林では820~2300であったが、郡山市の大部分の個体からは不検出であった。
7 0 0 0 SNS上で拡散するwebニュース説明文の調査と自動選択
- 著者
- 興梠 紗和 木村 昭悟 藤代 裕之 西川 仁
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J99-D, no.4, pp.403-414, 2016-04-01
SNSの隆盛によりニュースを取り巻く環境は大きく変化している.新聞やテレビから一方的に配信される記事を受け取るのではなく,膨大な情報で溢れるSNS上から関心のある記事を選択して購読する新たなニュースの読まれ方が生まれている.この変化により,ニュースメディアはSNS上で記事を読者に対して効果的にアピールする必要に迫られている.その一方で,刺激的な言葉を用いてむやみに拡散させるのではなく,記事を正確に説明し,その内容に興味をもつ読者に記事を届ける必要がある.本研究では,ニュース配信者がニュース消費者に適切なニュース記事を提供するための一手段として,ニュース記事を的確に説明する説明文が,SNS上でより多くの読者に読まれるために備えるべき性質を特定することを目指す.この目標に向け,本論文ではまず記者と編集者を対象としたヒアリング調査と,ニュースサイトがSNSに投稿している説明文の調査を行った.これらの調査を分析することで明らかになった,説明文がもつべき性質を利用することで,与えられたニュース記事をSNS上で紹介する説明文を幾つかの候補の中から自動的に選択する手法を提案する.
- 著者
- 折橋 裕二 新正 裕尚 ナランホ ホセ 元木 昭寿 安間 了
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.157, 2010
南米大陸西縁に発達するチリ・トレンチには約15Ma以降,断続的にチリ中央海嶺が沈み込んでおり,現在,タイタオ半島沖の南緯46°付近にはT-T-R三重点を形成している.したがって, SVZの最南端のハドソン火山からアンデス弧沿いの南緯34°まで発達するSVZ火山列の化学組成の側方変化を把握することで,定常的な沈み込み帯から中央海嶺沈み込みの開始に至るマントルウェッジ内の温度構造,スラブから脱水作用とマントルウェッジ内に循環するH2Oの変化を把握することができる.本講演ではSVZ全域の第四紀火山から採取した玄武岩質岩について,主・微量成分(ホウ素濃度を含む)を測定し,この結果から最南端のハドソン火山から最北端のサンホセ火山(南緯34°)に至るSVZ火山の化学組成の側方変化を 議論する.
7 0 0 0 OA 多摩川におけるカワラバッタの分布状況と生息地間ネットワークに関する研究
- 著者
- 野村 康弘 倉本 宣
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 環境システム研究論文集 (ISSN:13459597)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.73-78, 2005-11-03 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 4
本研究では多摩川に生息するカワラバッタについての分布状況と生息地間の移動に関して調べた. 分布調査の結果, 生息地が39ヶ所確認され, 本種は多摩川において連続的に生息していることが確認された. 標識再捕獲調査の結果, 標識数4641匹のうち85匹が生息地間を移動していたことが確認された. また, 総個体数と砂礫質河原面積には正の相関, 移出率と砂礫質河原面積には負の相関があった. 本種の通常起こりやすい移動距離を300mとしたbuffer-1と最大値の810mのbuffer-2を各生息地に発生させたところ, 本種の地域個体群が多摩川の河口から52.6~53.2km付近で大きく分断化されていることが推測された. 本種の保全のためには分断化されている地域個体群のネットワークをつなげることが重要と考えられた.