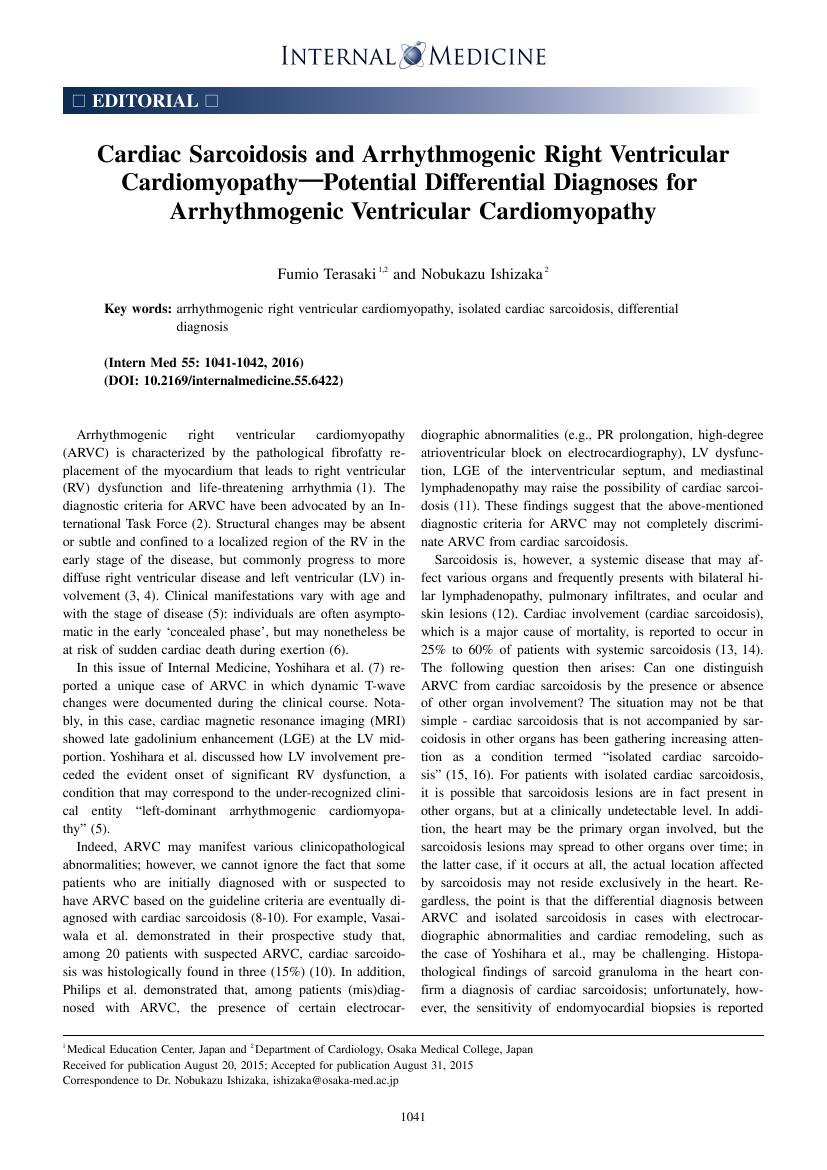- 著者
- 吉永 進一
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.721-725, 2006
- 著者
- Fumio Terasaki Nobukazu Ishizaka
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.1041-1042, 2016 (Released:2016-05-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4 3
5 0 0 0 OA カラオケを盛り上げるためのタンバリン演奏支援システム
- 著者
- 栗原 拓也 木下 尚洋 山口 竜之介 横溝 有希子 竹腰 美夏 馬場 哲晃 北原 鉄朗
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.1073-1092, 2017-05-15
本稿では,カラオケにおいて歌ってない人に対してタンバリンの演奏を促すことで,歌ってない人もカラオケを楽しみ,盛り上げることができるシステムを提案する.カラオケに行った際に,歌われている曲を知らなかったり,どのようにして一緒に盛り上げてよいか分からず,ただ曲を聴いているだけで退屈をしてしまう人は少なくない.そのような場合に対して,カラオケ店に置いてあるタンバリンの使用を促すため,どのようにタンバリンを演奏するか自動で生成・表示し,ゲーム風の画面により正しく叩けているかをフィードバックする.しかし,これだけではタンバリン演奏者が1人でタンバリンの演奏をゲーム感覚で楽しんでしまい,歌唱者や他の人と一体になってカラオケを楽しむ目的からは外れてしまう可能性がある.そこで,歌唱者も含めて全員がタンバリン演奏に参加するようにする.システムを実装し,実際にカラオケ店で実験したところ,次の可能性が示唆された.(I)本システムによりワンパターンなタンバリン演奏を防ぐことができる.(II)タンバリン奏者が知らない楽曲に対しては,譜面の表示によりタンバリンを演奏しやすくなる.(III)カラオケの一体感を高めるには,全員がタンバリン演奏に参加することが効果的である.一方,次のような課題も明らかになった.(i)生成されるタンバリン譜の難度が高く,正確なリズムで演奏できない場合があり,その場合むしろ歌いにくくなる.(ii)タンバリン演奏がうるさく感じられる場合がある.(iii)歌い手がタンバリンを叩く際に,歌いながらタンバリンを叩くのが難しい場合がある.
5 0 0 0 OA 教育社会学研究における能力の飼いならし
- 著者
- 小方 直幸
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.91-109, 2016-05-31 (Released:2017-06-01)
- 参考文献数
- 25
教育社会学研究は現在,伝統的ならびに現代的という二重の意味で,能力の飼いならしという課題に直面している。本稿は,1961年から2006年まで4度にわたり刊行され,我が国でも翻訳されてきた教育社会学のリーディングズに依拠しながら,この問題を考察する。教育社会学は伝統的に,階層,教育,地位達成の関係を考察し,不平等の構造を明らかにしてきた。しかし,教育は個人の能力の代理指標に過ぎず,能力の事後解釈というくびきから逃れられない。それは教育社会学の限界でもあるが,能力観を問わず教育機能を検証し続けられるという点で,強みでもある。教育社会学は50年前に経済と出会い,上記の経済に伴う不平等を考察する分析モデルを手にしたが,経済発展とそれに伴う教育拡大は,不平等を解消することはなかった。近年では,経済のグローバル化に伴い,分解,測定,比較という能力の可視化が,政治の世界で展開し,政治家や国民に不平等の現実を提示するという意味で,政治算術は教育社会学にとってますます重要になっている。他方で,能力の実態論を基盤としてきた教育社会学は昨今,能力の規範論であるシティズンシップ教育を重視し始めている。ただ,それが伝統的な階層,教育,地位達成をめぐる教育社会学のアプローチに及ぼすインパクトは定かでない。以上を総括すると,教育社会学は現在もなお,研究上も実践上も能力を飼いならせているとはいえない。
5 0 0 0 OA 日本の雑誌記事が描く日本人配偶者を持つ在日中国人女性 ─1990〜2000年代を中心に─
- 著者
- 鄧 婉瑩
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.58-79, 2020-04-15 (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 25
The purpose of this paper is to describe images of Chinese women with Japanese spouses in Japanese magazine articles during the 1990s and 2000s. In magazine articles from the 1990s, when international marriages between Chinese women and Japanese men were increasing, Chinese women were portrayed as “brides of the farmhouse” who could be purchased like products by Japanese men with economic power. The increase of international marriages between Chinese women and Japanese men has the background of a “shortage of brides” in rural Japan. They were regarded as alternatives to Japanese women who could support the patriarchal family system and fulfill the gender roles of “wife” and “mother.” However, in the 2000s, as Japan’s immigration control policies became stricter, Chinese women, who were supposed to become spouses of Japanese men, deviated from the gender norms and came to be seen as criminals that were a huge threat to “Japanese people” and “Japanese society,” as reported in the magazine articles. In this way, the images of Chinese women with Japanese spouses in magazine articles have primally changed from “good wives” who were subordinate to Japanese men sexually and performed their gender roles well, into that of criminals. This shift can be linked to the context where the Japanese government strengthened its control over illegal employment, “illegal residents,” and fake marriage cases involving foreigners in Japan.
5 0 0 0 OA 障害のある人の「障害」の語りの生起過程及び変化に関する検討
- 著者
- 田中 佑典
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院 臨床心理発達相談室
- 雑誌
- 臨床心理発達相談室紀要 (ISSN:24347639)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.49-69, 2022-03-18
障害当事者が自身の障害を語ろうとするときには何をいかに語ればよいのか、語り手と聞き手の相互作用という観点から「障害」の語りを実験的に検討し、考察した。先行研究では、当事者性の不確かな人が自分を語るときには、何をいかに語ればよいか、という知見が不在であった。そこで本稿では、自身が納得できるような「障害」の語りとはどのような場で何をいかに語ることか、そこでは「障害」はどのように語られていくのかを検討した。その結果、「障害」を語る際には、語り手が一方的に語るのではなく、語り手と聴き手が共に応答し合う必要性が明らかになった。また、引責から免責や主体の解体へ、因果論から現象や状況へと移行するように語り紡ぐことの重要性も示唆された。 なお、本研究では、筆者が医学的診断を受けた脳性麻痺や広汎性発達障害、それらの語義や症状を鍵括弧のつけない障害と定義する。それ以外の語られた物事をすべて「障害」として捉える。
5 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム障害児における聴覚性驚愕反射の特性とエンドフェノタイプ候補可能性の検討
- 著者
- 高橋 秀俊 石飛 信 原口 英之 野中 俊介 浅野 路子 小原 由香 山口 穂菜美 押山 千秋 荻野 和雄 望月 由紀子 三宅 篤子 神尾 陽子
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.103-108, 2015 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 3
聴覚性驚愕反射(ASR)は,精神医学領域におけるトランスレーショナル・リサーチにおいて,国内外で広く研究されており,特にプレパルス・インヒビション(PPI)は,精神障害の有力なエンドフェノタイプ候補と考えられている。自閉症スペクトラム障害(ASD)では,知覚処理の非定型性についてよく知られているが,ASD の PPI に関しては一貫した結論は得られていない。最近我々は,ASD 児では ASR の潜時が延長しており,微弱な刺激に対する ASR が亢進していることを報告した。そして,いくつか異なる音圧のプレパルスを用いて PPI を評価したところ,ASR の制御機構である馴化や比較的小さなプレパルスにおける PPI は,一部の自閉症特性や情緒や行動の問題と関連するという結果を得た。ASR およびその制御機構のプロフィールを包括的に評価することで,ASD や他の情緒と行動上の問題にかかわる神経生理学的な病態解明につながることが期待される。
- 著者
- 岡田 泰弘 Yasuhiro Okada
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集. 社会科学編 = Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin College (ISSN:04538862)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.80-94, 2011
- 著者
- 大久保 賢一 福永 顕 井上 雅彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.35-48, 2007-05-30 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 9
通常学級に在籍する他害的な問題行動を示す発達障害児に対して、大学相談機関と小学校が連携し、学校場面における行動支援を実施した。対象児に対する個別的支援として、(1)適切な授業参加を促すための先行子操作と結果操作、(2)課題従事行動を増加させるための結果操作、(3)問題行動に対する結果操作を段階的に実施した。また、校内支援体制を整備するために、(1)発達障害の特性や問題行動の対応に関する校内研修の実施、(2)支援メンバー間における情報の共有化と行動の継続的評価、(3)全校職員に対する情報の伝達といったアプローチを行った。その結果、対象児の適切な授業参加や課題従事行動が増加し、問題行動は減少した。また、大学スタッフと保護者の個別的支援を実施する役割を学校職員へ移行することが可能となった。対象児に対する個別的支援と校内支援体制の構築に関して、その成果と課題について考察を行った。
5 0 0 0 OA 漫画にみる図書館職員の人物像 (1990年代以降)
- 著者
- 山口 真也
- 出版者
- 沖縄国際大学日本語日本文学会
- 雑誌
- 沖縄国際大学日本語日本文学研究 (ISSN:13429485)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.左1-33, 2001-03
5 0 0 0 OA 漫画にみる学校図書館と学校図書館職員のイメージ
- 著者
- 山口 真也
- 出版者
- 沖縄国際大学日本語日本文学会
- 雑誌
- 沖縄国際大学日本語日本文学研究 (ISSN:13429485)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.左1-33, 2000-10
5 0 0 0 天台宗茨城教区寺史
- 著者
- 天台宗茨城教区寺史刊行委員会編
- 出版者
- 天台宗茨城教区宗務所
- 巻号頁・発行日
- 1994
5 0 0 0 OA ドイツ語圏における家族と離婚の周辺的課題
- 著者
- 柏木 恭典
- 雑誌
- 千葉経済大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Chiba Keizai College (ISSN:13498312)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.85-94,
This thesis discusses the problem of the family and the divorce in German speaking countries. First lyrics of a German song(G-POP) will be analyzed and interpreted. And, the difference of the understanding of the divorce between in Germany and in Japan is clarified. The latest issue of the family studies in German speaking countries will be continuously clarified. Finally, the problem of the concept of the patchwork-family will be described. A positive meaning of the divorce in German speaking countries will be clarified through this research. In German: Scheidungskind und seine Umgebung in den deutschsprachigen Landern.