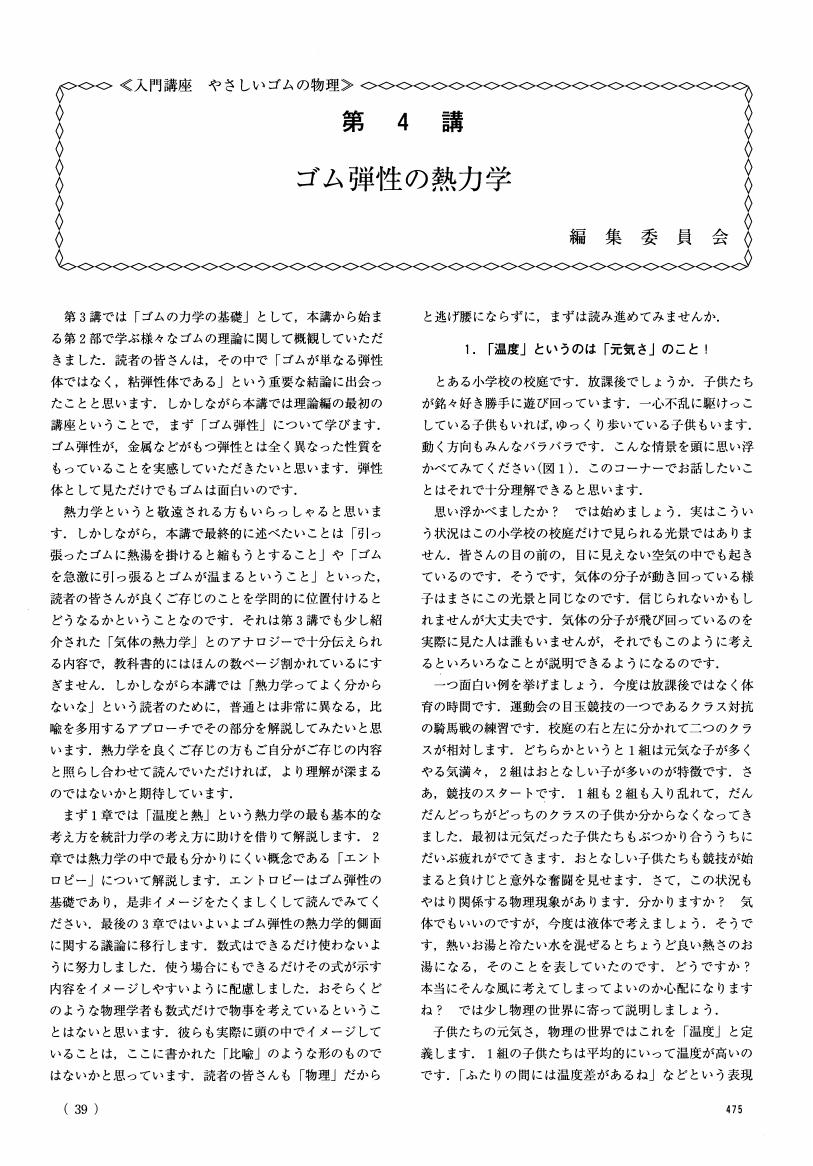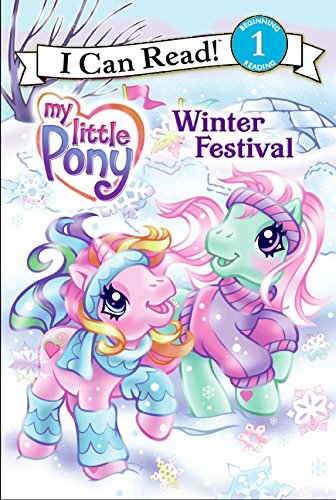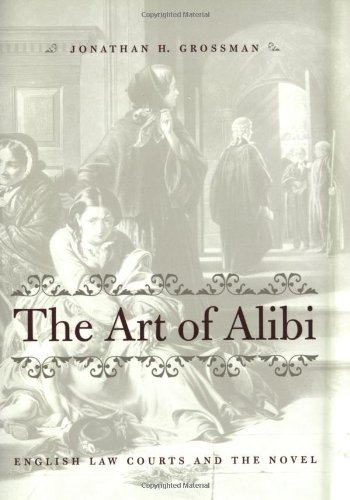1 0 0 0 OA やさしいゴムの物理第4講 ゴム弾性の熱力学
- 著者
- 編集委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.12, pp.475-482, 2007-12-15 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 OA やさしいゴムの物理第5講 ゴム弾性の統計力学 (その1)
- 著者
- 編集委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.128-134, 2008-04-15 (Released:2010-03-25)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 既存RDBを効率的にRDF化する支援ツールD2RQ Mapper
- 著者
- 和田 貴弘
- 巻号頁・発行日
- 2015-09-25
115p.
- 著者
- 吉松 梓 ヨシマツ アズサ Azusa Yoshimatsu
- 出版者
- 駿河台大学教養文化研究所
- 雑誌
- 駿河台大学論叢 (ISSN:09149104)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.143-157, 2015
1 0 0 0 OA 先哲叢談
- 著者
- 原念斎 (善) , 東条琴台 (耕) 著
- 出版者
- 松田幸助等
- 巻号頁・発行日
- vol.巻之3,4, 1880
1 0 0 0 スウェーデンにおける事実婚と婚姻 : 三四カップルの事例調査報告
- 著者
- 堀田 みゆき
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.154-161, 1997
The present thesis covers a case study on the relation between unmarrried cohabitation and marrige in Sweden, taking various legal aspects into account. In recent many western countries we can see the contemporary phenomenon of living together without gettin married. Especially in Sweden, it became more common for children to be born outside legal marriage. And today mostly all married couples have lived together as unmarried persons for some period before getting married. "Do people avoid marrying with some intention ?" or "Don't people care if they married or not when they form the family?" And then I performed researches on it by in-depth interviews in Stockholm and Halsingland of Sweden during March to May 1993. The total sample of couples consists of 21 cohabiting couples, 3 cohabiting couples with the fixed marriage date and 10 newly marride couples. 9 out of 24 cohabiting couples and 8 out of 10 married couples have 1-3 children. In Swedish society there is no longer any discrimination to children outside marriage even on peoples consciousness. In most cases the differences in their acutual life between legally married and unmarried are very few. As long as they lead their life as unmarried cohabiting couples, however, they could't get the right of succession to partners property but the right of property division by the cohabitees sct (sambalagen). Moreover, it is mostly impossible to take either of their family nam, e as the only family name. Then couples with children can't have the same family name as one family. The formal condition of marriage in Sweden is holding a wedding. the wedding is celebrated with festivities and today the wedding contains the meaning of confirmation rather than a rite of passage.
1 0 0 0 My little pony : winter festival
- 著者
- by Ruth Benjamin illustrated by Lyn Fletcher
- 出版者
- HarperCollins
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 韓国 朴槿恵大統領の対日政策及び対日発言
- 著者
- 菊池勇次
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 255-2), 2013-05
1 0 0 0 OA 安定同位体標識を利用した動的代謝プロファイリング
- 著者
- 蓮沼 誠久 原田 和生 三宅 親弘 福崎 英一郎
- 出版者
- 北海道大学低温科学研究所 = Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University
- 雑誌
- 低温科学 (ISSN:18807593)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.169-174, 2009-03-31
生体試料に含まれる代謝産物の量的情報をMSやNMRを利用して網羅的に解析する代謝プロファイリング技術は,微量な中間代謝物質を含む多様な化合物の一斉分析を可能にしたが,ここで得られる情報は代謝物質を抽出した時点での蓄積量のスナップショットであった.生体内で代謝物質が動的定常状態にある時,総量は変わらずに一定の同じ速度で分解と合成が行われて入れ替わっており,新規合成される物質の存在比率を知るためには安定同位体を用いたin vivo標識が必須である.代謝プロファイリングと安定同位体標識法の組合せを利用した「動的代謝プロファイリング」は,代謝産物の量的変動を網羅的に観測することを可能にする.植物の環境変化やストレスに対する応答はシステマティックな代謝変動に基づくことが予想され,「動的代謝プロファイリング」はこうした複雑な応答機構の解明に寄与することが期待できる.
1 0 0 0 ラベンダーの香りが上肢脊髄神経機能の興奮性に与える影響
- 著者
- 由留木 裕子 鈴木 俊明
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab1060-Ab1060, 2012
【はじめに、目的】 アロマテラピーは芳香療法とも呼ばれ、代替療法として取り入れられるようになってきた。アロマテラピーは、リラクゼーションや認知機能への効果、自律神経への影響から脈拍や血圧の変化、そして脳の活動部位の変化が示されてきている。しかし、アロマテラピーが筋緊張に及ぼす影響についての検討はほとんどみられない。本研究では鎮静作用や、抗けいれん作用があると言われているラベンダーの刺激が筋緊張の評価の指標といわれているF波を用いて、上肢脊髄神経機能の興奮性に与える影響を検討した。【方法】 対象は嗅覚に障害がなく、アロマの経験のない右利きの健常者10名(男性7名、女性3名)、平均年齢25.9±6.0歳とした。方法は以下のとおり行った。気温24.4±0.8℃と相対湿度64.3±7.1%RHの室内で、被験者を背臥位で酸素マスク(コネクターをはずしマスクのみの状態)を装着し安静をとらせた。その後、左側正中神経刺激によるF波を左母指球筋より導出した。この時、上下肢は解剖学的基本肢位で左右対称とし、開眼とした。F波刺激条件は、刺激頻度0.5Hz、刺激持続時間0.2ms、刺激強度はM波最大上刺激、刺激回数は30回とした。次にビニール袋内のティッシュペーパーにラベンダーの精油を3滴、滴下し、ハンディーにおいモニター(OMX-SR)で香りの強度を測定した。香りの強度が70.7±7.7のビニール袋をマスクに装着し2分間自然呼吸をおこない、F波測定を吸入開始時、吸入1分後、ビニール袋をはずし吸入終了直後、吸入終了後5分、吸入終了後10分、吸入終了後15分で行った。F波分析項目は、出現頻度、振幅F/M比、立ち上がり潜時とした。統計学的検討は、kolmogorov-Smirnov検定を用いて正規性の検定を行った。その結果、正規性を認めなかったために、ノンパラメトリックの反復測定(対応のある)分散分析であるフリードマン検定で検討し、安静時試行と各条件下の比較をwilcoxonの符号付順位検定でおこなった。【倫理的配慮、説明と同意】 被験者に本研究の意義、目的を十分に説明し、同意を得た上で実施した。【結果】 出現頻度においては、安静時と比較して吸入開始時、吸入1分後ともに増加傾向を示した。安静時と比較して吸入10分後は有意に低下した(p<0.01)。振幅F/M比はラベンダー吸入開始時、吸入1分後は安静時と比較して有意に増加した(p<0.05)。吸入終了直後からは安静時と比較して低下する傾向にあった。立ち上がり潜時は、ラベンダー吸入前後での変化を認めなかった。【考察】 本研究より、ラベンダー吸入中は出現頻度、振幅F/M比が促通され、吸入後は抑制された。出現頻度、振幅F/M比は、脊髄神経機能の興奮性の指標といわれている。そのため、本研究結果から、吸入開始時、吸入1分後には脊髄神経機能の興奮性が増大し、吸入後には抑制されたと考えることができる。吸入開始時、吸入1分後の脊髄神経機能の興奮性増大に関しては以下のように考えている。小長井らによると、ラベンダーの香りの存在下では事象関連電位P300の振幅がコントロール群と比較して増加したとの報告されている。事象関連電位P300は認知文脈更新の過程を反映するとされており、振幅の増大は課題の遂行能力が高いことを示している。感覚が入力され、脳内で知覚、認知、判断され、行動を実行するという能力が高いということであると考える。行動を実行するには運動の準備状態が保たれていることが推測され、脊髄神経機能の興奮性が高まっていることが考えられた。この報告と本研究結果から、ラベンダーの吸入時には大脳レベルの興奮性の増加が促され、その結果、脊髄神経機能の興奮性が増大したと考えることができた。脊髄神経機能の興奮性が吸入後から抑制されたことについては、ラベンダーが体性感覚誘発電位(SEP)に及ぼす影響を検討した研究で、ラベンダー刺激中から刺激後に長潜時成分の振幅が持続的に低下したと報告されている。これは、ラベンダーの匂い刺激が嗅覚系を介して脳幹部、視床、大脳辺縁系および大脳にそれぞれ作用し、GABA系を介して大脳を抑制したものと考えられた。今回の被験者は、アロマ未経験者を対象にしたが、アロマ経験者での結果と異なることも想定できる。また、アロマの種類によっても、効果の違いがあることが考えられる。今後、研究を行うことで、運動療法に適したアロマを取り入れ、新しい形の理学療法を展開したいと考えている。【理学療法学研究としての意義】 アロマ未経験者を対象とした筋緊張に対するラベンダーを用いたアプローチは以下のように考えることができる。上肢脊髄神経機能の興奮性を高めて筋緊張の促通を目的とする場合はラベンダー刺激中に、抑制したい場合はラベンダー刺激終了後に理学療法を行えば、治療効果を高める一助となる可能性があると考える。
1 0 0 0 OA Ten Times Eighteen
- 著者
- Sebastian Böcker
- 出版者
- 一般社団法人 情報処理学会
- 雑誌
- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.258-264, 2015 (Released:2015-05-15)
- 参考文献数
- 13
We consider the following simple game: We are given a table with ten slots indexed one to ten. In each of the ten rounds of the game, three dice are rolled and the numbers are added. We then put this number into any free slot. For each slot, we multiply the slot index with the number in this slot, and add up the products. The goal of the game is to maximize this score. In more detail, we play the game many times, and try to maximize the sum of scores or, equivalently, the expected score. We present a strategy to optimally play this game with respect to the expected score. We then modify our strategy so that we need only polynomial time and space. Finally, we show that knowing all ten rolls in advance, results in a relatively small increase in score. Although the game has a random component and requires a non-trivial strategy to be solved optimally, this strategy needs only polynomial time and space.
1 0 0 0 OA 天正豪傑八重垣主水輝秀
1 0 0 0 OA 三都勇劔伝 : 今古実録
- 著者
- 山元 大輔
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- no.36, 1992-09-10
1 0 0 0 OA 璣訓蒙鏡草 3巻
- 著者
- 多賀谷環中仙 撰
- 出版者
- 蓍屋傅兵衛[ほか2名]
- 巻号頁・発行日
- 1730
- 著者
- Moeko KOHYAMA Naomi TADA Hiroko MITSUI Hitomi TOMIOKA Toshihiko TSUTSUI Akira YABUKI Mohammad Mahbubur RAHMAN Kazuya KUSHIDA Keijiro MIZUKAMI Osamu YAMATO
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.15-0279, (Released:2015-11-06)
- 被引用文献数
- 1 11
Canine progressive rod-cone degeneration (PRCD) is a middle- to late-onset, autosomal recessive, inherited retinal disorder caused by a substitution (c.5G>A) in the canine PRCD gene that has been identified in 29 or more purebred dogs. In the present study, a TaqMan probe-based real-time PCR assay was developed and evaluated for rapid genotyping and large-scale screening of the mutation. Furthermore, a genotyping survey was carried out in a population of the three most popular breeds in Japan (Toy Poodles, Chihuahuas and Miniature Dachshunds) to determine the current mutant allele frequency. The assay separated all the genotypes of canine PRCD rapidly, indicating its suitability for large-scale surveys. The results of the survey showed that the mutant allele frequency in Toy Poodles was high enough (approximately 0.09) to allow the establishment of measures for the prevention and control of this disorder in breeding kennels. The mutant allele was detected in Chihuahuas for the first time, but the frequency was lower (approximately 0.02) than that in Toy Poodles. The mutant allele was not detected in Miniature Dachshunds. This assay will allow the selective breeding of dogs from the two most popular breeds (Toy Poodle and Chihuahua) in Japan and effective prevention or control of the disorder.
1 0 0 0 機械仕掛けの機械学習wizz
- 著者
- 黒松 信行 小林 健一 Viel Emeric 浦 晃 上田 晴康
- 雑誌
- 研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) (ISSN:21888841)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-HPC-150, no.18, pp.1-7, 2015-07-28
機械学習においては,処理するデータ量,得られる精度,実行に要する時間の制約を満たす中で,逐次・並列分散の観点も含めたライブラリやアルゴリズム,パラメータの膨大な組み合わせの中から最適なものを選択することは困難であった.そこで,許容できる実行時間と入力データを与えるだけで最も高い精度を得ることを目的として,条件を変えながら何度も機械学習を実行することで最適な選択肢を自動的に選ぶプラットフォーム wizz を Apache Spark 上に構築した.wizz は並列処理向けの Apache Spark の MLlib と逐次実行向けの R スクリプトおよび R スクリプトの分散実行によるアンサンブル学習機能を提供しており,並列処理ライブラリと逐次処理ライブラリを同時に多数実行することができる.
- 著者
- Jonathan H. Grossman
- 出版者
- Johns Hopkins University Press
- 巻号頁・発行日
- 2002