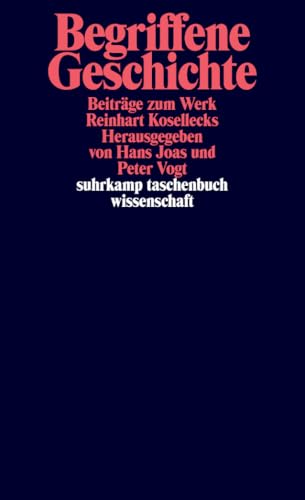- 著者
- herausgegeben von Hans Joas und Peter Vogt
- 出版者
- Suhrkamp
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 OA 同一音高の音符の相関を利用した音圧関数の1/fスペクトルと音高の1/fゆらぎ
- 著者
- 三谷 尚 井手 詩織
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011-MUS-92, no.5, pp.1-3, 2011-10-04
楽曲に関連するフーリエ・スペクトルを求めるために、一旦、相関関数を求め、Wiener-Khintchin の定理でスペクトルを求める方法に利点を見出した。なお、この方法によるスペクトルと、直接的スペクトル計算は比較し、妥当性をチェックしなければならない。これまでに音圧関数について、この方法を適用したが、近似を用いていた。今回、この近似の妥当性を明らかにし、かつ、音高関数についても、相関関数経由の方法を適用する。音高関数のスペクトルは、いわゆる 1/f ゆらぎとして知られるものであり、楽曲構成の点からこの本質に迫り得る。
1 0 0 0 界面物理制御を用いた高速マイクロリアクターの開発
本研究は、マイクロ流体デバイス内で生成した数百ナノメートルサイズの液滴(ナノ液滴)を用い、新たな微少量分析操作の開発を目的としている。本年度は、前年度に開発した自然乳化を利用したナノ液滴生成法を利用した、新たな選択的濃縮法の開発を目指した。1. ナノ液滴生成を利用したマイクロ液滴内包物の選択的濃縮法の開発前年度に、非イオン性界面活性剤(Span 80)を含む有機相中にマイクロ水滴を生成すると、マイクロ水滴からミセルへと水が分配し、マイクロ水滴界面から100 nm程度のナノ水滴が生成する(自然乳化)現象を見出した。この現象を利用し、マイクロ水滴内包物の濃縮が可能であると考えた。蛍光色素を含む40μm径のマイクロ水滴を用意し、自然乳化に伴うマイクロ水滴縮小と、マイクロ水滴内の蛍光強度の液滴径依存を観察した。その結果、親水性またはサイズの大きい分子はマイクロ水滴内に濃縮することが判明した。親水性の高いスルホローダミンを用いた場合、500倍に濃縮されることが分かった。また、サイズが小さく疎水性の分子はナノ水滴に分配し、マイクロ水滴内に濃縮されないことが分かった。2. 新規選択的濃縮法の生化学分析への応用可能性実証上記濃縮法の生化学分析への応用として、ビオチン・アビジンを利用したbound complex/ free ligand(B/F)分離を実証した。以上の成果は、マイクロ液滴を利用した微少量分析操作システムにおいてボトルネックであった、液滴内包物検出の感度向上を可能にすると期待する。これまで、マイクロ液滴は微少量試料分析のための反応場として注目を集めている一方で、液滴の光路長の短さと試料量の少なさゆえに、その内包物の検出法が限られていた。本研究の選択的濃縮法により、液滴内包物の検出法の自由度が向上し、より柔軟な微少量試料分析システムの開発が可能になると期待する。
1 0 0 0 OA 素人無線真空球式無線電話聴取装置の作り方
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.1124, pp.19-22, 2013-12-23
これまで主にディーゼル・エンジンと小排気量化で燃費規制に対応してきた欧州市場に、ようやく電動化の波がやってきた。フランスRenault社をはじめ、ドイツBMW社やドイツVolkswagen社といった欧州メーカーから電気自動車(EV)が相次いで発売され、2014年にはプラグ…
1 0 0 0 OA 福祉国家再編分析におけるアイデア・利益・制度(二) : 制度変化の政治学的分析に向けて
- 著者
- 加藤 雅俊
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.1-48, 2011-07-27
1 0 0 0 OA 福祉国家再編分析におけるアイデア・利益・制度(一) : 制度変化の政治学的分析に向けて
- 著者
- 加藤 雅俊
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.1-52, 2010-11-30
- 著者
- 加藤 雅俊
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.47-102, 2012-05-29
1 0 0 0 キンク不安定性
- 著者
- 宮本 健郎
- 出版者
- 社団法人プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.9, 1997-09-25
- 著者
- 水野 達朗
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科附属グローバル地域研究機構アメリカ太平洋地域研究センター
- 雑誌
- アメリカ太平洋研究 (ISSN:13462989)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.161-166, 2013-03
1 0 0 0 OA かいほジャーナル : 海上保安庁情報誌
- 著者
- 海上保安庁政策評価広報室
- 出版者
- 海上保安庁
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, 2011-10-14
1 0 0 0 高専関係者の応募の特徴(<特集2>文部省科学研究費補助金(1))
- 著者
- 編集委員会
- 出版者
- 日本高専学会
- 雑誌
- 高等専門学校の教育と研究 : 日本高専学会誌 (ISSN:1343456X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.29-37, 1998-04-30
1 0 0 0 OA 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震
- 著者
- MIYASAKO Nobuyoshi
- 出版者
- 外国語教育メディア学会
- 雑誌
- Language Education & Technology (ISSN:04587332)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.1-20, 2002-06
This paper examined the effects of reading, glossing and English ability on incidental vocabulary learning and its retention over a 18-day period for Japanese senior high school students (n = 187). The basic design was 6 (reading condition) x 2 (testing period) factorial between-groups with repeated measures on the second factor. The reading conditions were four different types of glossing, which were 12 nwltiple-choice glosses (MCG), Li MCG, L2 single glosses (SG) and Li SG, no glossing and control (no reading). The immediate and delayed vocabulary tests were conducted immediately after the reading phase and 18 days later. The results confirmed incidental vocabulary learning through reading for Japanese high school students, not retention. it was also acknowledged that this indirect vocabulary learning was enhanced with passage glossing, especially 12 MCG which had the students invest more mental effort. Further, the passage glossing was revealed to have a relationship with English ability: 12 glossing was more effective for higher-ability learners and Li for lower-ability ones. On the contrary, the existence or type of glossing did not have much effect on reading comprehension.
- 出版者
- 最高裁判所
- 巻号頁・発行日
- 2011-06