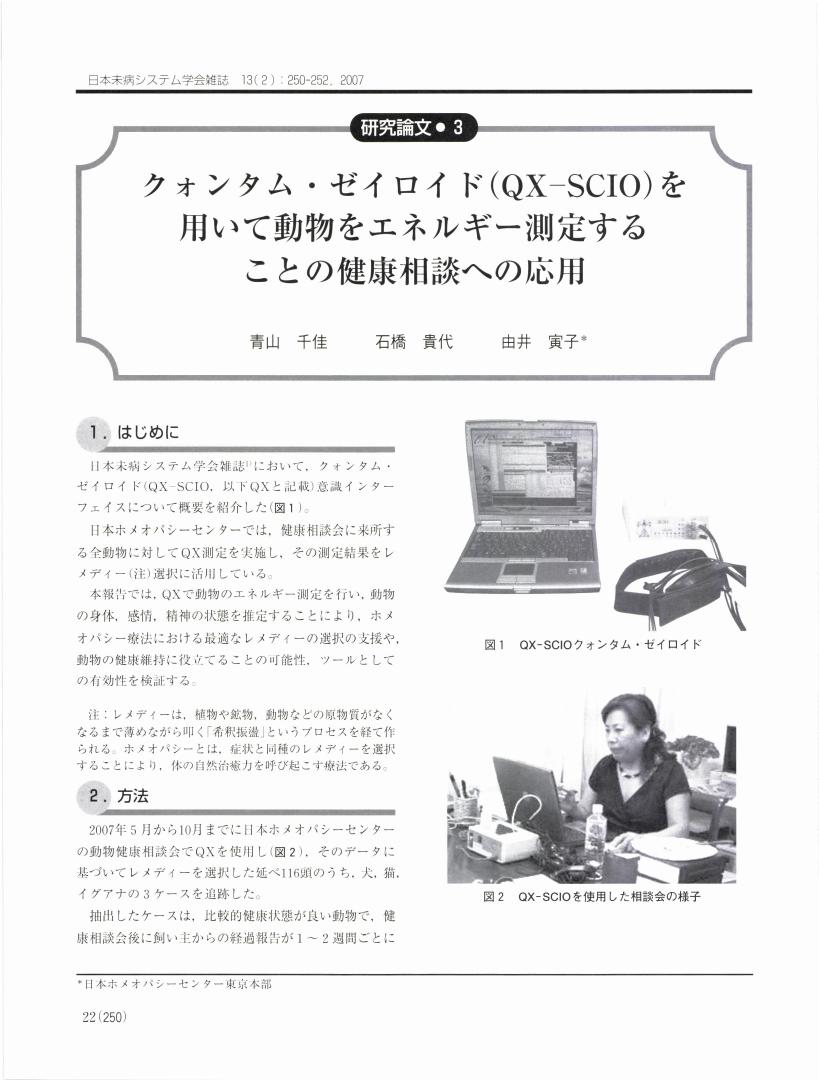1 0 0 0 IR バタイユの「欠落」とロール
- 著者
- 阿部 静子
- 出版者
- 慶應義塾大学藝文学会
- 雑誌
- 芸文研究 (ISSN:04351630)
- 巻号頁・発行日
- no.89, pp.185-170, 2005
立仙順朗教授退任記念論文集ロール伝説父親と「欠落」と「迂回」と出会いの前夜待ち望まれた「符合」アセファル共同体ロールの死/「欠落」とバタイユ
- 著者
- 鵜飼良平著
- 出版者
- フーディアム・コミュニケーション
- 巻号頁・発行日
- 1997
- 著者
- 青木 和也 鎌田 元弘
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会関東支部研究報告集
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.371-374, 2011-03-01
1 0 0 0 OA 医療事故生成プロセス防御モデルに基づく医療安全のための心理教育法の開発
1 0 0 0 OA 技術論文 H-ⅡBロケット試験機の打上げ成功
1 0 0 0 OA αシヌクレインの神経細胞生物学的研究
- 著者
- 上田 健治
- 出版者
- 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2011
我々が、アルツハイマー病脳のSDS不溶性成分の分析から未知分子として見出したαシヌクレインは、その遺伝子の変異体が優性遺伝型パーキンソン病の疾患責任遺伝子として同定された。しかし、αシヌクレインの生理的機能の詳細は不明のままである。我々は、αシヌクレインが脳神経細胞のミトコンドリア内膜に存在する事を見出した。さらに、αシヌクレインがadenylate translocatorに結合し、ATP産生の制御に関与する可能性を示した。培養細胞系を用いて、αシヌクレインが細胞増殖促進、神経細胞突起伸長を促進する事を見出し、その作用が微小管形成を介する事を示した。
1 0 0 0 OA 食材への切り込み操作が高齢者の咀嚼回数と嗜好性に及ぼす影響
- 著者
- 小出 あつみ 山内 知子 山本 淳子 松本 貴志子
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.48-55, 2012-02-05
- 被引用文献数
- 1
本研究では,高齢者が咀嚼しにくいと考えられる8種類の食材を試料として,切り込みにおける機器測定値,官能評価および咀嚼回数の関連から,高齢者における切り込みの有効性を検討した。切り込みによって煮にんじん以外の7試料(リンゴ,キュウ,煮ダイコン,煮コンニャク,カマボコ,イカ,タコ)は有意に軟らかくなった。咀嚼回数では切り込みによって全て試料の咀嚼回数が有意(p<0.05)に減少した。特にイカとタコの減少率が高かった。切り込みをした食材は高齢者に好まれなかったが,煮コンニャクとイカでは違和感は少なかった。したがって,イカヘの切り込みが,高齢者に違和感を与えず,食材の硬さと咀嚼回数を減少させる有効な調理操作であることが示された。
- 著者
- 清水 昌
- 出版者
- 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.2, pp.95-99, 2003-02-25
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 両大戦間期イングランド銀行の対外政策に関する研究‐エル・サルバドル準備銀行の創設
- 著者
- 佐藤 純
- 出版者
- 八戸工業高等専門学校
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2011
1930年代におけるイングランド銀行の対外政策に関しては、その影響力が及んだ範囲の大きさゆえに研究者の関心を集めてきた。これに関して先行研究は、同行がスターリング圏(sterlingarea)の安定と拡大を目的として、帝国内外の諸国にアドバイザーを派遣し中央銀行の創設を実現していったことは明らかにしているが、中央銀行創設に至るプロセスや、果たして中央銀行の創設によって上述の目的は達成されたのか否か、以上の点については十分には明らかにしてこなかった。本研究では、これらの点を1934年におけるエル・サルバドル準備銀行の創設に関する事例に即して明らかにした。
1 0 0 0 OA 中井和夫先生 業績一覧
- 著者
- [著者名なし]
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻
- 雑誌
- Odysseus : 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻紀要 (ISSN:13450557)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.95-99, 2013-03-05
1 0 0 0 IR 原敬の書(1) その評価をめぐって(書翰の書を中心に)
- 著者
- 玉澤 友基 TAMAZAWA Yuuki
- 出版者
- 岩手大学語文学会
- 雑誌
- 岩大語文 (ISSN:09191127)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.28-37, 1994-01-01
日本初の本格的政党内閣の組閣を行い、「平民宰相」と呼ばれた原敬〔安政三年(一八五六)-大正十年(一九二一)〕の、政治家としての業績や生涯の伝記等については今日に至るまで極めて多くの論評や出版がなされている。原の「書」もそれらの巻頭等に時折紹介されている。しかし、その書の全貌は意外と知られていないし、後で詳述するように評価も定着していない。先年、盛岡市の原敬記念館を訪れ、その書翰を閲覧する機会があった。政治家の書など俗物もいいところと決め込んでいたが、真蹟(注1)を見て、天馬空を駆けるような筆勢と躍動する筆に息をのんだ。筆は書者と一体となりその性能の限りを尽くしているではないか。草卒の書にもかかわらず、微塵の惑いも見せず縦横に運ばれる筆はその場その場で堂々と自在の造形を生み出している。凡庸の力量でできることではないと直観した。以来、原の書を掲載した出版物について努めて目を通した。また、原敬記念館の所蔵品や展示の資料(他機関からの借用資料等)についても種々拝見する機会を得た。その結果、原敬の書は、「書は人なり」という人間性の投影を明らかに示すばかりでなく、芸術性という点でもひとつの水準に到達した書といえるのではないかという思いを強めた。原の書は、多くの人に大きな感動を与えてくれるばかりでなく、さらに書の実作に携わる者にも貴重な示唆を与えてくれるものと思う。本稿では、原の書の中でも、書いた人物の書の実力を最もよく示すと言われる「書翰」に絞って、その書的価値について考察してみたい。
- 著者
- 宮下 晴輝
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.p7-37, 1986-10
1 0 0 0 現代金融論入門 : 不確実性下の金融行動理論
- 著者
- B.J.ムアー著 前田新太郎漆崎健治訳
- 出版者
- 第三出版
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 OA 記憶研究の現状と今後
- 著者
- 小松 伸一 太田 信夫
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.155-168, 1999-03-30
記憶研究において近年話題になっているトピックとして, 作業記憶, 潜在記憶, 展望記憶, 記憶の歪み, 自伝的記憶を取り上げ, それぞれのトピックにおける研究動向を展望した。作業記憶研究においては, 中枢実行系の機能を解明していくことがこれからの研究の焦点となっていた。潜在記憶研究では, 無意識的記憶過程との対比によって意識的記憶過程の解明が試みられ, 意図的な想起, 検索結果のモニタリング, 主観的意識経験, という3つの特徴が明示された。これら3つの特徴は, 生態学的妥当性を指向した研究の中で, より詳細な分析が積み重ねられてきた。まず展望記憶は, 回想記憶と比較した場合, 自己始動型検索に依存している点が特徴となっていたが, この特徴は実行機能の反映とみなされた。次に, 検索過程のモニタリングも実行機能の反映と考えられ, その失敗は記憶の歪みや誤りを引き起こすことが指摘された。さらに, 自伝的記憶の想起には, 自己概念が密接に関わり合っていることが示された。実行機能の解明は, 今後の記憶研究にとって重要な課題であることを示唆した。
1 0 0 0 OA 南ベトナム社会の構造と過程 : 1954-63
- 著者
- 中野 秀一郎
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.55-72, 1968-06
社会体系の成立・存続を合法的政権の存立を基準にして把えた理由は最初に述べたが, それはむしろ「構造」の在り方に対するタテマエに準じてのことであった。しかし, 現実には, 1957年以前と以後では, 特に「政府」の役割(その「能率性」と「正当性」)をめぐって顕著な差異が存する。consolidationの作業を中心とした初期のI・L次元での機能要件の充足は, 特に米国の強力な後押し, ジェムの民族主義者としてのイメージの斬新さ, 反仏・反封建・民族主義の一般感情など, favorableな諸条件にめぐまれていちおう成功的であった。もっとも, 政府・行政レベルにおけるkinship particularismの傾向はすでに1955年5月のジェム内閣の組閣にも顕著に現われているが, 1956年初頭の政治-宗教集団の掃討と政府軍の確立・強化とにみられる成功は, いちおう新政権が期待しうる成果としては上出来のものであった。しかし, 一方では主要な機能要件が対ゲリラ戦への諸活動となり, 他方, 行政の日常化(routinization)過程で権力の恣意性と権威主義(特に, ゴー一族の国政における私的干渉, 例, 1957年の"家族法")が増大し, 体系機能の全体的遂行という視角が消えてしまう。こうした体系機能要件遂行の阻害は, 組織論的には, particularismの進行に伴う, 命令統一・ライン組織の秘密警察組織による破壊が致命的であるが, これらはすべて「政策」施行のフィード・バック機構を閉ざすことになり, 権力の孤立化と独善化を招いた。特に, これが人的資源(忠誠と能力)の動員という社会構造の中心的要素を破壊するものであったことはここに詳らかにする必要もあるまい。(こうした行政的欠陥を如実に暴露しているのは, 1961年から始まった"戦略村"計画であった。)中央権力の機能喪失と正当性の失墜は, particularismの多元化として体系下位集団への「資源」配分の傾斜を招くが, それが伝統的な<kinship-oriented>の価値観を中核として, さらには第一次および文化的・派生的な機能をも充足させうる自足性の高い社会単位の生成を促す(もっとも, こうした状況自体を可能にするものは, 後進型社会に特徴的な社会的・機能的分化の未発達である)。こうして, 社会の四つの機能的下位領域で「政府」による「資源」動員の体制が空洞化し, 体系の崩壊が必然となるのである。
- 著者
- 森本 敏 小林 収
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1062, pp.74-77, 2000-10-16
問 日本の外交が、秋になって急速に動いています。森喜朗首相の日程を見ても、インド訪問の後、ロシア、韓国の大統領と会談し、中国の首相も来日が間近です。なぜ、重要外交がここまで集中したのでしょう。 答 片方に米大統領選があり、他方で国内の組閣を睨んでいるからでしょうね。
- 著者
- 青山 千佳 石橋 貴代 由井 寅子
- 出版者
- 日本未病システム学会
- 雑誌
- 日本未病システム学会雑誌 (ISSN:13475541)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.250-252, 2008-03-12 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 阿部 真大
- 出版者
- 日本労働社会学会
- 雑誌
- 日本労働社会学会年報 (ISSN:09197990)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.43-70, 2010
1 0 0 0 ユニットケアはケアヮーカーを幸せに するのか?
- 著者
- 阿部 真大
- 出版者
- 日本労働社会学会
- 雑誌
- 日本労働社会学会年報 (ISSN:09197990)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.43-70, 2010
1 0 0 0 OA 「政治的空白期」 : 戦後政治史時期区分試論
- 著者
- 木下 威
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 法政研究 (ISSN:03872882)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.81-130, 1966-07-15