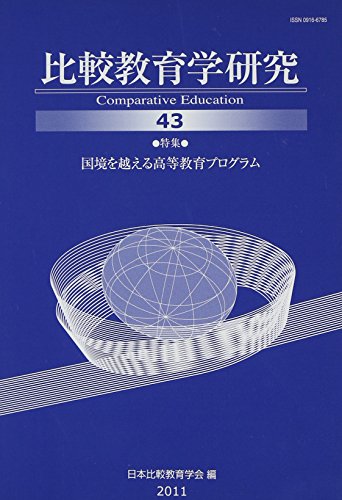1 0 0 0 2P1-C15 抑制足形状を有する2足受動歩行機による屋外歩行
- 著者
- 兵頭 和幸 押村 健史 三上 貞芳 鈴木 昭二
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp."2P1-C15(1)"-"2P1-C15(4)", 2009-05-25
- 被引用文献数
- 1
This paper verified the stability of the passive dynamic biped walk by not only indoor but also outdoor environments using a foot shape design to enhance stability. In outdoor environments, since the change of loose slope, small bumpy surface and the frictional force on a road surface are not constant, it is a difficult environment for realizing a walking. We propose about the walk stabilized comparatively in outdoor environment by control constraint mechanism.
1 0 0 0 大震災で見えてきた情報教育の課題
- 著者
- 奥村晴彦
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.8, pp.1-1, 2012-10-06
大震災によって情報の重要性が叫ばれている。これまでの情報教育は避難、復旧、復興の力になりえたであろうか。情報とは何かを考え、日常生活の活用場面を意識した教育、リテラシーの育成を考える。
1 0 0 0 OA 箱根地方ニ於ケル震害ト其復舊報告
1 0 0 0 OA IVRに伴う放射線皮膚障害報告症例から放射線防護を考える
- 著者
- 富樫 厚彦
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.12, pp.1444-1450, 2001-12-20
- 被引用文献数
- 26
1 0 0 0 ライフステージでみる日本の人口・世帯 : 平成22年国勢調査
1 0 0 0 「坊主主義」からの脱却を
- 著者
- 渋谷 国忠
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, 1957-04
1 0 0 0 特集国境を越える高等教育プログラム
1 0 0 0 醗酵鶏糞飼料のビタミン含量とその育雛効果
Recently, fermented products of chick droppings mixed up with rice bran or some other substances using special microbes are used for a poultry feed. Since the fermented chick droppings thus obtained contained considerable amounts of riboflavin, pyridoxine, pantothenic acid, and biotin, the substances seemed to be effective for promoting chick growth. The results from three times experiments indicated that the fermented chick droppings did not exert a significat effect on the chick growth, but that chicks did not hate to eat them and the addition of 10 to 20% of the products did not do harm to the chick growth.
1 0 0 0 IR 帝国議会における秩禄処分問題--家禄賞典禄処分法制定をめぐって
- 著者
- 落合 弘樹
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- no.73, pp.p177-199, 1994-01
1 0 0 0 Discours de la méthode
- 著者
- René Descartes
- 出版者
- Gallimard
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 Efficiencies of DNA inactivation and mutation induction by tritiated glycerol in bacterial systems.
- 著者
- 定家 義人 井上 正 望月 肇 賀田 恒夫
- 出版者
- Journal of Radiation Research 編集委員会
- 雑誌
- Journal of Radiation Research (ISSN:04493060)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.387-394, 1981
- 被引用文献数
- 2
When spores of Bccillus subtilis were treated in a frozen state with tritiated glycerol of different concentrations (up to 160 μCi/ml), efficiencies of killing and mutation induction per absorption dose were higher in solutions of lower tritium concentrations where low dose-rate β-irradiations were performed. Similarly when transforming DNA of Bacillus subtilis was kept with tritiated glycerol solution of concentrations ranging 0.05-500 μCi/ml at 4°C, efficiency of inactivation of the arginine marker increased strikingly by lowering the tritium concentration. On the other hand, the RBE of DNA-strand scissions of colicin El plasmids exposed to tritiated glycerol of a relatively high concentration (680 μCi/ml) was found to be approximately 1, when compared at the same absorption dose of gamma-irradiation (36 kR/hr) from a <SUP>137</SUP>Cs source.
1 0 0 0 Oeuvres complètes
- 著者
- Augustin Louis Cauchy
- 出版者
- Cambridge University Press
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 林羅山の読書
- 著者
- 宇野 茂彦
- 出版者
- 青山学院大学
- 雑誌
- 青山語文 (ISSN:03898393)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.12-26, 1984-03
- 著者
- 田中 淳夫
- 出版者
- 森林文化協会
- 雑誌
- グリーン・パワー (ISSN:03890988)
- 巻号頁・発行日
- no.349, pp.24-25, 2008-01
- 著者
- 関 満博
- 出版者
- 日本地域開発センタ-
- 雑誌
- 地域開発 (ISSN:03856623)
- 巻号頁・発行日
- vol.530, pp.47-49, 2008-11
1 0 0 0 備忘価額の会計機能
- 著者
- 山下 勝治
- 出版者
- 中央経済社
- 雑誌
- 企業会計 (ISSN:03864448)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.549-555, 1959-04
1 0 0 0 税務会計における減価償却制度の見直し問題
- 著者
- 大城 建夫
- 出版者
- 沖縄国際大学
- 雑誌
- 産業総合研究 (ISSN:13405497)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.1-11, 2005-03
減価償却制度の実態では、多くの会社が減価償却制度の見直しを求めていることを指摘した。減価償却に関する会計基準の具体的会計処理法が、まだ不十分であることを指摘せざるを得ない。減価償却の会計実務における税法との係わりを考えると、確定決算基準は基本的に維持されることが望ましいと考える。建物の定額法の限定した適用問題は、十分な実態調査に基づく定率法の減価償却方法の選択も認めていくべきである。定率法の算式の問題点は、わが国では、残存価額が10%となっているため現在は生じていない。しかしながら、最近では、残存価額等の適正化問題が生じており、定率法の算式問題について改めて検討すべき時期にきていると考える。税法が、耐用年数についてかなり詳細な内容になっているのであるが、法定耐用年数と実際耐用年数を比較した実態調査に基づく見直しが必要である。企業に自主的に耐用年数を決定させるために、耐用年数の適用範囲について弾力的に選択できるように認めていくべきである。残存価額と償却可能限度額は、定率法の算式の適用問題とも関わるが、備忘価額1円までの減価償却を税務署長への届出事項として認めていくべきではないかと考える。
1 0 0 0 ポリスとポリス的動物の自然性
- 著者
- 濱岡 剛
- 出版者
- 中央大学
- 雑誌
- 中央大学論集 (ISSN:03889033)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-23, 2007-03
1 0 0 0 ポリス的動物
- 著者
- 濱岡 剛
- 出版者
- 古代哲学会
- 雑誌
- 古代哲学研究 (ISSN:03865002)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.1-22, 2008
まず、アリストテレスが「ポリス(国家)的動物」という語をキーワードとしてポリスが「自然にしたがった」ものであることを論じている『政治学』第1巻第2章の議論を詳細に分析し、次のような点を明らかにした。家から村を経てポリスが形成される過程をアリストテレスは描いているが、その議論で繰り返し述べられている「自然によって」というのは、一貫して「人間の自然本性の実現に適う」という目的論的な意味で用いられており、人間がいわば本能のようなものによって家、村、ポリスを形成するということが語られているわけではない。『政治学』第1巻第2章の末尾では、個人がポリスの部分であることが指摘され、個人がまったくポリスに従属していることが強調されている。この点は『政治学』の他の箇所でも指摘されているように見える。しかし、それは特定の(生まれ育った)ポリスに従属し、そこから離れることが許されないというものではなく、人間の人間らしく生きているための「自足性」が確保される場として、ポリスに関わり、その政治的決定に参与する機会をもつことが必要である、ということが指摘されているあり、全体主義的な要素をそこに見いだすのは適当ではない。こうした分析を踏まえながら、『動物誌』第1巻第1章において、人間がミツバチなどと並んで「ポリス的動物」とされならがも、「群棲の動物と単独性の動物のとちらとも言える」両義的な存在であるとされていることの意味を探った。人間は他の「ポリス的動物」とは違って言葉によって価値の共有を可能とし、それによってポリスという集団を形成する。しかし他方で、言葉の習得を通じて熟慮能力をもつことができるようになり、人の集団から離れて暮らすことも可能となる存在である。