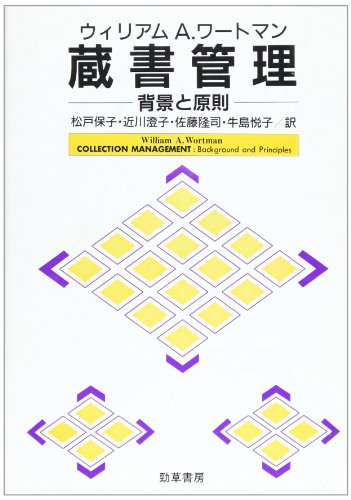- 著者
- 酒井 正博 青木 宙 北尾 忠利 ジョン ロオベック ジョン フライヤー
- 出版者
- 日本水産學會
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.7, pp.1187-1192, 1984
- 被引用文献数
- 15
The cellular immune response of rainbow trout <i>Salmo gairdneri</i> immunized by immersion or injection with <i>Vidrio anguillarum</i> bacterin was investigated using the passive antibody producing cell assay and passive antidody rosette-forming cell assay. Antibody-producing cels (plaqueforming cell: PFC) were rarely detected in the anterior kidney and spleen of raindow trout immunized by immersion. PFCs were detected in fish immunized by injection and reached the maximum level on the 13th day after immunization. The number of antigen-bingding cells (rosette-forming cells: RFCs) increased rapidly in the anterior kidney and spleen of rainbow trout vaccinated by immersion or injection. The RFC reached the maximum level on the 11th day after immunization. After that the number of RFCs gradually decreased until it reached the same level as that in non-immunized fish on the 28th day. The hemagglutinating antibody of the serum against <i>V. anguillarum</i> of fish vaccinated by immersion tended to be as low as the serum of non-vaccinated fish. However, the hemagglutinating antibody in fish vaccinated by injection was detected first on the 13th day after immunization. The maximum value of the titer was reached on the 28th day after immunization.
1 0 0 0 高電圧ソーラーアレイ宇宙実験とプラズマ干渉
- 著者
- 國中 均 高橋 慶治
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. PE, 電子通信用電源技術
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.149, pp.39-46, 1994-07-18
宇宙科学研究所は、再使用型宇宙実験プラットフォーム「スペース・フライヤー・ユニット(SFU)」を用いた高電圧ソーラーアレイ実験を開発し、1995年2月より宇宙実験に供する。本実験は大電力光発電のための高電圧送電の技術を宇宙環境で検証することを目的としている。4つの太陽電池モジュールの直並列切り替え機能を実証し、さらに最大260Vの高電圧により誘導される電離層プラズマ干渉を計測する。宇宙実験の概要とプラズマ干渉に関するこれまでの基礎研究について紹介する。
1 0 0 0 OA 自動フライヤーについて
- 著者
- 太田 静行
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.8-12, 1976-04-10
- 著者
- 北野 彰彦
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.226-229, 2011-04-20
1 0 0 0 SFUにおけるコンタミネーション分析結果
- 著者
- 永瀬 裕晃 中原 雅一 後藤 賢二 安西 徳夫
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. R, 信頼性
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.283, pp.7-12, 1997-09-26
近年, 衛星への光学機器搭載の増加に伴い, 衛星に使用している有機材料からの脱ガス, 衛星の姿勢制御用推進装置からの噴出ガス等による分子状の汚染物質であるコンタミネーションが衛星及び搭載機器へ及ぼす影響が今まで以上に重要視されている. 本論文では約10ヶ月間の宇宙空間での実験を終え, スペースシャトルで回収された衛星である宇宙実験・観測フリーフライヤ(SFU;Space Flyer Unit)に関して, 熱制御系の回収後評価の一つとして実施したコンタミネーション分析結果について述べる.
- 著者
- 岡林 洋
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.74-78, 1980-03-30
1 0 0 0 2p-J-13 イオンフライヤーの温度・密度・エネルギー分布特性
- 著者
- 村上 弘幸
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 秋の分科会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.4, 1990-09-12
1 0 0 0 OA サウンドスケープ研究の課題と展望
- 著者
- 鳥越 けい子
- 出版者
- The Institute of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.141-146, 1987-06-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 市民が捉えた記憶の音風景
- 著者
- 吉岡 宣孝
- 出版者
- The Institute of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.193-196, 1993-08-01 (Released:2009-10-06)
- 著者
- 加藤
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 機械學會誌
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.219, 1935-07-01
1 0 0 0 島津義久の孫たち--その小西行長との関わり
- 著者
- 中野 喜代
- 出版者
- 歴研
- 雑誌
- 歴史研究 (ISSN:02875403)
- 巻号頁・発行日
- no.475, pp.54-63, 2000-12
1 0 0 0 iSCSIストレージアクセスのトレースシステム
- 著者
- 山口 実靖 小口 正人 喜連川 研優
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告データベースシステム(DBS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.72, pp.447-454, 2004-07-14
本稿ではiSCIを用いたIP-SANのアクセストレースシステムの提案と それを用いた性能向上に関する考察について述べる.FC-SANの欠陥を補うSANとしてTCP/IPとEthernetを用いるIP-SANやiSCSIが期待を集めるようになっているが,IP-SANの欠点としては性能がFC-SANより劣るとの指摘もありIP-SANの性能向上の実現が重要であると考えられている.iSCSIを用いたIP-SANシステムではサーバ計算機とストレージ機器が孤立に個別のOS等で稼動し,それらがTCI/IPネットワークを用いて通信を行い強調して動作し全体のシステムを構築することとなる.よって,これらの統合的な解析の実現が重要である.本稿では,我々の実装した統合的なトレースシステムについて説明を行い,それを実際に高遅延環境における並列iSCSIアクセスに適用し性能制限原因の発見および発見された問題の解決により並列iSCSIアクセスの性能を向上させられることを示す.In this paper, we propose an IP-SAN access trace system and present performance improvement using the system. IP-SAN and iSCSI are expected to remedy problems of FC-based SAN. In IP-SAN systems using iSCSI, service and storage work cooperatively by communicating with each other via TCP/IP, thus integrated analysis of servers and storage can be considered important. We explain our integrated trace system and show that the system can point out the cause of performance degradation.
- 著者
- 栗木 恭一 黒河 治久
- 出版者
- 公益社団法人精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.1641-1644, 1995-12-05
- 著者
- Taigo Kintaka Takao Tanaka Makoto Imai Itaru Adachi Isamu Narabayashi Yasushi Kitaura
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.819-825, 2002 (Released:2002-08-25)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 6 18
Homozygous or compound heterozygous mutation of the CD36 gene (CD36-/-) in humans results in severe defects of the uptake of long-chain fatty acids (LCFAs) in the heart. Because the effect of a single mutation of this gene (CD36+/-) on the LCFA uptake is not known, it was evaluated in 29 subjects with the CD36 wild-type gene (WT) (6 healthy subjects, 10 patients with heart disease), CD36+/- (4 healthy subjects, 5 patients) and CD36-/- (4 patients). The CD36 genotype was identified in the coding region of genomic DNA, and the expression of CD36 protein was examined by flow cytometry after staining with monoclonal anti-CD36 antibody. The LCFA uptake in the heart was assessed as the radioactivity accumulation ratio of heart to mediastinum after intravenous administration of iodine-123 15-(p-iodophenyl)-3-R, S-methylpentadecanoic acid (H/M ratio). The H/M ratios in WT, CD36+/- and CD36-/- were 2.28±0.10, 1.90±0.06 and 1.40±0.11, respectively (p<0.0001, among groups). The H/M ratio between healthy subjects and patients with heart disease for WT and CD36+/- did not differ significantly (ie, those of WT and CD36+/- in healthy subjects and patients were 2.29±0.08 vs 2.27±0.12 and 1.90±0.07 vs 1.89±0.05, respectively). Not only CD36-/- but also CD36+/- resulted in a significant reduction of the LCFA uptake in the heart independent of heart disease, suggesting genotype dependency and that CD36 might be a fundamental determinant of myocardial LCFA uptake. (Circ J 2002; 66: 819 - 825)
1 0 0 0 OA Some notes on Formosan Butterflies
- 著者
- MURAYAMA SHU-ITI
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.66-68, 1959-11-15
著行は本文で台湾産コモンタイマイ及び5種の蝶類異常型の記載を行った.これらの材料は土として陳維寿氏の提供にかかるものでここに謝意を表する.コモンタイマイについては原種とみられる手もとのインド・アッサム産(Fig.3)や南シナ産の標本とくらべると,前翅表面1b室の中央1a脈に接して存在するやや矩形の緑色紋が基部の側に向ってこれに近く存在する,より小形な緑色紋と相融合する傾向をもつことが注意される.融合しない個体では,細い黒線で2つの紋が境され,原種の様に全く離れることはない.この点がもっと多くの個体で確認されると台湾の本種は地方型として分離出来るだろう.但し梅野氏(Zephyrus,5:247-248)が指摘された台湾産の本種は後翅の尾状突起が原種程長いものはないという点は,必ずしもすべての個体にあてはまらない.写真でみるように,♂には短い個体はあるが,♀は長く,♂でも♀と同様のものもあるから,これは固定した特徴となし難い.次にシロオビアゲハについては私はさきにNew Ent.Vol.7,No.1(1958)で応♂2異常型を記載したが,今回は2♀♀1♂を記載する。元来♂♀共に多型の種でこれらにすべて命名の必要があるとは思わないが,顕著なものにはある方が便利だろう。♀-ab.scintillansのTypeでない方の個体は一応同系列の異常型としたが,色彩は非常に趣きを異にし,中室端及び第2,3,4室基部の白紋は橙黄色をおび,これに続く赤紋及び第1室の長大な赤紋は紫白色をおび,後翅全体として赤紋はえび茶色を呈するが,裏面も同様赤紋に著しく紫白色鱗を交える.
1 0 0 0 OA 文章理解における接続詞の働き
- 著者
- 伊藤 俊一 阿部 純一
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.241-247, 1988-10-31 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 11
This experiment was conducted to investigate the function of connectives in text comprehension. Twenty six subjects were instructed to read six texts, each containing several target sentences. Eighteen target sentences were provided, and each of the subjects was presented half of the target sentences in their original form, i.e., with a connective (Connective condition, C), and the other half, without a connective (No-connective condition, NC). After reading, subjects were asked to recall all the target sentences. In recall, all the sentences preceding the target sentence were presented as a cue. Recall rate was higher for the C condition than for the NC condition. The result indicated that connectives facilitate text comprehension. This effect was seen most clearly in three connective categories called jyunsetsu (e. g., causality), gyakusetsu (i.e., adversative), hosoku (i.e., supplement) in Japanese.
- 著者
- 濱田 彰一 間野 隆久
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會誌 (ISSN:00214728)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.1019, pp.760-764, 2003-10-05
- 著者
- 吉利 賢治 山本 雅一 片桐 聡 濱野 美枝 有泉 俊一 小寺 由人 浦橋 泰然 高橋 豊 今井 健一郎 高崎 健
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, 2006-07-01
1 0 0 0 蔵書管理 : 背景と原則
- 著者
- ウィリアム A. ワートマン著 松戸保子 [ほか] 訳
- 出版者
- 勁草書房
- 巻号頁・発行日
- 1994