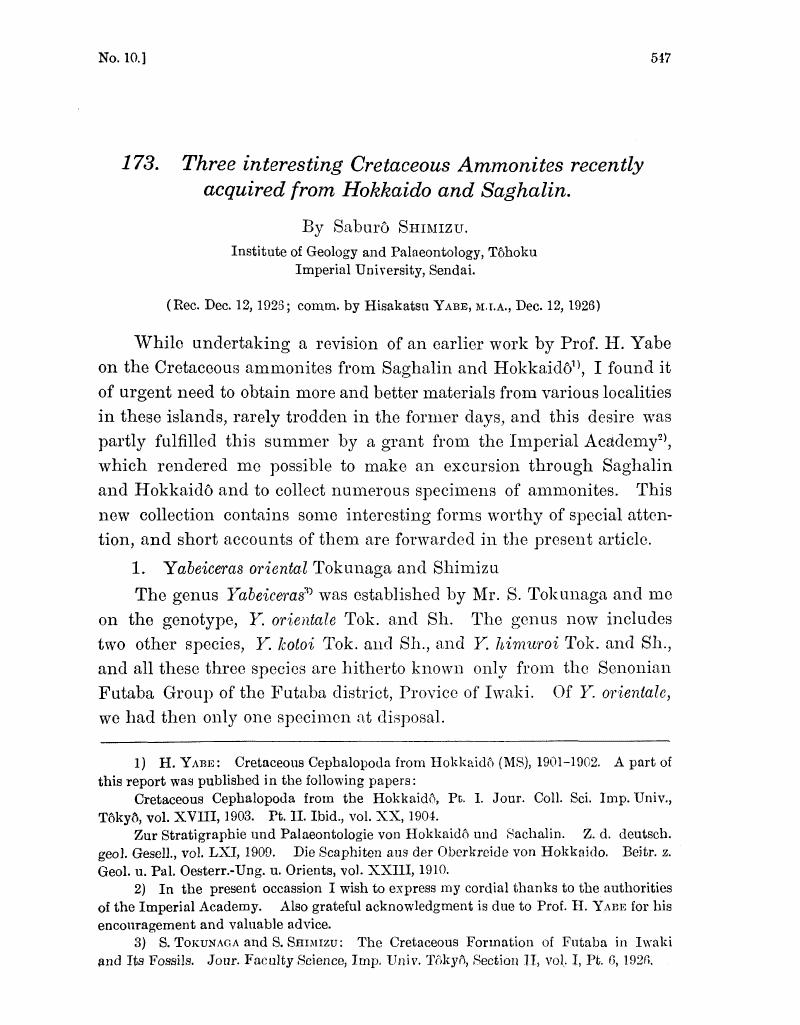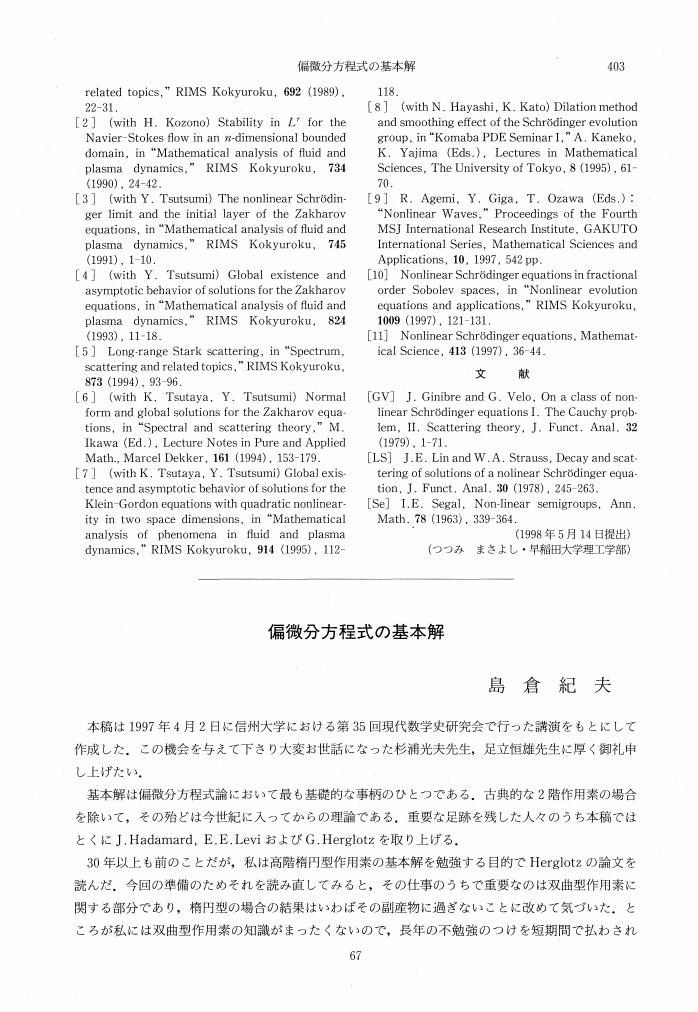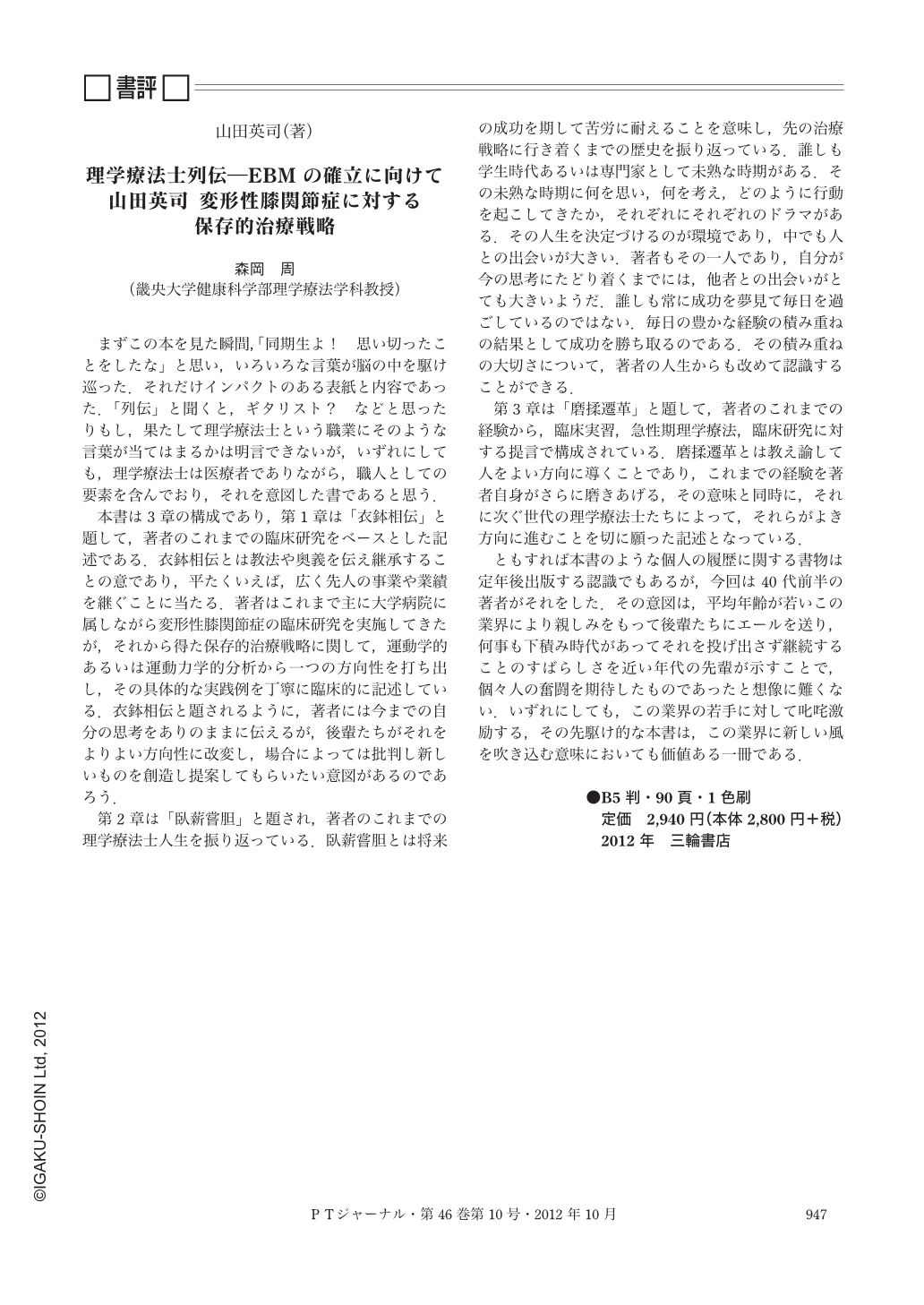- 著者
- 村井 活史 浦久保 知也 西田 靖武 洪 苑起 菅原 敬信 岡村 元義 小田 昌宏 川俣 治 小杉 公彦 塩見 哲次 高橋 英晴 殿守 俊介 林 秀樹 丸山 裕一
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.6-31, 2007 (Released:2008-06-06)
- 被引用文献数
- 1
The Bio-virus safety committee, one of the committees of the Parental Drug Association Japan (PDA Japan), has discussed various concerns on biopharmaceuticals from scientific, technical and regulatory perspective. One of the most significant concerns is the risk of viral contamination into the products. This risk should be addressed, as required per the international regulations, by minimizing to use raw materials sourced from animal origin and by performing viral clearance studies in order to evaluate capability of purification processing to reduce and/or inactivate known and/or adventitious viruses. The Bio-virus safety Committee has reported the conclusions of discussion how to prepare and qualify cell bank system as one of raw materials and how much Log Reduction Value (LRV) should be targeted in virus clearance studies in the annual conference of the PDA Japan in 20051). The Bio-virus safety committee has discussed the practical experimental procedures for viral clearance studies since 2006 and reported the conclusions in the annual conference of the PDA Japan in 2007. In this report, standardized and practical experimental procedures for viral clearance studies are shown, considering not only requirements for submission to regulatory agencies but also experimental technique. In addition, trouble shooting based upon experiences of the members, information regarding Contract Research Organizations (CROs), reference of international guidelines, and worksheets of viral clearance study are provided.
2 0 0 0 OA テストパイロットは緊急事態にいかに対処するか
- 著者
- 原田 実
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.Supplement, pp.100-103, 1993-05-16 (Released:2010-03-11)
- 著者
- Saburô SHIMIZU
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Imperial Academy (ISSN:03699846)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.10, pp.547-550, 1926 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 1
2 0 0 0 OA 偏微分方程式の基本解
- 著者
- 島倉 紀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.403-420, 1998-10-29 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 高等女学校における「衛生」と身体への管理 ――「女子特別衛生」が意味したもの――
- 著者
- 斉藤 利彦
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.55-65, 2017-10-20 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 25
近代日本における「衛生」の導入が、国民国家の形成にいかなる役割をはたしたのか、そしてそれがどのように身体への管理に結びついていったのかについては、すでに様々な視点からの研究が蓄積されている。ところで、戦前期の高等女学校や女子師範学校で行なわれていた「女子特別衛生」は、これまでの先行研究では全く取りあげられてこなかった。その対象は女学校という発達段階の特性から、特に「月経」に焦点化されていたが、具体的にどのような実態をもち、いかなる背景と論理をもって生み出されたものであったのか。それは、女生徒の身体への管理ととらえられるべきものなのか、あるいは月経時の女生徒の身体への保護を目的とした正当で必要な配慮というべきものなのかが明らかにされなければならない。その際、この「女子特別衛生」が、個々の高等女学校で個別的に案出されたものではなく、明治30年代における国家による月経への着目という事態の中で成立したものであったということが重要である。本稿では、1900(明治33)年の文部省訓令第六号による月経への取扱方を分析し、それが各地の高等女学校での「特別衛生心得」の制定へと具体化されていった実態を明らかにする。そこに現れていたのは、「良妻賢母主義」の身体的具体化であり、「 衛生」の啓蒙と脅迫的なトーン、そして月経時の過剰な指導であった。さらに、1919(大正8)年の文部省による全国調査「月経に関する心得方指導、月経時に於ける生徒の取扱」の検討を行う。そこでは、国家的規模での詳細な月経への調査が実施され、教師による日常的な観察を通して、何が「正常」な月経で、何が「異常」なのかを国家と学校が規定する、いわば他律的な「規格化」が行なわれていたのである。はじめに近代日本における「衛生」の導入が、国民国家の形成にいかなる役割をはたしたのか、そしてそれがどのように身体への管理に結びついていったのかについては、すでに様々な視点からの研究が蓄積されている。
2 0 0 0 OA スポロトリコーシス,黒色真菌感染症の治療
- 著者
- 本房 昭三 古賀 哲也 山野 龍文 占部 治邦
- 出版者
- The Japanese Society for Medical Mycology
- 雑誌
- 真菌と真菌症 (ISSN:05830516)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.152-158, 1985-09-20 (Released:2009-12-18)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 2
スポロトリコーシスと黒色真菌感染症の治療現況を報告するとともに, これらの疾患にたいする抗真菌剤の適応について述べた. スポロトリコーシスの治療としてはヨウ化カリウム (KI) の投与あるいは温熱療法が一般的であり, また使用さるべき治療法である. Flucytosine (5-FC) とケトコナゾールは数例において有効であったと報告されており, KIあるいは温熱療法が奏効しない場合には有用であるかも知れない. 黒色真菌感染症の治療としては, 病変が皮膚に限局され, かつ広範囲でない場合には外科的切除が first choice である. 現時点で黒色真菌感染症にもっとも有効な薬剤は5-FCであり, リンパ節転移などの内臓病変を有する場合, 広範囲の病変を有する場合には5-FC, あるいは5-FCとアムホテリシンB点滴静注の併用が推奨される.KIの作用機序についても検討を行なったが, KI投与後血中にヨウ素 (I2) を検出することは出来なかった. しかしヨウ化物イオン (I-) は30~60ppmの濃度に達した. In vitro の実験ではKI(1×10-4M)+H2O2(5×10-5M)+peroxidase, KI+H2O2+Fe++の条件下で Sporothrix schenckii の酵母形は5分後に完全に殺菌された. KI+I2(5×10-6M) の条件下でも5分後にはほぼ完全な殺菌効果がみられた. KI+H2O2 の条件下では120分後に完全な殺菌効果が認められた.また3×10-4MのKIと5×10-5MのH2O2の存在下では2×10-6M程度のI2が産生された. これらの結果から, peroxidase-iodide-H2O2 system, iron-H2O2-iodide system に加えてKIから酸化されて生じたI2が直接殺菌作用を示すためにスポロトリコーシスにおいてKIが特異的に奏効するのではないかと考えた.
2 0 0 0 OA 諸系譜
- 巻号頁・発行日
- vol.第7冊, 1800
まずこの本を見た瞬間,「同期生よ! 思い切ったことをしたな」と思い,いろいろな言葉が脳の中を駆け巡った.それだけインパクトのある表紙と内容であった.「列伝」と聞くと,ギタリスト? などと思ったりもし,果たして理学療法士という職業にそのような言葉が当てはまるかは明言できないが,いずれにしても,理学療法士は医療者でありながら,職人としての要素を含んでおり,それを意図した書であると思う. 本書は3章の構成であり,第1章は「衣鉢相伝」と題して,著者のこれまでの臨床研究をベースとした記述である.衣鉢相伝とは教法や奥義を伝え継承することの意であり,平たくいえば,広く先人の事業や業績を継ぐことに当たる.著者はこれまで主に大学病院に属しながら変形性膝関節症の臨床研究を実施してきたが,それから得た保存的治療戦略に関して,運動学的あるいは運動力学的分析から一つの方向性を打ち出し,その具体的な実践例を丁寧に臨床的に記述している.衣鉢相伝と題されるように,著者には今までの自分の思考をありのままに伝えるが,後輩たちがそれをよりよい方向性に改変し,場合によっては批判し新しいものを創造し提案してもらいたい意図があるのであろう.
2 0 0 0 OA 年縞環境史による国際貢献
- 著者
- 安田 喜憲
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1_46-1_59, 2010-01-01 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 19
- 著者
- 北 桂樹
- 出版者
- 京都芸術大学大学院
- 雑誌
- 京都芸術大学大学院紀要 = Journal of Kyoto University of the Arts Graduate School
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-13, 2022-11-10
2 0 0 0 OA 気候区から見た百歳長寿者の居住分布の経年変化に関する調査
- 著者
- 岩崎 輝雄 岩崎 洋一 矢崎 俊樹 森谷 〓 阿岸 祐幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.147-152, 2002 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 20
We plotted the distribution of long-lived persons derived from the national register of long-lived persons as of fiscal years of 1980 (N=1, 349) and 2000 (N=17, 740) prepared by the Ministry of Health and Welfare to investigate various factors such as medical climatology and geography on healthy aging. The data were plotted on a map of Japan classified into various living environments, such as coastal areas, forests, and mountainous areas. In addition, we investigated universal elements and transforming elements through year-by-year comparisons over a period of 20 years. Japan was divided into nine climatic districts Hokkaido, the Japan Sea area, the Pacific Ocean area, the Sanriku district, the Tokai district, the inland district, the Seto Inland Sea district, the Northern Kyushu district, the Nankai district, and the South-western Islands.Consequently, we found a common trend that relatively warm climates and climates in coastal areas are favorable for longevity. However, the following trends were also recognized as transforming elements that cannot be ignored: 1. A remarkable improvements in the rate (number of long-lived people per 100, 000 population) in cold climate regions, i.e., the Japan sea area, inland area, and Hokkaido; 2. A remarkable shift of higher rates from coastal areas, which are contaminated by industrial plants, to inland flat areas.As a result, it has become clear that research on factors of healthy aging, especially in cold climate regions, have to be made in the future.
2 0 0 0 OA 何桜彼桜銭世中 : 花莚七枚
2 0 0 0 OA 電信電話教科用参考書
- 出版者
- 逓信省
- 巻号頁・発行日
- 1897
2 0 0 0 OA 『教行信証』における『弁正論』の引用と法琳の人生
- 著者
- 張 偉
- 出版者
- 同朋大学仏教文化研究所
- 雑誌
- 同朋大学仏教文化研究所紀要 (ISSN:13412191)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.13-30, 2012
2 0 0 0 OA 国際人道法とは何か (文化の差異に関する研究部会 戦時海運研究部会 合同セッション報告)
2 0 0 0 OA 教授・学習・認知に関する研究の「探究的な学習」への展開可能性
- 著者
- 小山 義徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.28-42, 2020-03-30 (Released:2020-11-03)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
本稿は,この数年の間に発表された,日本教育心理学会における教授・学習・認知領域における研究を概観し,この分野における成果を紹介した。本稿の対象としたのは2018年7月から2019年6月末までに『教育心理学研究』に掲載された論文及び,2019年9月に日本大学で開催された日本教育心理学会第61回総会で発表された内容である。本稿では,『教育心理学研究』に掲載された研究と,総会で発表された研究を分けて紹介し,学会誌におけるトレンドと学会発表のトレンドが明らかになるように構成した。また,「探究的な学習」に関する理論やエビデンスとしてどのような研究があるかを検討した。その結果,「探究的な学習」に関する研究があまり多く行われていないことが明らかになった。そのため,最終節では,特に「疑問生成」にフォーカスして,教育心理学の「探究的な学習」への展開可能性について述べた。
2 0 0 0 OA 冷風乾燥と焙焼に伴うマアジ塩干品の呈味成分の変化
冷風乾燥した塩干品の呈味成分の変化を明らかにするため,マアジを約20℃(冷風乾燥区)または約50℃(熱風乾燥区)で20時間乾燥させ,FAAと核酸関連物質の経時変化を比較した。その結果,熱風乾燥区ではIMPの急激な減少に伴いHxが増加するとともに,苦味を呈するFAAの増加が著しかった。一方,冷風乾燥区ではIMPの減少が小さく,苦味を呈するHxとFAAはあまり増加しなかった。このような呈味成分の差異は乾燥時間の経過とともに顕著となった。一方,両乾燥区における乾燥2時間(水分約68%)の半乾品を焙焼すると,冷風乾燥区では,甘味を呈するアミノ酸が増加する傾向にあったが,熱風乾燥区では,Hx含量が増加し,リジンとヒスチジンが顕著に減少した。さらに,両区を官能評価すると,冷風乾燥区は,甘味が有意に強く,苦味が弱い傾向にあり,総合評価で有意に好ましい結果となった。これらの結果は,塩干品の冷風乾燥の優位性を呈味の面から示唆するものである。