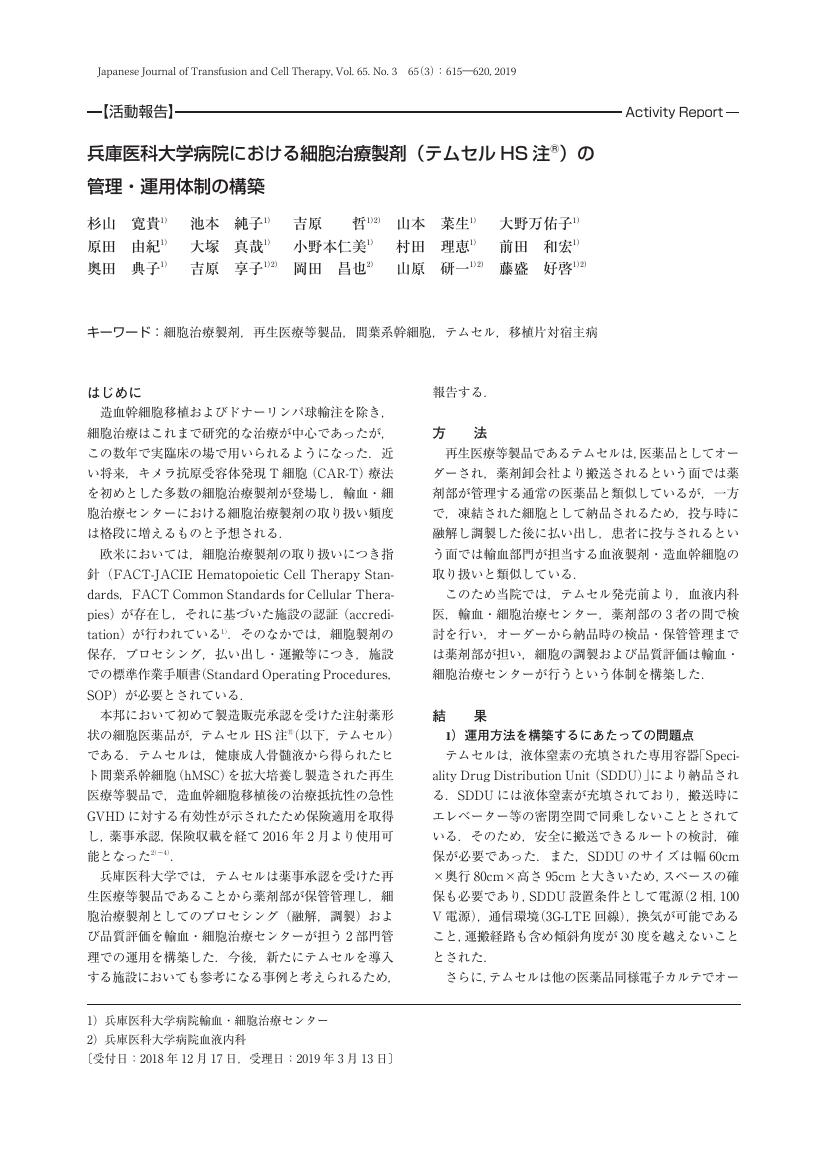2 0 0 0 OA 自己免疫性脳炎の基礎
- 著者
- 三須 建郎
- 出版者
- 日本神経感染症学会
- 雑誌
- NEUROINFECTION (ISSN:13482718)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.56, 2022 (Released:2022-05-12)
- 参考文献数
- 12
【要旨】抗アクアポリン4(aquaporin 4:AQP4)抗体が発見されて以後、細胞表面抗原に対する抗体を検出することに重点が置かれる大きなパラダイムシフトがあったといえる。そのようななかで、わが国でも非ヘルペス性の自己免疫性脳炎のなかから最初に発見されることになったのが NMDA 受容体抗体関連脳炎である。以後、辺縁系脳炎において LGI1 抗体や AMPA 抗体などつぎつぎと自己抗体が報告されるにいたっている。これらの自己抗体は髄腔内で持続的に産生されることが知られ、病理学的に異所性リンパ濾胞を形成する形質細胞から持続的に産生されていることが明らかになっているが、AQP4 抗体のような補体介在性の細胞傷害はまれであり、NMDA 受容体抗体は抗体介在性に内在化させることで病原性を発揮するほか、LGI1 抗体はシナプスにおける蛋白結合を阻害することで、てんかん発作を誘発する。
2 0 0 0 OA 琵琶湖流入河川,安曇川の河川水位と瀬切れ
- 著者
- 遊磨 正秀 小野田 幸生 太田 真人
- 出版者
- 環境技術学会
- 雑誌
- 環境技術 (ISSN:03889459)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.142-149, 2021-05-20 (Released:2021-05-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3 1
琵琶湖流入河川においては瀬切れが頻発している.その一つである安曇川の下流部に伏流時水位をも計測できる低水位対応型水位計を設置し,2005-2008年に記録した河川水位から瀬切れの発生状況を把握した.安曇川下流部においては5月から12月まで様々な時期に瀬切れが生じていた.瀬切れ時の河川水位と降水量,農業用水取水,琵琶湖水位との関係を検討した結果,農業用水の取水や琵琶湖の低水位が関与していることが示唆された.琵琶湖と流入河川を回遊する魚類等の保全のためにも,低水位環境をモニタリングができる水位計ならびに流量監視カメラの設置が必要であることに加え,農繁期・農閑期および治水期・非治水期の各季節における河川・琵琶湖における水管理の再検討が必要である.
2 0 0 0 世界少年少女文学全集
- 出版者
- 創元社
- 巻号頁・発行日
- vol.26(東洋編 2), 1954
中国の2大古典をやさしい少年向の抄訳と再話として収める。 (日本図書館協会)
- 著者
- 松本 武志
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Respica = レスピカ : みんなの呼吸器 : 呼吸療法の現場を支える専門誌 (ISSN:24344567)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.152-156, 2019-02
- 著者
- 佐藤 浩史
- 出版者
- 函館大学
- 雑誌
- 函館大学論究 (ISSN:02866137)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.1-37, 2022-03
本研究では、地域活性化イベントを持続可能なスポーツツーリズムイベントとするための戦略策定モデルに必要な要素の探索をする。プレイス・ブランディング論に述べられる sense of place の概念が地域のステークホルダーには、どのようにとらえられているのか長期に継続される昭和新山国際雪合戦大会のステークホルダーから聞き取り調査を行った。地域のステークホルダーは、スポーツツーリズムイベントが施行される地域に対して、野菜や温泉など産品である有形の資源と人柄、街、大会そのものというイメージからなる無形の資源が重要であることが共存しどちらかが優位ということではなかった。結果この事例からは、スポーツツーリズムを継続していくためには、有形の資源と無形の資源の両方が結び付いて戦略策定していくことを重視しておくことが必要であろう。
2 0 0 0 OA 3a-GH-4 トンネルと列車との空気力学の数値計算 II
- 著者
- 山本 彬也
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会春季分科会講演予稿集 1970.2 (ISSN:24331120)
- 巻号頁・発行日
- pp.13, 1970-04-02 (Released:2018-03-29)
2 0 0 0 鉄道総研報告 = RTRI report : 鉄道総合技術論文誌
- 著者
- 鉄道総合技術研究所 監修
- 出版者
- 鉄道総合技術研究所
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, 1995-01
2 0 0 0 OA 認知資源の個人差と急性ストレス
いくつも仕事がある場合,同時にはたくさんには対応できない。また,頭を使って疲れたら,そのぶんミスが増えたりうまく頭が回らない。心理学では,認知資源という共通のリソースを仮定し,この多寡で複数の課題遂行成績や疲労,個人差を説明してきた。非常に似通った注意の課題で認知資源が枯渇するという説明が成されていることに本研究では注目し,これらの課題間で共通の認知資源が使われているかを調べた。実験の結果,共通性は殆ど無いことがわかった。本研究の結果は,これまで,認知資源という漠然とした用語で解釈されてきた注意の配分モデルに対して見直しを迫るものであるといえる。
2 0 0 0 日本中等教育数学会雑誌
2 0 0 0 偉大なるジャロ : ライオン物語
2 0 0 0 OA 熊本地震における災害関連死認定の市町村による違い
- 著者
- 福元 健太郎 早坂 義弘 Kentaro Fukumoto Yoshihiro Hayasaka
- 出版者
- 学習院大学法学会
- 雑誌
- 学習院大学法学会雑誌 = Gakushuin review of law and politics (ISSN:13417444)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.19-41, 2019-11
熊本地震の特徴として,災害関連死に認定された人数の多さと,発災から認定されるまでの期間の長さ(認定される時点の遅さ)が挙げられる.本稿は,熊本地震における災害関連死認定の市町村による違いがあるかを明らかにするために,関連死が認定されるタイミングに着目し,生存分析の枠組みを適用した.その結果,熊本市は他の市町村と比べて統計的に有意に早く関連死を認定していることがわかった.また益城町は遅めであった.さらに証拠はやや劣るが,大津町は早め,宇城市は遅めといった傾向も見られた.分析上の細かな設定を多少変えてみても,以上の結論は大筋変わらず,頑健である.ここから,データ分析が難しい関連死認定の他の側面(例えば,人数の多寡,認定基準,審査委員の傾向など)についても,市町村による違いがあったのではないだろうか,ということが示唆される.
2 0 0 0 OA 小泉内閣の支持率とメディアの両義性
- 著者
- 福元 健太郎 水吉 麻美 Kentaro Fukumoto Asami Mizuyoshi
- 出版者
- 学習院大学法学会
- 雑誌
- 学習院大学法学会雑誌 = Gakushuin review of law and politics (ISSN:13417444)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.1-21, 2007-09
2 0 0 0 OA アリストテレス『形而上学』A (第一) 巻第一章~第三章 : 訳と注解
- 著者
- 坂下 浩司
- 出版者
- 南山大学
- 雑誌
- アカデミア. 人文・自然科学編 = Academia. Humanities and natural sciences (ISSN:21853282)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.119-151, 2022-01-31
2 0 0 0 OA 保育現場における前言語期の子どもの「指さし行動」
- 著者
- 宮津 寿美香
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.105-113, 2010 (Released:2010-12-29)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
This study aimed to observe infants' production of pointings during the preverbal vocal period at a nursery school. Participants were four 1-year old children (one boy and three girls). The characteristics on infant production of pointing were classified into seven categories ("a. attention getting", "b. place and direction", "c. naming", "d. demand", "e. question", "f. explanation", "g.imitation"), and of those which were inapplicable to any other categories were classified into the category of "h. others". The main results were as following. First, in the nursery school, the frequency of pointing increased as children developed. Second, by comparing the average frequency of infants' pointing manipulated "in infant-adult (nursery teacher) interaction" and "in peer interaction", the frequency of pointing "in peer interaction" was significantly more than that "in infant-adult interaction". Third, the ratio of infants' pointing, categorized into "f. explaination" was high, both "in infant-adult interaction (36 %)" and "in peer interaction (31 %). Although the ratio of infants' pointing "in infant-adult interaction" was high in "d.demand" (20 %) , and in "e. question" (14 %), the ratio of pointing "in peer interaction" was high in "h. others" (23 %), and in "g.imitation" (17 %). Moreover, the ways of pointing gestures were different among these categories. These findings suggest that children's intention to produce pointing, should be considered to be different, depending on whom they tried to interact (adults and peers). Finally, because there were some distinctions among infants' pointing categorized as "h. others", further categorization was done, and classified into three categories ("instructive pointing", "greeting/confirmation", and "pointing toward imaginative objects").
2 0 0 0 OA 第五回内国勧業博覧会御料局出品説明書
- 出版者
- 宮内省御料局
- 巻号頁・発行日
- 1903
2 0 0 0 OA 六朝文人伝 : 「晋書」潘岳伝
- 著者
- 坂元,悦夫
- 出版者
- 広島大学文学部中国中世文学研究会
- 雑誌
- 中国中世文学研究
- 巻号頁・発行日
- no.16, 1983-12-25
2 0 0 0 OA 高齢犯罪者の実態と特質
- 著者
- 髙山 佳奈子
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.380-394, 2014-04-30 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 スイングジャーナル
- 出版者
- スイングジャーナル社
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.11, 1957-11
2 0 0 0 OA 兵庫医科大学病院における細胞治療製剤(テムセルHS注Ⓡ)の管理・運用体制の構築
2 0 0 0 OA 原子力業界OBたちに学ぶ
- 著者
- 福田 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.9, pp.600, 2008 (Released:2019-06-17)