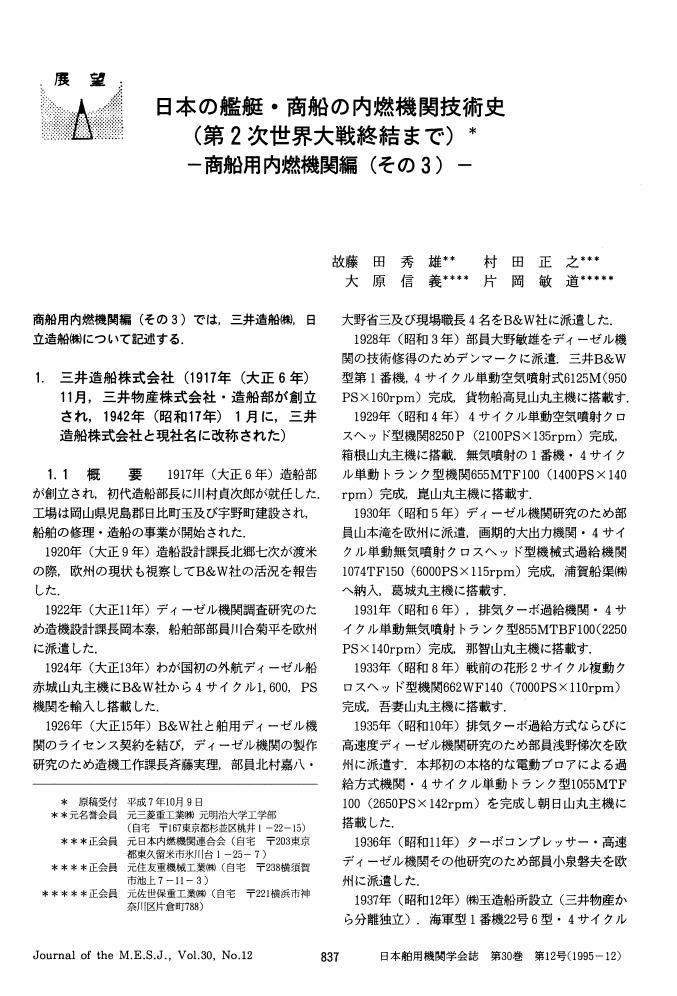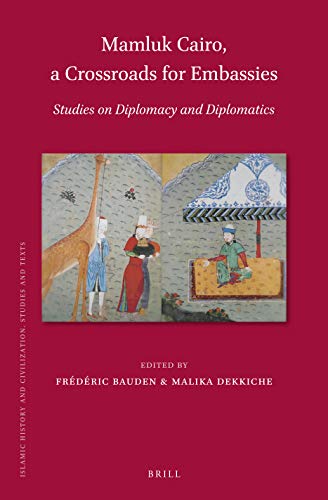2 0 0 0 OA 第6回定例研究会 参加報告
- 著者
- 平野 桃子
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.409-410, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 著者
- 月尾 嘉男
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.405-408, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
2 0 0 0 OA 「デジタルアーカイブ産業賞」の創設と第1回(2018年度)授賞式の開催
- 著者
- 編集事務局
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.403-404, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
2 0 0 0 OA 「アーカイブサミット2018-2019」概要報告
- 著者
- 渡邉 太郎
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.399-402, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 参考文献数
- 5
本稿では、2019年6月11日に千代田区立日比谷図書文化館において開催された「アーカイブサミット2018-2019」の概要を報告する。同サミットでは、これまでの成果と課題に関する基調講演、異なるテーマの3つの分科会、有識者・専門家によるラウンドテーブル等が行われ、活発な議論が交わされた。2015年にスタートしたアーカイブサミットは、我が国におけるアーカイブ及びデジタルアーカイブの現状や課題等について議論すると共に、民産学官の関係者を横につないでいく機能を果たしてきた。しかし、デジタルアーカイブ学会の設立等の環境変化に対応し、位置付けを再定義すべき時期に来ている。
2 0 0 0 OA 欧州の映画アーカイブ
- 著者
- 時実 象一
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.388-393, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 参考文献数
- 43
欧州は映画発祥の地でもあり、各国に独自の映画アーカイブが存在する。ここでは文献調査と面談により、英国、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、オーストリアの映画アーカイブの歴史と現状についてまとめた。
2 0 0 0 OA 「映画の復元と保存に関するワークショップ」について
- 著者
- 太田 米男
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.379-382, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 参考文献数
- 2
「映画の復元と保存に関するワークショップ」も2019年には14年目になる。この間に、「アナログ」から「デジタル」へ、映画製作や上映を取り巻く環境も大きく変わってきた。過去に、サイレントからトーキーへ、ナイトレートからアセテートへと、映画の歴史を見ても、規格が変った時に、過去のソフトは失われている。この点を危惧する思いで、ワークショップを提案した。120年以上の歴史を持ち、世界で唯一の共通規格である35mm映画フィルムは膨大な量の映像遺産を残した。それをどのように生かすのか。「ビネガー・シンドローム」、「デジタル・ジレンマ」の問題を抱え、山積する難問は多い。この「ワークショップ」を多くの人たちの情報交換の場と考えている。
2 0 0 0 OA 国立映画アーカイブ:その現状と展望
- 著者
- 岡島 尚志
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.370-374, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 参考文献数
- 5
2018年4月にわが国6番目の国立美術館組織として誕生した国立映画アーカイブについて、組織の構造と名称の由来を述べ、映画フィルムの収集に関する“網羅的”な原則とそれを実現するための多年にわたる努力、対象となる自国映画遺産の巨大な量などを論じる。また、映画保存の観点からフィルムアーカイブに相応しい上映番組の在り方や、コレクションの利活用に関して期待されるデジタル・アーカイビングの方向性について分析し、世界のアーカイブ・コミュニティで、復元の倫理を逸脱するものとして問題視されている“スーパーエンハンスメント”についても短く言及する。
2 0 0 0 OA 『デジタルアーカイブ・ベーシックス』第2巻「災害記録を未来に活かす」発刊
- 著者
- デジタルアーカイブ学会事務局
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.367, 2019-12-16 (Released:2019-12-16)
- 著者
- 池谷 和信
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 科学 (ISSN:00227625)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.10, pp.958-962, 2017-10
- 著者
- 三宅 裕
- 出版者
- 雄山閣
- 雑誌
- 季刊考古学 (ISSN:02885956)
- 巻号頁・発行日
- no.141, pp.33-36,6, 2017-11
- 著者
- France Marie de 横山 安由美
- 出版者
- フェリス女学院大学国際交流学部紀要委員会
- 雑誌
- 国際交流研究 : 国際交流学部紀要 (ISSN:13447211)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.25-57, 2016-03
2 0 0 0 OA イギリスの多民族化とロンドンのマルチェスニックスクール
- 著者
- 小内 透
- 出版者
- 北海道大学大学院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13457543)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.91-117, 2004-12
2 0 0 0 OA 転写後・翻訳制御の解明に向けたプロテオミクス基盤技術の開発
- 著者
- 今見 考志
- 出版者
- 日本プロテオーム学会
- 雑誌
- 日本プロテオーム学会誌 (ISSN:24322776)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.61-69, 2019 (Released:2019-12-11)
- 参考文献数
- 32
リボソームはmRNAのコドンを読み取りタンパク質へと翻訳する分子マシーンである.近年,リボソームはタンパク質合成装置としての機能のみならず,リボソームへの結合因子や化学修飾を介して,翻訳制御にも積極的に関与することが報告されている.我々はこのような特殊なリボソームをプロテオームワイドに同定するために,質量分析法を用い,翻訳制御に関与しうる結合タンパク質とリン酸化部位を系統的に同定することに成功した.本稿では,遺伝子からタンパク質に翻訳されるまでの複数の制御レイヤーの全体像を俯瞰しつつ,我々が最近報告したリボソームのリン酸化を介した翻訳制御について紹介する.
2 0 0 0 OA 包摂/排除をめぐる現代デモクラシー理論
- 著者
- 山田 竜作
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.1_143-1_162, 2007 (Released:2012-02-22)
So-called “radical democracy” has been concerned with problems of inclusion and exclusion, discussing difference, identity or citizenship. Now radical democracy seems to be divided into two models, agonistic and deliberative. Chantal Mouffe strongly criticizes deliberative democracy through insisting conflict as a fundamental element of “the political”. On the other hand, Iris Young, whose democratic theory is not simply labelled as agonistic or deliberative, conceptualized inclusive democratic model which can be bound on Mouffe’s. Both of them reject the essentialist idea of identity and acknowledge the fact that the constitution of “we” needs the determination of “they”. Mouffe’s idea of “adversary” and Young’s recognition of communication as “struggle” show that democratic dialogue can be a non-violent conflict in a public sphere. Such a conflict should be a type of inclusion because any identity cannot exist without others. The acknowledgement of changeableness of self-identity or self-interest seems to require what Young called “reasonableness” as “hearing the other”, which is not based on particular culture (e. g., white male) nor contain any notion of the common good which might oppress diversity. This can meet Mouffe’s emphasis upon a “practice of civility” which is based on Michael Oakeshott’s notion of societas.
2 0 0 0 OA 日本の艦艇・商船の内燃機関技術史 (第2次世界大戦終結まで)
- 著者
- 藤田 秀雄 村田 正之 大原 信義 片岡 敏道
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.12, pp.837-853, 1995-12-01 (Released:2010-05-31)
2 0 0 0 OA 日本の艦艇・商船の内燃機関技術史 (第2次世界大戦終結まで)
- 著者
- 藤田 秀雄 村田 正之 大原 信義 片岡 敏道
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.8, pp.603-619, 1995-08-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 52
- 著者
- edited by Frédéric Bauden Malika Dekkiche
- 出版者
- Brill
- 巻号頁・発行日
- 2019
2 0 0 0 IR 曲亭馬琴『漢楚賽擬選軍談』翻刻(二) -初編その2-
- 著者
- 神田 正行
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.543, pp.(1)-(37), 2019-09-30
2 0 0 0 IR 曲亭馬琴『漢楚賽擬選軍談』翻刻(一) -初編その1-
- 著者
- 神田 正行
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.539, pp.(81)-(117), 2019-03-31