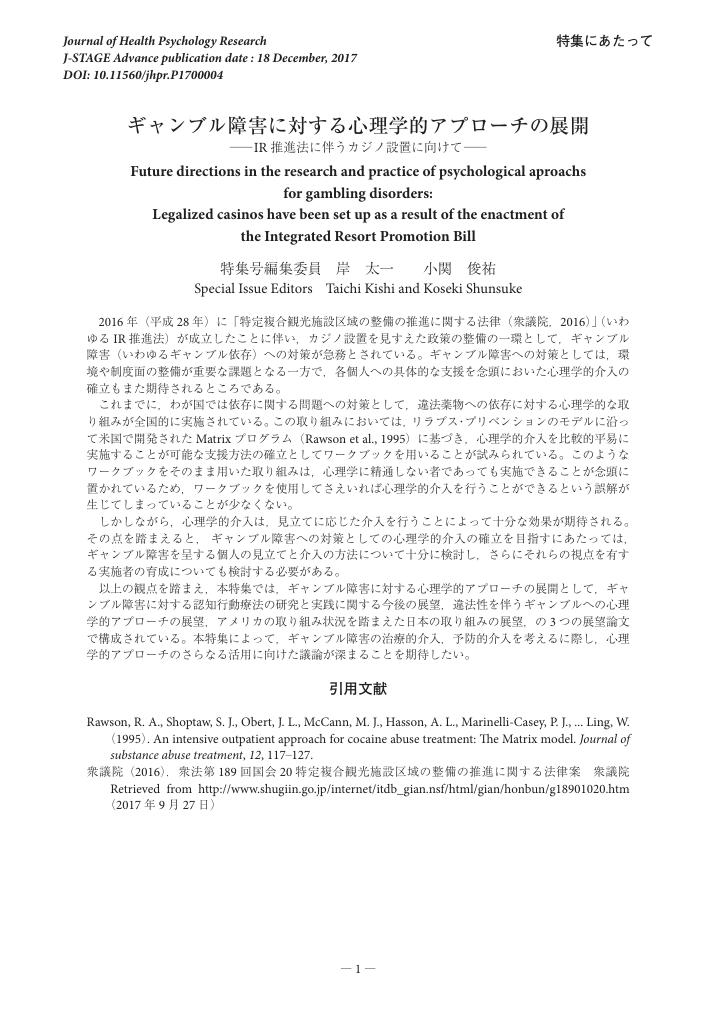2 0 0 0 日本中世における桶・樽の展開--結物の出現と拡散を中心に
- 著者
- 鈴木 康之
- 出版者
- 考古学研究会
- 雑誌
- 考古学研究 (ISSN:03869148)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.44-64, 2002-03
2 0 0 0 OA 署名代理と二段の推定
- 著者
- 川添 利賢 カワゾエ トシカタ Toshikata Kawazoe
- 雑誌
- 立教法務研究
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.127-144, 2008
2 0 0 0 私の経験(<シリーズ>"ポスドク"問題)
- 著者
- 杉浦 方紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.193-194, 2007
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.292-293, 2004-10-28 (Released:2017-04-15)
2 0 0 0 OA インターネット時代における統制語彙の意義と役割(<特集>統制語彙・シソーラスの現在)
- 著者
- 岸田 和明
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.62-67, 2007-02-01 (Released:2017-05-09)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
本稿では,シソーラスや件名標目表をはじめとする統制語彙に関して,その基本的な機能や限界を整理した上で,インターネットが高度に発達し,サーチエンジンが広く普及した現在における統制語彙の意義と役割について議論する。具体的には,再現率向上および精度向上のための装置としての統制語彙の機能を確認した上で,検索実験や種々の実証研究等で明らかになっている,その限界について述べる。次に,その点を踏まえ,専門的データベースの検索におけるその意義,ウェブなどの全文検索におけるその意義,複数根拠を提供するための表現としての意義について議論する。さらに,今後の可能性として,シソーラスの自動構築や索引語の自動付与,オントロジやフォークソノミーとの関連についても触れる。
2 0 0 0 OA Coupled Drive of the Multi-DOF Robot
- 著者
- Shigeo HIROSE Mikio SATO
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Robotics Society of Japan (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.128-135, 1989-04-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 11
ロボットの機能性向上のためには多自由度化することが不可欠である.しかし, 在来のアクチュエータの出力重量比は著しく制限されている.単純な多自由度化はロボット重量の過大な増加を招く.そのため機能性を十分発揮し得る軽量で現実的なロボット, 特にこれから必要とされてゆく自律移動ロボットを実現してゆくためには, 従来とはまったく異なる新しい設計手法が必要とされる.本研究は, 多自由度化と同時に軽量化も計る新しいロボット設計手法を提案する.提案する設計手法は, ロボットに装備する複数の自由度を使用頻度の高い作動状態において出来る限り相互に干渉させ, 共同駆動させようとするものであり「干渉駆動」と呼ぶ.干渉駆動によれば, 多自由度的な機能を発揮するために複数のアクチュエータが装備されていたとしても, 各アクチュエータが装備すべき出力容量は低く抑えられる.よってロボット本体の重量も軽減できる.従来, 制御性の観点からはロボットの駆動系は出来る限り非干渉化すべきであるとされてきた.提案する干渉駆動は, 逆に出来る限り干渉化させるべきであることをハードの立場から主張している.干渉駆動の評価関数として, 装備すべき全出力パワーに対する作業のためのパワーの比である「駆動率ηc」を導入する.干渉駆動の考え方に基づくロボットの機構設計および制御法を検討するため, 4足で壁面を垂直上方に吸着歩行するロボットを想定しシミュレーション実験を行う.実験は準静的な運動を対象とし, 歩行ロボットの機構や歩行姿勢が与えられたとき, その駆動率を最大化する歩行を線形画法によって誘導している.この実験により, 干渉駆動の考え方の導入がロボットの軽量/高速化設計に有効であることを明らかにしている.
2 0 0 0 語の用法より観たる変体漢文中の〈訓点語〉について
- 著者
- 田中 草大
- 出版者
- 明治書院
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.52-65, 2018-03
2 0 0 0 IR 現代社会の「個人化」と親密性の変容 : 個の代替不可能性と共同体の行方
- 著者
- 小田 亮
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 日本常民文化紀要 (ISSN:02869071)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.188-156, 2007-03
2 0 0 0 OA 放射性セシウムの長期的挙動:オクロ天然原子炉の例
- 著者
- 日高 洋
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2011年度日本地球化学会第58回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.74, 2011 (Released:2011-09-01)
中央アフリカ・ガボン共和国東部オクロ鉱床は約20億年前に部分的に核分裂連鎖反応を起こした形跡のある「天然原子炉」の化石として知られている。核分裂によって多量に生成された放射性核種は現在ではすべて安定核種へと壊変し尽くされているが、その長期的挙動は安定同位体組成の変動から推定することができる。本研究ではオクロ原子炉関連試料のBa安定同位体組成変動から放射性セシウムの長期的挙動を推測した。
- 著者
- 柴崎 礼士郎
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.47-60, 2005-10-01
本稿では、日本語の補文標識「と」が証拠表示化する談話的基盤を文法化の観点から考察する。本稿の中心点は以下の3点である。a.文法化には段階性があり、広範なデータベースに基づく具体的頻度によりそれを裏付ける点。b.補文標識「と」が補文動詞を省略して証拠表示化するのは特定の談話構造に起因している点。c.その文法化を特徴付ける談話構造は複数存在し、それぞれの構造的特徴に動機付けられ、頻度として中心的なものから頻度として周辺的なものへと層状の広がりを見せている点。言語変化の層状性は一定の談話構造に起因するものであり、繰り返し生起する談話的基盤に裏付けられたものである。現在進行中の文法化を考察するには具体的頻度の提示が必須であり、具体的頻度の提示は文法化を動機付ける談話的基盤の尺度となる。
2 0 0 0 IR 佐賀方言における主格助詞「ノ」と「ガ」について
- 著者
- 佐野 舞 サノ マイ SANO Mai
- 出版者
- 東京外国語大学地域文化研究科・外国語学部記述言語学研究室
- 雑誌
- 思言 : 東京外国語大学記述言語学論集 (ISSN:18844391)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.93-100, 2008-11-30
2 0 0 0 IR 歴史物語の方法論 : 連結作用概念と物語文
- 著者
- 伊賀 光屋
- 出版者
- 新潟大学教育学部
- 雑誌
- 新潟大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:18833837)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.157-170, 2013
- 著者
- 耳塚 寛明 MIMIZUKA Hiroaki みみづか ひろあき
- 出版者
- ジアース教育新社
- 雑誌
- 文部科学教育通信
- 巻号頁・発行日
- vol.278, pp.10-11, 2011-10-24
- 著者
- 一澤 圭
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.31-97, 2012-12-28 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 115
- 被引用文献数
- 1
アヤトビムシ科9属46種.ニシキトビムシ科3属3種,オウギトビムシ科3属7種,アリノストビムシ科2属2種,キヌトビムシ科2属5種について,科ごとの検索図および形質識別表を示し,各属・種の特徴を解説した.識別の指標となるおもな形質は,カラーパターン,ウロコの有無や分布,小眼数,口器・爪・跳躍器の形状,剛毛配列である.
- 著者
- 田中 健一 岡本 豊 竹岡 明美 井野 隆光 河野 茂勝 大幡 勝也 川合 満 前川 暢夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.199-206, 1984-04-30 (Released:2017-02-10)
- 被引用文献数
- 3
喘息惹起を目的として作られた同じ動物モデルに鼻アレルギーが惹起できる可能性を示した.酢酸エチルに溶解した10%TDI溶液を1日1回連続5日間モルモット鼻前庭に塗布し, 3週間の無処置期間をおいて5%TDI溶液で同様の方法によりチャレンジした.この誘発法をその後週2回約3カ月くりかえした.誘発期間中呼吸困難の程度にかかわらず, くしゃみ, 鼻汁が動物に観察された.鼻汁中には多数の好酸球が認められた.組織学的検索においては分泌機能の亢進と共に, 好酸球浸潤, 肥満細胞の脱顆粒を示唆する像が鼻粘膜に認められた.TDI結合モルモット血清アルブミンを用いて鼻粘膜よりのヒスタミン遊離を検討した場合, 抗原刺激による有意のヒスタミン遊離増加が感作動物に観察された.実験結果は喘息と鼻アレルギーの発症機序に共通性のあることを示唆すると共に, TDIによる喘息モデルがアレルギーの基礎的臨床的研究にも適していることを示した.
2 0 0 0 OA 2.Basedow病クリーゼ
- 著者
- 赤水 尚史
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.4, pp.763-768, 2010 (Released:2013-04-10)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
甲状腺中毒クリーゼは「生命が危険となるような激しい症状を呈する甲状腺中毒症」であり,多臓器における非代償性状態を特徴とする.甲状腺基礎疾患としては,Basedow病が最も多い.かつては甲状腺亜全摘術後発症する外科的甲状腺クリーゼが多かったが,現在は内科的甲状腺クリーゼがほとんどである.臨床症状に基づいて診断されるが,明確な診断基準は国際的にも確立されておらず,疫学データも乏しい.日本甲状腺学会と日本内分泌学会は共同して,『甲状腺クリーゼの診断基準の作成と全国疫学調査』を臨床重点課題と定め,新診断基準に基づいた全国疫学調査を実施した.その調査結果に基づいて,発症実態の解明,診断基準の改訂,予後規定因子の解析,治療指針の作成が予定されている.
2 0 0 0 OA ギャンブル障害に対する心理学的アプローチの展開――IR推進法に伴うカジノ設置に向けて――
- 著者
- 岸 太一 小関 俊祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- Journal of Health Psychology Research (ISSN:21898790)
- 巻号頁・発行日
- pp.P1700004, (Released:2017-12-18)
- 参考文献数
- 2