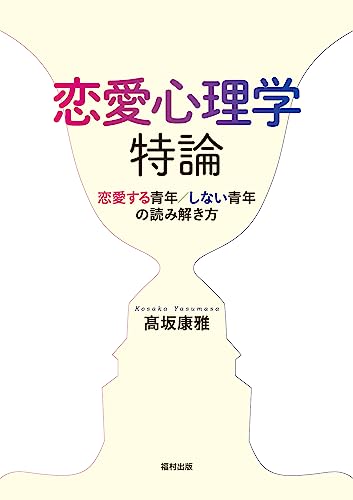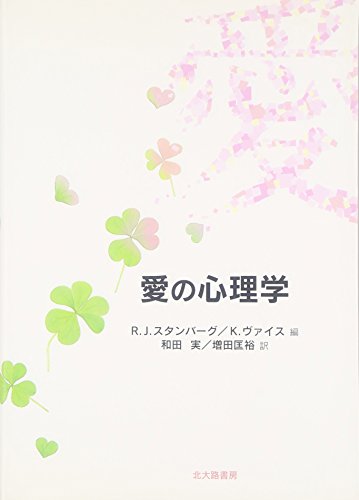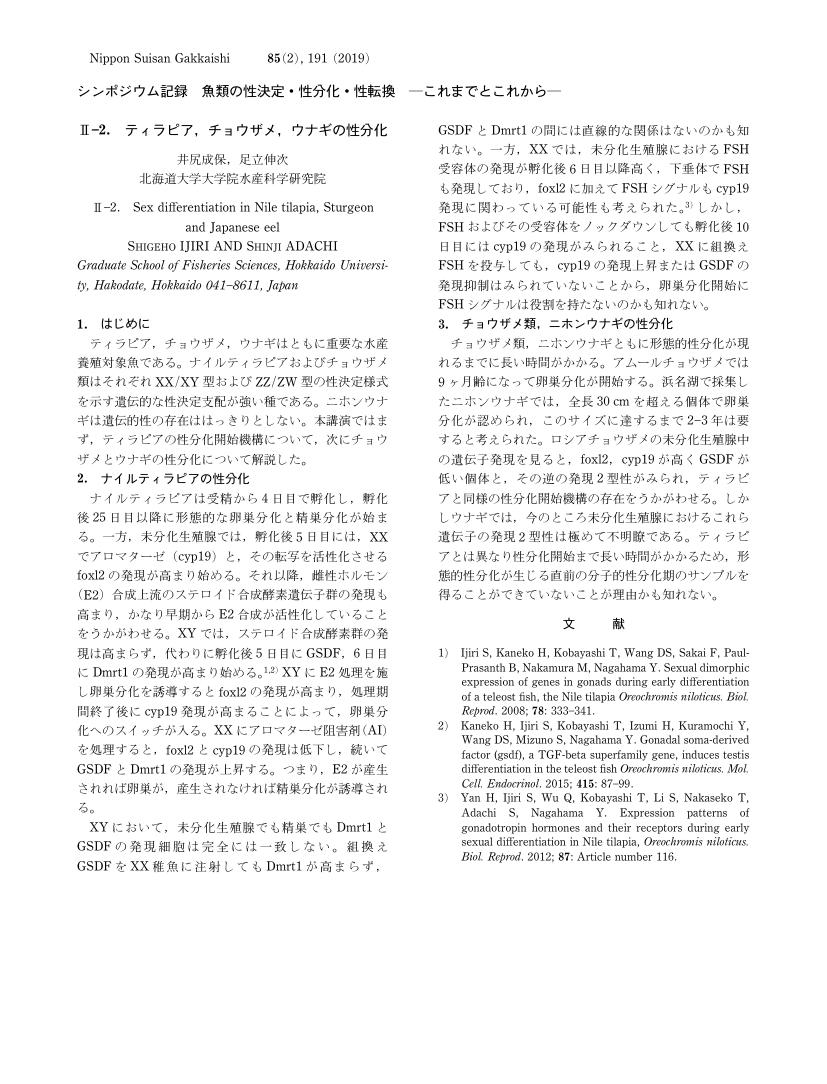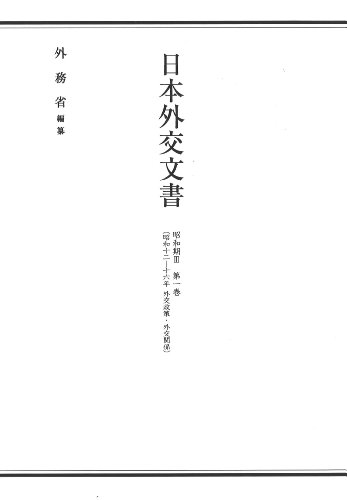2 0 0 0 IR 誰が医者になるのか--医学部入試選抜システムと文化的再生産についての社会学的考察
- 著者
- 中川 さおり NAKAGAWA Saori なかがわ さおり
- 出版者
- お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
- 雑誌
- 人間文化創成科学論叢 (ISSN:13448013)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.207-216, 2007
2 0 0 0 恋愛心理学特論 : 恋愛する青年/しない青年の読み解き方
2 0 0 0 愛の心理学
- 著者
- R.J.スタンバーグ K.ヴァイス編 和田実 増田匡裕訳
- 出版者
- 北大路書房
- 巻号頁・発行日
- 2009
2 0 0 0 親行本『下官集』考 (日本語学の諸問題)
- 著者
- 遠藤 和夫
- 出版者
- 國學院大學綜合企画部
- 雑誌
- 國學院雜誌 (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.11, pp.247-256, 2007-11
2 0 0 0 IR 英語学習にまつわるOPTIMISMを斬る : 第2言語習得研究の観点より
2 0 0 0 IR ハリー・ポッターのイギリス(3)『ハリー・ポッター』と現代イギリス社会のジェンダー観
- 著者
- 坂田 薫子
- 出版者
- 日本女子大学文学部
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 文学部 (ISSN:02883031)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.33-44, 2015
2 0 0 0 IR 合成糊料C.M.C.の粘度について
- 著者
- 稲垣 和子
- 出版者
- 奈良学芸大学
- 雑誌
- 奈良学芸大学紀要 (ISSN:0369321X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.177-180, 1955-12-25
2 0 0 0 楽神一考--台湾における田都元帥と西秦王爺の信仰について
- 著者
- 鄭 正浩
- 出版者
- 日本道教学会
- 雑誌
- 東方宗教 (ISSN:04957180)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.p24-48, 1983-05
2 0 0 0 OA 生成モデルを用いた結晶構造探索
- 著者
- 福島 真太朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会
- 雑誌
- ケモインフォマティクス討論会予稿集 第42回ケモインフォマティクス討論会 東京
- 巻号頁・発行日
- pp.2B03, 2019 (Released:2019-10-22)
- 参考文献数
- 7
近年,機械学習を用いて物性を予測したり,結晶構造を探索したりする研究が行われている.本研究では,生成モデルを用いた結晶構造生成について考える.この問題に対して,CrystalGANと呼ばれる手法が提案されている.この手法は”A-H-B” (A, B:金属,H:水素)という結晶構造を持つ化合物を探索するために,異なるドメイン間を横断した生成モデルであるDiscoGANを使用する. CrystalGANは,結晶構造生成の簡便な手法である.一方で,POSCARファイルに記録された格子ベクトルと,水素や金属の座標を結合して特徴量を構築するため,結晶の幾何学的構造の反映が十分ではないという問題点がある.本研究ではこの問題点を解決するために,結晶をグラフ構造で表現して幾何学的構造を織り込み生成モデルを学習する方法を提案する.
2 0 0 0 OA Ⅱ-2. ティラピア,チョウザメ,ウナギの性分化
- 著者
- 井尻 成保 足立 伸次
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.191, 2019-03-15 (Released:2019-04-02)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 佐々木 直亮
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.954-963, 1990
- 被引用文献数
- 1
Prospective epidemiological studies of blood pressure in a high-salt population in northeastern Japan were investigated along with dietary habits such as miso soup, rice, apple, fish, milk and sake consumption as well as smoking habits.<br>Blood pressures of the populations in 3 villages were determined once or twice a year by mass surveys from 1954, 1957 or 1958 through 1975. The means and transitions of the personal blood pressure were calculated by regression analysis of the data obtained during each entire period.<br>The number of persons was 1127 males and 1369 females and the response rate was 98.7 percent. The average number of times of determination of blood pressure for a person was 12.9.<br>Stepwise multiple regression analyses were run with the means and transitions of systolic and diastolic blood pressure as the dependent variables and the life styles of the population in 1958 as an independent variable based on data of persons whose blood pressures were determined 5 or more times during the entire period. According to the backward stepwise method this study confirmed the positive relationship of age and sake drinking and the negative relationship of apple eating habits to blood pressure.
2 0 0 0 OA 日本産ミジントビムシ亜目およびマルトビムシ亜目(六脚亜門:内顎綱:トビムシ目)の分類
- 著者
- 伊藤 良作 長谷川 真紀子 一澤 圭 古野 勝久 須摩 靖彦 田中 真悟 長谷川 元洋 新島 溪子
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.99-156, 2012-12-28 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 86
日本産ミジントビムシ亜目1科2属2種およびマルトビムシ亜目6科(2亜科を含む)19属63種1亜種について,同定に必要な形質について説明するとともに,検索図と形質識別表を示し,種類別の特徴を解説した.識別のための主な形質は体の色と模様,体形,特殊な体毛,小眼の数,触角の長さと各節の比率,触角第3,4節の分節数,雄の触角把握器,触角後毛の有無,雄の顔面毛,脛〓節の先の広がった粘毛の方向と,各肢の粘毛の数,脛〓節器官の有無とその形態,爪(外被,偽外被,側歯,内歯の有無)や保体(歯や毛の数)の形態,跳躍器茎節の毛の形質,端節の形態,雌の肛門節付属器,胴感毛の数と配置などである.
2 0 0 0 OA 音声外科に必要な喉頭の臨床組織解剖
- 著者
- 佐藤 公則
- 出版者
- 日本喉頭科学会
- 雑誌
- 喉頭 (ISSN:09156127)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.57-65, 2018-12-01 (Released:2019-06-17)
- 参考文献数
- 29
1. Phonosurgery is performed on the human larynx to treat phonatory dysfunction and improve the quality of voice. 2 . There are two major categories of phonosurgery. One surgical option is open-neck laryngeal surgery, which is performed via an extralaryngeal approach. The other is endolaryngeal microsurgery and endoscopic surgery, which are performed via an intralaryngeal approach. 3. When performing phonosurgery via an extralaryngeal approach, it is very important to be able to visualize the internal laryngeal structures by looking at the laryngeal cartilage. Furthermore, when performing phonosurgery via an intralaryngeal approach, it is important to be able to visualize the internal laryngeal structures, including histoanatomy, by observing the mucosa of the lumen. An understanding of the histologic structures of the vocal fold is also essential when performing phonosurgery. 4. Knowledge of the three-dimensional structure, histology and histopathology of the larynx is indispensable when performing phonosurgery.
2 0 0 0 手の身体所有感覚とラバーハンド錯覚
- 著者
- 金谷 翔子 横澤 一彦
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.69-74, 2015
自分の身体やその一部が自分のものであるという感覚のことを,身体所有感覚と呼ぶ.この感覚がどのようにして生じるのかを調べることは非常に困難と考えられていたが,近年,ラバーハンド錯覚と呼ばれる現象の発見により,手の所有感覚の生起機序について多くの知見が得られた.この錯覚は,視覚的に隠された自分の手と,目の前に置かれたゴム製の手が同時に繰り返し触られることにより,次第にゴム製の手が自分の手であるかのような感覚が生じるというものであり,視覚情報と触覚情報の一貫性によって手の所有感覚が変容することを示唆している.本稿では,このようなラバーハンド錯覚に関する研究の最近の進展を紹介する.一つは手の所有感覚の生起条件について,もう一つは錯覚による身体所有感覚の変容が手の感覚情報処理に及ぼす影響について,検討したものである.最後に,ラバーハンド錯覚を通じて,手の身体所有感覚がある種の統合的認知に基づいて形成されることの意味について議論を行う.
- 著者
- 高田 三枝子
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.17-30, 2007-04
本研究では日本語の語頭の有声破裂音/b,d,g/のVOT(voice onset time)について鹿児島県出身在住話者の音声を分析し,語頭有声破裂音の半有声化(VOTがプラスの値をとる現象)と,語中有声破裂音の鼻音化および語中無声破裂音の有声化との共起関係を考察した。その結果,語頭有声破裂音の半有声音化は語中有声化・鼻音化と直接的な共起関係にはないことを指摘した。また鹿児島県のVOT値比率の結果を東北,北関東,新潟北東部,関東,四国の結果と比較することにより,当該現象に関する鹿児島県の地域的タイプとしては関東や四国に代表される完全有声音統一タイプに近いが,一方高年層にやや半有声音化の割合が高く見られ,この点で中間的タイプに含める可能性と今後の更なる分析の必要性を指摘した。
2 0 0 0 OA 水温落差は副交感神経活動を促通する
- 著者
- 西山 保弘 工藤 義弘 矢守 とも子 中園 貴志
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A1O2003, 2009 (Released:2009-04-25)
【目的】 本研究では温浴と冷浴との温度の落差が自律神経活動や体温に与える影響を検討したので報告する.【方法】 文書同意を得た健常男性5名(平均年齢23.8±4.91歳)に温浴41°Cと冷浴15°Cならびにその両方を交互に行う交代浴の3つの部分浴を実施した.交代浴の方法は水関らの温浴4分,冷浴1分を4回繰り返し最後は温浴4分で終わる方法に準じた.温浴のみは計20分、冷浴のみは計10分浸漬した.安静馴化時から部分浴終了後120分間の自律神経機能、舌下温度、血圧、心拍数、動脈血酸素飽和度、手足の表面皮膚温を検出した.測定間隔は安静馴化後、施行直後、以下15分毎に120分までの計7回測定した.表面皮膚温度は、日本サーモロジー学会の測定基準に準じサーモグラフィTH3100(NEC三栄株式会社製)を使用した.自律神経機能検査は、心電計機能を有するActivetracer (GMS社製 AC301)を用いて被検者の心拍変動よりスペクトル解析(MemCalc法)を行いLF成分、HF成分を5分毎に平均値で計測した.統計処理は分散分析(one way ANOVA testと多重比較法)を用いた.【結果】 副交感神経活動指標であるHF成分は、交代浴終了後60分以降より有意差をみとめた(P<0.05).温浴と冷浴は終了後60分で変化が一定化し有意差は認めなかった.交感神経活動指標とされる各部分浴のLF/HF比は、温浴と冷浴は変化が少なく交代浴は終了後60分から低下をみたが有意差は認めなかった.舌下温度は、交代浴と温浴(P<0.01)、交代浴と冷浴(P<0.01)、温浴と冷浴(N.S.)と交代浴に体温上昇を有意に認めた.表面皮膚温にこの同様の傾向をみた.最高血圧は、交代浴と温浴(P<0.01)、交代浴と冷浴(P<0.01)、温浴と冷浴(P<0.01)で相互に有意差を認め交代浴が高値を示した.【考察】 交代浴と温浴および交代浴と冷浴の相異はイオンチャンネル(温度受容体)の相異である.温浴は43°C以下のTRPA4、冷浴は18°C以下のTRPA1と8°Cから28°CのTRPM8、交代浴はこのすべてに活動電位が起こる.もう一つは温度幅である.温水41°Cと冷水15°Cではその差は26°C、体温を36°Cとすれば温水温度とは5°C、冷水温度とは21°Cの温度差がある.この温度幅が交代浴の効果発現に寄与する.単温の温浴や冷浴より感覚神経の刺激性に優れる理由は,温浴の41°Cと冷浴の15°Cへの21°Cの急激な非侵害性の温度差が自律神経を刺激しHF成分変化を引き起こす.また交代浴の体温上昇からは、温度差は視床下部の内因性発熱物質(IL1)を有意に発現させたことなる.【まとめ】 温度落差が自律神経活動に及ぼす影響は、単浴に比べ体温を上昇させること、副交感神経活動を一旦低下を惹起し、その後促通するという生理的作用に優れることがわかった.
2 0 0 0 OA 「自決権」を通じたロシアの国家戦略:その法的基盤と言説
ソ連解体後のロシアは、周辺の旧ソ連諸国に集住するロシア語系住民の庇護および保護を「同胞支援」の名のもとで、国策の次元にまで高めてきた。とりわけソ連解体後、ウクライナ領であったクリミア州はロシア語系住民が多く居住し、1954年以前は当地がロシア領であったという事実を追い風に、当地の住民がロシアとの再統合を望んでいるという「自決権」の言説をもとに2014年にロシアへの編入に乗り出した。西側諸国からは「国際法違反」が指摘されるクリミア併合について、ロシア国内の言説は正反対で、むしろ国際法と民主的手続きに乗っ取ったものという認識のギャップが深刻であることに注意を向ける必要がある。
- 著者
- Hirokazu KAWAGISHI
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.1, pp.29-38, 2019-01-11 (Released:2019-01-11)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3 34
2-Azahypoxanthine (AHX, 1) and imidazole-4-carboxamide (ICA, 2) were isolated from a fairy-ring-forming fungus Lepista sordida. AHX was converted into a metabolite 2-aza-8-oxo-hypoxanthine (AOH, 3) in plants. It was found out that these three compounds, named as fairy chemicals (FCs), endogenously exist in plants and are biosynthesized via a new purine metabolic pathway. FCs provided tolerance to the plants against various stresses and regulated the growth of all the plants. In addition, FCs increased the yield of rice, wheat, and other crops in the greenhouse and/or field experiments.
2 0 0 0 日本外交文書
- 著者
- 外務省 [編]
- 出版者
- 巌南堂書店 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1992