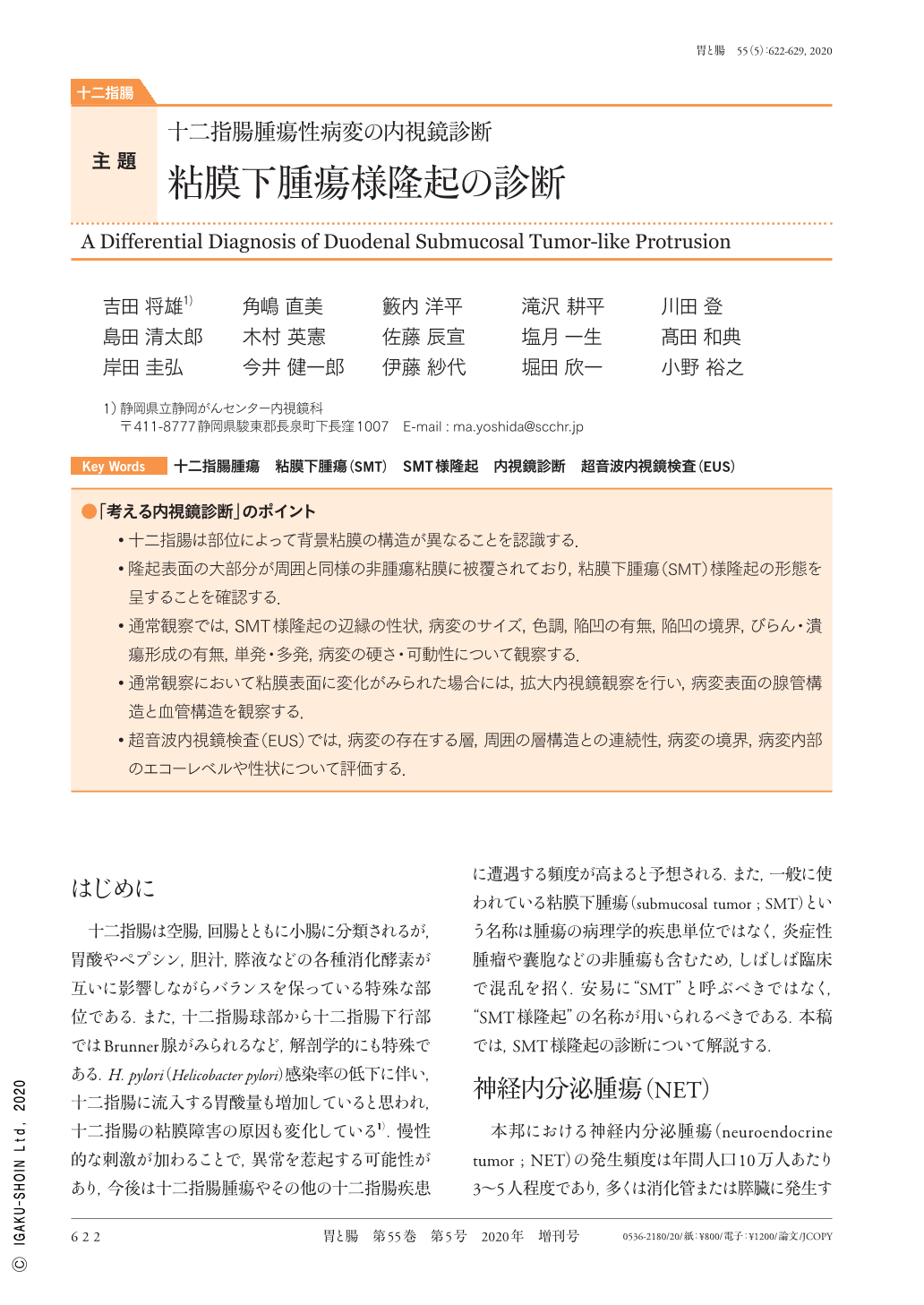61 0 0 0 OA 水酸化カルシウム系歯科根管充填材料によって生じた上顎血管塞栓症の1例
- 著者
- 矢島 優己 藤盛 真樹 嶋崎 康相 佐藤 栄晃 吉田 将亜 竹川 政範
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.11, pp.565-571, 2020-11-20 (Released:2021-01-20)
- 参考文献数
- 15
Calcium hydroxide formulation is frequently used in the treatment of root canals. We report a case where this formulation caused maxillary vascular embolism. A patient received an injection of calcium hydroxide formulation in to the right maxillary lateral incisor in a dental clinic. Immediately after, he presented with swelling of the surrounding gingiva, right cheek swelling, pain, and malaise. Necrosis of the right palate mucosa was observed. A CT image showed calcium hydroxide formulation confirmed to running from the greater palatal artery to the maxillary artery. We diagnosed maxillary vascular embolism caused by calcium hydroxide. On day 32, necrotic tissue of the palate mucosa was removed as much as possible under local anesthesia. On Day 233, the right upper 2 teeth were extracted and a radicular cyst was removed. On day 335, the redness on the right cheek skin almost disappeared, and the opening increased to 42 mm. The right oral and extraoral hypoesthesia remained, but was improving, and the right palate mucosa was completely epithelialized.
24 0 0 0 OA 魚類における恐怖・不安行動とその定量的観察
- 著者
- 吉田 将之
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.317-325, 2011 (Released:2012-01-11)
- 参考文献数
- 60
恐怖や不安は,動物の生命存続のためになくてはならない情動であり,様々な情動のうちでも比較的研究が進んでいる。魚類における恐怖や不安の神経機構を調べる上で,それらの情動を再現し,定量的に計測するための有効な方法が不可欠である。最近,従来の動物心理学的な手法に,エソロジカルな考え方も取り入れた魚類の不安の定量化法が導入されつつある。代表的な例のひとつが「新奇環境テスト」であり,これは不安を惹起するような新しい環境(水槽)に魚が遭遇したとき,どのように対処するかを定量的に観察する方法である。もう一つが明暗(白黒背景)選好性テストであり,背景が暗いほうが安心するという魚の習性を利用した不安の定量法である。一方,恐怖については,古典的恐怖条件付けや回避条件付けなどの手法で定量化できるほか,警報物質や捕食者に対する生得的な恐怖反応を利用する方法も開発されている。これらの恐怖・不安定量化法を利用して,情動のメカニズムに関する行動神経科学的,生物医学的研究が進められている。 魚類は多様な環境に適応放散しているが,そのごく一部が研究対象となっているにすぎない。今後,興味深い不安・恐怖行動を示す魚種が発見され,情動メカニズムの進化の解明に寄与することを期待する。
11 0 0 0 フナの遺伝子および行動の解析によるキンギョのルーツ解明
オランダ国ライデン自然史博物館に保管されているシーボルトが採集した日本産フナのタイプ標本を現地で精査した結果、C. cuvieriはゲンゴロウブナに,C. langsdorfiiはギンブナに,C. grandculisはニゴロブナによく一致したが、キンブナに対応するタイプ標本はなかった。一方、C. buergeriのタイプシリーズにはオオキンブナとナガブナが混入している可能性が示唆された。日本各地および韓国群山市で採集したフナ59個体と7品種のキンギョを入手し、筋肉断片から抽出したミトコンドリアDNA(mtDNA)ND4/ND5領域の約3400塩基配列に基づく近隣結合法による系統樹作成、外部形態・計数形質・内部形態の計28項目の計測比較、倍数性の確認を行なった。その結果、これらは1.琵琶湖起源のゲンゴロウブナからなる集団、2.韓国・南西諸島のフナとキンギョからなる集団、3.日本主要集団からなることが遺伝学的にも形態学的にも確認された。日本産と韓国産の2倍体フナは異なる久ラスダーを形成したことから、両者には異なる学名を与えるべきと考えた。日本主要集団の2倍体個体はさらに東北亜集団(キンブナ)、中部亜集団(ナガブナとニゴロブナ)、そして南日本集団(オオキンブナ)に分けられるので、これらに与えるべき学名を新たに提案した。また、ゲンゴロウブナ集団はすべて2倍体であったが、他の2集団は、遺伝的に非常に近い2倍体と3倍体からなる集団であった。すなわち、2倍体と3倍体は各地域集団において相互に生殖交流しつつ分化したものと考えられた。キンギョは遺伝的に日本主要集団のフナとは明らかに異なり、韓国・南西諸島の集団に属するので、大陸のフナがその起源であることがあらためて確認された。フナとキンギョの行動特性(情動反応性)が明らかに異なることを示すとともに、その原因となる脳内発現遺伝子の候補を得た。
7 0 0 0 文節数最小法を用いたべた書き日本語文の形態素解析
- 著者
- 吉村 賢治 日高達 吉田 将
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.40-46, 1983-01-15
- 被引用文献数
- 31
文節内における単語間の連接規則を記述した文法規則を用いるべた書き日本語文の形態素解析では 日本語文としては不適当な解析を含む多くの解析結果が生じる.これらの解析結果から正しい解析を効率的に得る方法として ヒューリスティックな構報が利用される.従来 この手法としては最長一致法が用いられているが 根拠が明らかでないうえに解析結果に尤度による優先順位をつけることができないという根本的な欠点がある本論文では 解析結果の文節数によってその尤度を評価する文節数最小法を提案し この手法に適した表方式の形態素解析アルゴリズムを与える.アルゴリズムの能率は 最悪の場合に必要とするステップ数 メモリ数ともに入力文字列の長さnに対してΟ(n^2)である.また 1 000文の入力文に対して解析実験を行い 文節数最小法の有効性を確認した.その結果 960文については文節数が最小となる解析に正解が存在し 残り40文も一つ文節数が多い解析に正解が存在した.その他 能率 最初に出力される解析結果の誤り率 尤度による順位付けの能力についても最長一致法と比較実験を行った.最初に出力される解析結果の誤り率は 文節数最小法で7.0% 最長一致法で12.4%であり このことも文節数最小法の有効を十分示している.
4 0 0 0 —十二指腸腫瘍性病変の内視鏡診断—粘膜下腫瘍様隆起の診断
- 著者
- 吉田 将雄 角嶋 直美 籔内 洋平 滝沢 耕平 川田 登 島田 清太郎 木村 英憲 佐藤 辰宣 塩月 一生 髙田 和典 岸田 圭弘 今井 健一郎 伊藤 紗代 堀田 欣一 小野 裕之
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.622-629, 2020-05-24
●「考える内視鏡診断」のポイント・十二指腸は部位によって背景粘膜の構造が異なることを認識する.・隆起表面の大部分が周囲と同様の非腫瘍粘膜に被覆されており,粘膜下腫瘍(SMT)様隆起の形態を呈することを確認する.・通常観察では,SMT様隆起の辺縁の性状,病変のサイズ,色調,陥凹の有無,陥凹の境界,びらん・潰瘍形成の有無,単発・多発,病変の硬さ・可動性について観察する.・通常観察において粘膜表面に変化がみられた場合には,拡大内視鏡観察を行い,病変表面の腺管構造と血管構造を観察する.・超音波内視鏡検査(EUS)では,病変の存在する層,周囲の層構造との連続性,病変の境界,病変内部のエコーレベルや性状について評価する.
3 0 0 0 夢精以外で射精を経験したことがない挙児希望の3例
- 著者
- 今井 伸 吉田 将士 米田 達明 工藤 真哉
- 出版者
- 日本性科学会
- 雑誌
- 日本性科学会雑誌 = Japan Journal of Sexology (ISSN:13496654)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.65-68, 2010-07-31
2 0 0 0 ブログ記事と Web ページを用いたイベント情報抽出手法の提案
- 著者
- 吉田 将人 福原 知宏 増田 英孝
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告デジタルドキュメント(DD)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.35, pp.37-44, 2009-03-18
ブログ記事と Web ページを利用したイベント情報抽出手法を提案する.提案手法は,ブログ記事からイベント名抽出パターンを構築し, Web ページからイベント名を抽出する.本研究では,ブログ記事と Web ページを利用したイベント情報抽出手法を提案する.ブログ記事を用いることにより,記事の書かれた日付が分かり,イベント名抽出パターンとイベント開催日の関係を把握できる.Web ページを用いることにより,イベント名検索の網羅性を広げることができる.提案手法では,まず,いくつかのイベント名に対してブログ記事を収集し,そこからイベント名の前後に連接しやすいパターンを抽出する.次に,抽出したパターンを用いて Web 全体からイベント名を収集する.提案手法のイベント名収集適合率と将来構想について報告する.An extraction method of event names appeared on the Web using blog and Web articles is described. Proposed method extracts event names from Web pages by finding extraction patterns of event names from blog articles. The method finds extraction patterns from blog articles that contain event names given by a user. Because different names for the same event can be appeared on the Web, the method identifies the same event using a string kernel that can measure similarities of event names. Then, the method finds event names by using extracted patterns. Preliminary results of an experiment are described.
2 0 0 0 語義文からの動詞間の上位-下位関係の抽出
- 著者
- 冨浦洋一 日高達 吉田 将
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.42-49, 1991-01-15
- 被引用文献数
- 5
本格的な意味処理を行うためには 単語の意味に関する知識が必要であることは言うまでもないその中で 語彙間の上位-下位関係は 最も基本的な知識の1つである本研究では 動詞間の上位-下位関係を国語辞典から抽出する手法を開発することを目的とする動詞は第一階述語論理ではn項述語に対応するまた 動詞は一般に多義であり 語義が異なれば 上位-下位関係にある動詞も異なるそこで 動詞をその語義ごとに述語に対応させ 動詞間の上位-下位関係を述語間の関係として捉えるしたがって 動詞間の上位-下位関係の抽出では 単に見出し動詞と上位-下位関係にある動詞(定義動詞)を抽出するだけでなく 定義動詞の語義の選択 および 見出し動詞と定義動詞の変数の対応も考慮しなければならない本稿では まず (1)動詞間の上位-下位関係を論理的に定義し (2)見出し動詞とその語義文の論理的関係 および 語義文の統語構造と論理的性質について述べ (3)動詞間の上位-下位関係を示す情報は語義文の統語構造中のどこに現れるかについて述べるさらに (4)定義動詞の語義 および 見出し動詞との変数の対応を適切に選択するための必要条件とヒューりスティックについて述べ 最後に (5)抽出結果について述べる
- 著者
- 吉田 将之 長峰 麻妃子 植松 一眞 広島大学大学院生物圏科学研究科 広島大学大学院生物圏科学研究科 広島大学大学院生物圏科学研究科
- 雑誌
- 日本水産学会誌 = Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, 2006-07-15
1 0 0 0 OA 歯科処置ならびに口腔疾患との関連が疑われた感染性心内膜炎患者の検討
- 著者
- 福元 俊輔 吉川 博政 樋口 崇 吉田 将律 杉 幸祐 山本 千佳
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.336-340, 2010-05-20 (Released:2013-10-19)
- 参考文献数
- 9
We retrospectively studied of 20 patients who were admitted to the department of cardiovascular internal medicine of our hospital between January 2001 and March 2007 for a diagnosis of infective endocarditis. On blood cultures, oral bacteria were detected in 9 patients. Furthermore, 10 of the 20 patients visited our department. We examined the correlation of dental treatments and oral diseases with infective endocarditis in the 10 patients. The results of the blood cultures suggested correlations of dental treatments or oral diseases with infective endocarditis in 4 patients. Two patients had oral infections, while the other 2 had undergone dental treatment within 2 weeks before the onset of infective endocarditis. Currently, there are two different guidelines (AHA2007 and JCS2008) for the prevention of infective endocarditis. As stated in the JCS2008 guidelines, we believe that, it is necessary to carefully administer prophylactic antibacterial drugs to patients undergoing dental treatments. In addition, we also believe that it is necessary to improve oral hygiene conditions to prevent infective endocarditis associated with dental treatments or oral diseases.
1 0 0 0 3次元立体ないし空間の説明に係る図的表現の許容限界について
- 著者
- 吉田 勝行 吉田 将行
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.127-132, 2001
パーソナル・コンピューター, カラー・プリンター, ディジタル・カメラ等のハードウェアと画像処理ソフトウェアの普及により, 3次元立体や空間に関する図や写真の加工が容易となり, その結果が説明図として, 一般にも利用されるようになってきている。しかし, 図法に対する理解が無いまま3次元立体や空間に関する図に加工がなされると, 思いもよらない誤りが図中に生じ得る。しかも, 平成10年12月14日に告示の小学校及び中学校学習指導要領, および平成11年3月29日に告示の高等学校学習指導要領によれば, 高校卒業までにこうした事柄について学ぶ機会は設けられていない。身の回りの空間や立体を図として正確に美しく表現し, 誤り無く他に伝えるための素養は, 加工された図が一般に流布する時代には, 文字による正確で美しい文章の作り方等と同様に, 初中等教育の中で修得させておく必要がある重要な項目の一つである。図的表現についての許容限界を吟味して, 初等および中等教育に盛り込むべき内容を検討する。
- 著者
- 吉田 将人 大澤 宏祐 高木 基樹 広川 貴次 植草 義徳 加藤 晃一 新家 一男 夏目 徹 土井 隆行
- 出版者
- 天然有機化合物討論会
- 雑誌
- 天然有機化合物討論会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.241-245, 2011-09-02
Thielocin B1 (1), isolated from the fermentation broth of Thielavia terricola RF-143 in 1995, consists of five multi-substituted benzene rings, which are connected with a 2,2', 6,6'-biaryl ether and four ester linkages. Recently, it was found that 1 strongly inhibits protein-protein interactions (PPIs) of PAC3 homodimer (IC_<50>= 0.02 μM) without inhibition of other PPIs such as PAC1/PAC2 or TCF/P-catenin. Since we are interested in the mode of action mechanisms of 1, we performed total synthesis of 1, and docking studies by NMR and in silico analyses. The key intermediate 2,2', 6,6'-biaryl ether 4 was synthesized from 7-membered lactone 6, which was prepared by oxidative lactonization of benzophenone 7, followed by chemoselective reduction of the lactone and removal of the resulting alcohol. The side wing 5 was synthesized from aldehyde 8 via formation of 3 and its coupling by esterification. Condensation of biaryl ether 4 and 5 was smoothly performed using trifluoroacetic anhydride to afford 21 in high yield. Formylation of 21 by treatment with dichloromethyl methyl ether and AgOTf, followed by Kraus oxidation provided acid 2. Coupling of the resulting acid 2 with phenol 3 afforded 22 in 70% yield. Finally, removal of the benzyl groups by-hydrogenation furnished thielocin B1 (1), whose spectral data were in good agreement with those of the natural product.
1 0 0 0 OA 3次元立体ないし空間の説明に係る図的表現の許容限界について
- 著者
- 吉田 勝行 吉田 将行
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.Supplement, pp.127-132, 2001 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
パーソナル・コンピューター, カラー・プリンター, ディジタル・カメラ等のハードウェアと画像処理ソフトウェアの普及により, 3次元立体や空間に関する図や写真の加工が容易となり, その結果が説明図として, 一般にも利用されるようになってきている。しかし, 図法に対する理解が無いまま3次元立体や空間に関する図に加工がなされると, 思いもよらない誤りが図中に生じ得る。しかも, 平成10年12月14日に告示の小学校及び中学校学習指導要領, および平成11年3月29日に告示の高等学校学習指導要領によれば, 高校卒業までにこうした事柄について学ぶ機会は設けられていない。身の回りの空間や立体を図として正確に美しく表現し, 誤り無く他に伝えるための素養は, 加工された図が一般に流布する時代には, 文字による正確で美しい文章の作り方等と同様に, 初中等教育の中で修得させておく必要がある重要な項目の一つである。図的表現についての許容限界を吟味して, 初等および中等教育に盛り込むべき内容を検討する。
- 著者
- 吉田 将也 西村 康孝 吉原 貴仁
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.2, 2013-09-03
1 0 0 0 IR DNA鑑定の威力
- 著者
- 水上 創 吉田 将亜 斉藤 修
- 出版者
- 旭川医科大学
- 雑誌
- 旭川医科大学研究フォーラム (ISSN:13460102)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.5-11, 2000-12
出版社版
1 0 0 0 語義文の機能表現について
- 著者
- 鶴丸 弘昭 城戸 健雄 日高 達 吉田 将
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. NLC, 言語理解とコミュニケーション
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.429, pp.47-54, 1995-12-15
- 被引用文献数
- 1
本稿は国語辞典の語義文に現れる機能表現について調査・整理したものである。機能表現は,語義文の末尾に現れ,語義文から定義語,および,定義語と見出し語との間の階層関係を求める際に意味情報(ρ_<FE>)を与えるものである。調査対象は主として新明解国語辞典^<(1)>の語義文であるが,他の同様な辞典(旺文社^<(2)>,岩波^<(3)>,角川^<(4)>)も参考にしている。約一万の語義文^<(1)>のなかて,機能表現を含んでいる語義文は約1,500文であった。調査結果は,表1,表2,表3にまとめて示している。
1 0 0 0 IR 集合指向首語SOLのデータベースへの応用
- 著者
- 重松 保弘 輿那覇 誠 吉田 将
- 出版者
- 社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.1041-1051, 1992-08-15
- 被引用文献数
- 1
関係データベース言語SQLをホスト言語埋込み形式で使用する場合 現在のJIS(ANSI ISO)規格で標準化されているホスト言語ではSQLとの不整合性が問題とされているこれは 本質的にはホスト言語が集合や関係を言語仕様に含まないことに起因するそこで この不整合性の改善 とくに集合変数を用いたSQLインタフェースの改善をはかる目的で 著者らが開発した集合指向言語SOLをSQLのホスト言語として応用し SOL/SQLシステムを開発した具体的にはSQL文のうちSELECT文 INSERT文およびUPDATE文についてスカラ変数列 集合変数および写像列が指定できるよう埋込み構文を拡張するとともに カーソル処理によるデータアクセス機構などをSOL/SQL言語処理系によって隠ぺいすることにしたその結果 ホスト言語SOLとSQL間で集合単位および関係単位のデータの受渡しが自然な形式で記述できるようになり ホスト言語とSQL言語の整合性を改善することができたまた 応用プログラムの記述量もPLI/SQLの場合と比較して大幅に縮小できるようになった本稿では SQL文の拡張埋込み構文の仕様とIBM 4381上で開発したSOL/SQL言語処理系について述べるとともに SOL/SQLとPLI/SQLで比較記述した応用プログラム例を示す