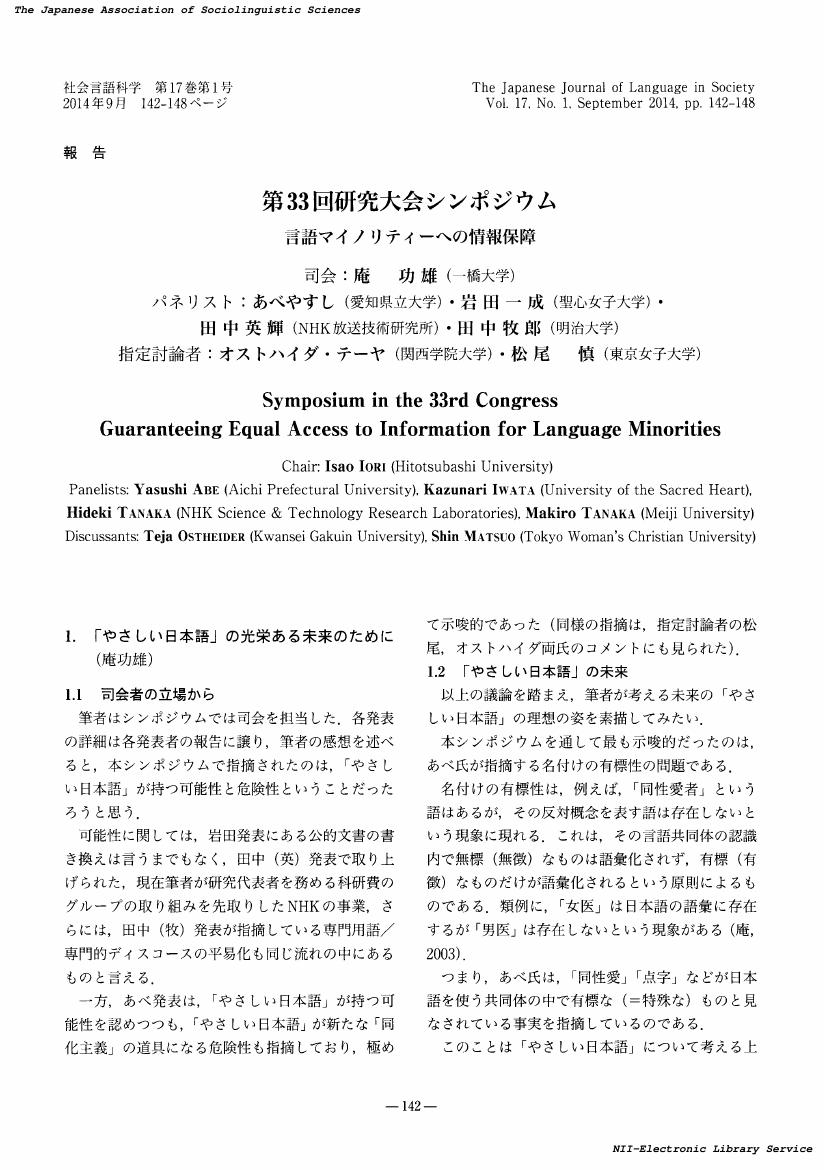17 0 0 0 OA 社会参加のための情報保障と「わかりやすい日本語」 : 外国人,ろう者・難聴者,知的障害者への情報保障の個別課題と共通性(<特集>ウエルフェア・リングイスティクスにつながる実践的言語・コミュニケーション研究)
- 著者
- 松尾 慎 菊池 哲佳 モリス J.F 松崎 丈 打浪(古賀) 文子 あべ やすし 岩田 一成 布尾 勝一郎 高嶋 由布子 岡 典栄 手島 利恵 森本 郁代
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.22-38, 2013-09-30
本論文は,外国人,ろう者・難聴者,知的障害者など,誰もが社会参加ができるために必要不可欠な条件である「情報保障」の考え方を紹介します.また,今後情報保障を進めていくための課題や枠組みを提示します.本論文では,情報保障の範囲を「震災」などの非常時だけに特化せず,平時における対応も含めます.情報保障の基本は,「情報のかたちを人にあわせる」「格差/差別をなくす」ことと,「情報の発信を保障する3ことです.本論文では,まずこうした基本的な観点を紹介します.特に,情報の格差/差別をなくすという課題にはどのようなものがあり,それを解決するためには,どのような手段があるのかについて述べます.さらに,情報保障が,情報へのアクセスだけでなく,情報発信の保障をも含む考え方であることを指摘します.その上で,これまで個別に扱われてきた外国人,ろう者・難聴者,知的障害者の情報保障の問題について,個別の課題とともに,共通性としての「情報のユニバーサルデザイン化」の必要性を指摘します.そして,その一つの方法として「わかりやすい日本語」の例を挙げ,今後の情報保障のあり方について議論します.
11 0 0 0 OA 第33回研究大会シンポジウム : 言語マイノリティーへの情報保障
- 著者
- 庵 功雄 あべ やすし 岩田 一成 田中 英輝 田中 牧郎 オストハイダ テーヤ 松尾 慎
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.142-148, 2014-09-30 (Released:2017-05-03)
11 0 0 0 OA I 地理学の制度化と日本地理学会の創設
- 著者
- 中川 浩一 竹内 啓一 岩田 一彦 立岡 裕士 久武 哲也 源 昌久
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.225-247, 2000-04-01 (Released:2008-12-25)
10 0 0 0 IR 日本語教育初級文法シラバスの起源を追う : 日本語の初級教材はなぜこんなに重いのか?
- 著者
- 岩田 一成
- 出版者
- 聖心女子大学
- 雑誌
- 聖心女子大学論叢 (ISSN:00371084)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, pp.92-67, 2015-12
9 0 0 0 OA 日本語教育初級文法シラバスの起源を追う-日本語の初級教材はなぜこんなに重いのか?-
- 著者
- 岩田 一成
- 出版者
- 聖心女子大学
- 雑誌
- 聖心女子大学論叢 = SEISHIN STUDIES (ISSN:00371084)
- 巻号頁・発行日
- no.126, pp.67-92, 2015-12-25
- 著者
- 打浪 文子 岩田 一成 熊野 正 後藤 功雄 田中 英輝 大塚 裕子
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.29-41, 2017-09-30 (Released:2018-02-07)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
本研究では,知的障害者に対する「わかりやすい」情報提供を実践する媒体である「ステージ」と,外国人向けの「やさしい日本語」で時事情報の配信を行うNHKの「NEWSWEB EASY」(以下NWE),およびNWE記事の書き換え元であるNHKの一般向けニュース原稿の3つのメディアのテキストを,文長や記事長,難易度や使用語彙の観点から計量的および質的に分析し,その共通点および相違点を明らかにした.分析の結果から,ステージとNWEの共通点として形態素数や和語の率が近いことや,「外来語」や「人の属性を表す語」などの名詞や動詞を中心とした難解語彙の群があることが示された.また相違点として,ステージには副詞や接辞等に「やさしい日本語」の基準に照らせば書きかえ可能なものがあること,さらにステージのみの特徴として同じ動詞をさまざまな形で重ねて使っていることが示された.条件を統制した上で上記3つのメディアの共通・相違性に関する比較研究を深めること,知的障害者向けの情報提供のさらなる分析と知見の収集を行うこと,従来の研究領域を超える「言語的な困難を有する人」すべてを対象とした「わかりやすい」日本語による情報保障の具体的な方法を提示することの3点が本研究の今後の課題である.
7 0 0 0 OA 看護師国家試験対策と「やさしい日本語」
- 著者
- 岩田 一成
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.158, pp.36-48, 2014 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 13
近年,日本語学習者の教育内容を議論するような文脈で「やさしい日本語」という概念が用いられるようになっている。本稿で扱うのは看護師候補者に対する教育内容である。看護師国家試験受験の目安となりつつある日本語能力試験2級レベルを基準として文法や語彙を分析した。データとして過去の看護師国家試験問題7回分を用いた。文法に関しては,一試験に1回以上出現する可能性がある2級文法はせいぜい15程度であり,2級文法170項目の一部にすぎない。名詞語彙に関しては,65%が級外または1級語彙であり,2級語彙では全く対応できない。つまり,2級を目指すのではなく,文法内容を最小限に絞って語彙を増やしていく指導が必要になる。また本稿では,1233の必修問題用名詞語彙に519を追加すれば,一般・状況設定問題の約80%が理解でき,1624を追加すれば約90%が理解できるようになることを指摘し,語彙指導の道筋を示した。
6 0 0 0 OA 明治後期における少年の書字文化の展開 : 『少年世界』の投稿文を中心に
- 著者
- 岩田 一正
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.417-426, 1997-12-30
本論文は, 義務教育制度がその内実をほぼ完備し, 地域共同体が再編成されつつあった明治後期に, 少年たちが, 書字文化を媒介とした固有名の個人が集う公共圏をどのように構築していたのかを検討することを目的としている. 少年たちが雑誌への投稿者として共同性を構成する過程は, 自らを言葉を綴る主体として保つ近代に特有な方法を, 我々に開示してくれるだろう. 本論文が史料とするのは, 当時最も読まれていた少年雑誌であり, 明治後期の「出版王国」博文館によって発行されていた『少年世界』である. 『少年世界』に掲載された投稿文の分析を通して, 三つの観点が示されることになる. 第一に,1903年頃に『少年世界』の主筆である巌谷小波によって提示された言文一致体は, 天真爛漫な「少年」という概念を創出した. さらに, 『少年世界』編集部は投稿作文欄の規定を改正し, 少年たちは言文一致体で投稿するように要請された. その結果, 煩悶する「青年」と天真欄漫な「少年」が差異化され, 『少年世界』は後者のための雑誌となった. 第二に, 『少年世界』は, 少年に固有名をともなった他者とのコミュニケーションの場を提供した. しかし, その場は, 抽象的で均質な時空によって構成されていた. それゆえ, 少年たちは地域共同体からの切断に由来する, いまだかつて経験したことのない孤独を感じることになった. しかしながら, 投稿欄を利用することによって, その孤独を補償し, 他者との交歓=交感を享受するために, 少年たちは誰かに向かって何かを書こうとする欲望を生み出し, ある場合には, 同好のコミュニケーション・ネットワークを形成したのである. そして, この文脈において, 言文一致体は適合的な文体であった. なぜなら, 言文一致体は, 少年に見えざる他者の声を想像させることができるからである. また, 当時は, 国家的な郵便制度が確立したことによって, 文通によるコミュニケーションの制度的な基盤が整備された時期であった. 第三に, 少年たちは, 自らの手で雑誌を出版するようになった. ここで注目に値するのは, 活字で構成される一般の雑誌とは異なり, 少年が制作した雑誌は, 肉筆やこんにゃく版, 謄写版によって作られており, 手作りの感触を残していることである. 少年の雑誌制作は, 大正期以降の同人雑誌文化の基層を形成するものであり, この同人雑誌文化から, 数多くの文学作品が創出されることになる.
4 0 0 0 OA 第33回研究大会シンポジウム : 言語マイノリティーへの情報保障
- 著者
- 庵 功雄 あべ やすし 岩田 一成 田中 英輝 田中 牧郎 オストハイダ テーヤ 松尾 慎
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.142-148, 2014-09-30
- 著者
- 松尾 慎 菊池 哲佳 モリス J.F 松崎 丈 打浪(古賀) 文子 あべ やすし 岩田 一成 布尾 勝一郎 高嶋 由布子 岡 典栄 手島 利恵 森本 郁代
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.22-38, 2013-09-30 (Released:2017-05-02)
- 被引用文献数
- 1
本論文は,外国人,ろう者・難聴者,知的障害者など,誰もが社会参加ができるために必要不可欠な条件である「情報保障」の考え方を紹介します.また,今後情報保障を進めていくための課題や枠組みを提示します.本論文では,情報保障の範囲を「震災」などの非常時だけに特化せず,平時における対応も含めます.情報保障の基本は,「情報のかたちを人にあわせる」「格差/差別をなくす」ことと,「情報の発信を保障する3ことです.本論文では,まずこうした基本的な観点を紹介します.特に,情報の格差/差別をなくすという課題にはどのようなものがあり,それを解決するためには,どのような手段があるのかについて述べます.さらに,情報保障が,情報へのアクセスだけでなく,情報発信の保障をも含む考え方であることを指摘します.その上で,これまで個別に扱われてきた外国人,ろう者・難聴者,知的障害者の情報保障の問題について,個別の課題とともに,共通性としての「情報のユニバーサルデザイン化」の必要性を指摘します.そして,その一つの方法として「わかりやすい日本語」の例を挙げ,今後の情報保障のあり方について議論します.
- 著者
- 我妻 了 井上 拳斗 岩田 一
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.381-382, 2015-08-24
- 著者
- 松尾 慎 菊池 哲佳 モリス J.F 松崎 丈 打浪(古賀) 文子 あべ やすし 岩田 一成 布尾 勝一郎 高嶋 由布子 岡 典栄 手島 利恵 森本 郁代
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.22-38, 2013-09-30
本論文は,外国人,ろう者・難聴者,知的障害者など,誰もが社会参加ができるために必要不可欠な条件である「情報保障」の考え方を紹介します.また,今後情報保障を進めていくための課題や枠組みを提示します.本論文では,情報保障の範囲を「震災」などの非常時だけに特化せず,平時における対応も含めます.情報保障の基本は,「情報のかたちを人にあわせる」「格差/差別をなくす」ことと,「情報の発信を保障する3ことです.本論文では,まずこうした基本的な観点を紹介します.特に,情報の格差/差別をなくすという課題にはどのようなものがあり,それを解決するためには,どのような手段があるのかについて述べます.さらに,情報保障が,情報へのアクセスだけでなく,情報発信の保障をも含む考え方であることを指摘します.その上で,これまで個別に扱われてきた外国人,ろう者・難聴者,知的障害者の情報保障の問題について,個別の課題とともに,共通性としての「情報のユニバーサルデザイン化」の必要性を指摘します.そして,その一つの方法として「わかりやすい日本語」の例を挙げ,今後の情報保障のあり方について議論します.
- 著者
- 岩田 一正
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城文藝 (ISSN:02865718)
- 巻号頁・発行日
- no.218, pp.84-65, 2012-03
2 0 0 0 OA 言語政策から見た「公用文のわかりやすさ」
- 著者
- 岩田 一成
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.28-37, 2019-09-30 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 24
本論文では,戦後の言語政策において「公用文のわかりやすさ」がどのように扱われてきたかを分析した.指摘したことは以下の4点である.1点目,公用文は規定上職員や関係者などへの内部向け文書が想定されてきた.2点目,日本の言語政策の歴史は,文字・表記の規範化のために多大な労力をかけてきたため,文章の内容に踏み込んだ議論が深くはなされていない.3点目,語句レベルの言い換え提案はいくつかなされてきているが,談話レベルに踏み込んだものはまだない.4点目,談話レベルのわかりやすさとは,相手への配慮(美しい言葉,丁寧な言葉)や行き届いた叙述などと両立が難しい.こういったわかりやすさの分析がこれまでの言語政策では見過ごされてきた可能性がある.これらを踏まえて,以下の提案を行った.①公用文の定義において部外用文書と部内用文書に分ける②内容に関する談話レベルの解決策を提案する③わかりやすさの阻害要因を抽出し整理する
- 著者
- 薮崎 清・ヒベルト 岩田 一明 荒井 栄司 小野里 雅彦
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會論文集. C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.584, pp.1734-1739, 1995-04-25
Computer representation of the product object is necessary for realization of concurrent engineering. This representation should be determined cooperatively by design and production departments using communication systems. This paper describes minimum design and production criteria to meet requirements and functions for modelling. The authors propose one method for representation of the product object, using object-oriented programming and an object-oriented database management system. Reliable data for this product object representation were obtained by interviewing several experienced designers and manufacturing engineers and through a literature search. Then, the authors developed a prototype and verified the validity. Based on a simple design experiment, the possibility of realizing human-centered concurrent engineering was clarified.
- 著者
- 鷲頭 祐樹 末松 伸朗 林 朗 岩田 一貴
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.461, pp.279-284, 2010-03-02
混合ディリクレ過程(DPM)モデルは,要素モデル数を指定する必要のないノンパラメトリック混合モデリングを可能にする.要素モデル数の指定が必要ないことは,クラスタリングにとって非常に有益であり,DPMモデルは多くのクラスタリング問題へ適用され成功を収めている.共役事前分布が使用される場合には,DPMモデルに対するギブスサンプリング法が確立されているが,ARMAモデルのように共役事前分布を持たない要素モデルの場合には困難に直面する.本論文では,ギブスサンプリ ングに内在するメトロポリス・へイスティングスのマルコフ連鎖を導入することでこの問題に対応し,ARMAモデルべースの時系列クラスタリング法を実現する.
2 0 0 0 階層隠れCRF
- 著者
- 玉田 寛尚 林 朗 末松 伸朗 岩田 一貴
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J93-D, no.12, pp.2610-2619, 2010-12-01
HMM(Hidden Markov Model)は時系列データの生成モデルとしてよく知られている.しかし,近年,HMMに対応する識別モデルであるCRF(Conditional Random Field)が提案され,多くの応用問題で有効性が示されている.HHMM(Hierarchical HMM)はHMMを一般化した生成モデルであり,時系列データの状態を階層的に表現する.我々はHHMMに対応する識別モデルとして,HHCRF(Hierarchical Hidden CRF,階層隠れCRF)を提案する.HHMMとHHCRFの性能比較のために,生成モデルと識別モデルの性質を考慮しつつ人工データ実験を行い,パラメータ学習時の訓練集合サイズが大きくなり,かつデータ生成源が非一次マルコフモデルに近づくにつれて,状態系列推定におけるHHCRFの性能がHHMMのそれよりも,より高くなることを示す.
1 0 0 0 OA 過労死・過労自殺の心理的要因と職務状況との関係
- 著者
- 岩田 一哲
- 出版者
- 労務理論学会
- 雑誌
- 労務理論学会誌 (ISSN:24331880)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.151, 2009 (Released:2018-05-04)
1 0 0 0 OA 高分子のトポロジー的相互作用
- 著者
- 岩田 一良
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.408-414, 1994-06-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
高分子の絡み合いをトポロジーの立場から見ると,全く新しい高分子の姿が見えてくる.絡み合いには斥力が存在し,高分子の物性に大きな影響を与えることを環状高分子や架橋高分子系などを例に取り上げて議論する.とくに,環状高分子の絡み合いだけで形成されたカテナ網目について詳しく論ずる.