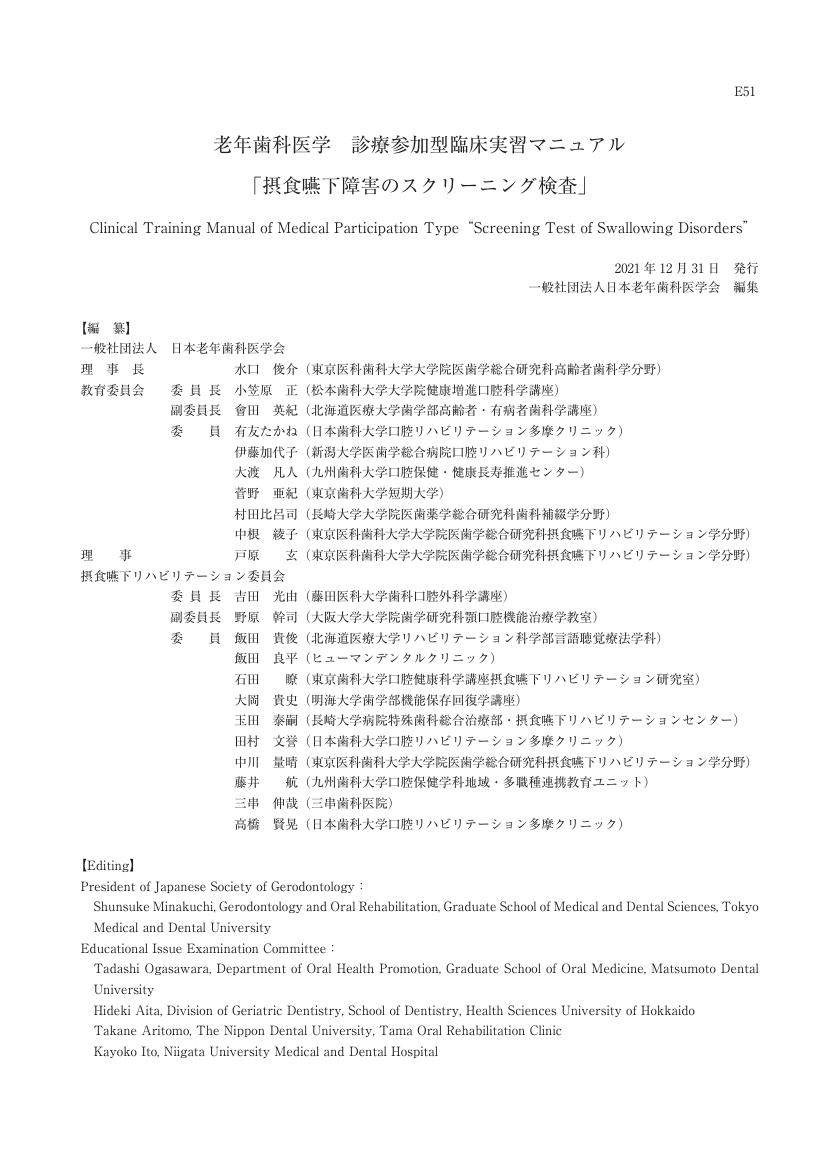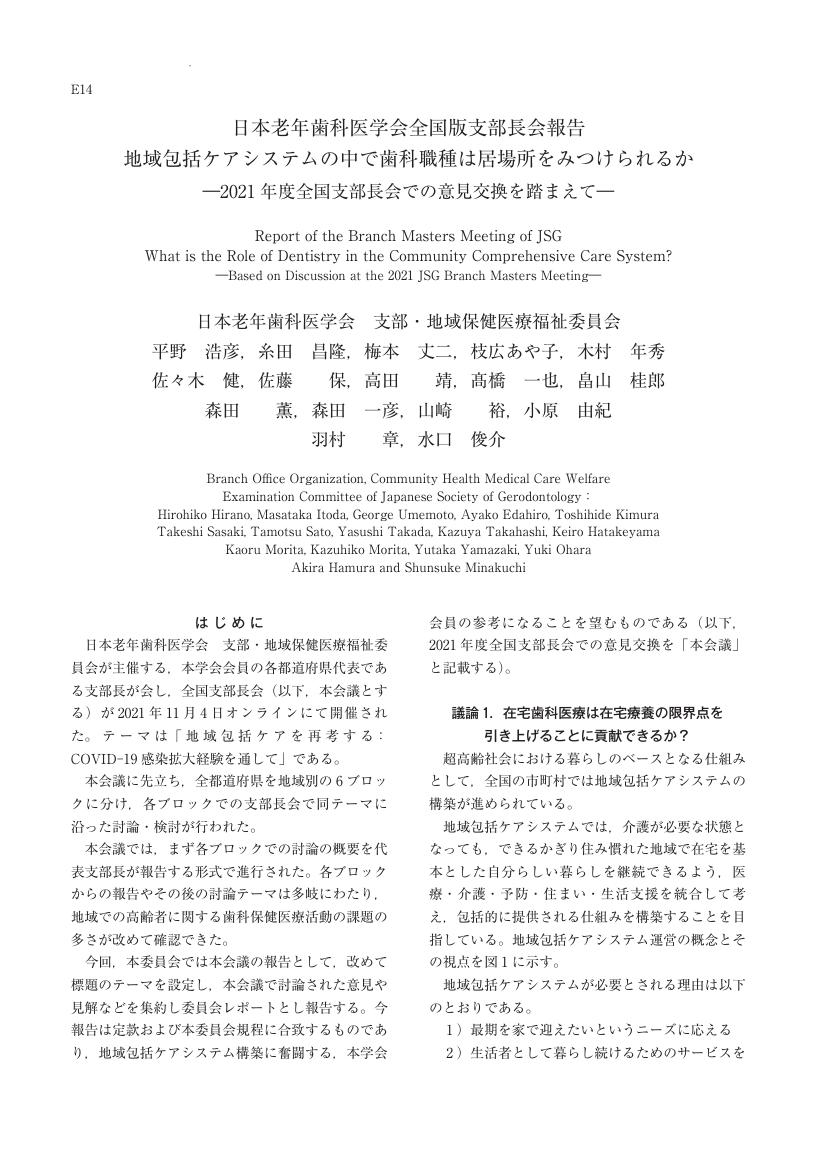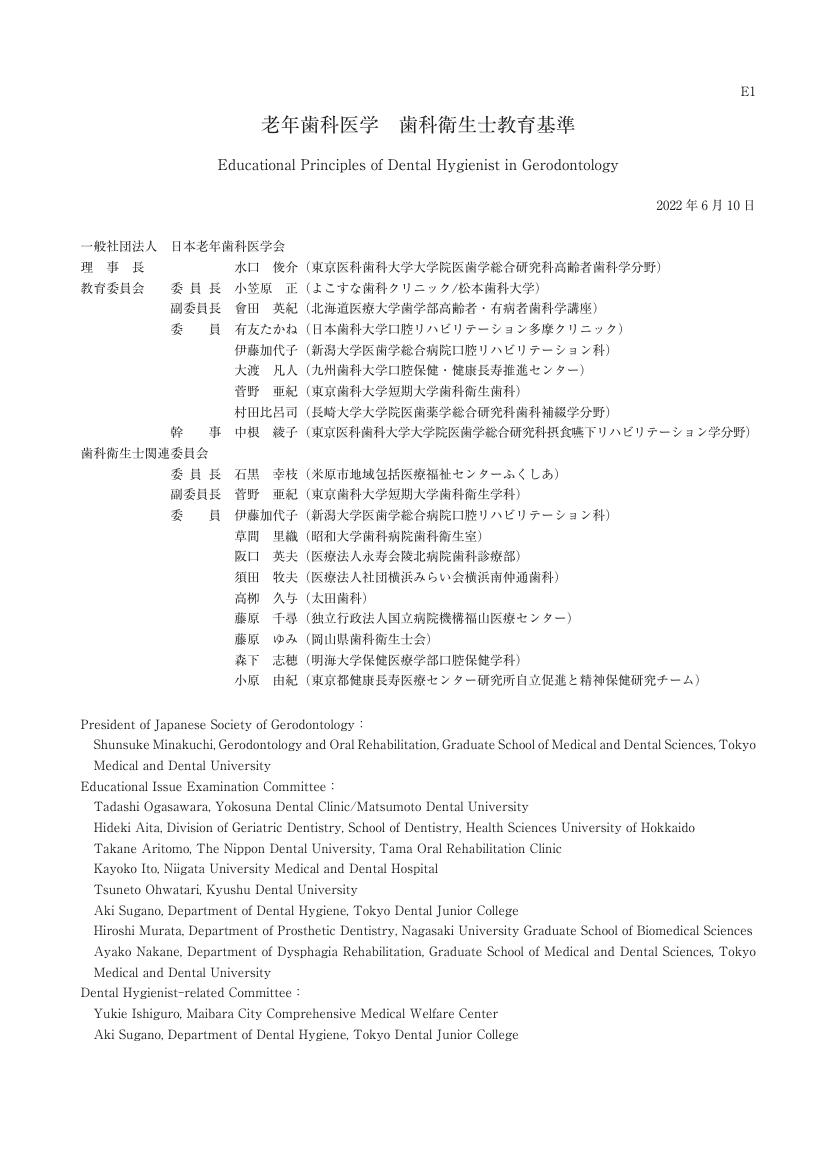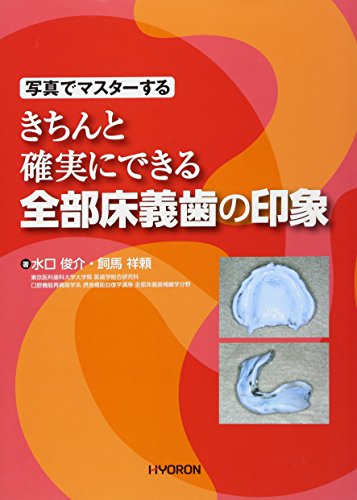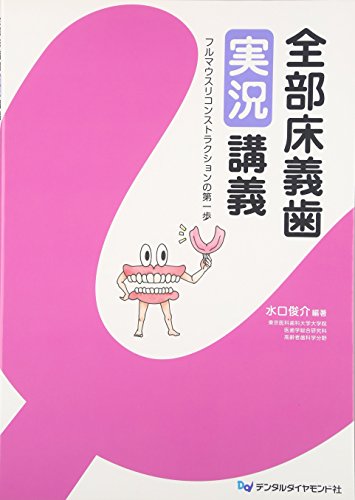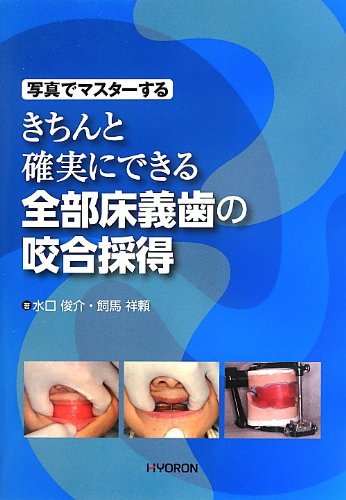45 0 0 0 OA 摂食嚥下障害のスクリーニング検査
17 0 0 0 OA 歯科訪問診療における感染予防策の指針 2022年版
9 0 0 0 OA 急性期病院入院高齢者における口腔機能低下と低栄養との関連性
- 著者
- 松尾 浩一郎 谷口 裕重 中川 量晴 金澤 学 古屋 純一 津賀 一弘 池邉 一典 上田 貴之 田村 文誉 永尾 寛 山本 健 櫻井 薫 水口 俊介
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.123-133, 2016-09-30 (Released:2016-10-22)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
目的:高齢者では,加齢だけでなく,疾患や障害などさまざまな要因によって,口腔機能が低下する。経口栄養摂取のためには,口腔機能の維持は重要な因子と考えられるが,口腔機能低下と栄養状態との関連性についてはまだ不明な点が多い。そこで,本研究では,全身疾患を有する入院高齢患者における口腔機能低下と低栄養との関連性を明らかにすることを目的とした。 方法:対象は,2015年10月から2016年2月までに藤田保健衛生大学病院歯科を受診した入院中の患者とした。対象者の口腔機能,口腔衛生に関する項目および栄養と全身状態に関する項目を調査した。Mini Nutritional Assessment-Short Form(MNA-SF)を用いて,栄養状態を正常群と低栄養群の2群に分類し,口腔と全身の評価項目が栄養状態と年齢で相違があるか検討した。 結果:口腔衛生,多くの口腔機能の項目で,低栄養群で有意な低値を示した。特に筋力系の項目で顕著であった。一方,高齢群においても,若年群と比して多くの口腔機能の項目が低値を示した。また,QOLやADLは,低栄養者および後期高齢群において有意な低下を認めた。 結論:入院高齢患者の低栄養は,多くの口腔機能の低下と関連していた。本結果から,栄養を指標として口腔機能低下を評価することの意義が示唆された。また,入院患者の良好な栄養状態を維持するためには,入院前からの適切な口腔管理により口腔機能が維持されることが重要であると考える。
4 0 0 0 OA 老年歯科医学 歯科衛生士教育基準
3 0 0 0 OA 歯科訪問診療における感染予防策の指針 2023年版
3 0 0 0 OA 歯科における訪問診療を示す学術用語に関する本会としての考え方
- 著者
- 水口 俊介 大神 浩一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.206, 2021-12-31 (Released:2022-01-28)
1 0 0 0 OA 補綴装置製作に関するドグマ─全部床義歯の製作法,特に印象法について─
- 著者
- 水口 俊介
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.315-321, 2011 (Released:2011-12-08)
- 参考文献数
- 35
全部床義歯の製作法には多くのドグマが潜んでいる.しかし超高齢社会を迎えたわが国において,各種コストを浪費するこのようなドグマが存在することは許されない.個人トレーとコンパウンド等を用いた辺縁形成による印象法が多くの大学で採用されている.しかしコンパウンドは,習熟するまでには訓練が必要であり,技術修練のための教育時間が著しく削減された現状の教育環境ではそれが達成できているかどうか疑わしい.またそのように手間をかけて製作した義歯が必ずしも患者の満足につながらないという報告は多い.われわれは,これまでの製作法や教育法を綿密に再検討し,真に適切な手法で教育しなければならない.
1 0 0 0 OA 高齢者の口腔内環境改善を目指した超高齢社会におけるS-PRGフィラー含有材料の応用
- 著者
- 水口 俊介 猪越 正直
- 雑誌
- 一般社団法人日本老年歯科医学会 第32回学術大会
- 巻号頁・発行日
- 2021-05-19
超高齢社会を迎えた日本では、今後も高齢者人口の増加が予想されている。平成28年の歯科疾患実態調査によれば、残存歯数の増加に伴って、高齢者におけるう蝕罹患者数の増加が示されている。一方、高齢者において義歯装着者の割合は減少しているものの、高齢者人口増加のため義歯装着者数は減少していないと考えられる。このような背景を鑑みると、高齢者の根面う蝕への対応と、義歯装着者の口腔内環境改善は、今後取り組むべき重要な課題であると考えられる。 株式会社松風が開発したSurface reaction-type Pre-Reacted Glass-ionomer (S-PRG) フィラーは、多機能性ガラス(フルオロボロアルミノシリケートガラス)を微細化及び多孔質ガラス化表面処理を施した後、ポリアクリル酸水溶液と反応させることにより、安定化したグラスアイオノマー相をガラスコアの表層に形成させた3層構造からなるバイオアクティブ新素材である。このS-PRGフィラーは、6種類のイオン(ストロンチウムイオン、ナトリウムイオン、ホウ酸イオン、アルミニウムイオン、ケイ酸イオン、フッ化物イオン)を徐放することにより、歯質強化能、酸緩衝能、抗菌効果を示すことが文献的に示されている。S-PRGフィラー含有材料は、そのバイオアクティブな作用による口腔内環境改善が可能となる材料として期待されている。 我々は今まで、株式会社松風と共に、S-PRGフィラー含有材料の高齢者歯科分野への応用を進めてきた。まず、根面う蝕への対応として、S-PRGフィラー含有セメントの開発を進め、イオン徐放能を持つ新規根面う蝕修復材料を開発した。また、S-PRGフィラーを義歯安定材に添加することにより、抗菌効果を持つ義歯安定材の開発を進めてきた。さらに、S-PRGフィラーをナノサイズ化した、S-PRGナノフィラーをティッシュコンディショナーに添加することにより、ティッシュコンディショナーへのカンジダの付着を抑制することに成功した。 本セッションでは、これらの高齢者歯科分野で応用可能なS-PRGフィラー含有材料について紹介させていただき、今後の展望についてお話しさせていただく予定である。
1 0 0 0 OA 市中病院におけるリハビリテーション歯科医療の取り組み
- 著者
- 尾﨑 研一郎 寺中 智 岡田 猛司 水口 俊介
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.17-24, 2018-06-30 (Released:2018-07-25)
- 参考文献数
- 24
当歯科はリハビリテーション科(リハビリ科)を起点として医科歯科連携を行っており,対象は主に入院患者である。今回,当歯科での活動報告として開設した2010年10月から2011年1月までの間にリハビリ科依頼となった急性期入院患者への口腔内検診の結果と2010年10月から2016年3月までの間に歯科介入した入院患者の実績について,診療録と当科データベースより後ろ向きに調査した。開設後の4カ月間に行った急性期におけるリハビリ科依頼患者への口腔内検診の結果,歯科介入の必要性は404人中259人(64%)であることが分かった。次に開設から5年5カ月の間に歯科介入した患者数は男性2,554人,女性1,829人(平均年齢72±13歳)であった。原疾患は呼吸器疾患755人(17%),脳血管障害746人(17%),消化器疾患593人(14%)と続いた。主な歯科介入の内容は口腔衛生管理2,668人(61%),義歯治療910人(21%),処方を要する粘膜治療426人(10%),保存治療212人(5%),抜歯145人(3%)であった。口腔内検診の結果より,急性期におけるリハビリ科依頼患者の約6割に歯科介入の必要性があり,歯科ニーズが潜在していることが明らかになった。歯科介入の内容は口腔衛生管理が最も多かったが,介入の内容は多岐にわたっていた。
- 著者
- 尾﨑 研一郎 馬場 尊 中村 智之 稲葉 貴恵 川島 広明 中島 明日佳 福井 友美 間々田 浩明 黒後 祐美 中里 圭佑 堀越 悦代 寺中 智 加藤 敦子 亀山 登代子 川﨑 つま子 水口 俊介
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.225-236, 2018-12-31 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 37
【目的】今回,病棟専属の常勤歯科医師,歯科衛生士が急性期病棟の看護師とリハビリテーション科が参加する肺炎予防システムを構築した.本研究では,急性期脳卒中患者に対する本システムの効果について,入院中の肺炎発症と退院時の経口摂取不能の観点から調査した.【方法】肺炎予防システムは病棟の全患者に対する看護師による口腔アセスメントと口腔衛生管理の標準化,歯科依頼手順,リハビリテーション科による摂食嚥下評価の情報共有からなる.対象は,当院に入院した脳卒中患者のうち,肺炎予防システム導入前の2012年4月から2013年3月に関わった234人(男性127人,女性107人,平均年齢72±13歳)と肺炎予防システム定着後の2014年4月から2015年3月に関わった203人(男性107人,女性96人,平均年齢74±11歳)とした . 診療録とThe Japanese Diagnosis Procedure Combinationデータベース,リハビリテーション科と歯科内で運用している患者臨床データベースより入院時の属性と帰結について調査し,導入前と定着後について解析を行った.【結果】定着後群は,導入前群よりも重度な症例が多かった.肺炎発症は,導入前群15%,定着後群8%であった.ロジスティック回帰分析において,導入前群の肺炎発症は定着後群の肺炎発症と比較してオッズ比2.70(95% CI 1.17―6.21, p=0.020)であった.肺炎予防システムのほかに肺炎発症と有意に関連したのは,入院時の意識レベルと,初回評価時の摂食嚥下障害の重症度であった.退院時の経口摂取可能例の割合については導入前群と定着後群の間で変化を認めなかったが,導入前群より重度であった定着後群に対し経口摂取の割合を減らさなかった.【結論】肺炎予防システムは,肺炎予防と経口摂取維持に効果が認められた.これは,急性期病棟の看護師,歯科,リハビリテーション科が,患者の状態を共有したうえで専門的介入ができたことによる結果と考えられる.
1 0 0 0 OA 高齢者の咬合支持状況に関する研究
- 著者
- 鈴木 哲也 熊谷 宏 内田 達郎 吉富 信幸 渡邊 竜登美 石鍋 聡 水口 俊介 関田 俊明 平野 滋三 宮下 健吾 小林 賢一 長尾 正憲
- 出版者
- 社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.476-484, 1994-04-01 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 2 4
The distribution of occlusal support of 366 aged patients of over 70 years was surveyed and analyzed in this study. Their masticatory abilities were also evaluated by the questionnaire on the masticatory aspects of 20 kinds of foods, and their maximum occlusal forces were measured with the pressure sensitive foil. The relations among masticatory ability, maximum occlusal forces and the distribution of occlusal support were analyzed.The results were as follows.1. 52.8% of the upper and lower dentulous patients had less than 5 occlusal tooth contacts.2. Posterior tooth contacts were less than anterior ones, and even in posterior areas, occlusal contacts tended to be less from the second molar to the first premolar.3. 61.2% of the upper and lower dentulous patients had no occlusal support or only unilateral occlusal support. It is evident that occlusal support is extremely ill-conditioned in elderly patients.4. It was found that if the aged have more occlusal tooth contacts and wider occlusal support areas, they would show better masticatory ability and greater maximum occlusal forces.5. In thier initial visits to our clinic they had poor occlusal support with their dentures.6. It is suggested that occlusal tooth contacts and occlusal support areas should be important for maintaining a healthy oral function in elderly people.
1 0 0 0 写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の印象
- 著者
- 水口俊介 飼馬祥頼著
- 出版者
- ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の試適・装着
- 著者
- 水口俊介 飼馬祥頼 菊池圭介著
- 出版者
- ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 全部床義歯実況講義 : フルマウスリコンストラクションの第一歩
- 著者
- 水口俊介編著
- 出版者
- デンタルダイヤモンド社
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の咬合採得
- 著者
- 水口俊介 飼馬祥頼著
- 出版者
- ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 OA 胃瘻療養中の脳血管障害患者に対する心身機能と摂食状況の調査
- 著者
- 原 豪志 戸原 玄 近藤 和泉 才藤 栄一 東口 髙志 早坂 信哉 植田 耕一郎 菊谷 武 水口 俊介 安細 敏弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.57-65, 2014-10-16 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 32
経皮内視鏡的胃瘻造設術は,経口摂取が困難な患者に対して有用な栄養摂取方法である。しかしその適応基準はあるが,胃瘻造設後の経口開始基準や抜去基準はない。 われわれは,胃瘻療養中の脳血管障害患者の心身機能と摂食状況を,複数の医療機関にて調査したので報告する。133 名 (男性 72 人,女性 61 人)を対象とし,その平均年齢は77.1±11.3 歳であった。患者の基本情報,Japan Coma Scale (JCS),認知症の程度,Activities of daily living (ADL),口腔衛生状態,構音・発声の状態,気管切開の有無,嚥下内視鏡検査 (Videoendoscopic evaluation of swallowing,以下 VE)前の摂食状況スケール (Eating Status Scale,以下 ESS),VE を用いた誤嚥の有無,VE を用いた結果推奨される ESS (VE 後の ESS),の項目を調査した。 居住形態は在宅と特別養護老人ホームで 61.3%を占め,認知症の程度,ADL は不良な対象者が多かったが,半数以上は口腔衛生状態が良好であった。また,言語障害を有する対象者が多かった。対象者の82.7%は食物形態や姿勢調整で誤嚥を防止することができた。また,VE 前・後の ESS の分布は有意に差を認めた (p<0.01)。胃瘻療養患者に対して退院後の摂食・嚥下のフォローアップを含めた環境整備,嚥下機能評価の重要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 咀嚼と嚥下の協調について
- 著者
- 戸原 玄 水口 俊介
- 出版者
- Japanese Society for Mastication Science and Health Promotion
- 雑誌
- 日本咀嚼学会雑誌 (ISSN:09178090)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.3-12, 2004-05-31 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
The rapid growth of aged population of Japanese society will force dentists to copewith physical problems of elderly. One of the major problems of elderly is the swallowing disorder, which should be managed by various profession, medical doctor, speech therapist, nurse and dentist. If a dentist has a patient with dysphagia, he must be a member oftreatment team for dysphagia and must have contact with other professions. Therefore, terminology about dysphagia is important matter in the treatment team.Mastication and swallowing are most important portions in a series of eating behaviors. However these objects had been studied as discrete objects. Past studies showed swallowing had 5 stages, anticipatory, preparatory, oral, pharyngeal, and esophageal stage. This model explained movement of water swallowing well, but couldn't be an explanation for another situation of swallowing. Recent studies have shown other models of swallowing, for example, swallowing after mastication and sequential swallow. These studies showed that normal swallowing has some varieties.The effect for our educational program about swallowing and dysphagia was shown. Many of the students could evaluate precisely some dysphagic problem after the program. Dentists should be a professional for oral problem, and should play a bigger role for a treatment of dysphagia.