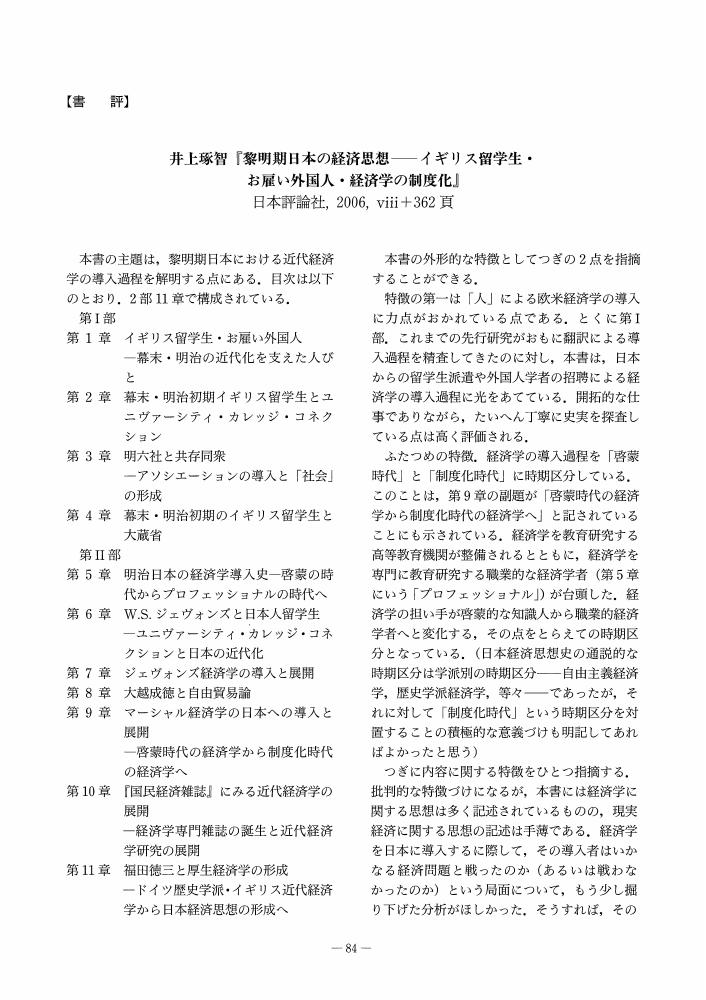1 0 0 0 粗骨材の品質がコンクリートの乾燥収縮ひずみに与える影響
- 著者
- 藤井隆史 丁上 谷口高志 綾野克紀
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2023(九州)
- 巻号頁・発行日
- 2023-06-16
本論文では,47種類の粗骨材を用いてコンクリートを作製し,粗骨材の品質がコンクリートの乾燥収縮に与える影響の検討を行った。吸水率の大きい砕石を用いるほど,コンクリートの乾燥収縮ひずみは大きくなる。火成岩や石灰岩の砕石を用いたコンクリートでは,骨材の品質の影響を表す係数αに4を用いた方が,土木学会コンクリート標準示方書の予測式による計算値と実験値の誤差が小さい。ただし,硫酸ナトリウムによる安定性試験における損失質量分率が大きいものは,αに6を用いた方がよい。石灰岩を除く堆積岩では,骨材の品質の影響を表す係数αに6を用いた方が,予測式による計算値と実験値の誤差が小さい。
- 著者
- 谷口高志 丁上 藤井隆史 綾野克紀
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2023(九州)
- 巻号頁・発行日
- 2023-06-16
本論文では,49種類の粗骨材を用いてコンクリートを作製し,粗骨材の品質および微粒分がコンクリートの凍結融解抵抗性に与える影響の検討を行った。骨材表面に付着する微粒分を完全に除去した状態で用いた場合には,硫酸ナトリウムによる安定性試験における損失質量分率が12%を超える堆積岩の砕石を用いたコンクリートでは,凍結融解抵抗性が低下する傾向が確認された。一方,JIS規格を満足する粗骨材であっても,粗骨材表面に微粒分が付着したままの状態でコンクリートを作製した場合には,凍結融解抵抗性が低下する可能性がある。
1 0 0 0 OA 日本の財政の持続可能性について ―H. Bohnの手法による再検証
- 著者
- 藤井 隆雄
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.97-117, 2010 (Released:2022-07-15)
- 著者
- 蓑輪 圭祐 下村 匠 川端 雄一郎 藤井 隆史 富山 潤
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造) (ISSN:21856567)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.134-149, 2021 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
温湿度,降雨,日射の環境作用がコンクリートの乾燥収縮に及ぼす影響を把握するため,同時に作製した角柱試験体を全国 4 地点で屋外暴露し,水分量と収縮量の経時変化を測定した.その結果,各地の一年間の収縮量はほぼ同等であったが,季節ごとの収縮の進行が異なることが明らかとなった.温湿度の変動・日射・降雨の影響を考慮できるコンクリートの水分移動および収縮に関する数値解析法を用いた検討により,湿度の変動と降雨が収縮量に及ぼす影響が大きいことを明らかにした.湿度の変動と降雨の影響を考慮する係数を平均湿度と降雨時間割合から算出し,平均湿度に乗じた見かけの相対湿度を乾燥収縮予測式に用いることで,屋外におけるコンクリートの収縮を簡易的に予測できることを示した.
1 0 0 0 Quantifying the Impact of the Tokyo Olympics on COVID-19 Cases Using Synthetic Control Methods
- 著者
- 報告者:江阪 太郎 藤井 隆雄 (1. 神戸市外国語大学 2. 神戸市外国語大学) 討論者:佐々木 周作 (東北学院大学)
- 雑誌
- 日本経済学会2022年度春季大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-03-22
1 0 0 0 OA 立位姿勢の足底圧中心位置の違いが着座動作の姿勢制御に与える影響について
- 著者
- 藤井 隆太 高木 綾一 山口 剛司 高崎 恭輔 大工谷 新一 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.85-94, 2008 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this study was to investigate the effect of differences of the foot center of pressure in standing on postural control of stand-to sit movement. It was thought that the reverse reaction phenomenon of standing posture in normal subjects at the fist of the sitting movement start by reduction of the muscle activity of the lumbar back muscles. Stable stand-to-sit movement was able to be performed when COP was located forward. From this, the position of foot COP in standing before stand-to-sit movement influences the difficulty of adjustment of COP and COG. Therefore, we suggest that in order to improve stand-to-sit movement, it is important to evaluate foot COP in the standing posture and muscle activity of the lumbar back muscles.
- 著者
- 蓑輪 圭祐 下村 匠 川端 雄一郎 藤井 隆史 富山 潤
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.134-149, 2021
- 被引用文献数
- 2
<p> 温湿度,降雨,日射の環境作用がコンクリートの乾燥収縮に及ぼす影響を把握するため,同時に作製した角柱試験体を全国 4 地点で屋外暴露し,水分量と収縮量の経時変化を測定した.その結果,各地の一年間の収縮量はほぼ同等であったが,季節ごとの収縮の進行が異なることが明らかとなった.温湿度の変動・日射・降雨の影響を考慮できるコンクリートの水分移動および収縮に関する数値解析法を用いた検討により,湿度の変動と降雨が収縮量に及ぼす影響が大きいことを明らかにした.湿度の変動と降雨の影響を考慮する係数を平均湿度と降雨時間割合から算出し,平均湿度に乗じた見かけの相対湿度を乾燥収縮予測式に用いることで,屋外におけるコンクリートの収縮を簡易的に予測できることを示した.</p>
- 著者
- 瀧口 響 森脇 拓也 藤井 隆史 綾野 克紀
- 雑誌
- 令和3年度土木学会全国大会第76回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2021-05-18
1 0 0 0 砕石の品質がコンクリートの乾燥収縮ひずみに与える影響
- 著者
- 藤井 隆史 臧 洪祥 瀧口 響 綾野 克紀
- 雑誌
- 令和3年度土木学会全国大会第76回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2021-05-18
1 0 0 0 けい酸塩系表面含浸材のスケーリング抑制効果に及ぼす施工方法の影響
- 著者
- 森脇拓也 大西豊 藤井隆史 綾野克紀
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2021(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-05
- 著者
- 藤井隆史 下村匠
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2021(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-05
- 著者
- 藤井 隆至
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.p259-290, 1993-11
本稿は,雑誌『郷土研究』がどのような主題をもち,どのような方法でその主題を分析していったかを解明する。この雑誌は1913年から1917年にかけて発行された月刊誌で,柳田国男はここを拠点にして民間伝承を収集したり自分の論文を発表したりする場としていた。南方熊楠からの質問に対して,この雑誌を「農村生活誌」の雑誌と自己規定していたが,それでは「農村生活誌」とは何を意味するのであろうか。彼によれば,論文「巫女考」はその「農村生活誌」の具体例であるという。筆者の見解では,「巫女考」の主題は農村各地にみられる差別問題を考究する点に存していた。死者の口寄せをおこなうミコは村人から低くみられていたけれども,柳田はミコの歴史的系譜をさかのぼることによって,「固有信仰」にあってミコは神の子であり,村人から尊敬されていた宗教家で,その「固有信仰」が「零落」するとともに差別されるようになっていったという説を提出している。差別の原因は差別する側にあり,したがって差別を消滅させるためには,すべての国民が「固有信仰」を「自己認識」する必要があるのであった。その説を彼は「比較研究法」という方法論で導きだしていた。その方法論となったものは,認識法としては「実験」(実際の経験の意)と「同情」(共感の意)であり,少年期から学んでいた和歌や学生時代から本格的に勉強していた西欧文学をもとにして彼が組み立ててきた認識の方法である。もう一つの方法論は論理構成の方法で,帰納法がそれであるが,数多くの民間伝承を「比較」することで「法則」を発見しようとする方法である。こうした方法論を駆使することによって彼は差別問題が生起する原因を探究していったが,彼の意見では,差別問題を消滅させることは国民すべての課題でなければならなかった。換言すれば,ミコの口寄せを警察の力で禁止しても差別が消滅するわけではなく,差別する側がミコの歴史を十分に理解することが必要なのであった。This paper elucidates what were the main subjects handed by the journal "Kyōdo Kenkyū (Studies of native lands)", and by what methods the subjects were analyzed. The "Kyōdo Kenkyū" was a monthly review issued from 1913 to 1917, which Yanagita Kunio used as a base for collecting folk tales and publishing his theses. In reply to a question posed by Minakata Kumagusu, he defined the periodical as a "journal of life in farming villages". Then, what did a "journal of life in farming villages" mean? According to Yanagita, his paper entitled "Study on Psychic Mediums" was a concrete example of the "journal of life in farming villages".In the opinion of the author, the main theme of his "Study on Psychic Mediums" lay in the examination of the problem of discrimination which was seen in farming villages everywhere. Mediums, who performed necromancy with the dead, were looked down upon by village people. However, tracing their historical lineage, Yanagita argued that mediums had been the children of gods in "the native belief", and religionists looked up to by village people, but came to be discriminated against as "the native belief" "went to ruin". The cause of the discrimination lay with the discriminators, and so, in order to eliminate discrimination, the whole nation should "realize for themselves" "the native belief".He came to this opinion by a methodology called "comparative study". The methodology came as epistemology from "jikken (actual experience)" and "dōjō (sympathy)" and was a method of understanding he built up based on the Japanese poems that he had studied since he was a boy, and the West-European literature he had studied earnestly since he was a student. Another methodology was the method of logical construction or the inductive method. It was a method to try to discover "rules" by the "comparison" of many folk tales.Making full use of these methodologies, Yanagita searched for causes from which the problem of discrimination arose. In his opinion, elimination of the problem of discrimination had to be a subject tackled by the whole nation. In other words, discrimination could not have been eliminated simply by the prohibition of necromancy by police power; a full understanding of the history of mediums on the part of the discriminators was essential.
1 0 0 0 OA 1.自己抗体
- 著者
- 藤井 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.10, pp.2395-2400, 2014-10-10 (Released:2015-10-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
膠原病において臨床的意義を有する自己抗体は多く報告されてきた.多発性筋炎/皮膚筋炎では自己抗体により予後推定が可能で,しばしば致命的となる急性~亜急性間質性肺炎と抗MDA5抗体,癌合併皮膚筋炎と抗TIF1-γ抗体との関連が明確に示され,治療方針に強く影響を与えるマーカーとなっている.また,中枢神経ループスでは脳脊髄液中の自己抗体(抗NR2抗体,抗U1RNP抗体)が重要であり,病因的意義が示唆されている.
- 著者
- 藤井 隆至
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.84-85, 2007-12-25 (Released:2010-08-05)
1 0 0 0 OA 日本経済思想史: 政策学から経済学へ
- 著者
- 藤井 隆至
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.45, pp.55-65, 2004 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 108
The third report in the present series, this paper offers an analysis of important recent studies (from 1980 to the present) of Japanese economic policy and thought in the 1910's and 20's.The economy of Japan following WWI can be described particularly in terms of its emphases on scientific development and industrial production. However, this progress in industrial development led to the appearance of a widened gap between rich and poor, and one of the major issues concerning the economic thought of the time was how to improve the lot of the poorer levels of society, including workers, farmers and city dwellers.Research in the field of economics during the 1910's and 20's had as one of its focal points the attempt to alleviate this exaggerated difference between the haves and havenots. The economics of the Association for the Study of Social Policy attempted to reduce the gap between rich and poor through the implementation at a national level of specific social policies. The ineffectiveness of these policies, however, resulted in a lack of faith in the ability of the Association to do anything about the situation in a concrete way.The crumbling of the economic policies associated with this Association for the Study of Social Policy allowed for the appearance new approaches, such as the Neoclassical economics of Tokuzo Fukuda and the Marxist economics of Hajime Kawakami.The present study introduces the work of Kanae Iida and Kanji Kobayashi. Seeking an approach to the study of economics based on firmly-grounded economic theories, this paper presents and comments on the work of Kanae Iida, Mikio Nishioka, Takutoshi Inoue, Tamotsu Nishizawa, Hideomi Tanaka, who themselves each analyzed the ideas of Tokuzo Fukuda. It also introduces and comments on the work of Shiro Sugihara, who investigated the thought of Hajime Kawakami.This paper also presents the research of Kunio Yanagita, and comments on the ideas of Yoshiteru Iwamoto and Takashi Fujii, with a particular emphasis on the idea that a suitable ethical policy is critical to the success of any given economic policy.Finally, this paper reports a decline, dating from the 1980's to the present day, in the number of studies of particular economic questions and problems, accompanied by a corresponding increase in research on historical individuals. However, it suggests that the work of Aiko Ikeo and others seems to be slowly bringing about a return to a question-centered focus.
- 著者
- 藤井 隆至
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.259-290, 1993-11-10
本稿は,雑誌『郷土研究』がどのような主題をもち,どのような方法でその主題を分析していったかを解明する。この雑誌は1913年から1917年にかけて発行された月刊誌で,柳田国男はここを拠点にして民間伝承を収集したり自分の論文を発表したりする場としていた。南方熊楠からの質問に対して,この雑誌を「農村生活誌」の雑誌と自己規定していたが,それでは「農村生活誌」とは何を意味するのであろうか。彼によれば,論文「巫女考」はその「農村生活誌」の具体例であるという。筆者の見解では,「巫女考」の主題は農村各地にみられる差別問題を考究する点に存していた。死者の口寄せをおこなうミコは村人から低くみられていたけれども,柳田はミコの歴史的系譜をさかのぼることによって,「固有信仰」にあってミコは神の子であり,村人から尊敬されていた宗教家で,その「固有信仰」が「零落」するとともに差別されるようになっていったという説を提出している。差別の原因は差別する側にあり,したがって差別を消滅させるためには,すべての国民が「固有信仰」を「自己認識」する必要があるのであった。その説を彼は「比較研究法」という方法論で導きだしていた。その方法論となったものは,認識法としては「実験」(実際の経験の意)と「同情」(共感の意)であり,少年期から学んでいた和歌や学生時代から本格的に勉強していた西欧文学をもとにして彼が組み立ててきた認識の方法である。もう一つの方法論は論理構成の方法で,帰納法がそれであるが,数多くの民間伝承を「比較」することで「法則」を発見しようとする方法である。こうした方法論を駆使することによって彼は差別問題が生起する原因を探究していったが,彼の意見では,差別問題を消滅させることは国民すべての課題でなければならなかった。換言すれば,ミコの口寄せを警察の力で禁止しても差別が消滅するわけではなく,差別する側がミコの歴史を十分に理解することが必要なのであった。
- 著者
- 瀧口 響 王 亮 藤井 隆史 綾野 克紀
- 雑誌
- 令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2020-05-15
1 0 0 0 けい酸塩系表面含浸材によるひび割れ透水抑制効果に関する研究
- 著者
- 藤井 隆史 安藤 尚 森脇 拓也 綾野 克紀
- 雑誌
- 令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2020-05-15
1 0 0 0 OA ELF帯における地震電磁波観測装置の開発
- 著者
- 畑 雅恭 内匠 逸 太田 健次 井筒 潤 藤井 隆司 佐藤 時康 矢橋 清二 渡辺 伸夫
- 出版者
- Society of Atmospheric Electricity of Japan
- 雑誌
- Journal of Atmospheric Electricity (ISSN:09192050)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.37-52, 2010 (Released:2012-04-07)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
ELF (30-300 Hz) band three-axial magnetic-flux receiver was developed for detecting electromagnetic-wave precursor of earthquakes and volcanic eruption. The receiver attained a high sensitivity of 0.4pT/√Hz (223Hz) and 4.5 pT/√Hz (17Hz) for the ground based observation of the ambient magnetic flux anomaly. The receiver was extended to detect ultra-low-frequency (ULF) variation (0.1 to 10-7Hz) of crust magnetic flux by through MMD (Modulated Magnetic-flux Detection) reception. It detects the modulated components of the ELF band atmospheric signal which are produced by the crust ULF magnetic-flux variation. The receiver noise due to the artificial noise can be smoothed out from the objective ULF magnetic flux signal by introducing long term integration for the period of 107 seconds of the detected signal. The receiver detected the ULF anomaly of magnetic variation and the Schumann Resonance variation appeared before the two earthquakes of the class M7 occurred in Japan in 2005 and 2007 respectively.
1 0 0 0 OA 《第4回》: 制御の基本的性質と Riccati 方程式
- 著者
- 藤井 隆雄
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.11, pp.878-886, 1996-11-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 13