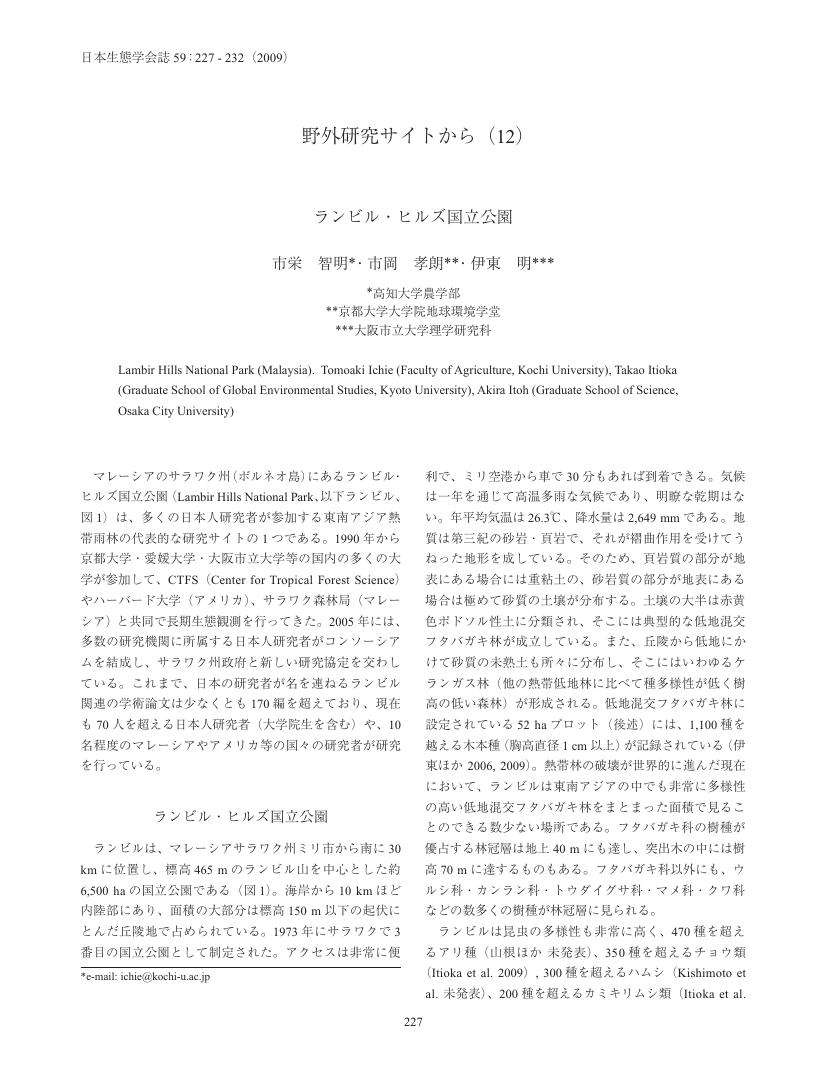1 0 0 0 OA 趣旨説明: DNAメタバーコーディングによる野生動物の食性解析手法
- 著者
- 安藤 温子 小村 健人 向井 喜果 安藤 正規 井鷺 裕司
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.71-75, 2020 (Released:2020-05-21)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 日本生態学会誌に求められる役割
- 著者
- 永光 輝義
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.1, 2021 (Released:2021-04-02)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA ランビル・ヒルズ国立公園(<連載1>野外研究サイトから(12))
- 著者
- 市栄 智明 市岡 孝朗 伊東 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.227-232, 2009-07-31 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 群集生態学の最近の動向について : 平衡と非平衡群集
- 著者
- 武田 博清
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.41-53, 1986-04-30 (Released:2017-05-24)
The balance of nature has been a background concept in community ecology. In contrast to the concept, the variability of biological populations has been appreciated in mature, such as in outbreak and extinction of species. The two concepts have been transformed into density dependent and density independant regulation in population dynamics and then into equilibrium and non-equilibrium community theories. The competition-equilibrium community theory has been advanced in the empirical and theoretical studies of community and has explained the community organization by the niche theory. The non-equilibrium community theory has argued the importance of non-equilibrium conditions of populations in nature and the reconsideration of community organization from the individualistic or auto-ecological studies of populations constituting communities. The two theroies represent the opposite ends in the continuum of the community patterns in the nature. In the recent 20 years, community ecology has advanced in the diversity studies, competitive-equiliblium and non-equilibrium community theories and now is entering a new stage over these past community studies.
1 0 0 0 OA 釧路湿原大島川周辺におけるエゾシカ生息痕跡の分布特性と時系列変化および植生への影響
- 著者
- 冨士田 裕子 高田 雅之 村松 弘規 橋田 金重
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.143-153, 2012-07-30 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 9
近年、ニホンジカの個体数の急激な増加により、各地で自然植生に対する様々な影響が現れている。森林に対する影響の報告が多いのに対し、踏査等が困難な湿原へのシカの影響については報告が少ないのが現状である。そこで北海道東部の釧路湿原中央部の大島川周辺をモデルサイトとし、2時期に撮影された空中写真からGISを使用してエゾシカの生息痕跡であるシカ道を抽出し、その変化と分布特性を調べた。さらに、現地で植生調査を行い、調査時よりエゾシカの密度が低かったと考えられる5年前の植生調査結果との比較を行った。また、植生調査区域でエゾシカのヌタ場の位置情報と大きさの計測を行った。その結果、調査範囲62.2ha内のシカ道の総延長は、1977年に53.6kmだったものが2004 年には127.4kmとなり、約2.4倍の増加が認められた。ヌタ場は、2時期の空中写真の解析範囲内では確認されなかったが、2009年の現地調査では大島川の河辺に11ヶ所(合計面積759m2)形成されていた。以上から、大島川周辺では30年間でエゾシカの利用頻度が上昇し、中でも2004年以降の5年間でシカ密度が急増したと考えられた。両時期とも川に近いほどシカ道の分布密度が高く、ヌタ場は湿原内の河川蛇行部の特に内側に好んで作られていた。蛇行の内側は比高が低く、川の氾濫の影響を受けやすいヌタ場形成に都合のよい立地であることに加え、エゾシカの嗜好性の高いヤラメスゲが優占する場所で、えさ場としても利用されていた。大島川周辺には既存のヨシ-イワノガリヤス群落、ヨシ-ヤラメスゲ群落が分布していた。ただし、河辺のヌタ場付近にはヤナギタデ群落が特異的に出現し、DCA解析からこの群落はエゾシカの採食、踏圧、泥浴びなどの影響で、ヨシ-ヤラメスゲ群落が退行して形成された代償植生であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 社会性狩りバチにおける血縁認識 (<特集>社会性昆虫における認識機構とカースト分化機構)
- 著者
- 熊野 了州 粕谷 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.183-191, 1999-08-25 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 56
1 0 0 0 OA 日本に自生している針葉樹の耐凍度とそれらの分布との関係
- 著者
- 酒井 昭 倉橋 昭夫
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.192-200, 1975-12-31
- 被引用文献数
- 5
Dormant one-year-old twigs were collected from the mature and young plants of a number of conifer species cultivated at Yamabe, Hokkaido, and other places during midwinter, these were artificially hardened at sub-freezing temperatures to overcome differences in site of collection and to induce maximum freezing resistance. In most of the species distributed in the sub-alpine and sub-cold zones, the leaves and the twigs resisted freezing to -70℃ or below, while most of the species distributed in the temperate zone resisted freezing to only about -30℃, and the leaves and the twigs were found to be nearly equally hardy unlike the conifers distributed in sub-alpine and sub-cold zones. Also, most of these temperate conifers were observed not to be grown in a severe cold climate in Hokkaido. Thus, in the conifers distributed in the temperate zone, winter minimal temperatures appear to be the principal factor governing their growth in severe cold climates. A marked variation in hardiness was not observed among the pines Pinus denslflora and Pinus thunbergiana from different provenances.
1 0 0 0 OA 多様度指数間の相関関係 : 各種の指数値は何を表すか
- 著者
- 伊藤 秀三
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.187-194, 1990-12-31 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 2
Correlations among nine indices of species diversity, HURLBERT's S(100), ITOW's b, FISHER's α, three varieties of SIMPSON's d, MCINTOSH's index, SHANNON's H', and PIELOU's J', were studied using measurements taken in 57 forests, from the humid tropical to the humid warm-temperate regions of East Asia, Pacific islands and Amazonian upstream. The indices were categorized into two groups according to their correlations. In first group, consisting of S(100), b, α and 1/d, values are sensitive to changes in species richness. (1-d), (1-d)/(1-d)max, MCINTOSH's index, H' and J' belong to the second group. The indices studied showed intra-but not inter-group correlation. The number of species occurring once in the community is significantly correlated with FISHER's α.
1 0 0 0 OA 季節適応としての昆虫の表現型可塑性
- 著者
- 石原 道博 世古 智一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.27-32, 2007-03-31 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
表現型可塑性は、昆虫では翅多型や季節型および光周期による休眠誘導などの現象として一般的に知られ、季節適応にきわめて重要な役割を果たしている。これらの可塑性は異なる季節に出現する世代の間で見られ、季節的に変動する環境条件に多化性の昆虫が適応した結果、進化したと考えられている。しかしながら、これまでの研究は、可塑性が生じる生理的メカニズムについて調べたものばかりが目立ち、適応的意義まで厳密に調べた研究は少ない。表現型可塑性に適応的意義があるかどうかを明らかにすることは、表現型可塑性の進化を考えるうえでも重要なことである。この総説では、イチモンジセセリとシャープマメゾウムシの2種の多化性昆虫を対象に、世代間で見られる表現型可塑性が寄主植物のフェノロジーに適応したものであることを紹介する。シャープマメゾウムシでは、春に出現する越冬世代成虫は繁殖よりも寿命を長くする方向に、夏や秋に出現する世代の成虫は寿命よりも繁殖に多くのエネルギーを配分している。イチモンジセセリでは、秋に出現する世代のメス成虫は春および夏に出現する世代のメス成虫に比べてかなり大きな卵を産む。また、この世代が野外で遭遇する日長・温度条件下で幼虫を飼育すると、他の世代のものよりも大卵少産の繁殖配分パターンを示す。これらの表現型可塑性は、世代間で生活史形質問のエネルギー配分量の割合が変化するものであり、寄生植物のフェノロジーおよび寄主植物の質の季節変化に対する適応と考えられる。
1 0 0 0 OA 水辺生態系の物質輸送に果たす遡河回遊魚の役割
- 著者
- 帰山 雅秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.51-59, 2005-04-25 (Released:2017-05-27)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 7
The consequences of nutrient loss (oligotrophication) and attendant low productivity on biodiversity and productivity in the ecosystem has recently invoked the interest of researchers, as result of loss of wild anadromous fish by acceleration of urbanization and deterioration of natural riparian ecosystem such as dam construction, habitat destruction, and artificial hatchery program. In Japan, chum salmon (Oncorhynchus keta) have been mass-produced by hatchery program, while numerous wild Pacific salmon have been almost extinguished by a combination of the urbanization and the deterioration of riparian ecosystem. This review focuses on effects of anadromous fish on biodiversity and productivity in the riparian ecosystem with relation to dynamics of nutrient, biofilm, aquatic insects, salmonids, terrestrial animals, and human activity, and isotopic evidence for enrichment of salmon-derived nutrients. Anadromous fish are key species for sustaining production and biodiversity in the riparian ecosystem. For sustainable conservation management of riparian ecosystem, the rehabilitations of wild salmon population, system of material cycle, and natural rivers are critical important issues in Japan.
- 著者
- 深澤 圭太 石濱 史子 小熊 宏之 武田 知己 田中 信行 竹中 明夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.171-186, 2009-07-31 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 10
野外の生物の分布パターンは生育に適した環境の分布や限られた移動分散能力などの影響をうけるため、空間的に集中した分布を持つことが多い。データ解析においてはこのような近隣地点間の類似性「空間自己相関」を既知の環境要因だけでは説明できないことが多く、近い地点同士ほど残差が類似する傾向がしばしば発生する。この近隣同士での残差の非独立性を考慮しないと、第一種の過誤や変数の効果の大きさを誤って推定する原因になることが知られているが、これまでの空間自己相関への対処法は不十分なものが多く見られた。近年、ベイズ推定に基づく空間統計学的手法とコンピュータの能力の向上によって、より現実的な仮定に基づいて空間自己相関を扱うモデルが比較的簡単に利用できるようになっている。中でも、条件付き自己回帰モデルの一種であるIntrinsic CARモデルはフリーソフトWinBUGSで計算可能であり、生物の空間分布データの解析に適した特性を備えている。Intrinsic CARモデルは「空間的ランダム効果」を導入することで隣接した地点間の空間的な非独立性を表現することが可能であると共に、推定された空間的ランダム効果のパターンからは対象種の分布パターンに影響を与える未知の要因について推察することができる。空間ランダム効果は隣接した地点間で類似するよう、事前分布によって定義され、類似の度合いは超パラメータによって制御されている。本稿では空間自己相関が生じるメカニズムとその問題点を明らかにした上で、Intrinsic CARモデルがどのように空間自己相関を表現しているのかを解説する。さらに、実例として小笠原諸島における外来木本種アカギと渡良瀬遊水地における絶滅危惧種トネハナヤスリの分布データへの適用例を紹介し、空間構造を考慮しない従来のモデルとの比較からIntrinsic CARモデルの活用の可能性について議論する。
1 0 0 0 OA 適応的な表現型可塑性による複数ハビタット利用とハビタット選択
- 著者
- 工藤 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.66-70, 2007-03-31 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
ハビタットの環境が大きく変わると、適応度が大幅に低下する可能性がある。適応的な表現型可塑性は、環境変動に際して適応度の低下を防ぐ働きがある。本稿では、適応的な表現型可塑性の機能として、複数ハビタット利用とハビタット選択とがあることを指摘した。複数ハビタット利用では、それぞれのハビタットでの適応度を高めるような表現型を可塑性によって実現する。ハビタット選択では、不適な環境を回避し好適な環境を利用するような形質変化が可塑性によってもたらされる。複数ハビタット利用の例としては、両生類の対捕食者誘導防御・昆虫の季節多型・水生植物の陸生型形成などがある。また、ハビタット選択の例としては、昆虫の相変異に伴う飛翔多型・休眠による季節適応・植物の被陰回避反応・開花調節などがある。
- 著者
- 松村 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.179, 2022 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
移動は雄の繁殖に多大な影響を与える。移動活性の高い雄は多くの雌と遭遇することが可能であるため、交尾成功度が増加すると予想される。その一方で、移動活性の低い雄は雌との遭遇頻度が低い分、交尾後の受精成功度の増加のための投資量が多いと予想される。昆虫において、脚は移動のみならず、交尾の際にも使用される重要な付属肢としての役割も持ち、様々な種で脚の形態に性的二型が見られる。雄の脚において、移動に有利な形態は、交尾時の雌の把握では不利になる可能性もあり、雄の脚は様々な選択圧のバランスによって形作られていることが推測される。受精成功度への投資量が多い移動活性が低い雄は、移動活性の高い雄とは異なる形態の脚を持つことが予想される。本研究では、コクヌストモドキTribolium castaneum Herbstを対象として、歩行活性に対する人為選抜への繁殖形質や脚の形態の反応について調査を行った。その結果、移動活性の低い方向へ選抜された系統の雄は、移動活性の高い系統の雄よりも脚が有意に長いことが明らかとなった。長い脚を持つ雄は、交尾時の雌からの抵抗に耐えることを可能とし、交尾時間の延長による受精成功度の増加において有利であることが示唆された。筆者らによる研究の結果から、脚の性的サイズ二型の進化やその度合いに種間変異が見られる現象についても議論したい。
1 0 0 0 OA 西太平洋湿潤地域の植生帯と針葉樹優占の生物地理学
- 著者
- 相場 慎一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.313-321, 2017 (Released:2017-12-05)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 4
日本から台湾・東南アジア島嶼部・ニューギニア・オーストラリア東岸を経てタスマニアとニュージーランドに至る西太平洋湿潤地域では、巨視的に見ると、寒冷な気候で針葉樹と落葉広葉樹が優占し、温暖な気候では常緑広葉樹が優占する。ただし、針葉樹が優占する植生帯は、北半球だけに存在する「落葉広葉樹林」(暖かさの指数、WI=45〜85℃、寒さの指数、CI<−15℃)を挟んで、「北方針葉樹林」と南北両半球にまたがる「温帯・熱帯針広混交林」という2つの森林帯に別れている。北方針葉樹林は夏が短く冬が厳しい大陸性気候(WI=15〜45℃、CI<−15℃)に成立するのに対し、両半球にまたがる温帯・熱帯針広混交林は寒い冬を欠く海洋性気候(WI<144℃、CI>−15℃)に成立する。さらに、熱帯低地を中心とするWI>144℃の地域には「熱帯・亜熱帯常緑広葉樹林」が分布し、西太平洋湿潤地域の森林帯は以上4つに大別される。北方針葉樹林は日本の高緯度または高標高に分布し、亜高山帯林や亜寒帯林とも呼ばれる。温帯・熱帯針広混交林は、日本では太平洋側の狭い標高帯に限って分布する(いわゆるモミ・ツガ林など)が、台湾やニュージーランドではより広い標高帯に渡って(より暖かい気候にまで)分布する。これら両半球の温帯針広混交林は、東南アジアやニューギニアの熱帯山地の針広混交林へと連続的に変化していく。以上のことから、針葉樹が優占する温帯・熱帯林を総称して、北方針葉樹林とは独立した、温帯・熱帯針広混交林と名付けたのである。温帯・熱帯針広混交林では、比較的涼しい夏(熱帯山地では年を通じた低温)が常緑広葉樹の生育を制限する一方、温暖な冬(熱帯山地では冬がないこと)が落葉広葉樹の生育を制限することで、針葉樹が優占しているのであろう。巨視的に見た時に針葉樹が寒冷な気候で優占することは、土壌の貧栄養条件と関連している可能性があり、広葉樹が優占する気候帯であっても貧栄養土壌上では局所的に針葉樹が優占しうることは、その可能性を支持する。西太平洋地域と世界各地を比較すると、東太平洋地域で2つの針葉樹林帯が連続するのと対照的であることを指摘した。
- 著者
- 名取 俊樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.183-189, 2008-11-30 (Released:2016-09-17)
- 参考文献数
- 18
氷河期からの遺存種であるキタダケソウ(Callianthemum hondoense Nakai et Hara)は、北岳(南アルプス北部、山梨県)の南東斜面のみに生育する固有種であり、将来、地球温暖化の影響などにより、その存続が危惧されている。そこで、公表されている気象資料やキタダケソウに関する資料の整理、キタダケソウの満開日や生育場所の土壌pH、消雪時期の野外調査を行った.そして、富士山頂での年平均気温が20世紀後半から上昇していること、また、キタダケソウの満開日の経年変化や、キタダケソウの生育場所の土壌pHと消雪時期の特性を明らかにした。それらの結果をもとに、キタダケソウに及ぼす地球温暖化の影響について考えた。
1 0 0 0 OA トビムシと微生物のリンク(<特集2>土壌生態学の新展開)
- 著者
- 金田 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.217-225, 2004-12-25 (Released:2017-05-26)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 OA ブナ・ミズナラ林における遷移過程の解析
- 著者
- 野本 宣夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.102-107, 1956-12-31 (Released:2017-04-07)
- 被引用文献数
- 1
The deciduous broadleaved forests dominated by beech (Fagus crenata) and oak (Quercus crispula) are found widely in the cool temperate mountains of Japan. The oak forest has been regarded as a seral forest succeded by the beech climax forest. 1) Three stands in the beech-oak forests of Okutama near Tokyo were researched comparatively by the author, and the process of ruin and rise between the oak and beech is illustrated in Fig. 2. The typical beech forest (C) might be regarded as stable for a long time, because there grew a great number of young beeches, while the oak forest (A) is regarded as unstable because it had none of its own inheritors, but beech ones. This fact shows clearly that the oak forest would be gradually succeeded by the beech forest with the progress of time. 2) In order to analyse such a process of succession mentioned above, the author applied the analytical method of MONSI and OSHIMA (1955). On the basis of the mutual action between the main physiological action of plants (production of matter-photosynthesis) and the main environmental condition in a forest (light intensity), the height-growth curves of young trees of oak and beech in the forest communities of various densities were calculated and drawn as shown Figs. 6 and 7. The fact of young trees under the Sasa-layer in the forest was also discussed.
1 0 0 0 OA 昆虫のオスにおける脚の誇張化とテナガショウジョウバエの闘争
- 著者
- 工藤 愛弓
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.157, 2022 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 67
昆虫の中には、性淘汰によって進化した誇張化形質を有する種がいる。体のどの部分が誇張化するかは種によって様々である。性淘汰によって誇張化する部位やその程度は、生息環境や餌、配偶相手および縄張りなどの資源を巡る闘争の形式とその強度、繁殖行動への利用の有無と密接に関連している。そのため、性淘汰に伴い誇張化した形質がどのように進化・維持されてきたのかを明らかにするには、それぞれの種が有する生活史についても理解を深める必要がある。著者がこれまで扱ってきたテナガショウジョウバエは、オスのみが誇張化した前脚を有し、オス間闘争やメスへの求愛に利用することが分かっている。一方で、野外における生態の理解は進んでいない。ハエ目において、テナガショウジョウバエのように脚を同性間闘争の武器として利用していることが分かっている例は極めて少ない。テナガショウジョウバエのオスにおける前脚の誇張化に影響を与えた要因を探ることで、他のハエ目昆虫で脚が武器として利用されない理由を明らかにできるかもしれない。本稿では、昆虫綱に属する種のうち、脚に性的二型性を有する種について、生息環境や食性・産卵基質などの生態との関連から、性淘汰に伴う脚の誇張化の理由を考察した。また、テナガショウジョウバエの形態と行動の種間差や系統間変異について紹介するとともに、現在進めている闘争と生活史形質との関連性についても概説する。これまでに組み立てられてきた精密な行動評価システムに加えて、今後は生活史形質や野外での生態を明らかすることで、テナガショウジョウバエが有するユニークな形質の進化メカニズムが明らかになることを期待している。
1 0 0 0 OA ガン細胞に見るクローン増殖と適応進化 ―細胞の特殊性とクローン生物との共通性を考える―
- 著者
- 荒木 希和子 福井 眞 杉原 洋行
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.169-180, 2017 (Released:2017-08-03)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 2
質を示すのは良性腫瘍である。また、悪性腫瘍(ガン)は、自らゲノムを改変したサブクローンを作り、そのニッチ幅もしくは環境収容力を広げることによって、周辺組織や他臓器に適応し、浸潤・転移する。これは細菌以外の生物個体レベルでは知られていない特異的な進化メカニズムである。マクロな生物の成育環境と同様、ガン細胞も変動環境下に存在し、治療や免疫は生体内での細胞に対する攪乱と捉えられる。そして、腫瘍細胞に突然変異等の遺伝的変化が蓄積するに伴い、ゲノム構成もサブクローン間で異なってくる。この遺伝的変化の時間的進行は、クローン性進化の分岐構造として、系統樹のような分岐図として示すことができる。組織内でのガン細胞の空間的遺伝構造は、組織内や成育地内で環境の不均一性とサブクローンの限られた分散距離を反映し、サブクローンがパッチ状に分布した構造になっている。このように、細胞レベルのクローン性の特性を生物のクローン性と比較することで、両分野に新たな研究の進展をもたらすことが期待される。
1 0 0 0 OA 行動傾向の一貫した個体差と個体の発達変化の統合的理解に向けて
- 著者
- 酒井 理
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.55-64, 2020 (Released:2020-05-21)
- 参考文献数
- 68
近年の動物行動学では行動傾向の一貫した個体差に高い関心が注 がれ、幅広い分類群の動物種において個性の形成要因の探求や評 価手法の確立が進められてきた。しかしながら、発達的な観点が 当該分野の理解を複雑にしており、時間的に安定した個体差を扱 う「個性」と発達的な個体変化を扱う「発達可塑性」では互いに 概念の混乱を招いてきた。本稿では、発達的な観点が個性研究に おいてどのように扱われているかを俯瞰し、行動傾向の一貫した 個体差と個体の発達変化を統合的に扱う枠組みを紹介する。さら に、発達的な観点から個性を扱っている研究例を概観し、そこか ら見えてきた傾向や今後の展望について議論する。概念としては、 対象動物の生活史に基づいて一貫性を評価し、発達段階の変化し ない短期間における個性の存在と、重要な生活史イベントをまた ぐような長期間における個性の安定性とを区別することが重要で ある。また、発達的な観点から個性を扱うには、行動傾向の平均 値、個性の構造、個性の安定性の3点を意識することが有用となっ てくる。さらに、当該分野の文献調査から、様々な動物種におい て個性とその構造が発達段階をまたいで安定していないという傾 向が見受けられた。この結果は、個性は短期的には安定なものだ が長期的には不安定なものとして捉えることの重要性を提起する ものである。しかし現状では、個性の発達変遷や発達段階特異的 な構造に一般的な法則を見出すことが難しく、更なる知見の蓄積 と整理が必要である。