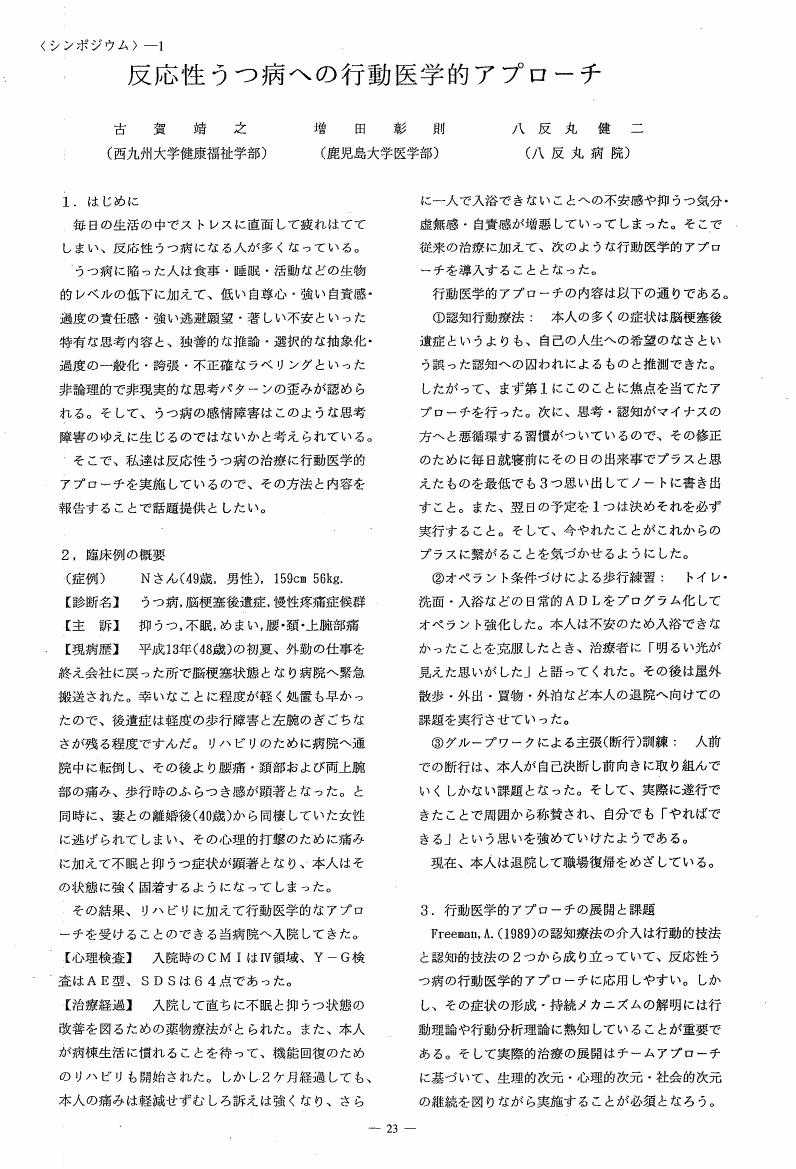1 0 0 0 OA 病棟看護師における感情労働とワーク・エンゲイジメントおよびストレス反応との関連
- 著者
- 加賀田 聡子 井上 彰臣 窪田 和巳 島津 明人
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.83-90, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 39
看護師を対象に、感情労働による心理学的影響を調べた近年の先行研究では、感情労働がバーンアウト/抑うつの悪化や職務満足感の向上に影響を与えることが着目されている。しかし、日本の看護師を対象に感情労働の心理学的側面に着目した先行研究は少なく、感情労働を要素別に分類し、ワーク・エンゲイジメントやストレス反応との関連を検証した研究は、我々の知る限り見当たらない。そこで本研究では、日本の看護師を対象に「看護師の感情労働測定尺度:ELIN」を用いて感情労働の要素を詳細に測定し、これらの各要素とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討することを目的とした。関東圏内の1つの総合病院に勤務する女性病棟看護師306名を対象に、感情労働(ELIN:「探索的理解」、「ケアの表現」、「深層適応」、「表層適応」、「表出抑制」の5下位尺度からなる)、ワーク・エンゲイジメント(The Japanese Short Version of the Utrecht Work Engagement Scale:UWES-J短縮版による)、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応(職業性ストレス簡易調査票:BJSQによる)、個人属性(年齢、診療科、同居者の有無)に関する質問項目を含めた自記式質問紙を用いて調査を実施した(調査期間:2011年8~9月)。分析は、感情労働とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討するため、感情労働の各下位尺度を独立変数、ワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応を従属変数、個人属性を調整因子とした重回帰分析を実施した。重回帰分析の結果、感情労働の構成要素の一つである「探索的理解」とワーク・エンゲイジメントとの間に正の関連が、「表出抑制」とワーク・エンゲイジメントとの間に負の関連が認められた。また、感情労働の構成要素の一つである「深層適応」と心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との間に正の関連が認められた。これらの結果から、「探索的理解」を高め、「表出抑制」や「深層適応」を低減させるようなアプローチによって、看護師が自身の感情をコントロールしながらも、心身の健康を保持・増進するために有効な可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 一過性の有酸素運動が唾液中コルチゾールの分泌に与える影響に関する予備的検討
- 著者
- 荒井 弘和 岡 浩一朗 竹中 晃二
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.30-35, 2009 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 26
現在、運動心理学において、精神神経免疫学に関する測定指標に注目が集まっている。そこで、本研究の目的は、一過性の有酸素運動が唾液中コルチゾール分泌に与える影響を予備的に検討することとした。本研究では、10名の対象者(平均年齢24.50±2.68歳;男性5名/女性5名)が招集され、(1) 自転車エルゴメータを用いた中等度の強度による20分間のサイクリングを行う条件と、(2) 20分間の読書を行うコントロール条件という、2つのカウンタ・バランスされた実験条件を行った。全ての対象者は、インフォームド・コンセントシートに署名した。唾液中のコルチゾール濃度は、各実験条件の前後に測定され、唾液中のコルチゾール濃度は、放射免疫測定法(radioimmunoassay: RIA)によって分析された。本研究は、2(条件:運動/コントロール)×2(時間:前/後)の対象者内要因計画である。繰り返しのある分散分析は、条件の主効果、時間の主効果、および交互作用を示さなかった。結論として、本研究では、一過性の有酸素運動はコルチゾール濃度を変化させない可能性が示された。
1 0 0 0 OA 冠動脈疾患と社会経済的要因 —メカニズムと予防の視点から—
- 著者
- 坪井 宏仁 近藤 克則 金子 宏 山本 纊子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-7, 2011 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 46
心疾患は、本邦では悪性新生物に次ぐ死因の第2位を占め、その多くが「冠動脈疾患(coronary heart disease, CHD)」である。CHDのリスクファクターとして、高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣に基づくものが一般に知られているが、心理的・社会的・経済的因子も無視できない。多くの欧米諸国では長年にわたり心疾患が死因の第1位であるため、その原因と予防に関する研究も多く、CHDと心理的社会的因子や社会経済的因子に関する研究結果が多く得られている。わが国でもライフスタイルの変化により動脈硬化病変がさらに増加し、CHD罹患率やそれによる死亡率の上昇することが予測される。その予防において、個人の生活習慣以外にCHDの重要なリスクファクターである社会経済的要因を把握することも重要であろう。わが国は、高度成長時代を経て平等と言われる社会を築いてきたが、1990年代後半以降は個人間の社会経済的格差が広がっている。その変化の長短は視点によって異なるところであろうが、社会経済的格差が健康に影響を及ぼすのであれば、格差の変革が疾病予防にもつながるはずである。そこで本稿では、CHDと社会経済的状況(socioeconomic status, SES)の関係について、まず両者の関係を述べ、次に両者をつなぐメカニズムを主に心理社会的側面から触れ、最後にCHD予防の可能性を社会的側面から考察した。CHDは、冠動脈壁に経年的に形成される内膜の肥厚病変とその破裂により発生し、原因は酸化・炎症や交感神経系の亢進などである。一方、SESは収入・教育歴・職業(職の有無、職場での立場も含む)などから成り、さまざまな経路でCHDに影響すると考えられる。健康行動はSESによって差があり、高SES層ほど健康によい行動を取る傾向にある。その差が、健康増進資源・医療へのアクセスの違いにつながり、CHDの発症および予後に影響する。次に、心理社会的経路であるが、この経路では、心理的・社会的特性の差異が自律神経・内分泌・免疫系を介してCHDの成因に影響する。低SES層には、慢性ストレスやライフイベントが多く、抑うつ傾向・怒り・攻撃性・社会的孤立などが認められる一方、高SES層ではコントロール感や自己実現感が高い。このような差違が、視床下部-下垂体-副腎皮質(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)系または交感神経-副腎髄質(sympathetic-adrenal-medullar, SAM)系を介し、炎症・酸化・血糖の上昇・交感神経系の亢進に影響し、長年の間にCHDイベントのリスクが高まる。また、両親および幼少期のSESが、HPA系およびSAM系の反応を脆弱にしたり、成人後の行動的・心理社会的リスクファクター(喫煙・運動不足・攻撃性・職場での緊張・不健康な心理状態など)に影響を与え、CHDに影響を及ぼす可能性も示唆されている。さて、CHDの予防は、生活習慣予防として特定健康診査・特定保健指導により個人および職場レベルで2008年より行われている。しかしSESとCHDの関連性を考慮すると、社会レベルでの予防策も必要であろう。WHOは、健康を決定する社会的要因として「社会経済環境」「物理環境」「個人の特性と行動」を挙げている。このうち、社会経済環境を整備することがCHD予防につがなる可能性を示した。教育による介入、社会保障制度の整備、人生の節目でのサポートなどが有効であろうことが海外の研究で示されている。SESを改善しCHDを予防する戦略には、エビデンスに基づいた社会疫学的研究が必要であろう。
1 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.Supplement, pp.S23-S26, 2002 (Released:2014-07-03)
1 0 0 0 OA ストレス―コーピング過程と心理生物学的ストレス反応との関連性
- 著者
- 津田 彰 片柳 弘司
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.1-7, 1996 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 15
ストレス―コーピングの今日的なトランスアクショナル理論に従えば、心理生物学的ストレス反応は要請 (すなわち、ストレッサー) と心理社会的コーピング資源との不均衡によって発現すること、またこのトランスアクショナル (相互作用的) 過程には様々な要因 (たとえば、コントロールの機会、ストレッサーの持続性や予測性、怒りの表出と完了行動の終結可能性など) が関与していることが確認されている。本論文では、さまざまなコーピング方略が種々の心理生物学的ストレス反応パターン (たとえば、胃潰瘍の発生、脳内ノルアドレナリンと血黎コルチコステロンの放出増加、回避―逃避行動の障害) と相関すること、心理生物学的視点からすれば絶対的な有効なコーピング型は存在しないといった見解を支持する。問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピングに大別される心理生物学的ストレス反応の類別化を行うことで、いろいろな場面で適応を目指して行われるコーピング行動の同定に役立つと思われる。
1 0 0 0 OA Evidence-Based Medicineについて
- 著者
- 名郷 直樹
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.9-13, 1997 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 21
Evidence-Based Medicine (EBM) はより質の高い根拠に基づいて医療を行っていこうという問題解決の一手法であるが、その大きな特徴は患者の問題から始め、患者の問題の解決に終わるという視点、行動科学に基づいたプロセスの組立にある。そして、そのプロセスは以下の四つのステップで示される。1. 患者についての疑問の定式化、2. 疑問についての情報収集、3. 収集した情報の批判的吟味、4. 情報の患者への適用。注目すべきは、それぞれのプロセスが思考様式でなく行動様式として提示されている点である。患者の問題解決のための勉強を医師の行動という面からとらえ、よりよい患者管理を実現する、そこにEBMの特徴と目的が集約されていると考えている。
1 0 0 0 OA リハビリテーションにおける患者と医療者の 合意形成に関する文献的検討 ―Shared Decision Making の要素を用いた Informed Consent の内容分析―
- 著者
- 今 法子 藤本 修平 中山 健夫
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.18-24, 2016 (Released:2017-06-23)
医療上の治療方針の決定やその評価の際に、患者の価値観への配慮は不可欠である。診療上で、患者の価値観を尊重して合意を形成する方法に、Informed Consent(IC)とShared decision making(SDM)がある。両者は患者と医療者のコミュニケーションに基づくという点で共通だが、SDMは意思決定過程を共有することが重視される。しかし、両者が混同され、SDMのもつ本来の意義が明確にされていない場合も少なくない。そこで、リハビリテーション分野の論文で、ICに対する言及とSDMの定義を比較することで、SDMの意義を明確にすることを目的に文献レビューを実施した。文献の検索には、7つのデータベース(MEDLINEのPubMed、 Cochrane database、 Web of Science、Physiotherapy Evidence Database(PEDro)、Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence(OT seeker)、Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature(CINAHL)、医中誌Web(医中誌)を用いた。検索式は、ICをタイトルに含み、リハビリテーションの語を本文中に含む文献(英文・和文)とした。データ検索日は、2014年10月31日とし、その時点で各データベースの最新の文献までを対象とした。包含基準は、1)全文が入手可能であること、2)記載言語が英語または日本語であること、3)原著論文であることとした。除外基準は、1)総説、レビュー論文、症例報告、レター論文、会議録であること、2)ICについての記載がないこと、3)研究倫理についての内容であることとした。対象文献に記載されたICの定義にCharlesの示すSDMの必須4要素1)少なくとも医師と患者が参加する、2)医師と患者が情報を共有する、3)医師と患者が希望の治療について同意を形成するステップをふむ、4)医師と患者が実施する治療についての合意に達するが含まれているか否かを2名の評価者が独立に評価した。ICの定義にSDMのどの側面が含まれているかを検討するために、それぞれの項目が含まれる数とその割合、ならびにどの項目が含まれていたかを記述した。データベースの検索により、65件の文献が抽出された。そのうち、包含基準を満たした論文は54件であり、除外基準に従い選択をした結果、9件が選択されたこの中にSDMの言葉を含む文献はなかった。ICの定義にSDMの必須4要素のいずれかが含まれているか評価した結果、全ての文献で1)少なくとも医師と患者が参加すること、が含まれた。2)医師と患者が情報を共有すること、が含まれた文献は6件(67%)、3)両者が希望の治療について同意を形成するステップをふむこと、が含まれた文献は2件(22%)、4)実施する治療についての合意に達すること、が含まれた文献は2件(22%)であった。この9件のうち、4要素全てを含む論文は1件(11%)、3要素を含む論文は2件(22%)、2つを含む論文は3件(33%)、1つのみ含む論文は3件(33%)であった。ICを主題とし、SDMの言葉は含んでいないにもかかわらず、1/3の文献でSDMの必須4要素のうち3要素以上を含んでおり、両者の明確に使い分けられていないことが示唆された。
1 0 0 0 OA 心理医療と行動医学―臨床心理学の立場から
- 著者
- 橋口 英俊
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-7, 2001 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 9
筆者はこれまで、専門の臨床心理学や東洋医学を通じて、病院や大学その他の相談機関で数多くの悩める方の相談に従事してきた。ここでは、これらの経験を踏まえ、最近、カウンセリングや臨床心理の世界で注目されている代表的な認知行動療法の1つであるREBT (Rational Emotive Behavior Therapy) について、若干の資料と共にご紹介したい。ここで、REBTの特徴を要約しておくと次のようになる。(a) 症状の除去より、その背後の人生哲学に注目し、その矛盾に気づかせ、ラショナルなものに変えることに関心がある。(b) 実存的人間主義的立場に立つ。人が今ここに生き、存在することに価値があり、人間はあくまで人間であり、不完全で過ちを犯しやすい存在であることを前提に、それを受容し、克服する道を示す。(c) 感情行動を重視し、それがビリーフを変えることでよりよく幸せに生きる道が拓かれることを学ぶ。最後に筆者の関わった事例 (手記、REBTインペントリー) を紹介し参考に供したい。
1 0 0 0 座り行動と睡眠障害:系統的レビューとメタ分析
- 著者
- 中村 志津香
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.111-112, 2018-06-29
1 0 0 0 OA 運動器疼痛管理のための認知行動療法
- 著者
- 岡 浩一朗
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.76-82, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 27
心理的要因(たとえば、痛み対処方略)が高齢者における運動器疼痛管理に重要な役割を果たすというエビデンスは増加している。それ故に、運動器疼痛管理のために認知行動療法(たとえば、痛み対処スキルトレーニング)を利用することへの興味・関心が高まっている。本稿では、まず初めに運動器疼痛管理における認知行動療法の必要性に関する背景について概観した。次に、痛み対処スキルトレーニングで使用される5つの主な技法(認知再構成、リラクセーション、ディストラクション、快活動の計画、活動ペース配分)に焦点を当てて解説した。さらに、日本人の膝痛高齢者に対する痛み対処スキルトレーニングおよび運動療法に活用するために新しく開発した2つの印刷教材を紹介した。最後に、この領域における研究の今後の方向性について議論した。本総説より、運動器疼痛管理に認知行動療法(痛み対処スキルトレーニング)を応用することの重要性が示された。
本研究は2つの目的を達成するために行われた。第1の目的は、Pro-Change's self-efficacy measure for stress management behavior(PSSM)韓国語版を開発することであった。第2の目的は、韓国の大学生において、ストレスマネジメント行動の変容ステージとセルフエフィカシーとの関連性を検討することであった。本研究ではストレスマネジメント行動を定期的にリラクセーションする、運動する、他者と話をする、あるいは社会的活動に参加するなど、ストレスを緩和するための活動を1日に少なくとも20分間行うことと定義した。参加者は228名の男子大学生と517名の女子大学生である。参加者はストレスマネジメント行動の変容ステージとセルフエフィカシー、および抑うつに関連する質問紙に回答した。セルフエフィカシーに関しては2週間後にも回答した。因子分析の結果、9項目からなり、受容可能な信頼性を有するPSSM韓国語版が開発された。自己効力感は抑うつと負の相関を示したことから、PSSM韓国版の妥当性が一部支持された。ストレスマネジメント行動のセルフエフィカシーは、その他の変容ステージに属する者と比較して、維持期に属する者で高く、多理論統合モデルをストレスマネジメント行動に適用できる可能性が支持された。
1 0 0 0 OA よく眠るための行動医学
- 著者
- 高橋 正也
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-1, 2018 (Released:2017-11-29)
1 0 0 0 OA 境界性パーソナリティ傾向に対する予測因子としての抑うつと回避
- 著者
- 安達 圭一郎 上野 徳美
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.25-31, 2013 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 31
近年、うつ病などの気分障害患者は増加傾向にある。また、こうした気分障害と境界性パーソナリティ障害との併存率の高さを指摘する研究は数多くなされてきた。しかしながら、気分障害と境界性パーソナリティ障害との関連性について、診断学的に因果関係があるのかどうかについては十分なコンセンサスを得ていない。そこで、本研究は、探索的研究として、大学生を対象に、抑うつ傾向と境界例心性との関連性について、回避を媒介変数としたパスモデルを作成し、共分散構造分析で検討した。その結果、抑うつ傾向は回避を媒介として境界例心性に影響をもつということ、さらに、抑うつ傾向は直接的に境界例心性に影響することが確認された。一方、回避を媒介としないものの、境界例心性から抑うつ傾向への逆向きのパスモデルも適合度指標が高かった。以上の結果から、今後は、臨床群を対象にしたモデルの再検討の必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.Supplement, pp.S16-S67, 2007 (Released:2014-07-03)
1 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.Supplement, pp.S17-S29, 2006 (Released:2014-07-03)
1 0 0 0 OA 循環器疾患のQOL評価
- 著者
- 竹上 未紗
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.17-21, 2015 (Released:2015-04-16)
- 参考文献数
- 11
循環器疾患は短期的な死亡率が比較的高い疾患であるため、評価指標として生命予後の重要性が他の疾患に比べて際立っており、QOL研究の発展は遅れた。循環器領域における初期のQOL研究としては、降圧剤の影響に関するものがある。治療の結果、医師側が全員、患者は改善したと答えたのに対し、改善したと答えた患者は10%未満であった。医師が患者の血圧コントロールに関心があるのに対し、患者は活力や活動の低下などを問題にしていることが明らかになり、Patient-Reported Outcomesの測定の重要性が示された。近年では治療技術の向上に伴い治療の主な目的が長期予後の改善だけでなく、QOLを改善することにあるとの認識が広まり、循環器疾患領域の種々のガイドラインにおいてもQOL評価が取り入れられつつある。しかしながら、未だに日本でQOL評価が十分になされていない疾患も多い。成人先天性心疾患もその一つである。本稿では、QOLの概念を改めて整理し、循環器疾患領域におけるQOLを用いた臨床研究を紹介するとともに、その一例として国立循環器病研究センターの小児循環器科と共同で実施している成人先天性心疾患患者とその親を対象としたQOL調査を報告する。この調査より通常の診療ではケアの対象となっていない親のQOLが低下していることが示され、QOL評価の必要性が再認識された。
1 0 0 0 OA 健康習慣に対する遺伝要因・環境要因の影響
- 著者
- 大木 秀一
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.31-37, 2002 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 18
目的は包括的な健康習慣に対してどの程度遺伝要因が関与しているかを数量的に評価する事である。対象は東京大学教育学部附属中等教育学校を卒業した成人双生児である。2000年前半に、卒業生双生児に対して「生活習慣等についての質問紙調査」を実施した。ペアで回答を得ることが出来た同性双生児 (一卵性双生児145組、二卵性双生児14組) を分析対象とした。包括的な健康習慣を表わす指標として以下の基準を採用した。「7~8時間の睡眠時間」「週に1度以上の運動をする」「自覚的なストレスが中等度以下である」「毎日飲酒でない (過度の飲酒をしない)」「喫煙をしない (喫煙習慣なしまたはやめた)」「朝食を毎日食べる」「栄養のバランスを考えている」の7項目を良い生活習慣とみなした。良い生活習慣を取っている個数の合計は0点から7点に分布し、高得点の方が包括的な生活習慣がよいと考えた。全ての質問項目の回答を得た141組に対して双生児研究法の原理に共分散構造分析を応用し、健康習慣の背後に仮定した遺伝要因・環境要因の関与の程度を推定した。潜在変数としては2種類の遺伝要因 (相加的遺伝要因 (A)・優性遺伝要因 (D)) と2種類の環境要因 (共有環境要因 (C)・非共有環境要因 (E)) および年齢要因を仮定した。最適のモデルはAESモデル (年齢要因を考慮したAEモデル) であった。相加的遺伝要因の寄与は27%、非共有環境要因の寄与は72%であった。我が国ではこれまで、生活習慣は環境面からのみ検討される事が多かったが、一部で遺伝的に規定されている事が確認された。量的遺伝学の概念は集団を対象に定義されており個人に対するものではない。また、生活習慣に対する遺伝規定性と言った場合には、単一の遺伝子や生物学的な問題を想定しているわけではない。広く、ある種の行動パターンを選択したり、嗜好するような心理的要因・性格傾向の遺伝規定性をも念頭に置いている。ただし、健康習慣を全体として見れば70%以上が非共有環境要因により説明されており、個人に特異的な環境要因の影響が強い。それゆえ、環境要因を改善することで生活習慣の是正を図る事は行動遺伝学的な見地からも妥当なものである。生活習慣の評価や改善を論じる上でも遺伝要因の影響を無視し得ないと結論できる。
1 0 0 0 OA 過敏性腸症候群の背景:心理と遺伝要因
- 著者
- 濱口 豊太 金澤 素 福土 審
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-5, 2007 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 42
過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome;IBS)は脳腸相関の異常が病態の中心をなす疾患群である。IBSの病態は、消化管運動異常、消化管知覚過敏、心理的異常で特徴づけられる。消化管知覚過敏の発生機序の解明に、脳腸ペプチド・免疫・粘膜微小炎症による消化管機能変化・遺伝子・学習・神経可塑性・脳内神経伝達物質およびヒトの心理社会的行動などから進歩が見られる。消化管への炎症や疼痛を伴う刺激が先行刺激となって内臓知覚過敏を発生させる機序の一つとしてあげられる一方で、腹痛や腹部不快感の二次的な増悪を心理ストレスが引き起こし、そのときの消化器症状が関連づけられている可能性がある。本稿は、消化管知覚過敏が発生するメカニズムとして考えられている消化管粘膜微小炎症後の消化管知覚過敏、繰り返される大腸伸展刺激後の内臓知覚と情動変化の視点から、ヒトの心理的背景と遺伝要因について概説する。
- 著者
- 井上 茂
- 出版者
- The Japanese Society of Behavioral Medicine
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.47-51, 2014
現在、大学医学部では大幅なカリキュラム改編が進行している。背景にはいわゆる「2023年問題」がある。2010年に米国のECFMG(Educational Commission for Foreign Medical Graduates)は「2023年以降、国際基準の認証を受けていない医学部の卒業生にはECFMGの受験を認めない」ことを宣言した。日本人が米国で診療するためにはECFMGが行う試験に合格する必要があり、2023年以降は日本の医学部を卒業した者が米国で診療を行うためには、国際基準に則った認証を受けた医学部を卒業していることが前提となる。大学の国際化が進む中で、認証の取得は各大学にとって必須の課題となっている。これを受けて、2012年にWorld Federation for Medical Education(WFME:国際医学教育連盟)は医学教育のグローバルスタンダードを発表し、2013年には日本医学教育学会がこのスタンダードに準拠した「医学教育分野別評価基準日本版」を発表した。今後は日本医学教育質保証評議会(Japan Accreditation Council for Medical Education:JACME)が、この基準に沿って各大学の医学教育を認証する体制が構築されることになる。ところで、この認証基準において「行動科学」が教育プログラムのなかに、大きな見出し語として取り上げられている。これに従えば、各大学のカリキュラム担当者は「行動科学」の教育を実施する必要がある。一方、医学教育者間で行動科学・行動医学という領域は十分に認知されておらず、標準的な行動医学の教育内容も示されていない。このような背景のもと、日本行動医学会は「行動医学コアカリキュラム」を提案するための作業を進めている。そこで、医学教育における行動医学の位置づけを確認すべく、「医学教育分野別評価基準日本版」およびその原本(国際版)を行動科学の視点から検討した。また、行動医学に関連した部分をできるだけ原本から忠実に引用し、まとまった資料として整理した。さらに、その他の医学教育に関連したガイドラインとして「医師国家試験出題基準」「医学教育モデル・コア・カリキュラム」を行動医学の視点から検討した。その結果、医学教育分野別評価基準日本版においては「行動科学」が大きな見出し語となっており、行動医学の社会医学的側面を踏まえた記載が中心となっていた。医師国家試験出題基準には行動医学の特に臨床医学的側面が比較的体系立てて示されていた。また、医学教育モデル・コア・カリキュラム(準備教育モデル・コア・カリキュラム)には心理学的側面に関するキーワードが多く掲載されていた。これらの文書は医学教育のカリキュラム作成において大きな影響があることから、これらを踏まえて、各大学医学部のカリキュラム作成担当者の指針となるような、行動科学・行動医学の標準的な教育内容が提案されることが期待される。
1 0 0 0 OA 不眠者の生活習慣と、睡眠に対する不適応的認知
- 著者
- 羽山 順子 足達 淑子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.25-35, 2006 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 36
不眠者の行動観察から、いくつか仮説が提起されている。それは「不眠者は、不眠を補おうとして不眠を悪化させるような行動をとる、睡眠に対し過度の期待や思い込みのような不適応的な認知を持つ」というものであるが、日本ではまだこの仮説を検証した研究は少ない。また、生活習慣と不眠の関連は一定した結果が得られていない。本研究は以上の仮説と、生活習慣と不眠の関連を検証することを目的とした。保健所主催の睡眠改善セミナー参加者(以下不眠群)16名の睡眠に関連する生活習慣と睡眠に関する認知を、セミナー参加者と同じ地域の住民(以下一般群)73名と比較した。また、地域住民の中でも睡眠の良否で違いがあるかどうか確認するため、一般群について睡眠効率を基準に睡眠不良群18名と睡眠良好群55名に分け、生活習慣と睡眠に関する認知を比較した。不眠群と一般群を比較したところ、不眠群は一般群よりも入眠潜時は16.3分、要起床時間は50.4分長く、これは睡眠不足を補うための行動ではないかと考えた。睡眠に関連する生活習慣は、全体得点では傾向差がありやや不良であることがうかがわれたが、その内容を詳細に観察すると睡眠薬使用と寝室の環境以外は差が認められず、必ずしも不眠群の生活習慣が不良であるとはいえなかった。不適応的認知の保有数に差はなく、下位項目ごとに比較をしても、不眠群で「不安やイライラは不眠のせい」が多く見られたのみで、「不眠で身体や神経がまいる」はむしろ一般群の方が多い傾向にあった。その他の8下位項目に差はなかった。さらに睡眠不良群と睡眠良好群の比較では、睡眠不良群は睡眠良好群よりも、入眠潜時は58.4分、要起床時間は45.5分長く、睡眠効率は19.8%低いという不眠群同様の特徴が認められた。生活習慣は運動と就寝直前の活用の2項目で睡眠良好群よりも良好であり、不適応的認知については全ての項目において差がなかった。以上より、不眠を補う行動と睡眠効率についての仮説は不眠群も睡眠不良群もあてはまっていると考えられたが、生活習慣と不適応的認知に関しては、一概に不眠と関係があるということはできなかった。睡眠改善の指導はその人一人一人に適した指導が必要であると考えられた。また、睡眠の良否と生活習慣、睡眠に関する不適応的認知に関連がなかったことは、睡眠に関する一般的な知識が浸透していないためとも考えられ、睡眠に関する健康教育は、不眠者ばかりでなく、睡眠に問題がない者にも必要であると考えられた。