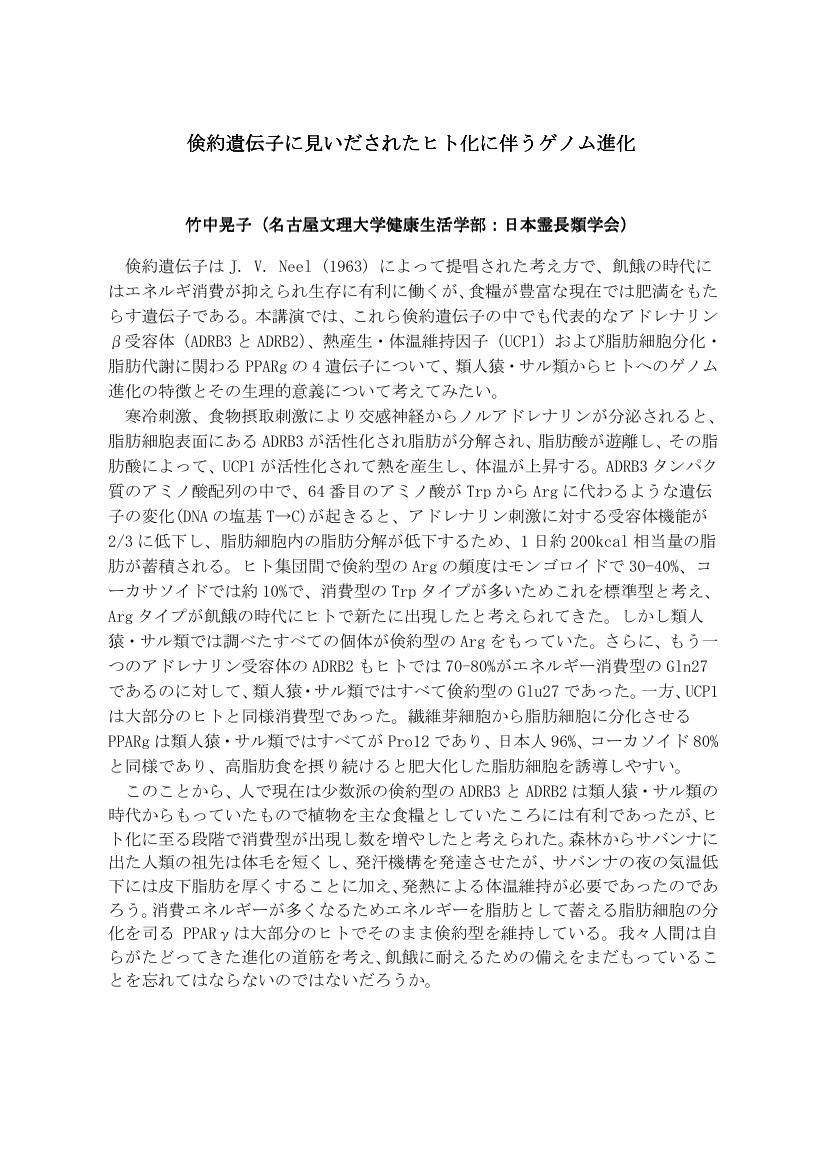- 著者
- 国分 直一
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.420-423, 1980-03-31
- 著者
- 柄木田 康之
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.86-101, 1997-06-30
あらゆる文化・伝統は多文化的状況下の虚構であるのに, 人類学は操作的に構成された現実を他者のカテゴリーに押し込めてきてしまってきた。このような主張は, 近年多くの支持者を集めている。ところがこのような本質主義批判が, また調査地側からの激しい批判を招き, 他者表象をめぐる植民地主義が再生産される, というジレンマが存在する。ミクロネシア連邦ヤップ州オレアイ環礁では1986年, 1993年にWoleai Conferenceとして環礁全体の伝統文化を確認する会議を開催している。二つの会議は, いずれも, 伝統を議題とし, 伝統文化を再確認し実践することで, 近年の社会変化にともなう混乱に対抗しようとする試みであった。しかし二つの会議のトーンには大きな違いがあった。93年会議では再確認された規則の侵犯に対する貨幣による罰金が制度化され, また環礁を構成する島間の海面権に関する不一致・対立が噴出した。この結果, 会議を主導した町にすむオレアイ出身のエリートが会議を高く評価するのに対し, オレアイ居住者は概して批判的である。オレアイにおける伝統文化の再生産は一枚板では捉えられない。「表象する権利は誰にあるのか」という問題は, 研究者と調査地の間だけではなく, 調査地において競われる問題でもある。
1 0 0 0 台湾東部と沖縄先島諸島にみる越境現象
- 著者
- 上水流 久彦
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.248-248, 2008
現在、台湾東部と沖縄県の先島諸島の間は距離的には近いが、国境が存在するため、その往来はかなり不便である。だが近年、両地域間では交流が盛んに行われるようになってきており、チャーター便を利用した直行便もすでに飛んでいる。その基盤には国境を越えた同一生活圏像という発想が存在する。国境をまたぐ形での同一生活圏像の生成には、植民地時代の国境がなかった時の交易などの移動経験が深く関係している。
- 著者
- 重信 幸彦
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.344-361, 2001-03-31
- 被引用文献数
- 1
本稿は,昭和初期に主に印刷メディア上で「愛国美談」として喧伝された,日露戦争時の出来事をめぐって語られた「久松五勇士」の成立と展開を検討し、「沖縄」という場所が近代「日本」のどのような視線により語られ意味づけられたか,その政治的布置を歴史的に考察するものである。それは,近代「日本」を覆う印刷メディア群のなかを,一つの「話」が様々に文脈化されて流通するさまを通して民俗話を構成する試みでもある。まず,「美談」の素材となった歴史的逸話が,本土から赴任した国語教師に再発見され,それが中等学校用「国語読本」の教科書に教材として掲載されて全国的に流布した「美談」化の過程から,そこに,「沖縄」を覆う近代「日本」の「国語」という制度が介在していることを指摘した。さらに,この「美談」の素材なった逸話を再発見した国語教師は,「沖縄の土俗」にも興味を示し,それを積極的に喧伝していた。「沖縄」に注がれた,「美談」を発見する視線と「土俗」を対象化する視線は,ここでは極めて近い位置にあった。また,こうして「日本」という文脈をあたえられた「五勇士」は,「沖縄」生まれの研究者たちにより、昭和初期の「郷土沖縄]を語る場に取り込まれ、「沖縄」の自画像を描く要素の一つとして位置づけられる。そこには近代「日本」のナショナリズムと,「沖縄」で描き出される自画像の共犯関係を見出すことができる。そして,昭和初期に「日本」のなかの「沖縄」の「美談」として喧伝された「久松五勇士」は, 1980年代に,宮古島の久松が与那覇湾の淡水湖化計画に対する反対運動を組織していくなかで,今度は久松の「海」と「漁師の魂」を象徴するものとして再解釈されることになる。そこに,地域の結集のために既成の「美談」を脱文脈化し再利用していく,したたかな戦術を見出すことができるのである。
1 0 0 0 アサイラム空間と都市下層
- 著者
- 山北 輝裕
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.48-48, 2011
現代日本の路上に留まる野宿者の包摂を見据えつつ、戦後「都市下層」の多様な現れを検討する。失対事業の労務管理員、70年代日雇労働者運動の活動家、現代野宿者支援・NPOなど都市下層と向き合ってきた他者に注目し、<アサイラム化>との共振と間隙を明らかにし、都市下層と他者の関係性の位相の変化を浮き彫りにする。
- 著者
- 内藤 直樹
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.45-45, 2011
本分科会の目的は、グローバリゼーションと社会的排除/包摂をめぐる諸問題の検討を通じて、これまでの国民国家が再編されるなかでの私たちの生のあり方の可能性を模索することである。そのために、社会的排除/包摂にかかわる諸実践が展開される様々な場がもつ空間性の位相を捉える枠組みとして、<アサイラム/アジール空間>という概念を提出する。
1 0 0 0 OA 現代美術の実践におけるエージェンシーのあり方
- 著者
- 登 久希子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.I02, 2016 (Released:2016-04-23)
本発表は、現代美術におけるエージェンシーのあり方について、「関係性の美学(relational aesthetics)」として注目されてきた実践と「オルタナティヴ・スペース」の取り組みを事例に再考するものである。
- 著者
- 相原 健志
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
本発表は、ブラジルの人類学者E. ヴィヴェイロス・デ・カストロの多自然主義に含まれる身体の存在論の含意と射程を析出することを試みる。その記述を辿ると、多自然主義の機制における存在者間の食人的関係は、スピノザ哲学に由来するコナトゥス概念において捉えられる。そしてコナトゥスは、食人のみならず、「翻訳」といった人類学者の実践をも、つまり他者と人類学者のあいだの差異を横断する力として思考されている。
- 著者
- 左地 亮子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.470-491, 2014-03-31
近年、人文社会科学の諸領域において、「語り」が意味生成に関与し、個人と他者や共同体との関係を架橋する社会的行為として注目されてきたのに対して、「語らないこと」や「沈黙」は、共同性に対立する孤立や孤独と結びつけられ中心的に扱われてこなかった。本論文は、こうした研究動向に新たな視座を提示すべく、フランスに暮らすマヌーシュの死者をとりまく「沈黙の敬意」を事例に、沈黙の共同性を明らかにすることを試みた。その際に注目したのは、服喪のあいだに死者をめぐって生じるマヌーシュの沈黙が、これまでの「死の人類学」において指摘されてきた、「個別特異な死者から集合匿名的な祖先への移行」を妨げる側面である。マヌーシュは死者の名前や記憶を口にすることを避け、遺品を廃棄する。先行研究は、この死者に属し死者を喚起するあらゆる有形無形の事物を共同体から排除するマヌーシュの態度を、死者の「忘却」を導き、死者を「集団の永続性」を保障する「匿名の祖先」に変換する手続きとみなしていた。しかし本論文では、マヌーシュの沈黙が、むしろ死者や遺族という共同体内部の個人の存在や体験の「特異性=単独性」を保護するために「敬意」という価値を与えられること、そしてそれがゆえに、個の体験を全体性の中に解消することを阻み、死者から祖先への移行が果たされる服喪の終了を先延ばしにすることを指摘した。マヌーシュの沈黙は、「個の全体への統合」を志向する調和的な儀礼モデルに抗いながら、差異の「分有」としての共同性を開示するのだ。
1 0 0 0 OA 祭りの「当事者」としてのローカルメディア
- 著者
- 石川 俊介
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第47回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.42, 2013 (Released:2013-05-27)
本発表では、長野県諏訪地域のケーブルテレビ局A社を事例に、ローカルメディアが地元の祭りに「当事者」として深く関わっていることについて論じる。発表者はA社の番組制作課にアルバイトとして関わりながらフィールド調査を行った。その中でA社が氏子である視聴者のニーズに即した番組制作を行っていること、氏子たちもそのサービスを祭りの一部として認識していることが明らかになった。
1 0 0 0 文化相対主義を再構築する(<特集>文化相対主義の困難を超えて)
- 著者
- 小田 亮
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.184-204, 1997-09-30
本論文は, 文化相対主義を「理論」としてではなく状況や発話の位置に左右される「戦略」として再構築することを目的とする。自文化中心主義に反対する真の文化相対主義は, 浜本満(1996)が明らかにしているように, 自文化中心主義的な文化相対主義および自文化中心主義的普遍主義と対立するものであり, むしろ真の普遍主義に類似している。理論として再構築された文化相対主義は, 自文化と異文化双方の否定を介して第三の共通の基盤を開く弁証法的運動として捉えられよう。しかし, 普遍主義と共有する, そのような弁証法的運動は, 西欧近代に特有のものであり, 西欧のヘゲモニーの下では, 西欧近代だけがその第三の地平を専有する西洋中心主義に陥る。戦略としての文化相対主義は, 第三の地平を普遍的な真理としたり, 自文化や他文化より一般的な概念枠組としたりする普遍主義や理論としての文化相対主義とは異なる。さらに, それは, グローバル化による異種混淆性の賛美や, 文化の構築における操作性や主体性を評価する議論に共通する「記憶の抹消」にも反対する。戦略としての文化相対主義は, 文化の違いを一般性に規定された特殊性としてではなく, 文化の純粋性に先行する雑種性による文化的差異を単独性として語るものでなくてはならない。その一つのモデルは, 「戦略的本質主義」であるが, 戦略と結び付いた発話の位置が, 近代の知と支配のシステムが依拠する「種的同一性」によって規定されるものと捉えるならば, それは植民地主義/帝国主義の言説と変わらなくなってしまう。種的同一性には捉えきれない普通のひとびとの実践と, 雑種性や文化的差異を排除せず記憶が生きている「生活の場」における文化の真正性に留意することこそが, 近代の知と支配の体系への無意識でしたたかな抵抗を可能にし, 「相対主義のニヒリズム」やグローバル化による異種混淆性の無批判な賛美に陥らないことを可能にするのである。
1 0 0 0 OA 倹約遺伝子に見いだされたヒト化に伴うゲノム進化
- 著者
- 竹中 晃子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.3, 2009 (Released:2009-05-28)
1 0 0 0 北上山地の屋號と聚落
- 著者
- 山口 彌一郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.365-391, 1943-01-25
- 著者
- 瀬川 清子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 季刊民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.246-254, 1952-03
Upon coming of age, Ainu women used to tatoo their mouths, cut their hair short, wear a cylindrical undershirt (called mour), and wear a sash-the upshor (s. figure on p.69) around the waist under their clothes. Women who do not wear this sash were believed to be unqualified not only to make fire and cook, but also to make their husband and children happy. The form of the upshor was transmitted from mother to daughter. Women who had the same form of upshor in common were called shine-upshor (same upshor) and helped one another on ceremonial occasions throughout their lives. Even after death they were believed to depend on each other, and therefore the wearing of the upshor, even in the grave, was considered indispensable for women. Even to-day, the Ainu male may not marry a woman who wears (or should properly wear) the same upshor as his mother. If he wants to marry her in spite of this restriction, the girl must be given a different upshor and a different fictitious lineage. The showing of one's upshor to other people is strictly tabooed, so the authoress has not yet been able to trace the varieties of upshor-types in detail. It has been ascertained, however, that in spite of the patrilineal kinship structure of the Ainu, a woman is considered to retain some affiliation with her mother's matrilineal female group and that this group still has a latent function in social life.
1 0 0 0 OA 拡張(extend)する理論
- 著者
- 清水 高志
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.A16, 2016 (Released:2016-04-22)
ストラザーンの『部分的つながり』が切り拓く思想的な展望を、二十一世紀の哲学の諸動向と同種の問題意識を孕んだものとして捉え直す。彼女が集団の全体という「一」と、その部分としての「多」を自明なものとして想定せず、媒体的なモノ=道具が集団形成に果たしている能動的な機能と、その変容を重視していることの意味を哲学的に考察する。
- 著者
- 佐々木 重洋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.242-262, 2015-09-30
本稿の目的は、エヴァンズ=プリチャード(以下、E-P)の思考の軌跡と、彼が示していた問題意識と手法をあらためて批判的に再検討し、その知的遺産と検討課題を現在に再接続させることにある。本稿では、民族誌や論考、講義録や書簡から読み取ることができるE-Pの構想のなかでも、人間の知覚と認識、その作用に影響を与えるものとしての社会、それも決して閉じた固定的なシステムではなく、人間関係の動態的な諸関係としてのそれとは何かをモンテスキューにさかのぼりつつ自省し続けた点と、民族誌と人類学の主要な仕事としていち早く解釈という営為を強調した点にとくに注目し、その背景を再検討した。アザンデの妖術やヌアーの宗教を扱った民族誌においては、当時の西欧的思考の枠組みに対する疑義ないし違和感が表明されていたが、E-Pとその後進たちの遺産は、そこに「インテレクチュアル・ヒストリー派」としての省察がともなうかぎり、主知主義批判、表象主義批判や言語中心主義批判、主客二元論批判や心身二元論批判としても、今なお私たちにとって着想の源泉たり得る。さらに、共感や友情を強調したその人文学的経験主義からは、絶えず自己に立ち返り、自らが影響を受けている知的枠組みと社会背景に対する自省を保ちつつ、調査する者と調査される者のあいだの共約不可能性を乗り越えようとする姿勢を継承でき、それはフィールドワークと民族誌を取り巻く思想的、物理的環境が大きく変わりつつある今こそ、あらためて参照に値することを指摘した。今日、E-Pに立ち返って考えることは、モンテスキューを脱構築しつつ、人類学的思考が哲学や社会学はもとより、法学や政治学、経済学などと未分化の状態であった時点に立ち返って考えることにつながるものでもあり、今後の人類学が人文学とどのように関係すべきかという点も含めた人類学の知のあり方を模索するうえで一定の意義があると考える。
1 0 0 0 OA 逃れる女神と包摂を夢見るデュモンの全体
- 著者
- 内山田 康
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.A15, 2016 (Released:2016-04-22)
全てを階層的な関係の中に包摂する全体論的な構造から逃れる先住民の女神がいる。この南インドの女神は、ある女性の非業の死から単独の神として生まれた。女神はヒンドゥー寺院の象徴的階層構造に取り込まれて穢れた部分を排除される。だが全体からは予測できない飛躍の中で排除された部分から意味が生み出される。系列と系列を横切って創発が起こり、全体論的な構造が部分化する過程を記述した後、部分と全体の関係を再考する。
1 0 0 0 OA 憧憬としての青年団
- 著者
- 黒崎 岳大
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.213, 2009 (Released:2009-05-28)
米国信託統治領下のマーシャル諸島では、各地の離島で日本の青年団をモデルとした「クミ」と呼ばれる協働組織が形成された。同組織は、70年代には政治等の分野において強い影響力を見せたものの、90年代以降は急激に消滅していった。本発表では「クミ」という組織を巡る歴史的変遷を通じて、マーシャル人にとっての日本統治時代に対する過度に理想化された憧憬と急激に進む米国化に対する抵抗の関係について検討していく。
1 0 0 0 OA 〈趣旨説明〉 旧南洋群島における日本統治経験
- 著者
- 飯高 伸五
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.211, 2009 (Released:2009-05-28)
日本統治下南洋群島の「島民」は帝国臣民とは明確に異なる存在と規定され、日本国籍を付与されなかった一方で、公学校における日本語や修身の授業、青年団の組織化などを通じて文化的同化の対象とされた。本分科会では日本統治下で「島民」が文化的同化をいかに受容したのか、戦後のアメリカ統治期から国家形成期にかけて日本統治経験をいかに解釈、再解釈していったのかを検討する。
1 0 0 0 OA 年齢集団と青年団の節合
- 著者
- 飯高 伸五
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.214, 2009 (Released:2009-05-28)
日本統治下のパラオでは既存の年齢集団を包摂しつつ、青年団が組織された。男子の青年団は、道路建設をはじめとする勤労奉仕、体育デーなどの文化イベントへの参加を求められた。当時の勤労奉仕や体育デーを歌った歌からは、パラオの人々が、統治政策の一環として組織された青年団の活動を、植民地統治以前に行われていた村落間の交流活動など、年齢集団の活動と連続するものとして解釈したことが読み取れる。