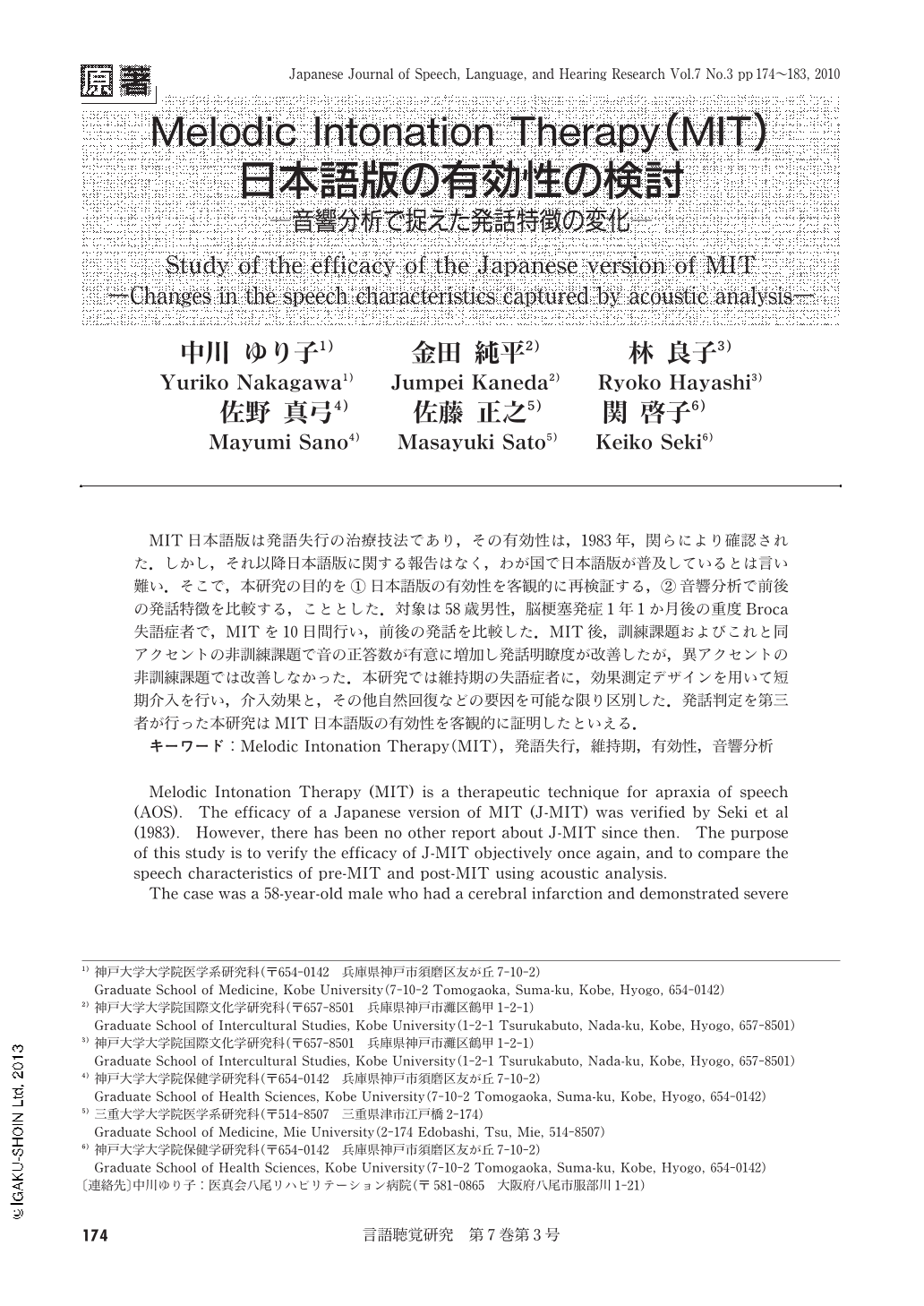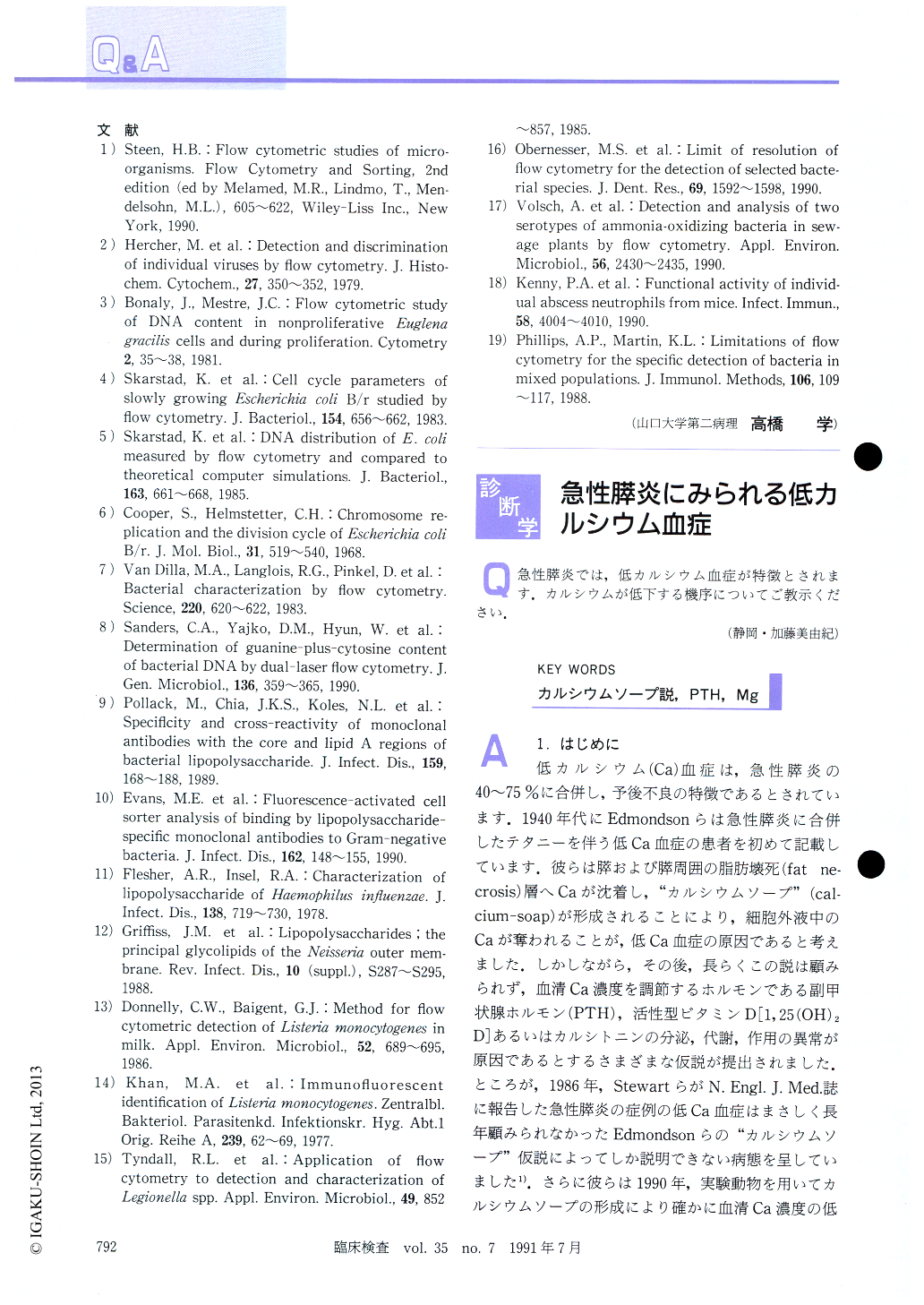MIT日本語版は発語失行の治療技法であり,その有効性は,1983年,関らにより確認された.しかし,それ以降日本語版に関する報告はなく,わが国で日本語版が普及しているとは言い難い.そこで,本研究の目的を①日本語版の有効性を客観的に再検証する,②音響分析で前後の発話特徴を比較する,こととした.対象は58歳男性,脳梗塞発症1年1か月後の重度Broca失語症者で,MITを10日間行い,前後の発話を比較した.MIT後,訓練課題およびこれと同アクセントの非訓練課題で音の正答数が有意に増加し発話明瞭度が改善したが,異アクセントの非訓練課題では改善しなかった.本研究では維持期の失語症者に,効果測定デザインを用いて短期介入を行い,介入効果と,その他自然回復などの要因を可能な限り区別した.発話判定を第三者が行った本研究はMIT日本語版の有効性を客観的に証明したといえる.
1 0 0 0 OA 小児の睡眠時無呼吸症候群と手術適応
- 著者
- 鈴木 雅明
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.11, pp.1444-1445, 2016-11-20 (Released:2016-12-15)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 軽合金の特質と工作法講習会
- 著者
- 島田 正雄
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具研究会会報 (ISSN:02892391)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.11, pp.25-38, 1977-02-20 (Released:2010-02-23)
1 0 0 0 OA 咽喉頭異常感への対応
- 著者
- 大越 俊夫
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.11, pp.891-896, 2006-11-01 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
Abnormal sensations in the throat can be induced by a wide variety of causes, and therefore requires both mental and physical approaches to treatment. In addition, malignant tumors maybe detected in a small number of patients with complaints of abnormal sensations in the throat, and this must never be overlooked. While there have been numerous reports descring various tests, diagnostic methods for determining the causes of abnormal sensations in the throat as well as administration the of therapeutic drugs vary among facilities and few reports have investigated cases of abnormal sensations refractory to initial treatment. Furthermore, although the involvement of psychogenesis in this illness is not small, the extent of its involvement is extremely difficult to assess. While therapeutic determination using various psychological tests and the effects of mild tranquilizers has been attempted, clarification of the extent of psychogenic involvement in this illness remains difficult, as does the treatment of this illness as a psychosomatic illness in the field of otolaryngology.Improvement in abnormal sensations in the throat is determined by changes in the subjective symptoms of the patient. Many reports on the treatment of abnormal sensations in the throat have focused on the effects of administering a specific drug in response to a defined cause of illness, and few have reported the final improvement rates of the patients included in these studies. In other words, it is important to investigate secondary and tertiary treatment methods and the extent to which abnormal sensations in the throat has been improved in patients with abnormal sensations refractory to initial treatment, as well as the appropriate course of action when improvements are not observed.
1 0 0 0 OA 耳鳴に対する認知行動療法 ~エビデンスおよび本邦の現状と対応~
- 著者
- 高橋 真理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.109-114, 2020-04-28 (Released:2020-05-23)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
要旨: 2019年5月に日本ではじめて耳鳴診療ガイドラインが発刊された。この耳鳴ガイドラインでは, エビデンスに基づき推奨されており, 認知行動療法は強く推奨されている。しかし, 日本ではうつ病などに対して認知行動療法は行われているが, 耳鳴に対してはまだ行われていない。 日本で耳鳴に対する認知行動療法が行われていない理由の1つに, 海外では精神科医も耳鳴治療を行うという治療者の違いがある。また, 本邦では認知行動療法を行う精神科医も少なく, 認知行動療法が保険適応されているのは, うつ病など限られた精神疾患であることも要因であろう。現在, 慢性疼痛などへの効果など認知行動療法は注目されてきている。今後本邦においても耳鳴に対して認知行動療法が行われることを期待するとともに, 耳鼻咽喉科医ができる耳鳴の認知行動的介入 (アプローチ) として, 教育的カウンセリングや認知行動療法的アプローチをしっかり行っていくことが重要である。
1 0 0 0 急性膵炎にみられる低カルシウム血症
1 0 0 0 高橋貞一郎滞欧作品集
- 出版者
- 美術工芸会
- 巻号頁・発行日
- vol.第1, 1940
1 0 0 0 宮城県中央図書館月報
- 出版者
- 宮城県立図書館
- 巻号頁・発行日
- vol.6(12), no.24, 1938-12
1 0 0 0 多賀城町誌
- 著者
- 多賀城町誌編纂委員会 編
- 出版者
- 多賀城町誌編纂委員会
- 巻号頁・発行日
- 1967
1 0 0 0 OA 半正多面体の生成 (第2報) 切頭・切稜による生成とパソコンによる作図
- 著者
- 立花 徹美
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.25-32, 1987 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 東京の屋根の下 : 山岸曙光歌謡集
1 0 0 0 ヒトの中強度有酸素運動による脳由来神経栄養因子の反応に関する研究
- 著者
- 合田 明生 佐々木 嘉光 本田 憲胤 大城 昌平
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2012
<b>【目的】 </b>近年、運動が認知機能を改善、または低下を予防する効果が報告されている。運動による認知機能への効果を媒介する因子として、脳由来神経栄養因子(Brain-derived Neurotrophic Factor;BDNF)が注目されている。BDNFは、中枢神経系の神経活動によって神経細胞から刺激依存性に分泌される。そこで本研究では、BDNFと交感神経活動の関係に着目し、運動ストレスによる交感神経活動が、神経活動亢進を介して中枢神経系におけるBDNF分泌を増加させる要因であると仮説を立てた。よって本研究の目的は、健常成人男性を対象に、運動の前後でBDNFを測定し、運動が交感神経活動を亢進させることで、中枢神経系の神経活動を引き起こし、末梢血流中のBDNFを増加させるという仮説を検証することである。その結果から、運動によるBDNF分泌メカニズムの解明の一助とすることを最終目標とする。<br><b>【方法】 </b>健常成人男性10名を対象に、30分間の中強度有酸素運動(最高酸素摂取量の60%)を実施した。運動の前後で採血を実施し、末梢血液中のBDNF、ノルアドレナリン(Noradorenaline:NA)を測定した。運動中の交感神経活動指標としてNAを用いた。また運動中の中枢神経活動指標として、前頭前野領域の脳血流量を用いた。以上の結果から、運動前後のBDNF変化量、交感神経活動の変化(NA)、大脳皮質神経活動の変化(脳血流量)の関連性を検討した。各指標の正規性の検定にはShapiro-wilk検定を用いた。血液検体の運動前後の比較には、対応のあるT検定を用いた。各指標の相関の分析には、Pearsonの相関係数を用いた。いずれも危険率5%未満を有意水準とした。<br><b>【結果】 </b>中強度の有酸素運動介入によって、10人中5名では運動後に血清BDNFが増加したが、運動後のBDNFの値はバラつきが大きく、運動前後のBDNF量に有意な差は認められなかった(p=.19)。またBDNF変化量と交感神経指標の変化の間(BDNF-NA r=.38, p=.27)、中枢神経活動指標と交感神経指標の変化の間(脳血流量-NA r=-.25, p=.49)、BDNF変化量と中枢神経活動指標の変化の間(BDNF-脳血流量 r=-.16, p=.66)には有意な相関は認められなかった。<br><b>【考察】 </b>本研究では、健常成人男性を対象に、30分間の中強度運動の前後でBDNFを測定し、運動が交感神経活動を亢進させることで、中枢神経系の神経活動を引き起こし、末梢血液中のBDNFを増加させるという仮説の検証を行った。その結果、中強度の運動介入によって、10人中5名は運動後の血清BDNF増加を示したが、運動前後のBDNF量に有意な差は認められなかった。この要因として、刺激依存性のBDNF分泌を障害するSNP保有が考えられた。また、BDNF変化量と交感神経指標の変化の間、交感神経指標と中枢神経活動指標の変化の間、BDNF変化量と中枢神経活動指標の変化の間には、有意な相関は認められなかった。この要因として、交感神経活動が急性BDNF増加に直接的には関与しないことが考えられる。<br><b>【まとめ】 </b>健常成人男性における30分間の中強度有酸素運動は、末梢循環血流中のBDNFを有意に増加させず、運動によるBDNF変化には、交感神経活動や中枢神経活動は関連しないことが示唆された。
1 0 0 0 原住民族の遺蹟 : 八ケ岳山麓尖石遺蹟研究
1 0 0 0 OA 仏国商社法要義
- 著者
- ジェー・アッペール 著
- 出版者
- 薩埵正邦
- 巻号頁・発行日
- 1890