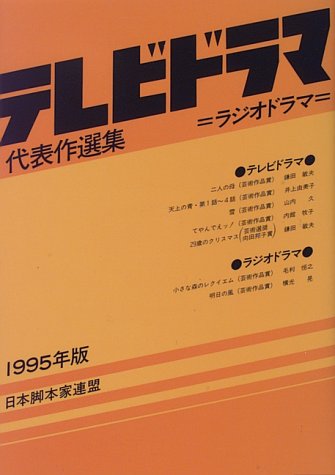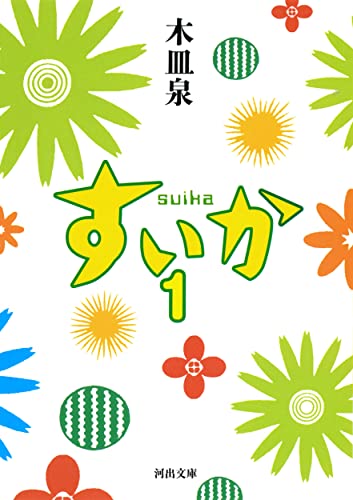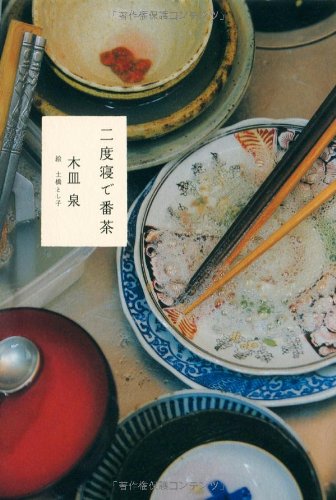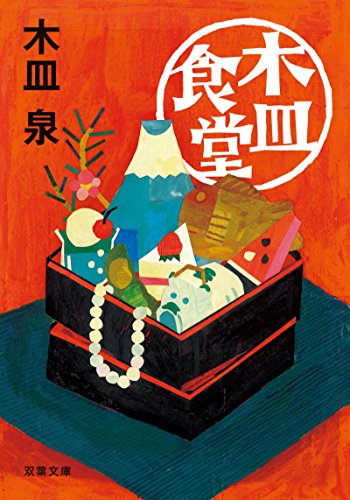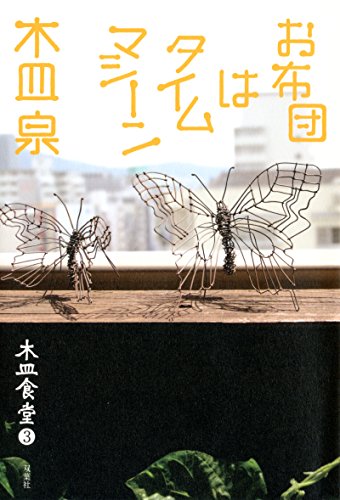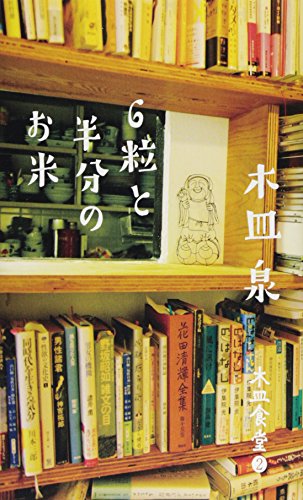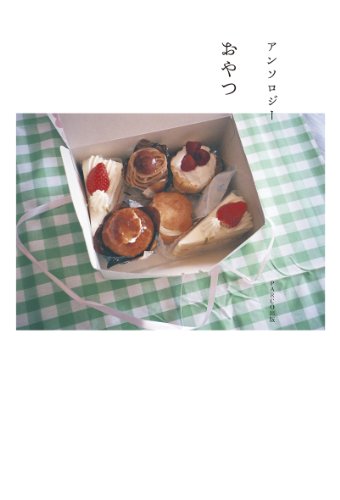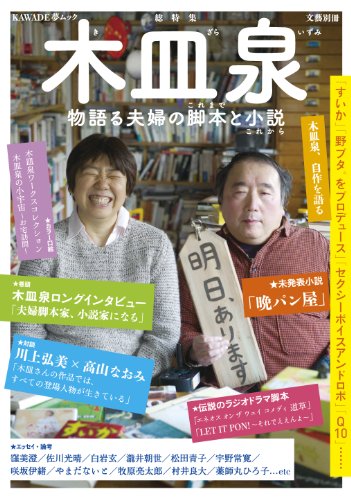1 0 0 0 OA A-18 West症候群におけるビタミンB6大量療法の有効性と副作用の検討
- 著者
- 島邊,泰久
- 出版者
- 日本てんかん学会
- 雑誌
- 日本てんかん学会プログラム・予稿集
- 巻号頁・発行日
- no.34, 2000-09-21
1 0 0 0 OA 醤油醸造業史研究の回顧と展望(竹浪祥一郎教授退任記念号)
- 著者
- 長谷川 彰 Akira Hasegawa 桃山学院大学経営学部 St. Andrew's University
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST. ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.29-54, 1992-03-01
1 0 0 0 OA 運動負荷後の血圧回復の及ぼす香りの効果
- 著者
- 坂田 裕美 徳田 良英
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0471, 2008 (Released:2008-05-13)
【目的】運動負荷後の血圧変動,疲労感を生じやすい症状などへのリスク管理が問題となる例が多い.ところで近年芳香を持つ植物から抽出した精油を使って、心身の自然治癒を高めるアロマセラピーの応用が多分野で活用されるようになった。リハ現場における匂い環境を整備することによる臨床応用の可能性を模索することを念頭に、香りのリラックス効果について運動負荷後の血圧回復の観点から検討することを目的とした。【方法】対象は既往歴の無い成人男女6 名(男性3 名,女性3 名,平均年齢:22.3±1.03 歳)とした.運動前に血圧,脈を計測し,その後運動負荷を行った.血圧・脈の測定には自動血圧計(OMRONデジタル自動血圧計:HEM-6011)を使用した.運動負荷についてはトレッドミル(CYBEX 900T)を使用した.5 分間,10km/h前後の速度で,Borg 指数13~15 程度となるよう調整した.終了後,血圧,脈を1 分間隔で5 回計測し,アンケート調査も行った.この実験をグレープフルーツの香りを与えた群(以下GF 群),ラベンダーの香りを与えた群(以下LV 群),および対照群として芳香刺激を与えない群(以下NG 群)と分け,各群日を変えて実験した.統計解析はWilcoxon 検定を用い,有意水準を5%未満とした.解析にはSPSS for Windows を用いた.【結果】1)生理的変化についての比較:収縮期血圧において,1 分後,2 分後,3 分後,4 分後についてGF 群はNG 群と比較し有意に回復速度が速かった.拡張期血圧においても,1 分後,2 分後,3 分後,5 分後について同様であった.LV 群にも低下傾向が見られ,脈の変動についても,NG 群と比較し若干低下傾向にあった.2)精神的変化についての比較:アンケート調査結果では,実験後の疲労度において調査したところ,NG 群と比較しGF 群,LV 群において有意差は見られないが(p>0.05),疲労度,気分がリラックスしている傾向が見られた(GF群<LV 群).また,アロマテラピーに肯定的な考えを持っている方が6 名中5 名であった【考察・まとめ】アロマテラピーは運動後のリラックス効果について有用であるといえる.特にLVについては精神面でのリラックス効果が得られた.GF についても,運動後の血圧を有意に低下させるなど,身体面においてのリラックス効果が得られた.リハの場面においても芳香刺激を利用することで,患者のリラックス促進効果など期待できると思われる
1 0 0 0 OA ドイツ革命期の海軍兵士最高評議会
- 著者
- 山田 義顕
- 出版者
- 大阪府立大学
- 雑誌
- 大阪府立大学紀要(人文・社会科学) (ISSN:04734645)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.1-16, 1992-03-31
1 0 0 0 生き抜く人間の姿--宇野千代論
- 著者
- 森 順子
- 出版者
- 人間環境大学
- 雑誌
- こころとことば (ISSN:13472895)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.51-63, 2002-03
作家、宇野千代の九十九年間の人生は、絶対的権力者としての父親の存在を抜きにしては語ることが出来ない。それは恐怖心として、彼女の精神の髄まで刻み込まれる。父親の言葉によって植え付けられた自信喪失に懊悩し続ける中で、宇野千代がいかにして生涯、自分自身であることを希求して生き抜いたかを探る。
1 0 0 0 OA 437. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の四肢筋に対する治療的電気刺激(TES)効果の解析
- 著者
- 南 宏美 清水 洋 松村 康弘 伊橋 光二 八木 了 半田 康延 半田 郁子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.25 Suppl. No.2(第33回日本理学療法士学会誌 第25巻学会特別号 No.2 : 演題抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.437, 1998-04-20 (Released:2017-09-19)
1 0 0 0 Cutwail通信プロトコルの解析
- 著者
- 阿曽村 一郎 武田 康博
- 雑誌
- コンピュータセキュリティシンポジウム2018論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.2, pp.1053-1058,
オンラインバンキングなどの認証情報を盗むマルウェアはバンキングトロジャンと呼ばれる.多くの場合,これらはメール本文 URL からのダウンロードさせるかたち,またはメールの添付ファイルとして配布される.バンキングトロジャンを配布するための基盤として,Cutwail というボットネットがある.Cutwail についてのこれまでの研究によれば,ボットと C&C サーバ間の通信は攻撃者が望むコンテンツのスパムメールを送信するためのメカニズムを持つことが分かっている.本稿では,Cutwail のボットと C&C サーバの間の通信に着目し,我々が観察した結果と以前の研究結果との比較結果を説明する.
1 0 0 0 OA 「地域活性化」再考 : 人口と雇用の観点から
- 著者
- 市川 虎彦 Torahiko Ichikawa 松山大学人文学部 Matsuyama UniversityFaculty of Humanities
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.45-67, 2013-12-01
1 0 0 0 OA 日本銀行の銀行保有株式買入
- 著者
- 齊藤 壽彦 サイトウ ヒサヒコ Hisahiko SAITO
- 雑誌
- 千葉商大論叢
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.49-106, 2003-03-31
本論文において,日本銀行が大手銀行などから直接にその保有株式を買入れた問題を実証的,総合的に考察した。単なる現状分析にとどまらず,理論研究を基礎に,時間的推移も考慮に入れてこの問題を考察した。政策評価(意義と問題点の分析)も行った。本論文においては,まず本施策の決定過程を考察し,当初株式買入を拒否していた日本銀行が,不良債権問題の深刻化と株価低落に伴う大手銀行の経営悪化という状況変化のもとで,日本銀行自らがこの異例の施策の採用を決断するに至ったことを明らかにした。続いて本施策の目的,日銀の株式買入方法,買入れ状況を論述した。さらに日銀の株式買入限度額引上施策について,それが実施された背景や目的について考察した。最後にこの施策を信用秩序維持,証券市場,貨幣・中央銀行信認に及ぼす影響について検討した。本施策は日本銀行が銀行の株価変動リスク軽減を通じて金融システムの安定を図る政策であって,また,政府に不良債権の早期処理への取組を促すという役割をもっており,それは一定の役割を果たしたが,それは大きな限界をもっており,また証券市場の改善には役立たず,中央銀行の財務悪化を通ずる信認毀損の恐れという問題点をもっていたということをを明らかにしている。
1 0 0 0 OA 子ども時代の組織キャンプ経験に関する自伝的記憶 :
- 著者
- 佐藤 冬果 井村 仁
- 出版者
- 日本野外教育学会
- 雑誌
- 野外教育研究 (ISSN:13439634)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-18, 2018 (Released:2019-10-05)
- 参考文献数
- 32
The study aims to elucidate the lasting impacts of organized camp on participants as they reached their adulthood through the viewpoint of autobiographical memory and autobiographical reasoning. Qualitative data were collected by semi-structured interviews with three male and four female research subjects (20 to 40-years age) who had participated in an organized camp during their childhood. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used to analyze these seven case studies of organized camp experience. Through the IPA, 14 themes emerged which were categorized into two major domains. Domain of “impact on oneself” including seven themes ; “core of self,” “conception of nature,” “relationship to others,” “acquisition of sociability,” “improving confidence,” “interest and skill about outdoor education or outdoor activity,” “vitality,” and domain of “factor of impact on oneself” including seven themes ; “camper and adult staff,” “enjoyment,” “unusual situation,” “experience of severe situations,” “continuous participations,” “successful experience,” and “motivation for camp”. Results revealed that the duration of evaluation by participants about camp's significance is not confined within the immediate time frame of the occurrence. The camp's significance is reevaluated at different stages of one's life. This could be during the time when one goes to camp again, or when one is trying to figure out one's occupation, or even when one is facing an obstacle. Further, our analysis suggests that at each stage, the camp's experience is reassessed by the individuals and held a new meaning to them. This study confirms that the meaning-making process and lifelong benefits of camp experience during childhood to adulthood.
1 0 0 0 OA 子ども時代の組織キャンプ経験に関する自伝的記憶:
- 著者
- 佐藤 冬果 井村 仁
- 出版者
- 日本野外教育学会
- 雑誌
- 野外教育研究 (ISSN:13439634)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.15-26, 2018 (Released:2019-03-01)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
The memories recollected from an individual's life are referred to as autobiographical memory. When people recollect one’s past, we undergo the process of autobiographical reasoning as well as recalling merely. That is the activity of creating relations between different parts of one's past, present, and future life and personality and development. The purpose of this study was to elucidate the lasting impacts of organized camps on participants as they reached their adulthood through the viewpoint of autobiographical memory and autobiographical reasoning. The data were collected using a “Camp Memory Characteristics Questionnaire,” which was completed by 191 participants and analyzed using statistics. It was shown that memories of outdoor activities, such as “campfire,” “hiking or Solo,” “involvement with the camper,” “involvement with the camp counselor,” and “meaningful nature experience” were the most memorable events of camp in most of the respondents. Especially, the memories of “accomplishment,” such as “hiking or Solo” were recalled more frequently as well as more clearly, and they are valued as more important than the memories of other activities. In addition, the memories of camp remained in participants’ minds regardless of how much time has passed. By comparing and analyzing respondents' ages, these memories appear to have become more important as participants grew older. Furthermore, around 80% of respondents recognized the impacts of organized camp experiences. Participants also have attributed a variety of meaning to their camp experiences, and it was classified into 6 groups: “self,” “others,” “nature environment,” “outdoor activity,” “occupational choice,” and the other.
1 0 0 0 テレビドラマ代表作選集
1 0 0 0 お布団はタイムマシーン
- 出版者
- 双葉社
- 巻号頁・発行日
- 2018
1 0 0 0 おやつ : アンソロジー
- 著者
- 阿川佐和子 [ほか] 著
- 出版者
- PARCO出版
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 2013