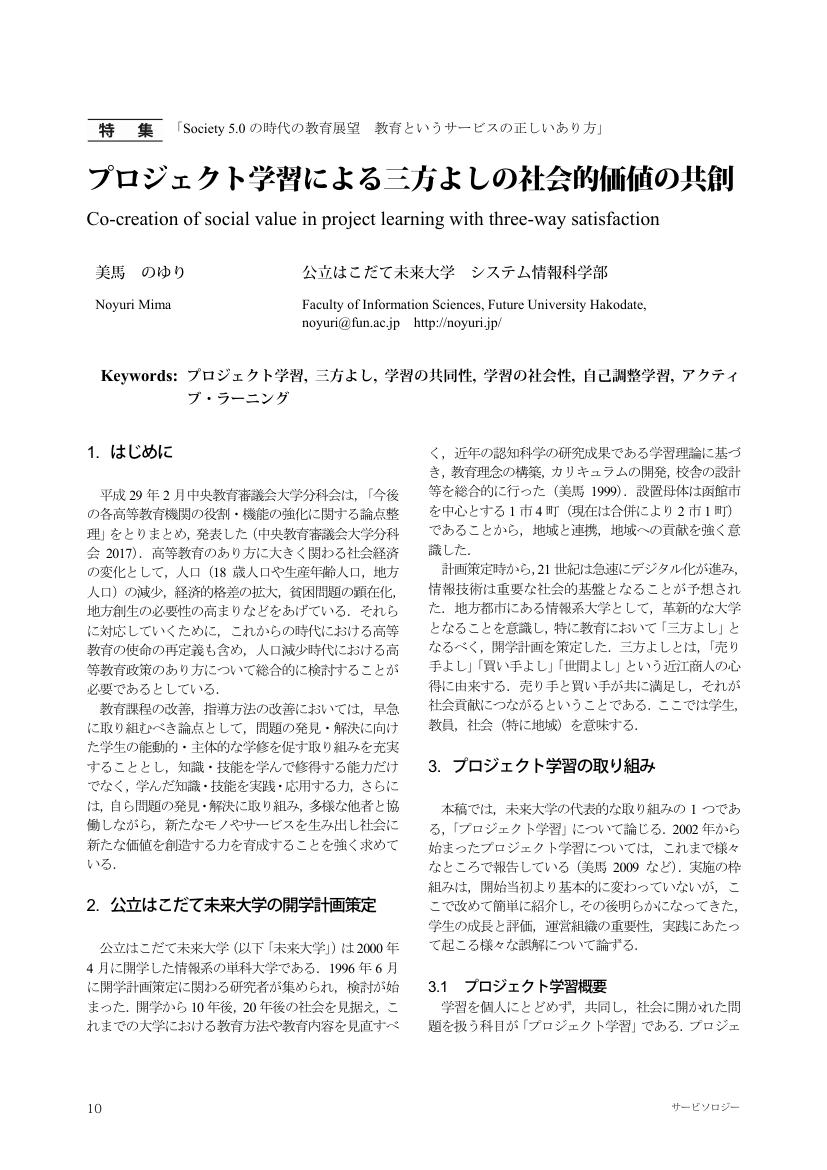1 0 0 0 コンピュータの教育的利用からラーニングトランスフォーメーションへ
- 著者
- 美馬 のゆり
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE) (ISSN:21884234)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.1-9, 2019-10-11
日本では人生100年時代といわれ,生涯学び続ける時代が到来した.学校教育から,職場での研修,地域活動や生涯学習施設,家庭まで,学習の場である学校,職場,地域では,学習者の背景は多様性を増してきている.これらの課題の解決において,情報科学・工学からの貢献が期待されている.社会全体に共通の教育にかかわる問題を解決するために,情報科学・工学,教育工学,認知心理学の横断的な観点から,学習方法や学習内容について歴史を振り返る.そこから,これらの分野の研究者が協力し,ラーニングトランスフォーメーションに向けた実現フレームワークを設計するための方向性を示す.
1 0 0 0 OA プロジェクト学習による三方よしの社会的価値の共創
- 著者
- 美馬 のゆり
- 出版者
- サービス学会
- 雑誌
- サービソロジー (ISSN:21885362)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.10-15, 2017-07-28 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- 森田 亜矢子 蒲生 諒太
- 出版者
- 関西大学教育開発支援センター
- 雑誌
- 関西大学高等教育研究 (ISSN:21856389)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.21-36, 2019-03-31
本稿は、情報通信技術(ICT: Information and Communication Technology)を活用したアクティブ・ラーニング授業の実践報告である。技術発展とグローバル化に伴い複雑に変化する今日の社会では、心理社会的リソースを活用しながら自律的に行動し問題解決を行うことができる人材の育成が求められている。他方で、大学のユニバーサル化が進み、学生の学力や学習習慣が多様化したことにより、一律の教育を施すことは困難になりつつある。様々な教育的ニーズを持つ入学者を、どのようにして専門的な学びへ導くかということは、初年次教育の課題である。本稿では、こうした背景をふまえて行った学習支援の取り組みと情報通信技術の活用について報告する。対象は、4年制大学の文系学部に所属する初年次生である。取り組みの内容は、次の5点である。1つめは、対話的で主体的な学習を促すための学生主導型の授業デザインの開発である。2つめは、オンデマンドな学習を質と量の両面から支援するための情報通信技術の活用である。3つめは、省察にもとづく自律的な学習の素材としてルーブリックを提示し、学習成果の可視化を試みたことである。4つめは、グループ学習とピア・レビューによる協調学習を組み入れて、社会的リソースを活用した連鎖型の学習を促したことである、5つめは、授業に対して学生がコミットしやすいよう、役割分担や教室内の配置に工夫をしたことである。結果、個別学習と協同学習を組み合わせた少人数ゼミナール形式の演習を実施し、情報通信技術を活用して授業内外の学習支援を行った。本稿では、取り組みの詳細を述べ、個々の取り組みについて考察を行う。
1 0 0 0 OA 三者間贈与の法的構造とその特質 : 英米法からみた寄付と公益信託に関する一考察
1 0 0 0 OA 突発性難聴のインターフェロン治療
- 著者
- 金丸 眞一 福島 英行 中村 一 木村 裕毅 玉木 久信
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.2, pp.171-176, 1994-02-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
The severe type of idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL) was treated with genetic recombination interferon alpha-2a (alpha-IFN) (3 million IU/day for 10 days) plus cortico-steroid, and the results were significantly better than those obtained by conventional treatment with cortico-steroid, vitamins, and vasodilators. Assays for 2'-5' oligoadenylate synthetase (2-5 AS), one of the indices of circulating anti-viral activity were performed patients before and on the third day of IFN therapy, and the levels were found to correlate well with the degree of their hearing improvement. These results suggest that viral infections may be related to the etiology of the severe type of ISSHL and that alpha-Interferon is useful in its treatment.
1 0 0 0 OA 呼吸不全を伴った急性肺炎に対するステロイド併用にかんする臨床的・実験的研究
- 著者
- 小林 宏行 押谷 浩 高村 光子 河野 浩太
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.10, pp.871-881, 1983-10-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 8
急性肺炎による呼吸不全を伴った症例 (15例) を対象に, 肺炎の早期治癒および呼吸不全の早期離脱を目的に広域抗生剤とステロイド剤の併用を行った.また家兎実験的肺炎を対象とし肺炎時呼吸不全発生のメカニズムおよびこれに対するステロイド剤の有用性について検討した.その結果, 肺炎発症後少なくとも4日以内にステロイドが併用されれば, 肺炎陰影の早期消失 (平均4.4日±1.7) およびPac2値の早期回復 (平均3.5日±1.4) が得られた.また, ステロイド併用によりその効果がみられなかった例は5例にみられ, これら症例のうち3例は高齢者高度進展肺炎で心不全併発による死亡例, 他の2例は肺炎治癒までに15日間を要した例であった. これら不成功例に共通することはステロイド併用開始時期の遅れ (平均7.6日±2.3) であった.肺炎時Pao2の低下は, 肺胞壁の著明な腫脹および肺胞腔内への滲出物充満等による肺内true shunt率増加にもとずくものとみられ, ステロイド剤はこれら肺胞壁の薄壁化あるいは滲出物を抑制しその結果呼吸不全の早期離脱を促進するものとみなされた.臨床的には以下の基準でステロイド併用が施行されることが望ましい. (1) 発病後4日以内, (2) Pao260mmHg以下, (3) 広域抗生剤の併用, (4) 使用期間は7日間以内.
1 0 0 0 OA 片麻痺患者の動作分析
- 著者
- 奈良 勲
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法のための運動生理 (ISSN:09127100)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.153-158, 1993 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 7
片麻痺患者の動作分析について、運動分析を含めた概念でそれぞれの障害レベルにおける運動・動作分析について述べた。いづれの分析においても、それらを片麻痺患者の障害像の把握と理学療法施行上のプログラム計画、更に理学療法効果の指標に役立てることである。これまで筆者らが行ってきた運動・動作分析に関連した研究の一部を紹介し、片麻痺患者の何を対象に、そして何の目的で行う必要があるかを提示した。
1 0 0 0 たのしい科学教育映画シリーズ : DVD版岩波科学教育映画選集
1 0 0 0 OA 現実構成と身体
- 著者
- 山岸 健
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.18-35, 1981-12-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1 1
社会学の研究領域では、まだ身体論と呼ばれるようなまとまった考察はおこなわれていないが、ヒューマニスティック・パースペクティヴで日常生活の世界と生活している人間に社会学のサーチライトが向けられてもいる現況において、私たちは、座標原点でもあれば根源的な表出空間でもある身体に注目しなければならないだろう。現象学的社会学でも身体についての若干の考察は見られるが、身体については、今日のところ、実存社会学の分野で積極的な検討が加えられている。ここでは、そのような検討をふまえて、人間と世界という軸で身体を視点として私たちが生きている世界地平に目を向けたいと思う。私たちにとって、現実構成は、日常的な営為なのである。現実構成とは何か、身体とは何か、ということを考えながら、人間そのものに向かっていきたいと思う。社会学的人間学にいたる一つのステップとして、現象学と社会学というコンテクストで身体について若干の考察を試みたいと思う。身体を考えるということは、日常生活の場面での世界経験を考えるということだ。私たちは、自分の身体によって、この世界に巻き込まれているのである。私たちが経験しつつある身体を出発点として私たちの身のまわりに目を向けるならば、私たちが生きている世界がどのように照らし出されるのだろうか。
1 0 0 0 J.D.ダグラスの実存社会学の理論的展開
- 著者
- 藤井 達也
- 出版者
- 早稲田大学社会学会
- 雑誌
- 社会学年誌 (ISSN:02887126)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.p19-35, 1983-03
1 0 0 0 IR ナメクジと蛇と蛙--今,ここの平和問題を考えるための一つの試み
- 著者
- 森島 吉美
- 出版者
- 広島修道大学
- 雑誌
- 広島修大論集 人文編 (ISSN:03875873)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.199-219[含 独文要旨], 2007-02
1 0 0 0 OA 周易正義序 譯注
- 著者
- 宇野 茂彦 UNO Shigehiko
- 出版者
- 名古屋大学文学部
- 雑誌
- 名古屋大学文学部研究論集 哲学 (ISSN:04694716)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.71-84, 1986-03
1 0 0 0 OA W. G. ゼーバルトにおける想起の空間 : 建築と記憶術
- 著者
- 鈴木 賢子
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.123-147, 2013
- 著者
- 井上 孝代
- 出版者
- 明治学院大学文学部心理学科
- 雑誌
- 心理学紀要 (ISSN:0918547X)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-11, 2003-03
- 著者
- 柳 久子 戸村 成男 森 淑江 江守 陽子 紙屋 克子
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 = Medical education (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.43-49, 2002-02-25
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 10