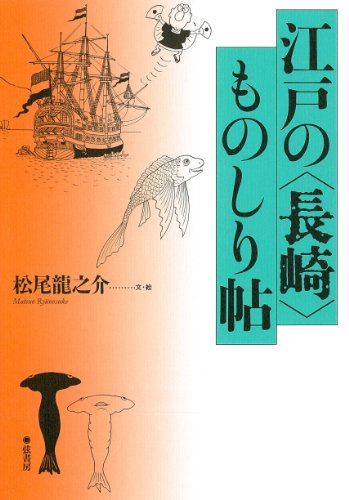6 0 0 0 OA 都市祭礼における「暴力」と規制 ―「スポーツ化」する岸和田だんじり祭―
- 著者
- 有本 尚央
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.59-71, 2017 (Released:2018-06-13)
- 参考文献数
- 17
本稿は、大阪府南部・岸和田市で行われる岸和田だんじり祭を事例に、都市祭礼の近代化の歴史を「暴力の抑制」という観点から分析することを通して、現代日本社会における祭りの変化について考察する。現在の岸和田だんじり祭は、地車(だんじり)と呼ばれる山車が事故を起こすほどの激しい曳行をする点に特徴があり、「やりまわし」と称される過激な地車の曳行が祭りの代名詞となっている。岸和田だんじり祭におけるけんかや事故などの過激で暴力的な特徴は、世間の耳目を集めると同時に、警察による規制の対象としても取り沙汰されてきた。こうした状況のなか、特に近年の岸和田だんじり祭ではやりまわしの高速化が指摘され、地車の曳行はますます過激なものへと変化する傾向にある。本稿では、現代社会においてなぜこのような祭りの変化が生じたのかという問いについて、祭礼組織と警察が暴力の規制をめぐって展開してきた過程に注目することで明らかにする。いわば、それぞれの時代における警察との関係のなかで、祭りの挙行に関してなにが問題とされたのか―祭りの渉外の焦点はどこにあったのかをたどることによって、祭りがどのようにかたちづくられてきたのかを分析する。その結果、現代社会における祭りが「スポーツ化」(Elias & Dunning 1986=1995)していることを明らかにする。
6 0 0 0 OA 帝都復興事業における隅田川六大橋の設計方針と永代橋・清洲橋の設計経緯
- 著者
- 中井 祐
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.13-21, 2004-06-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 2
This thesis discusses on the design concept of six bridges in Sumida river constructed as the Tokyo reconstruction work in Taisho era and the design process of Eitai bridge and Kiyosu bridge based on descriptions written by Enzo Ota and Yutaka Tanaka who was engineers of the Bureau of Reconstruction. Especially it is argued that the most essential design consept of six bridges was to introduce long spanned plate girder structure into six bridges and Eitai bridge and Kiyosu bridge were designed as a set by making reference to the design competition for Koln bridge in 1911. Furthermore, it is showed that there is possibility Eitai and Kiyosu bridges were constructed as the groundwork for furure development of technology of long spanned bridges in Japan.
6 0 0 0 OA Correlations Between Entrance Examination Scores and Academic Performance Following Admission
- 著者
- SHIYUE HE KAZUO KEMPE YUICHI TOMIKI MASAKO NISHIZUKA TSUTOMU SUZUKI TAKASHI DAMBARA TAKAO OKADA
- 出版者
- The Juntendo Medical Society
- 雑誌
- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.142-148, 2015 (Released:2015-08-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 8
Purpose: The present study was conducted to compare students’ entrance examination scores for a school and their grades following admission to discuss the methods for implementing screening tests and advice or guidance for students admitted to the school.Subjects and Methods: The subjects were students who took the general entrance examination for the Faculty of Medicine of Juntendo University and were admitted between 2004 and 2006. The entrance examination scores and academic performance were converted using a scale of one to 100, and Pearson’s product-moment correlation coefficient was calculated.Results: There were significant correlations between the English test scores for the entrance examination and academic performance in many subjects. On the other hand, there were non-significant negative correlations between the mathematics test scores for the entrance examination and academic performance in many other subjects.Conclusion: Students’ English test scores for the entrance examination are important since their academic performance following admission can be predicted from them. Students’ mathematics test scores for the entrance examination were negatively correlated with their academic performance in many subjects. Therefore, when students are provided with guidance for learning following admission, their mathematics scores should be taken into consideration.
6 0 0 0 OA 平民苗字必称令 : 国民皆姓
- 著者
- 井戸田 博史
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 日本法政学会法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.39-48, 1985-05-20
The present paper is an extract from my presentation "The Name Policy in the early Meiji Era" given at the conference of the Japan Association of Legal and Political Sciences in May, 1984. Before Meiji, a person's surname indicated his lineage and his privileged status. Only the people in the privileged classes-the samurai class and above-were permitted to have their family names. In the Meiji Era, however, the surname came to be regarded as the name of "Ie(家)" after many complicated processes, and it was ordered that all Japanese should have their surnames. After the Second World War, "Ie(家)" was abolished, and as the result, today's surname has come to be considered to be the name of the individual. Actually, however, the surname is not necessarily understood as the name of the individual in our feelings and customs, and consequently, it brings forward many problems. Therefore, the problems involved in the surname are old but new. Our surnames today are based on the name policy adopted in the early Meiji Era. The purpose of this paper is to clarify the nature of the name policy adopted in that period, because it will be an important clue to approach the complicated problems involved in the present-day surname. This paper contains the following items: 1. Introduction 2. The way to "the Ordinance to compel the Commoner to have their Surnames" (1) The denial of the "privileged surname" given by the former Tokugawa shogunate (2) "The Ordinance to Permit the Commoner to have thier Surnames" 3. The Ordinance to Compel the Commoner to have their Surnames 4. Prospects
6 0 0 0 OA 千葉県千葉郡誌
- 著者
- 千葉県千葉郡教育会 編
- 出版者
- 千葉県千葉郡教育会
- 巻号頁・発行日
- 1926
6 0 0 0 OA 世界映画俳優名鑑
- 著者
- 映画世界社編輯部 編
- 出版者
- 映画世界社
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和6年版, 1930
6 0 0 0 OA 学習方略としての言語化の効果
- 著者
- 伊藤 貴昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.237-251, 2009 (Released:2012-02-22)
- 参考文献数
- 71
- 被引用文献数
- 5 7
学習者に言語化を促すと学習効果が促進されることがある。本稿では, そのような学習方略として言語化を活用することの効果を検討するため, 関連する3つの研究アプローチ(自己説明研究, Tutoring研究, 協同学習研究)を取り上げ, その理論と問題点を概観した。その結果, (1) 自己説明研究では言語化の目的が不明確であるため, 方法論の多様性という問題を抱えており, (2) Tutoring研究では, 知識陳述の言語化に留まってしまう学習者の存在が指摘され, (3) 協同学習研究では言語化の効果ではなく認知的葛藤の源泉としての他者の存在を指摘していること, の3点が明らかとなった。これらの問題を解決するため, 本稿ではTutoring研究において指摘された知識構築の言語化を取り上げ, 認知的葛藤を設定することで, 関連する研究アプローチを統合するモデル(目標達成モデル)を提案した。このモデルによって, これまでの研究によって拡散した理論を一定の方向へと収束可能となることが示唆された。
6 0 0 0 OA デンプン病と綿ふき病
- 著者
- 二国 二郎
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.205-208, 1965-02-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 10
6 0 0 0 江戸の「長崎」ものしり帖
6 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1947年04月18日, 1947-04-18
6 0 0 0 OA MKng: 次世代マイクロカーネル研究プロジェクト
- 著者
- 徳田 英幸 追川 修一 西尾 信彦 萩野 達也 斎藤 信男
- 雑誌
- 全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.第53回, no.アーキテクチャサイエンス, pp.39-40, 1996-09-04
慶應義塾大学環境情報学部における次世代マイクロカーネル研究プロジェクト(MKngプロジェクト)は,1996年から参加企業10社, 3大学とともにスタートした.本プロジェクトは,慶應義塾大学が中心となって開発している分散実時間マイクロカーネル技術,および,IPA開放型基盤ソフトウェア研究開発評価事業「マルチメディア統合環境基盤ソフトウェア」プロジェクトで開発したマルチメディア拡張機能を踏まえ,分散/並列システム,マルチコンピュータシステム,組込みシステム,高速ネットワークシステムやモーバイルシステムに応用するための基盤ソフトウエアとしての次世代マイクロカーネル技術の研究開発,評価,普及拡大を目的としている.また,特に単一プロセッサアーキテクチャだけに依存せず,アプリケーション,ハードウェア,ネットワーク構成など個々のシステム特性に対して,動的に適応可能なカーネルアーキテクチャを研究し,マイクロカーネルによりモーバイルシステムからスケーラブルな並列システムまでを統合した分散コンピューティング環境を実現することが目的である.本論文では,MKngプロジェクトの目的およびプロジェクトの概要について解説する・
6 0 0 0 OA 反社会性人格障害傾向者における遅延ならびに確率による報酬の価値割引
- 著者
- 佐藤 徳
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.50-59, 2008-09-01 (Released:2008-10-24)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3 3
反社会性人格障害(ASPD)は,違法行為の反復,人をだます傾向,衝動性,無責任性,良心の呵責の欠如によって特徴づけられる。本研究は,2つの行動選択課題を用いて,ASPD傾向者が高い衝動性を示すかを検討した。遅延価値割引課題では,参加者は,即時小報酬と遅延大報酬の間で選択を行う。衝動性は即時小報酬への選好と定義される。他方,確率価値割引課題では確実な小報酬と不確実な大報酬との間で選択を行う。衝動性は不確実な大報酬への選好と定義される。16名のASPD傾向者と19名の健常者が両課題を行った結果,まず,遅延価値割引課題ではASPD傾向者は健常者より急激に遅延報酬の価値を割り引くことが示された。確率価値割引課題では両群の差はなかった。遅延価値割引は,「反社会的行為の反復」ならびに「性的関係における無責任性・搾取性」と有意に関連していた。本結果から,長期的な結果の価値を切り下げることがいくつかのASPD症状の根底にあることが示唆された。
6 0 0 0 OA 筑波大学工学システム学類における熱力学の教育改善
- 著者
- 金川 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.72-76, 2018-07-15 (Released:2018-08-15)
- 参考文献数
- 2
1.“工学科”での熱力学教育の問題点筑波大学理工学群工学システム学類は,機械,土木,建築,電気,情報などの工学分野を包含する,理工学部“工学科”なる表現が適切な学科である (以下,“工学科”).著者は“工学科”のう
- 著者
- 児島 亜紀子
- 出版者
- 日本ソーシャルワーク学会
- 雑誌
- ソーシャルワーク学会誌 (ISSN:18843654)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.5-8, 2022 (Released:2022-07-12)
6 0 0 0 OA バイオメトリック認証技術の研究開発と製品化への期待
- 著者
- 瀬戸 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.77-83, 2014-10-01 (Released:2014-10-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
日本におけるバイオメトリック技術は,2004年に金融機関のATM(Automatic Teller Machine)への静脈認証装置の採用,2006年にはIC旅券,2007年にはIC運転免許証への顔データの実装というように,社会基盤システムに着実に展開された.2010年を境に米国においてバイオメトリック市場のパラダイムシフトを目指す「Post 9.11」という動きが出てきた.次のステージに向けた市場の拡大の可能性はあるが,民生利用や行政サービスなどに利用されるには,バイオメトリクス特有の問題への対策が以前にも増して重要となっている.つまり,識別,認証のほか,ビッグデータ分野への応用として追跡という新しい利用分野が立ち上がり,これらの市場拡大には,プライバシーへの対策技術が重要である.本稿では,今後必要な技術開発及び製品化のポイントについて述べる.
6 0 0 0 OA イギリス 2022年議会解散及び召集法の制定
- 著者
- 上綱秀治
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 292-1), 2022-07