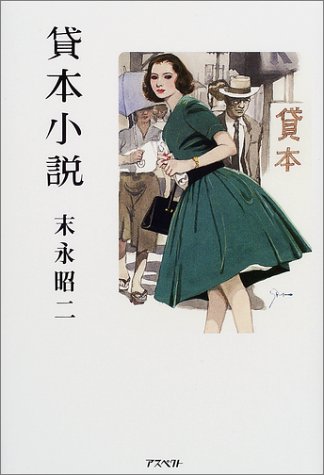- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.861, pp.23-26, 1996-10-14
シリコンバレーに本拠を置くベンチャーキャピタル(VC)では最大手のクライナー・パーキンスには,今年,予定する投資額の3倍以上の資金が集まった。同じVCのアクセルパートナーズのオフィスには,毎週月曜日になると未来のビル・ゲイツを目指した起業家の長蛇の列ができる。
1 0 0 0 J.B.コナント博士--その人となりと業績
- 著者
- 坂西 志保
- 出版者
- ぎょうせい
- 雑誌
- 文部時報 (ISSN:09169830)
- 巻号頁・発行日
- no.1006, 1961-04
- 著者
- 安達 洋祐
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床外科 = Journal of clinical surgery (ISSN:03869857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.458-461, 2013-04
1 0 0 0 OA 救急搬送症例における覚知時刻・場所および救急隊判断程度と搬送先病院の選定困難性の関連
- 著者
- 熊谷 美香 北野 尚美 小松 枝里香 道場 浩幸 上野 雅巳
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.116-124, 2018 (Released:2018-04-03)
- 参考文献数
- 19
目的 救急搬送所要時間に悪影響を及ぼす要因のうち,介入可能な要因の1つに,搬送先医療機関の選定に要する時間がある。そこで,本研究では,病院選定が困難だった救急搬送症例について,覚知時刻と覚知場所,救急隊判断程度の特徴を明らかとした。方法 研究期間は2014年1月1日から12月31日の1年間で,和歌山県内で救急車搬送された,小児疾患を除く41,574件を研究対象とした。本研究では,照会回数に欠損値があった129件を除いた41,445件を解析した。照会回数4回以上を病院選定困難として,覚知時刻と覚知場所,救急隊判断程度について,調整オッズ比(OR)と95%信頼区間(CI)を二項ロジスティック回帰分析によって計算した。全体と主要診断群分類(Major Diagnostic Category,MDC)で層別化して,外傷・熱傷・中毒,神経系疾患,消化器系疾患・肝臓・胆道・膵臓疾患,呼吸器系疾患,循環器系疾患について解析結果を示した。結果 照会回数の分布は1~12回で,全体の79.6%は1回であり,4回以上は3.5%であった。全体の解析では,照会回数4回以上について,覚知時刻は,平日日勤を基準とした場合に,その他いずれの時間帯も有意に照会回数4回以上で,土日祝深夜の調整OR(95%CI)は4.0(3.2-5.0)と最も高かった。また,中等症以下を基準とした場合に,重症以上の調整OR(95%CI)は0.8(0.7-0.9)で,照会回数が有意に3回以下であった。ただし,MDC分類で層別化した解析の結果,外傷・熱傷・中毒の疾患群では,救急隊判断程度が重症以上の調整OR(95%CI)は1.4(1.0-1.8)で照会回数が有意に4回以上であった。結論 和歌山県全域において1年間に救急車搬送された成人全例を対象とした解析で,覚知時刻が土日祝深夜であったことと,救急隊判断程度が中等症以下であったことは,搬送先病院選定の照会回数が4回以上のリスク因子であった。ただし,MDC分類で層別化した解析によって,外傷・熱傷・中毒の疾患群では,救急隊判断程度が重症以上の調整OR(95%CI)が1.4(1.0-1.8)で照会回数が有意に4回以上であった。
- 著者
- 堀之内 広子 本砥 貴子 宇田 英典
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.134-141, 2018 (Released:2018-04-03)
- 参考文献数
- 7
目的 医療や介護の基盤が十分でない外海小離島において疾病や加齢にともない生活を継続することが困難になったとしても,住み慣れた島での看取りを希望する住民のニーズに対応するための体制整備は,離島を有する自治体やそれを支援する都道府県といった行政の責務である。今回,外海小離島での看取り支援に活用することを目的として「看取りに関する事務マニュアル」を取りまとめたので,この作成プロセスとこれを用いた支援の展開について報告する。方法 外海小離島だけで構成される十島村の現状や看取りの阻害因子などを検討し,それらの結果をもとに,関係する機関・団体で協議を重ね「看取りに関する事務マニュアル」(以下マニュアル)を作成した。その後,マニュアルを活用して,看取り支援を行うとともに,課題や成果を検討しマニュアルの改訂を行った。結果 外界小離島での看取りにあたって,重要な問題となる死亡前後の関係機関・団体の対応について考え方や事務的手順をまとめたマニュアルを作成し,関係機関・団体で共有したことで,医療や介護の提供体制や専門職の人材が十分でない外海小離島であっても,複数の事例の看取り支援を行うことができた。さらに,これらの看取りを行う過程で生じた課題や成果を,関係機関・団体で情報共有,再検討し,マニュアルの改訂を行った。今後,地域や住民のニーズに即した看取り支援が行われることが期待される。結論 外海小離島という厳しい地域特性を踏まえながらも,現実的な支援を行うためにマニュアルの必要性は高い。また,村が主体となって進めるマニュアル作成や改訂作業のなかで,地域特性の分析・評価,協議の場の確保,広域に及ぶ医療機関や県,国の機関との調整など,保健所が果たすべき役割は重要であることが確認された。
- 著者
- 林 千景 前馬 理恵 山田 和子 森岡 郁晴
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.107-115, 2018 (Released:2018-04-03)
- 参考文献数
- 30
目的 住民の健康づくりには,個人への保健指導だけでなく,住民組織と協働した活動が有効とされ,住民組織である健康推進員(以下,推進員)の活動が注目されている。本研究は,現在活動している推進員(以下,現推進員),過去に推進員を経験した者(以下,既推進員),推進員を経験したことのない者(以下,非推進員)によるヘルスリテラシー,ソーシャルキャピタル,健康行動の特徴を明らかにし,推進員の育成について検討する資料を得ることを目的とした。方法 A町の現推進員87人,2009年4月~2015年3月の間に推進員を経験した既推進員158人,非推進員299人に,郵送による無記名自記式質問紙調査を行った。現推進員54人(有効回答率62.1%),既推進員69人(43.7%),非推進員136人(45.5%)から回答を得た。調査内容は,属性,現推進員および既推進員の活動状況,主観的健康観,健診(検診)の受診の有無,ヘルスリテラシー,ソーシャルキャピタル,健康行動等について質問した。結果 ヘルスリテラシー得点,ソーシャルキャピタル得点,健康行動得点のいずれの得点も現推進員,既推進員,非推進員間に有意な差は認められなかった。現推進員は,活動を「行政が企画する行事の手伝い」と感じている者が多かった。現推進員は地域の人々への働きかけと,主観的健康観で「健康」と感じている者が既推進員および非推進員に比べて有意に多かった。結論 推進員の育成にあたっては,推進員活動を主体的に取り組めるように支援することが必要である。
1 0 0 0 OA 役者見立東海道五十三駅 (目次)
1 0 0 0 潮岬周辺海域の微細構造
- 著者
- 前川 陽一 中村 亨 仲里 慧子 小池 隆 竹内 淳一 永田 豊 Maekawa Yoichi Nakamura Toru Nakazato Keiko Koike Takashi Takeuchi Junichi Nagata Yutaka
- 出版者
- 三重大学大学院生物資源学研究科
- 雑誌
- 三重大学大学院生物資源学研究科紀要
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.45-55, 2011-02
- 被引用文献数
- 1
By using the training ship Seisui-maru, we observed of detailed oceanic condition in the vicinity of Cape Shionomisaki, the tip of the Kii Peninsula in April, 2009 and in October, 2009. The sea level difference between Kushimoto and Uragami tide stations is used to monitor the flowing path of the Kuroshio, or to identify whether the Kuroshio is taking the straight path or the meandering path. It is shown that this sea level difference occurs in the narrow portion of about 7 km from off Cape Shionomisaki to off Oshima Island, and that the sea level difference is mainly created by the oceanic condition in the thin surface layer above 150 m. This indicates that the structure of the Kuroshio does not influence directly to the sea level difference between Kushimoto and Uragami. The sea level difference indicates whether warm and light Kuroshio Water is brought into shelf region to the west of Cape Shionomisaki or not, and whether the sea level difference between coastal waters to the west and to the east of Cape Shionomisaki. The success of this elaborated observation owe to improved facilities of the new training ship Seisui-maru2009 年 4 月と 10 月の 2 回にわたって, 勢水丸を潮岬周辺に派遣して, 従来に見られない詳細な海況の観測を実施した。黒潮の流路が直進路をとっているか, 蛇行路をとっているかをモニターするのに串本・浦神の検潮所間の水位差が用いられるが, この水位差は潮岬から大島の沖, 東西 7 km の部分で生じていることが示された。また, この水位差の殆どは, 僅か 100 ~ 150 m のごく表層の海洋構造によって作り出されたものであることが示された。串本・浦神の水位差には, 黒潮本来の構造が直接関与しているのではなく, 振り分け潮にともなう黒潮系水の潮岬西の沿岸域への侵入の有無, あるいはそれに伴って生じる潮岬東西の沿岸水の性質の違いを通してもたらされている。この微細海況観測成功には, 著しく向上した新しい二代目の勢水丸の能力が不可欠なものであった。
1 0 0 0 OA 大和物語 2巻
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1639
1 0 0 0 OA 労働力商品概念の形成(下)
- 著者
- 斎藤 彰一 SAITO Shoichi
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes liberales
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.57-71, 2001-01-01
1 0 0 0 OA 剰余価値の原因への問い : 『資本論』第1巻第5篇をめぐる諸問題について
- 著者
- 斎藤 彰一 SAITO Shoichi
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes liberales
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.83-94, 1999-01-01
1 0 0 0 OA ジョン・スチュアート・ミルにおける剰余価値率と利潤率
- 著者
- 齊藤 彰一 SAITO Shoichi
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes liberales
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.67-79, 2006-01-01
1 0 0 0 Netherlands journal of zoology
- 出版者
- E.J. Brill
- 巻号頁・発行日
- 1968
- 出版者
- Mauke's Verlag
- 巻号頁・発行日
- 1864
1 0 0 0 Biology of the reptilia
- 著者
- edited by Carl Gans
- 出版者
- Academic Press
- 巻号頁・発行日
- 1969
1 0 0 0 OA リカードウ分配論とマルクス剰余価値論
- 著者
- 斎藤 彰一 SAITO Shoich
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes liberales
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.89-100, 2000-01-01
1 0 0 0 OA 都立高校女性校長のキャリア形成過程に関する事例研究─男性校長との比較を通して─
- 著者
- 木内 隆生 Ryusei Kiuchi 東京農業大学教職課程 Teacher Education course in Tokyo University of Agriculture
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.47-55, 2017-09-29
本研究の目的は,都立高校の女性校長におけるキャリア形成過程を検討することである。先行調査からは近年の女性躍進の動きにかかわらず,中等教育学校段階で女性管理職数が少ないことが判明した。本研究では女性校長2名,男性校長2名の計4名に面接調査を実施し,5つの質問項目(ターニングポイント,自己開発,個人生活,後輩への助言,キャリアアップと力量形成)に対する女性校長の回答を男性校長との比較から分析した。その結果,女性校長のキャリア形成の特徴として20~30歳代での育児経験,40歳代での視野拡大と重要ポストの経験及びメンターの存在,50歳代でのしなやかな同僚性の構築が指摘された。