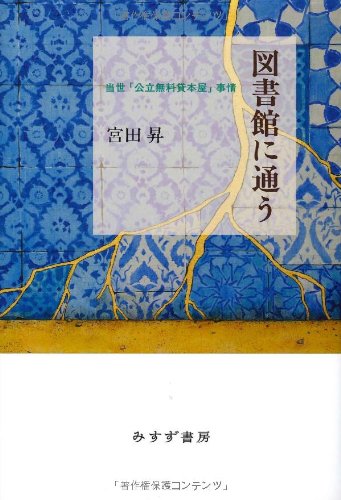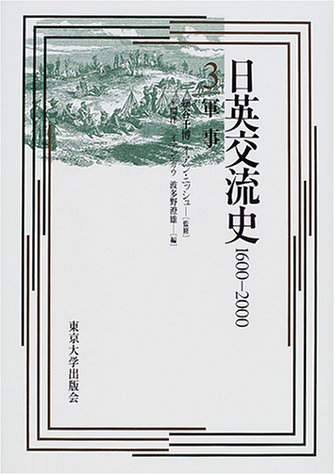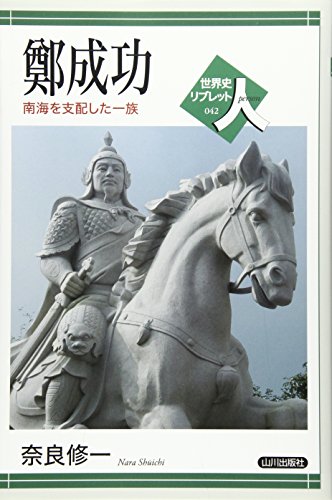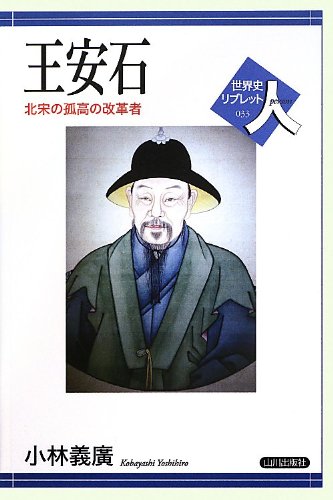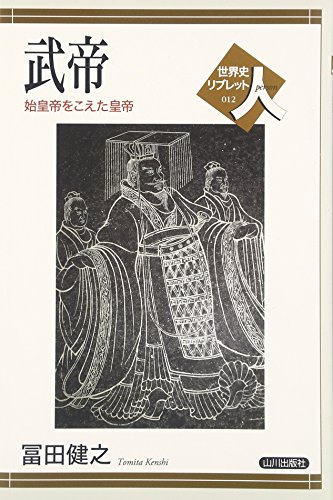1 0 0 0 OA 銭湯のデザインとライフスタイルの変遷に関する研究
- 著者
- 和田 菜穂子
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.50, 2005 (Released:2005-07-20)
公衆浴場は人々にとって身体を清めるだけでなく、コミュニケーションを図る場として重要な場所であった。江戸時代、公衆浴場のための水は、川や海から供給されていた。というのは、明治時代に公共の水道が開通するまで、水の供給はシステム化されておらず、水はとても貴重な資源であった。日本における公衆浴場の歴史は古く、身体を清めることが「沐浴」、「禊(みそぎ)」として宗教上行われていた。それは日本の風土、多湿な気候によるものが大きい。本稿では入浴の中でも特に公衆浴場(銭湯)に焦点をあて、デザインの歴史的背景を探る。手法として主に江戸時代における「浮世絵」や物語における「挿絵」などに描かれた建築デザインを分析することによって日本の文化、慣習を再現し、読み解いていくという新たな手法を用いる。江戸時代銭湯(公衆浴場)は社交の場として賑わいをみせていたが、第2次世界大戦後の日本人のライフスタイルの変化に伴い、銭湯の意味合いも大きく変化した。自家用風呂を所有する家庭が増え、銭湯離れが進むようになり今や問題となっている。
1 0 0 0 IR 地域外資源を活用した観光による内発的地域振興のあり方に関する研究
1 0 0 0 粛清の嵐と「プラハの春」 : チェコとスロヴァキアの40年
1 0 0 0 ハンガリーの「第三の道」 : 資本主義と社会主義のはざまで
1 0 0 0 図書館に通う : 当世「公立無料貸本屋」事情
1 0 0 0 OA 薬学における生命指向型化学(実用的ケミカルバイオテクノロジーの開発を目指して)
- 著者
- 猪熊 翼 佐藤 伸一
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.1, pp.37-38, 2018 (Released:2018-01-01)
1 0 0 0 軍事
- 著者
- 平間洋一 イアン・ガウ 波多野澄雄編
- 出版者
- 東京大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 鄭成功 : 南海を支配した一族
1 0 0 0 王安石 : 北宋の孤高の改革者
1 0 0 0 武帝 : 始皇帝をこえた皇帝
1 0 0 0 OA ロシア ロシア連邦対外政策概念の改定
- 著者
- 小泉悠
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 270-2), 2017-02
- 著者
- Makio Saeki Hiroshi Egusa
- 出版者
- The Japanese Pharmacological Society
- 雑誌
- Folia Pharmacologica Japonica (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, no.6, pp.277-280, 2014 (Released:2014-12-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
骨粗鬆症治療薬は骨吸収抑制薬と骨形成促進薬に分類される.従来の骨粗鬆症治療薬は骨吸収抑制薬が主流であったが,破骨細胞と骨芽細胞の活性が共役する機構が存在するために長期的には骨形成が低下して効果が減弱したり副作用が生じたりする問題点があった.骨形成促進薬anabolic agent としてはヒト副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)製剤であるテリパラチドが現在唯一の治療薬である.我々は破骨細胞におけるnuclear factor of activated T cells (NFAT)シグナルをターゲットとした骨吸収抑制薬の創薬を当初の目的として,RAW264.7 細胞を用いたセルベースアッセイ系を構築し,様々な化合物ライブラリーを用いた創薬スクリーニングを行ってきた.スクリーニング中に多くのNFAT 活性化小分子化合物を発見し,これらの破骨細胞を活性化させる化合物が,anabolic therapy に使用できる可能性があるのではないかと考えた.Anabolic agent として唯一臨床応用されているPTH 製剤が血中のカルシウム濃度を上昇させるしくみの一つに,骨吸収の促進がある.したがって,PTH の骨吸収促進という教科書的事実に固執していたら,テリパラチドが骨形成促進薬として開発されることもなかったであろう.PTH の持続的投与は骨吸収の促進をもたらすが,間歇的投与intermittent PTH(iPTH)treatment によるPTH の骨形成促進作用に注目したことが,テリパラチドという骨形成促進薬の開発につながった.我々はこのテリパラチドの例をヒントに,あえて破骨細胞の活性化薬をスクリーニングすることから,新しい骨形成促進薬を開発できないかと考えている.
1 0 0 0 OA ショーペンハウアーの美の形而上学における媒体論 --ヘーゲルの反映論と対照して
- 著者
- 鳥越 覚生
- 出版者
- 京都大学文学研究科宗教学専修
- 雑誌
- 宗教学研究室紀要 = THE ANNUAL REPORT ON PHILOSOPHY OF RELIGION (ISSN:18801900)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.58-77, 2017-12-28
Die Form und Farbe definieren sich Arthur Schopenhauer zufolge ein Medium, durch das man die Ideen anschauen kann. Wie kann man aber seine Lehre vom Medium verstehen, das er als die bloße Vorstellung(Erscheinung) charakterisiert? Um diese Frage zu beantworten, versucht dieser Aufsatz, seinen Begriff der „edlen Sinne(besonders Gesicht)" mit Helgels Konzept der „ideellen Sinne" zu vergleichen. Wie z.B. Nicolai Hartmann in „seiner Philosophie des deutschen Idealismus" analysierte, hätte Hegel den traditionellen Begriff vom Schönen wesentlich verändert. An sich genommen sollte die Idee vom Schönen schöner als ein sinnlich Schönes im daseienden Objekt. Die Idee als solche sei aber tatsächlich nicht schön. Der Satz, dass das Schöne Idee sei, drückt also Hegel zufolge nur die Härfte der Wahrheit aus. Denn die Idee ist erst „in ihrem Scheinen" schön. So identifizierte Hegel schließlich die ästhetische Idee mit ihrem Schein. Im Gegenteil verzichtet Schopenhauer auf die Überzeugung der ästhetischen Idee selbst. Er betrachtet nämlich das Schöne unter einer Perspektive auf die Konstruktion der Vorstellung(Objekt für Subjekt). Eine solche Einsicht über den Ideenverfall trifft für die nachhegelsche Zeitatmosphäre der Dekadenz und Pessimismus zu. Zusammenfassend kann man sagen, dass Schopenhauers Lehre vom Medium gerade ein typisches Beispiel der Übergangsperiode vom deutschen Idealismus ausmacht.
1 0 0 0 OA [天平年間宇陀郡収納状]
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1000
1 0 0 0 OA 本居宣長書簡二通 ―翻刻と考証―
- 著者
- 大久保 正
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 = The Bulletin Of The National Institute of Japanese Literature
- 巻号頁・発行日
- no.01, pp.233-249, 1975-03-25
まだ公刊されていない本居宣長の書簡中から、七月三日付門人荒木田尚賢宛の一通と、日付・宛名を欠くが、門人小篠敏宛と推定される一通の計二通を選び、本文を翻刻すると共に、その年次を考証し、あわせてその宣長研究上に有する意義を考察した。 From some letters of Motoori Norinaga which has not been yet published , a letter addressed to a disciple Arakida Hisakata dated July 3rd and the one with no address and date to a disciple Ozasa Minu, 2 letters in total were chosen, the text was reprinted and studied the year of historical evidence. In addition,the meaning in a study of Norinaga was considered.
- 著者
- 齊藤 万比古
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.277-284, 2010-04-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 7
発達障害は最初に子どもの年代で診断されることが多い障害の代表的なものであるが,発達障害とされる諸障害が成人で注目されるようになったのはわが国ではごく最近のことである.注目が集まるにつれ,成人の間に発達障害を見出したとの症例報告が増えているが,診断の困難さは成人における各発達障害の臨床像が必ずしも確立していないことにもある.診断を難しくしている最大の要因は,発達障害における併存精神障害の併発率の高さと多様さにある.難治性の,あるいは対応困難な成人期の精神障害や心身症の背景に発達障害が存在していないか否かを見極める視点が,この領域の臨床家にとって必須なものとなっている.こうした観点での精神医学および心身医学の整理が必要ではないだろうか.
1 0 0 0 小袖模様雛形本にみられる『源氏物語』を主題とした意匠について
- 著者
- 佐藤 了子
- 出版者
- 聖霊女子短期大学
- 雑誌
- 聖霊女子短期大学紀要 (ISSN:0286844X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.42-51, 2011-03-31