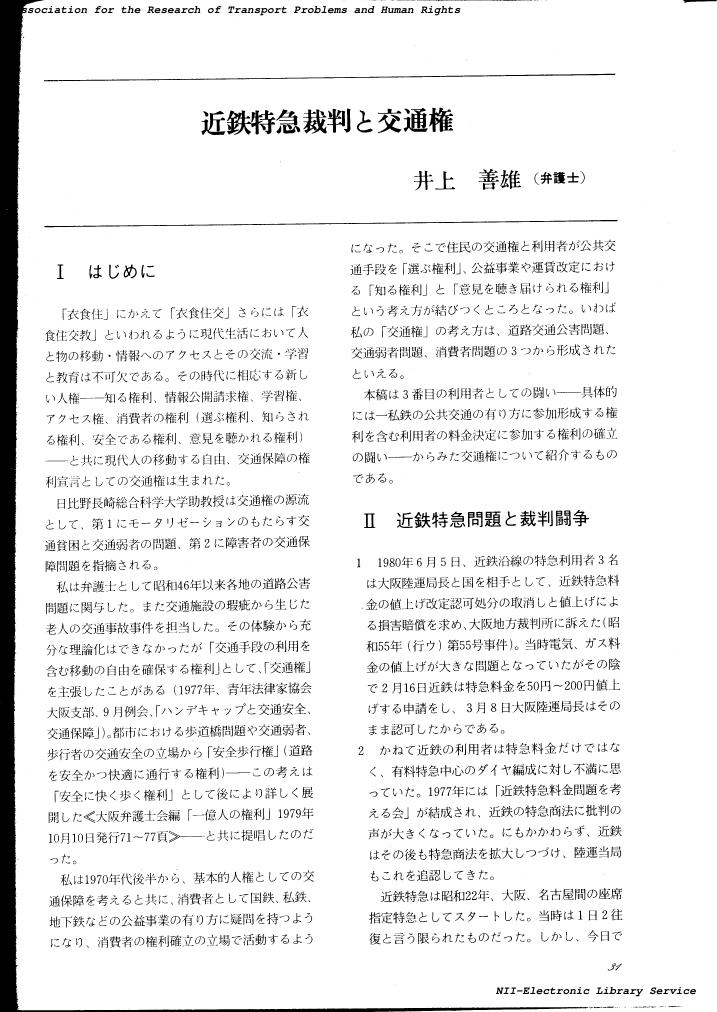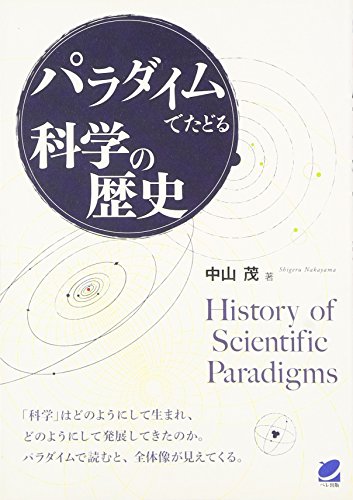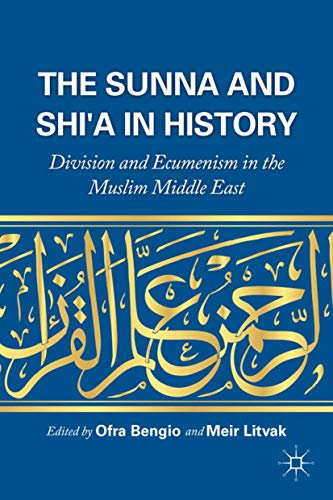5 0 0 0 OA 資産課税の構造
- 著者
- 小山 光一
- 出版者
- 北海道大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.49-78, 2003-06-10
5 0 0 0 OA 排泄をめぐる幼児語の研究-その1-
- 著者
- 小林 良夫
- 出版者
- 東海学院大学・東海女子短期大学
- 雑誌
- 東海女子短期大学紀要 (ISSN:02863170)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.131-138, 1996-03-31
5 0 0 0 OA 近鉄特急裁判と交通権
- 著者
- 井上 善雄
- 出版者
- 交通権学会
- 雑誌
- 交通権 (ISSN:09125744)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.3, pp.31-35, 1986 (Released:2017-04-10)
- 著者
- Masato Nitta Kazuya Nagasawa
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-5, 2017-05-25 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
Dactylogyrus oryziasi n. sp. (Monogenea: Dactylogyridae) is described from the gills of the southern medaka Oryzias latipes (Temminck and Schlegel, 1846) (Beloniformes: Adrianichthyidae) collected from an irrigation canal, Tokushima city, Tokushima Prefecture, Shikoku, Japan. This new species resembles Dactylogyrus rysavyi Ergens, 1970 in having a coiled penis passing through a tube of an accessory piece associated with a sigmoid rod, and shapes of haptoral parts, but these species differ from each other by turns of the penis and a connection point between the rod and tube of the accessory piece. This is the first record of Dactylogyrus from beloniform fish.
- 著者
- 安東 奈穂子
- 出版者
- 社団法人人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.643-652, 2010-09-01
- 参考文献数
- 6
5 0 0 0 OA マス・メディアによる性的描写の利用と効果に関する72の一般化
- 著者
- 浜野 保樹
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A, 教育研究 (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.91-121, 1979-03
Although sex explicit materials are often criticized because of their negative effects on the audience, there are very few scientific data on their influences in Japan. In several other countries including the United States, a considerable amount of empirical research on sex explicit materials has been done and published so far. Among them the Report of the Commission on Obscenity and Pornography, which was published in 1970, played a significant role in this field. This field, which deals with the effects of the sex explicit materials, can be included in the literature of mass communication study. In order to summarize and synthesize the results, more than 100 research papers were collected and, based on their findings, a total of 72 generalizations was led and proposed in this paper. Generalizations were led by the so-called head count approarch. According to this approach the following procedures are taken: 1. collecting studies which are satisfactory in statistical viewpoints and have verifications on at least one relationship between two variables. 2. grouping studies which deal with the same two variables. 3. when the supportive studies surpass the non-supportive, the relationship was put as a generalization. It should be noted, however, that the generalization method by head count approrch can not clearly reflect the qualitative aspects including research procedures. As far as the 72 generalizations concerned, they might give the impression that sex explicit materials are harmless. In Japan, however, it seems inadequate to conclude that they are harmless because the most of the studies were done in the United States and few cross-cultural studies have been done. In addition, unlike the United States, the television code on sex explicit contents are not so strict in Japan. Therefore, the effects to mass, especially to young chldren and adolescents should be thoroughly investigated before making such conclusions. For future studies, the cummulative effects or long term effects of such kind of materials and the relations between sexual behavior and violence should be challenged to have more reliable conclusions.
5 0 0 0 OA 読むことに障害のある児童生徒がアクセス可能な電子教科書の利用
- 著者
- 近藤 武夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.247-256, 2012 (Released:2013-09-18)
- 参考文献数
- 33
米国の公立初等中等教育では、視覚障害、肢体不自由、学習障害などの多様な障害を原因として印刷物にアクセスすることが難しい児童生徒に対し、電子データ形式で作られた教科書を無償で入手できる環境が、連邦政府により整備されている。また、こうした電子教科書の利用においては、電子教科書データの提供だけではなく、支援技術製品の児童生徒への提供、および支援技術の専門家による利用支援の提供が、個別障害者教育法(IDEA)を背景として制度化されている。本論文では、障害のある児童生徒にとってアクセス可能な電子教科書の入手および学校場面での利用とその支援に関して、米国の現状を概観し、また、日米の現状比較を通じて日本国内で解決すべき電子教科書および支援技術利用上の課題について検討する。
5 0 0 0 كتاب الفتوة
5 0 0 0 OA Web上の人物へのNDLSHの付与
- 著者
- 下倉 雅行 村上 晴美
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, 2017
Web上の人物の理解と選択を支援するために,Web上の人物に図書館の件名標目であるNDLSHを付与する手法を検討する.20氏名×50件のWeb検索結果を人手で同姓同名人物に分離した人物クラスタを対象として,NDLSHの付与実験を行った.テキスト(タイトル,全文,氏名の前後),Webページの件数,同義語の利用と重み,文書頻度と逆文書頻度の利用を組み合わせた調査結果を報告する.
5 0 0 0 IR おぞましさの美学の帰趨 : 「吐き気」の芸術的表象について
- 著者
- 長野 順子
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 美学芸術学論集 (ISSN:18801943)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.3-20, 2010-03
- 著者
- 澤本 裕明
- 出版者
- 防衛衛生協会
- 雑誌
- 防衛衛生 (ISSN:00065528)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.9, pp.143-148, 2005
5 0 0 0 パラダイムでたどる科学の歴史
5 0 0 0 OA 韓国券番 (1908-1942) における妓生教育
- 著者
- 許 娟姫
- 出版者
- 舞踊学会
- 雑誌
- 舞踊學 (ISSN:09114017)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.31, pp.48-59, 2008 (Released:2010-04-30)
Kwonbon is one of the systems transplanted from Japan to Korea during colony period and had been maintained from 1908 to 1942 under the governance of Japan. Kwonbon is mostly in charge of business management and art education for Geisha. Kwonbon system in Japan like this was applied to Korea in almost the same form with a policy. Kiseng, that is Female artists from the Palace and the Government, is an object. Kiseng during colony period had made a living and had kept traditional music and dance.Kwonbon had been completely disappeared around 1950's. However traditional dancers who have been lived in those periods testifies that numerous Korean traditional dancer including those who have important intangible cultural assets were educated at Kwonbon.This study focuses on how Kwonbon in Japan was transplanted and had rooted in Joseon (Korea), what was the details of education for Kiseng, and what kind of dance was educated. First of all, as a background of Kiseng education at Kwonbon, history from the introduction of Kiseng Union whose predecessor to the establishment of Kwonbon is reviewed and the role of Kwonbon as an administrative organization is summarized. From the examples of Seven Kwonbon in each area, basic Kiseng education and teacher, and details of dance education are studied.
5 0 0 0 OA 111. 原発事故分析をとおしての「科学社会学」の方法論
- 著者
- 桜井 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.462-468, 2002-12-25 (Released:2010-01-21)
- 参考文献数
- 31
The technology of light water reactor will continue as a realistic energy technology for about half century at least from now on. The social agreement is necessary to continue nuclear power generation. Nuclear community must renew the conventional thought partially and have to approach the thought close to the value judgment in another social coordinate. "The Sociology of Science" on the atomic energy shall be such contents that be able to contribute to the unify or to attaches both coordinates as near as possible.
5 0 0 0 OA 噴火史からみた伊豆大島噴火の類型・成因と1986年噴火の意味
- 著者
- 小山 真人 早川 由紀夫
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-10
1986年噴火は、地層として残る降下スコリアをカルデラ外に降らせたこと、カルデラ外で側噴火を起こしたこと、の2点で過去の伊豆大島の「大噴火」(Nakamura,1964,地震研彙報)と類似し、1986年と同程度の噴出量であった1912〜14年噴火や1950〜51年噴火とは異なっている。しかしながら、数年間にわたって継続的に火山灰を降らせる時期(火山灰期)がないこと、総噴出量が大噴火にしては小さいこと、の2点で過去の大噴火と異なっていたため、これらの欠損条件を満たすためにやがて火山灰期が始まると当初は予想された。ところが1987年11月18日の噴火をきっかけに火口直下のマグマはマグマ溜りに戻り(井田ほか,1988,地震研彙報)、 火山灰期は訪れなかった。1986年噴火は、カルデラ形成以降の過去1500年間に一度も起きたことのない特殊な噴火だったのか、それとも前提となる大噴火の概念に問題があるのか、の疑問が残された。その後、伊豆大島のカルデラ外に地層として確認できるテフラとそれを挟む噴火休止期堆積物の層序と分布を注意深く検討した小山・早川(1996,地学雑誌)は、明瞭な噴火休止期間に隔てられた24回の中〜大規模噴火を識別した上で、降下スコリアと降下火山灰の両方をともなう12噴火(Type 1)、降下スコリアのみをともなう7噴火(Type 2)、降下火山灰のみをともなう5噴火(Type 3)、の3類型に分類した。Type 1には噴出量1億トン以上の大規模な噴火が多く、1986年噴火はType 2のひとつである。また、Nakamura (1964)の提唱した降下スコリア→溶岩流出→火山灰期の噴火サイクルを厳密に満たす噴火は、Type 1の12噴火中の7つにすぎないこともわかった。こうして1986年噴火が伊豆大島の噴火史上とりたてて特殊な噴火でないことが明らかとなったが、肝心の噴火類型の成因は未解明のままであった。また、先述した1912〜14年噴火や1950〜51年噴火などの非爆発的な小〜中規模噴火の位置づけも十分できていなかった。中村 (1978,岩波新書)は、1)噴火末期に主火道内のマグマ頭位が低下すると、火道壁の崩落などでマグマ頭部のガス抜けが阻害されるために爆発的噴火が繰り返して火山灰を放出する火山灰期となり、2)さらにマグマ頭位が低下する場合には、火道内に地下水が浸入して水蒸気マグマ噴火が起きると考えた。噴火末期にマグマ頭位が中途半端に低下したまま停滞する場合には火山灰期が訪れるだろうが、すみやかに地下深部へ低下してしまえば火山灰期がないまま噴火が終了するだろう。主火道のマグマ頭位をすみやかに低下させる原因としては、側方へのマグマ貫入が考えやすい。貫入から約1年のタイムラグはあったが、実際にそれが起きたのが1986-87年噴火と考えることができる。三宅島2000年噴火でも、マグマの側方貫入によって主火道のマグマ頭位が約2ヶ月間かけて低下し、その後8月18日や29日の爆発的噴火が生じたが、火山灰期に相当する噴火は起きずに噴火が終了した。一方、カルデラ外に堆積物が確認できない1876年から1974年までの伊豆大島の一連の小〜中規模噴火は、全般的にマグマ頭位が高かった期間(火道内の赤熱したマグマ頭部が断続的に目視された期間)に発生した。この視点にもとづいて、カルデラ外に堆積物を残さなかった小規模噴火も含む伊豆大島の噴火の特徴とその成因を、統一的に次の5類型に再分類することができる。すなわち、(1)マグマ頭位が高い時期に生じた非爆発的な小〜中規模噴火(1974年、1950-51年など:旧類型の対象外)、(2)マグマの側方貫入が起きず、マグマ頭位低下が緩慢かつ限定的であったため短い火山灰期が生じた5つの中規模噴火(Y0.8、Y3.8、N3.0など:旧類型のType 3)、(3)マグマの側方貫入が起きてマグマ頭位低下がすみやかに進行したため火山灰期が生じなかった7つの中規模噴火(1986年、Y5.2、N3.2など:旧類型のType 2)、(4)マグマの側方貫入が起きたが、何らかの原因でマグマ頭位が中途半端に低下したまま停滞して長い火山灰期が生じた9つの中〜大規模噴火(1777-78年=Y1.0、Y4.0、N4.0など:旧類型のType 1)、(5)マグマの側方貫入が起きたが、何らかの原因でマグマ頭位が中途半端に地下水位付近で停滞し、大量の地下水浸入にともなう水蒸気マグマ爆発や岩屑なだれが生じた3つの中〜大規模噴火(S1.0、S1.5、S2.0:旧類型のType 1)。
- 著者
- edited by Ofra Bengio and Meir Litvak
- 出版者
- Palgrave Macmillan
- 巻号頁・発行日
- 2011
5 0 0 0 OA 図書紹介 『EPUB戦記:電子書籍の国際標準化バトル』
- 著者
- 仲俣 暁生
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.9, pp.644-644, 2016-12-01 (Released:2016-12-01)
5 0 0 0 OA 「酒呑童子枕言葉 鬼が城対面の段」二〇〇五年、奏演と研究
- 著者
- 内山 美樹子
- 雑誌
- 演劇研究センター紀要VII 早稲田大学21世紀COEプログラム 〈演劇の総合的研究と演劇学の確立〉
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.101-115, 2006-01-31