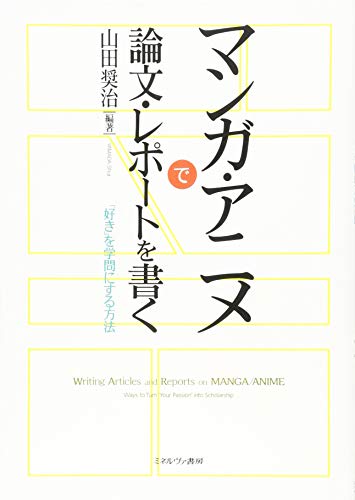2 0 0 0 OA <エッセイ : 小特集「元号を考える」>元号法再読
- 著者
- 瀧井 一博
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日文研 = Nichibunken
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.21-24, 2018-03-31
2 0 0 0 OA 不正融資と特別背任罪
- 著者
- 垣口克彦 かきぐちかつひこ
- 雑誌
- 阪南論集. 社会科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.117-131, 2009-03
2 0 0 0 OA 年功賃金制とモデル分析-世代間の所得移転機能を中心として-
- 著者
- 松本 直樹 Naoki Matsumoto 松山大学経済学部 Matsuyama UniversityFaculty of Economics
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.219-237, 2012-04-01
2 0 0 0 OA F. マイヤーと伝統的ホロコースト史学の崩壊 : マイヤー・ピペル論争から
- 著者
- 加藤 一郎
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 教育学部紀要 = Annual Report of The Faculty of Education (ISSN:03882144)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.95-107, 2004-12-01
En majo de 2002, F. Meyer, la eks-redaktoro de la germana revuo "Der\nSpiegel", publikis la artikolon "Die Zahl der Opfer von Auschwitz". En tiu c i artikolo li kritikis la vidpunktojn de la tradicia holocaŭsta historiografio pri la nombro de la viktimoj de la koncentrejo Auschwitz /Birkenau. Recenzinte la tiun ci artikolon, F. Piper, la direktoro de la historia departmento de la Auschwitz muzeo, kondamis lin kiel la revizioniston. Post ne longe, F. Meyer kontraukritikis la recenzion de F.Piper. En tiu ci diskuto, F. Meyer adoptis la revisionistajn metodojn kaj analizojn, dum F. Piper defendis la tradician holocaŭsta historiografion. Tiu ci diskuto klarigis la disfalon de la tradicia holocaŭsta historiografio.
- 出版者
- ミネルヴァ書房
はじめに / 山田 奨治目次序 章 マンガ・アニメで研究するということ / 山田 奨治第Ⅰ部 文化・社会からマンガ・アニメへ第1章 語り : マンガ・アニメの伝統的コンテンツからの継承性 / 谷川 建司 1 何を明らかにするのか 2 『魔法少女まどか☆マギカ』 3 『JIN─仁─』 4 日本人の好むナラティヴの完成形としての「忠臣蔵」 5 結 論コラム1 戦う文豪、闘う偉人 : 「異能バトル」作品からみる現在 / 飯倉 義之第2章 形態 : デジタル化時代のマンガと読者の生きられる時間 / 石田 佐恵子 1 時間の社会学から探求する「マンガと時間」 2 「連載」という作品発表形態の成立 : マンガ雑誌と市場構造 3 「物語の中の時間」と「読者の生きられる時間」との関係 4 デジタル化時代のマンガと読者の生きられる時間コラム2 マンガが社会と繋がるとき : 〈3・11マンガ〉から考える / イトウ ユウ第3章 教育 : 子どもだけの世界における子どもの自律性・生命性・道徳 / 宮崎 康子 1 子どもだけの世界 2 自律性の獲得と人間形成の物語としての『漂流教室』 3 『7SEEDS』における未来に蒔かれた種としての子どもたち 4 子どもの自律性・生命性・道徳コラム3 生命性の次元に触れる : 五十嵐大介『海獣の子供』 / 宮崎 康子第4章 政治 : 「伝記学習マンガ」を形作るもの / イトウ ユウ・山中 千恵 1 何を明らかにするのか 2 伝記学習マンガのタイトル選択傾向を分析する 3 伝記学習マンガの「表現」を分析する 4 「学習マンガ」と「伝記本」の親和性 5 結論 : 伝記学習マンガの〈政治性〉第5章 近代性 : 産科医・助産師の活躍する"医療マンガ" / 安井 眞奈美 1 少数派の立場から考える 2 産科医、助産師の活躍するマンガ 3 出産環境の近現代 4 医療マンガは何を物語っているのか 5 医療マンガの社会的意義コラム4 メディアに描かれる子どもイメージ / 宮崎 康子第Ⅱ部 マンガ・アニメから文化・社会へ第6章 舞台 : 日本のアニメ・マンガと観光・文化・社会 / 岡本 健 1 アニメ・マンガと観光の関係性 2 アニメ聖地巡礼とコンテンツツーリズム 3 アニメ・マンガ聖地における文化の伝達 4 コンテンツツーリズムに関わるコミュニケーション 5 観光コミュニケーションと文化創造第7章 メディアミックス : そういうのもあるのか / 横濱 雄二 1 メディアミックス 2 『孤独のグルメ』について 3 マンガ受容の広がり 4 井之頭五郎というキャラ 5 キャラと作品のメディアミックスコラム5 フランスにおけるmangaの受容 : 影響、占有、周縁? / 高馬 京子第8章 海外展開 : 『るろうに剣心』の映画化とフィリピンでの人気 / 北浦 寛之 1 映画のヒットと海外展開 2 『るろうに剣心』の映画化 3 フィリピンでの人気 4 他のアニメは「剣心」に続けるかコラム6 卒論テーマは「韓国でマンガが大人気」です! : それって、いつのどんなマンガの話? / 山中 千恵第9章 少女 : フランス女性読者のアイデンティティー形成とキャラクターの役割 / 高馬 京子 1 何を明らかにするのか 2 フランスにおけるshôjo受容の歴史的背景 3 フランスのメディア言説による追従すべき少女像の形成 4 フランス読者の言説により理想として形成されるshôjoの少女像 5 結論にかえてコラム7 英国新聞からみる日本の児童ポルノ問題 : マンガ・アニメの記述を中心に / 小泉 友則第10章 食 : ひとり飯にみる違和感と共感のゆくえ / 西村 大志 1 食べることの滑稽さ : 『かっこいいスキヤキ』 2 共感される自由なひとり飯 : 『孤独のグルメ』 3 共感から実用へ : 『花のズボラ飯』 4 滑稽さへの回帰とネット時代の食マンガのゆくえ : 『食の軍師』第11章 言語 : 日本語から見たマンガ・アニメ / 金水 敏 1 何を明らかにしようとするか 2 役割語とは何か 3 物語の構造とアーキタイプ 4 アーキタイプと役割語 5 ケーススタディ : 『風の谷のナウシカ』 6 研究法のまとめコラム8 「せんせい、ちょっと待っておれ!」 : マンガ・アニメに牽引された日本語学習 / 山本 冴里おわりにマンガ・アニメ作品名索引人名索引執筆者紹介奥付
2 0 0 0 OA 施設園芸環境での2.4GHz帯と429MHz帯無線通信特性の分析
- 著者
- 李 鵬昆 井林 宏文 峰野 博史
- 雑誌
- 第77回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.1, pp.233-234, 2015-03-17
無線センサネットワークの配線しやすさと作業者の負担が少ないため,施設園芸環境で使用されている.しかしながら,施設園芸のような複雑な環境では,環境条件が無線電波に大きく影響を与える.結果として,施設園芸環境での無線通信が不安定になり,RSSI低下やパケットロスの現象を発生する.そこで本研究では,施設園芸環境での無線通信品質を低下させる要因を解明するため,電波への影響要素を分類し,影響が大きな要素を分析した.電波暗室で検証実験を行った.また,施設園芸環境で主な影響要素が2.4GHz帯と429MHz帯へ与える影響の割合を検証した.その結果,2.4GHz帯と429MHz帯では無線通信に影響を与える要素の占める割合が異なることを示し,施設園芸環境に最適な無線周波数帯を確認した.
- 著者
- 道免 逸子 Itsuko Domen
- 出版者
- 甲南大学
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-31
本論文の目的は、ナラティブ・エクスポージャー・セラピー(Narrative Exposure Therapy、以下NET)の、日本の心理臨床現場における適用可能性を検証することである。 精神病院に長年通院・入退院を繰り返し、情緒不安定で自傷・自殺企図の傾向が高く、安定した治療に乗りにくい患者には、原病にPTSD(心的外傷後ストレス障害)が併存することが多い。子ども虐待やDV、いじめ等長期的反復的な被害から生じる複雑性PTSDは、PTSDの中核症状に情動調整の困難を伴い、原病の症状を増幅し治療を困難にしている。 NETは、曝露療法に証言療法を組み合わせたPTSD治療のための認知行動療法である。馴化による恐怖反応の消去と全人生史の構築による自伝的記憶整理は、特に複雑性PTSDに有効とされる。NETは、国際的ガイドラインで複雑性PTSDに対する有効な治療法として推奨されている。日本では2010年に試行的に導入され、次第に実施例が増加しているが、さらに系統的な導入を図るべき段階に至っている。本研究は、今後の普及の準備として、日本の臨床現場におけるNETの有効性を検証しようとするものである。 この目的を達成するために、道免氏は、まず第1章で、PTSDおよび複雑性PTSD、解離、自伝的記憶、複雑性悲嘆という、NETの治療メカニズムに関係する諸概念について、近年の診断基準の改訂状況も含めて概説する。そのうえで、開発者が提示するNETの技法とそこに含まれる治療的要素を記述する。第2章では、まず、NETがPTSDに対して推奨される治療技法として、ISTSSをはじめとする関係機関の近年のガイドラインで紹介されていることが示される。そして、現在までの先行臨床研究を網羅的に調査し、戦争や武力紛争という「組織的暴力」に由来するPTSDへの治療実践とその効果検証研究が行われてきた経過と、近年、通常の医療機関における市民生活由来のPTSD治療に対象を拡大していることを明らかにする。効果検証結果には、PTSDへの効果だけでなく、併存するうつ症状、BPD(境界性人格障害)症状、解離症状などの軽減が報告されていた。 第3章では、実施されたNETによる効果検証の結果が報告される。治療実践を行った臨床機関は、精神病院外来と大学心理相談室であり、対象者は複雑性PTSDと診断された14名(精神病院12、大学相談室2;女性13、男性1;平均38.1歳)である。複雑性PTSDの併存症状として、うつ病、双極性感情障害、BPD、アルコール依存症、摂食障害、複雑性悲嘆、解離性障害、適応障害、線維筋痛症があり、通院歴は0〜23年、入院歴は0〜33回であった。実施者はNET研修を受けた臨床心理士で、面接頻度は週1回〜2回、NET回数は8〜46回、平均27.4回であった。 効果評価のために用いた症状評価尺度は、PTSD症状にIES-RとCAPS、うつ症状にSDS、解離症状にDESを使用し、NET実施前、実施2週間後、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後に評価した。 症状評価尺度によって実施1年後に評価された治療効果は、以下の通りであった。IES-R のCohen’s d は2.972、CAPSのCohen’s d は2.587であり、PTSD症状が著しく軽減したことを示す結果であった。IES-R得点は、14例中6例において、過去の出来事から影響を受けていないと判定される水準までに低下した。他の例においても1年間を通じて漸減傾向にあった。CAPSは実施の負担から6例のみに実施された結果である。PTSDの3大症状以外の、罪悪感、注意減退、非現実感、離人感においても症状が軽減していた。うつ症状については、NET実施1年後の SDSのCohen’s d は0.953であり、明らかな軽減を示す結果であった。ただし、PTSD症状と異なり、6ヶ月後では軽減が少なく、効果が得られるまでに時間を要した。解離症状では、低得点に偏った偏りの大きな分布であるため、いくつかの指標によって結果が示された。BPD症状の著しい軽減は先行研究と一致するものであった。他の併存症状にも軽減が見られたが、アルコール依存への効果は明らかではなかった。 第4章において道免氏は、第3章で確認された症状評価尺度上の全般的効果を踏まえて、本研究から得られたNET実施上の知見を提示し、考察を加える。解離症状の軽減が大きかったことは先行研究と一致する。治療前に解離傾向が高かった例では、すべて治療過程で新たな記憶の想起があった。解離傾向が少なく侵入症状の強い例では、NETの進行に従って侵入症状が速やかに軽減し、症状が及ぼす苦痛が軽減することを実感するのに対し、解離傾向の高い例では、解離されていた記憶や感覚が繋がってくる第1段階から、喪失体験への直面から生きづらさを改めて感じる第2段階へ進んだ時点で、安全の確保と共感的・支持的環境とともに感情の重要性に関する心理教育が必要である。特に環境調整が重要と考えられた。それら留意点を有するものの、NETには、記憶整理の効果、人生を理解されることによる愛着外傷への治療効果、言語化能力の向上による対人関係改善などの効果が期待でき、解離症状を併存するPTSDの治療に有望な技法であると考えられた。 BPD患者の60%にはPTSDが併存すると言われるように、BPDの診断名を持つ患者のPTSDに対するNETの有効性を指摘する文献が増加している。本研究は、BPD治療を直接対象としたものではないが、14例中7例に、BPD周辺の症状があった。孤独感や不安定な対人関係を特徴とするそれらの例について、治療中の語りを整理すると、治療中および治療後のフォローアップの中で、交友関係を楽しめる、一人の時間を楽しめる、怒りがコントロールできるなどの症状軽減を示す内容が多く見られた。これらの知見および先行研究の知見を総合し、道免氏は、PTSDを構成する恐怖ネットワークと、過去の体験に由来する怒りのネットワークの相乗効果から症状を理解し、人生史の整理という目標を共有することで、対等な関係の中で治療に取り組む道を開くことができると考察する。 NETが対象とするPTSD症状を有する患者には、死別体験を有するものが含まれる。NET後に悲嘆を扱うグリーフワークを組み合わせる方法を有効とする先行研究も存在する。今回対象とした例の中にも、近親者との死別による重い悲嘆を伴う例があった。この例に対してグリーフワークに取り組むことによって、うつ症状が軽減されたことから、死別を伴う例に対しては、NETだけでなく、グリーフワークを治療計画に組み入れることが有効であると示唆された。 以上のような検討の後、道免氏は、第5章の総合考察によって全体を総合した上、NETには多くの治療的要素が複合的に組み込まれていると指摘しながら、NETで扱えない要素を以後の治療で扱うことの必要性、安全を確保することの重要性、普及のためのスーパーバイザーの育成の必要性を指摘する。最後に、事例数による限界、比較対照群を持たないことの限界、評価尺度の不足という本研究の限界を整理し、さらなる効果検証の必要性を述べて論文を締めくくっている。
2 0 0 0 OA 第38次南極地域観測隊ドームふじ観測拠点越冬報告1997-1998
- 著者
- 金戸 進 山内 恭 Susumu Kaneto Takashi Yamanouchi
- 雑誌
- 南極資料 = Antarctic Record (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.459-476, 1999-11
第38次南極地域観測隊ドームふじ観測拠点越冬隊9名は, 1997年1月25日から1998年1月24日までの1年間, ドームふじ観測拠点での3年目, 最終年の越冬観測を実施した。今次隊では, 気水圏系プロジェクト研究観測の「氷床変動システム研究観測」と「南極大気・物質循環観測」を主に実施した。前者では, 36次隊から続けられた氷床深層掘削が中心課題として計画されていたが, 前次隊末のドリルスタック以来, 液封液の補充を続けたがドリルを回収できず, 深層掘削の再開には至らなかった。しかし, 前年までに掘削された氷床コアの現場処理・解析を続け, 多くのコア試料を持ち帰った他, 雪氷観測, 浅層掘削, 内陸旅行観測を行った。後者では, 新たな観測として, ライダーによる極域成層圏雲の観測やGPSゾンデによる高層観測, 大気循環場の観測等を精力的に実施し, 初めて内陸での極成層圏雲の通年の盛衰を捉えたり大気循環場のブロッキング高気圧に伴う熱や水蒸気の流入を捉えるといった成果を上げることができた。これら観測を支える設営面では, 水作りのための雪取りや, 燃料ドラムの搬入, 低温下での車両の立ち上げに苦労した。燃料事情は厳しかったが, 昭和基地からの補給を行ったことで内陸調査旅行が可能となった。越冬最後に, 基地の閉鎖作業を行い, 基地を後にした。
2 0 0 0 OA 幼稚園教育研修ノート : 幼稚園と小学校の連携について
- 著者
- 小林 美智
- 出版者
- 新潟県立教育センター
- 雑誌
- 研究報告 / 新潟県立教育センター
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.1-30, 1989-03-31
2 0 0 0 OA 家族間の葛藤とその社会的背景 : 7つの事例から
- 著者
- 大宮 録郎 Rokuro Omiya
- 雑誌
- 東海女子大学紀要 = Bulletin of Tokai Women's University (ISSN:02870525)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.121-141, 1989-01-01
2 0 0 0 OA 家庭での子どもの生活(実態調査)
- 著者
- 長屋 美穂子
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Human Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.58-69, 1984-12-01
The purpose of this study is to research the condition of children's living at home.The report is based on the questionnaire to the children's parents of an elementary school in Saitama prefecture.The contents are as follows, 1. Diet life2. Time budget 3. TV Watching4. Private school5. Play6. Pocket money7. Habit of life 8. Health conditionIn this study it is found that it is necessary to improve living of children's parents so as to bring up children sound.
2 0 0 0 OA 乳児期の母性的態度と母親行動に影響する要因について
- 著者
- 大薮 泰
- 出版者
- 長野大学
- 雑誌
- 長野大学紀要 = ACADEMIC BULLETIN OF NACANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.45-50, 1990-03-31
2 0 0 0 OA 幼稚園・保育所選択要因の検討
- 著者
- 上野 礼子 Reiko Ueno 生活科
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.169-176, 1989-03-31
2 0 0 0 OA 生涯学習と学校教育
- 著者
- 菊池 幸子
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Human Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.91-97, 1986-12-01
Lifelong education have payed interesting attention since Paul Lengrand had reported to Commitee of adult education in UNESCO in 1965.As the national educational policy, there have been twice reported on lifelong education by the Central Educational Council in Japan, too.The third report on lifelong integrated learning have been proposed by the National Council on Educational Reform April 23 in 1986.This report says that basic direction of educational system for the 21centry is to reform to lifelong learning system to solve many educational problems. It is the reason of written this report and its main contents are as follows;1. Lifelong education as the national educational policy in Japan.2. Move to lifelong integrated learning society to solve many educational problems.3. The adquate curriculum on each life stage.4. Cooperation with home, school and Community.
2 0 0 0 OA 上田市における1歳6ヵ月児健康診査の概要
- 著者
- 大薮 泰 細渕 富夫
- 出版者
- 長野大学
- 雑誌
- 長野大学紀要 = ACADEMIC BULLETIN OF NACANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.55-64, 1989-05-01
2 0 0 0 OA シリコンバレーのベンチャーエコシステムの発展:「システム」としての体系的理解を目指して
- 著者
- 岸本 千佳司 Chikashi Kishimoto
- 雑誌
- AGI Working Paper Series
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-03, pp.1-52, 2018-05
本稿は、米国シリコンバレーのベンチャー企業やビジネスモデルおよびそれを支える各種アクターを、相互に関連し支え合う「エコシステム」として理解し、その体系的解説の提示を課題とする。そこで、ベンチャーエコシステムを「起業家とベンチャー企業」と「支援アクター」という大きく二つのセグメントの間の循環で構成されるものと想定する。「支援アクター」は、「大学と研究機関」「経営支援専門家(法律家、会計士、アクセラレータ等)」、「資金提供者(ベンチャーキャピタル等)」、「大企業」で構成されると考える。彼らは「起業家とベンチャー企業」に対し、各々の立場から各種支援やリソースの提供を行う。逆に、ベンチャー企業が成功した際は、それを支えてきたアクターに、色々な形での見返りを与える(キャピタルゲインの獲得、事業・技術の補完、人材獲得等)。この循環が回り続けることでエコシステム全体が存続していくのである。 本稿では、両セグメント、およびその中の各アクターの動向を、従来の状況に加え、近年(概ね2000年代以降)の新たな展開について可能な限り解説した。その内容を簡単に紹介すると以下のようになる。先ず、「起業家とベンチャー企業」セグメントについては、活発な起業文化と濃密な技術コミュニティの存在が、起業家の輩出、および起業家・経験者の蓄積を支えてきた。加えて、近年では、起業サポートインフラの整備が進み、かつシリコンバレー流のビジネス手法が確立した結果、起業が一層容易となり、特に若者の間で起業の「ポップカルチャー」化が進んだ。合わせて、ユニコーン企業が輩出している。「支援アクター」の「大学と研究機関」では、スタンフォード大学等からの豊富な人材と技術シーズの供給、産業界との連携に加え、近年は、起業家育成プログラムの充実がみられ、学生や教授らによる起業が強く奨励されている。 「経営支援専門家」については、従来からある、ベンチャー経営に精通した経営実務専門家(法律家、会計士等)からのサービスに加え、近年は、コワーキングスペースやアクセラレータのような起業家支援施設・育成プログラムが登場し、事業成長の加速と起業家コミュニティ形成の促進がなされている。「資金提供者」の分野では、従来、当地の半導体・エレクトロニクス産業の技術的・起業家的発展とシンクロする形でベンチャーキャピタル(VC)業界が発展してきた。近年は、新世代Web起業家登場に合わせるように、VC業界の再編(従来型VCの停滞と「スーパー・エンジェル」の発展)がみられた。同時にクラウドファンディングが生み出され、資金調達ルートが一層多様化した。「大企業」の存在もエコシステムにとって不可欠である。かつては、スピンオフ等を通じた起業家・経営人材の供給が主な役割であったが、近年は逆にM&Aによりベンチャー企業を活発に取り込んでいる(出口戦略としてのM&Aの重要性上昇)。また、コーポレート・ベンチャーキャピタルもブームとなり、M&Aやオープンイノベーションを支えている。 以上のように、エコシステムの各分野で新陳代謝や新たな仕組みが生み出され、層が厚くなり、全体として支援/リソース/見返りの流れが血液のごとく循環して、システムの生命を維持しているのである。
- 著者
- 赤木 玲子 赤木 正明
- 出版者
- 岡山県立短期大学
- 雑誌
- 岡山県立短期大学研究紀要 = BULLETIN OF OKAYAMA PREFECTURAL JUNIOR COLLEGE (ISSN:02871130)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.55-59, 1991-12-25
2 0 0 0 OA 破損症例2例から見たγ‐ネイル型髄内釘の適応に関する生体力学的検討
- 著者
- 小林 正典
- 出版者
- 大同大学研究・産学連携支援室
- 雑誌
- 大同大学紀要 = Bulletin of Daido University (ISSN:21852375)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.109-114, 2015-03
2 0 0 0 OA 道内の獅子舞活動 : 富山県・香川県から伝承された獅子舞
- 著者
- 浅見 吏郎 アサミ シロウ Shiro Asami
- 雑誌
- 札幌大学総合論叢
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.133-146, 2013-03
- 著者
- 米地 文夫 今泉 芳邦
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.131-144, 1994-10-01