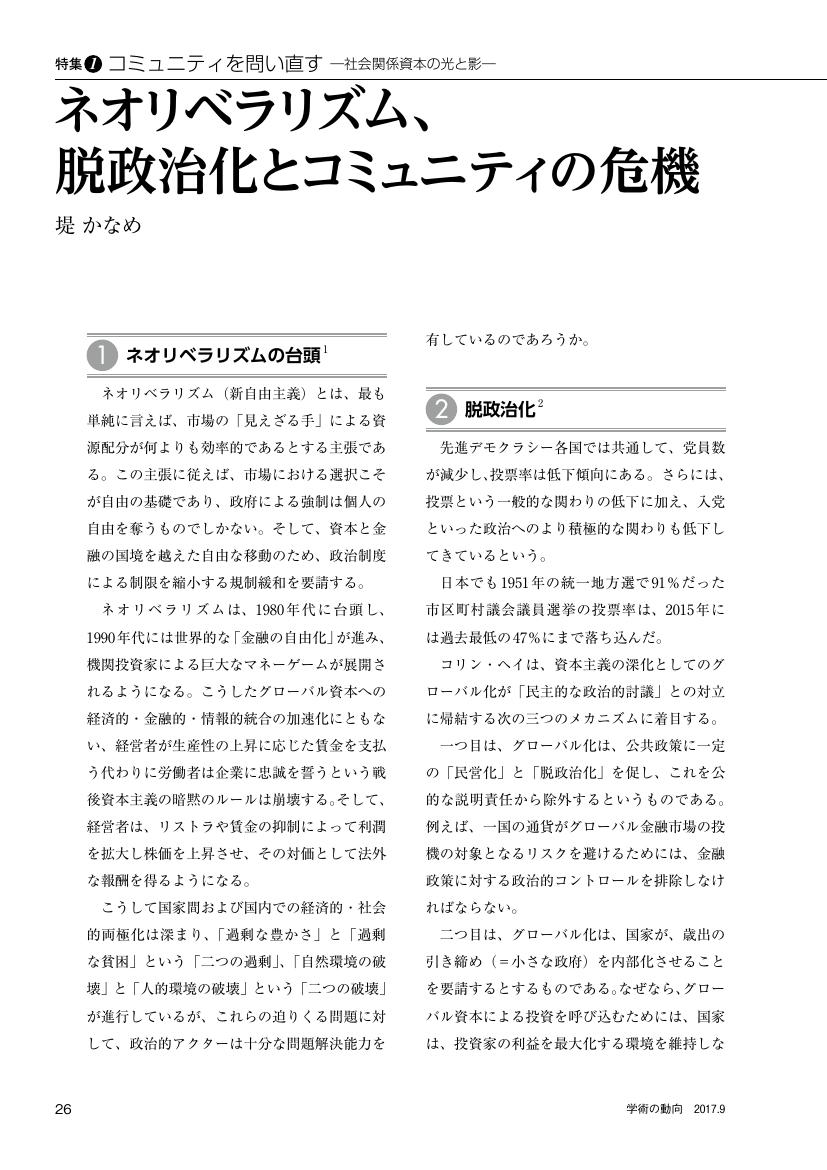2 0 0 0 「隠す」心理を科学する
2 0 0 0 関西近世考古学研究
- 著者
- 関西近世考古学研究会編
- 出版者
- 関西近世考古学研究会
- 巻号頁・発行日
- 1991
- 著者
- .*田中 恒彦 金城 志歩
- 雑誌
- 日本心理学会第86回大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-07-29
2 0 0 0 調音の動きと単語の好ましさ
- 著者
- .*大竹 裕香 山本 健太郎 布目 孝子 山田 祐樹
- 雑誌
- 日本心理学会第86回大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-07-29
2 0 0 0 自己嫌悪感における完全主義と社会的比較の効果の検討
- 著者
- .*郭 ブン 山田 祐樹
- 雑誌
- 日本心理学会第86回大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-07-29
2 0 0 0 OA 視覚の解放にむけて
- 著者
- 清川 清
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.7-11, 2019-09-30 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 森 貴史
- 出版者
- 早稲田ドイツ語学・文学会編集委員会
- 雑誌
- Waseda Blätter (ISSN:13403710)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.54-69, 2000-03-25
2 0 0 0 OA 新しい技術を用いた倫理的責任のガイドライン設定の課題 -Winny事件を通して
- 著者
- 瀬口 昌久
- 出版者
- 名古屋工業大学技術倫理研究会
- 雑誌
- 技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-21, 2009-12-31
ファイル共有ソフトWinnyを自己のホームページ上で公開し、それをダウンロードした者が犯した著作権法違反を幇助した罪に問われて開発者が起訴された事件は、一審の京都地裁では有罪、二審の大阪高裁では逆転無罪となり、司法判断に大きな違いが生じ、検察の逮捕や司法判断の妥当性をめぐって社会的関心を広く集めて盛んに論じられている。Winnyの事件には、ソフトウェアの技術開発者に著作権法(公衆送信権)違反の幇助罪を適用したことが、司法判断として妥当かという法的解釈にとどまらず、インターネットの発展した世界でのデジタルコンテンツの著作権のあり方や、技術開発者が負うべき責任の範囲や判断について重要な問題が含まれている。本論では、一審と二審判決について検討し、アメリカのMITの学生は通信詐欺で起訴されたラマッキア事件と対比し、新しい技術開発における技術者が負う倫理的責任のガイドライン設定の問題を考察する。
2 0 0 0 岩波講座応用数学
- 著者
- 甘利俊一 [ほか] 編集
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1993
2 0 0 0 横隔神経の遠心性発射活動が筋弛緩薬ブロック離脱に及ぼす影響
筋弛緩薬ブロックからの離脱には弛緩薬濃度、アセチルコリン濃度が関与する。このアセチルコリンの濃度を高める為に、神経にテタヌス刺激を与え神経の末端からのアセチルコリンの放出を促す方法がある。全身の神経に刺激を与えるのは不可能に近いが呼吸筋のみ限定するなら、respiratory driveという、生体には持って生まれた現象がある。高炭酸ガス血症群(炭酸ガス分圧45〜55mmHg)では100HZ前後のテタヌス刺激が中枢より横隔神経に伝達されているのが観察された。この研究はこの点に光を当ててみた。高炭酸ガス血症では換気を引き起こす為に、中枢からの横隔神経などを介して遠心性の発射活動がある。これは正にテタヌス刺激であり、アセチルコリンの放出が起こる。今までに、この現象と非脱分極性筋弛緩薬ブロック拮抗現象とを結び付けた研究は見あたらないが、理論的には生体が有するアセチルコリン放出促進現象であり、非脱分極性筋弛緩薬ブロックからの離脱に関して大きな役目を果たしている可能性が高い。我々の研究では左右の横隔膜から、別々にtwitch responcesを取ることに成功し、respiratory driveがブロック離脱に関与していることが実証された。従来ブロック離脱には抗コリンエステラーゼの作用に依存していたが、生体に有する中枢からのrespiratory driveもまたブロック離脱におおいに関与していること証明され、臨床的にもこの研究は有用の情報を与えてくれた研究である。
2 0 0 0 OA ネオリベラリズム, 脱政治化とコミュニティの危機
- 著者
- 堤 かなめ
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.9, pp.9_26-9_30, 2017-09-01 (Released:2018-01-25)
2 0 0 0 OA 保育所適合型見守り支援を可能にする疫学と現場観察双方からの事故状況分析
- 著者
- 田島 怜奈 尾崎 正明 内山 瑛美子 西田 佳史 山中 龍宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.554-557, 2022 (Released:2022-07-20)
- 参考文献数
- 13
Many serious injuries occur in preschools. Effective injury prevention requires measures customized to the individual preschool. This paper proposed a field-adaptive injury prevention support system that combines both epidemiological analysis of big data of accidents occurred at Japanese preschools and video analysis on accidents/incidents occurred at a specific preschool. While the big data analysis revealed serious injury patterns common in preschools, the video analysis allowed us to extract behavioral patterns in real situations arising at the target preschool. Analysis from both sides enabled the grasping of the behaviors and environments that could lead to serious accidents at the target preschool.
2 0 0 0 IR 目的節「ために」、「ように」の意味分析--主体と意思のありかたをめぐって
- 著者
- 田中 寛
- 出版者
- 大東文化大学別科日本語研修課程
- 雑誌
- 別科論集
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.31-66, 2002-03
目的節「ために」、「ように」はこれまで、意志動詞の介在を主要な論点として、その使い分け、特徴が論じられてきたが、そのほかにも「意味の整合性」においても特徴が見出される。本稿では従来あまり議論されなかった「ためには」「ためにも」などの用法も視野におきながら、目的節と主節の意味的な交渉について考察するものである。その結果、「ために」と「ように」の重なる用法や、「ためには」・「ためにも」のように、「は」、「も」を付加することによって、条件的な意味が含意され、"中和化"が進んで「ように」節との重なりが見られることを確認した。また、「ように」節は「ようにする」、「ようになる」と連鎖関係にあり、結果を見越した目的を設定してそれに近づく努力をあらわすのに対し、「ために」には初期の目的そのものを設定する意図が内包されていることを検証した。また、複合形「-ようにするために」などの用法についてもふれた。
2 0 0 0 OA 家政学部の成立過程に基づく一考察 —日本女子大学を事例校として—
- 著者
- 新井 恵子
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース
- 雑誌
- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.183-198, 2018 (Released:2022-04-28)
- 参考文献数
- 25
This paper examines the functioning of the home economics department, which was established as a faculty in a new university after the war. Based on the process of the establishment of the Faculty of Home Economics, the focus was on the position of “Home Economics Principles,” established on the philosophy of home economics. In addition, focusing on the transition of the department, the degree of faculty, the title of the doctoral thesis, which are the elements that constitute the home economics department, were analyzed based on the data derived from school. The focus of the analysis is to clarify that a structural problem exists “at the postwar home economics department, wherein the core is weak and the surroundings are strong.” As a result of the examination, it was found that the objective of the study was derived from the conventional home economics field and had deepened thereof.
2 0 0 0 IR 農業集落の比較研究--農業集落カ-ドの計量的研究-2-
北海道・青森県・福島県・香川県・愛媛県・佐賀県・長崎県・熊本県の1990年の農業集落の特性を計量的に明らかにすることが主目的である。すでに、1990年の全国標本(3%の無作為抽出標本4049集落)、近畿2府4県(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)、東北4県(岩手県、宮城県、秋田県、山形県)と新潟県の農業集落カードの分析を済ませているので、これらと今回の分析結果をくらべることで、北海道および上記諸県の農業集落の特性をより明らかにできると考えられる。
- 著者
- 児島 俊弘
- 出版者
- THE ASSOCIATION OF RURAL PLANNING
- 雑誌
- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.33-39,59, 1984
私がいま手がけている 「 パーソナルコンピュータによる農業集落カード利用システム 」 について 『 農村計画学会誌 』 に書けという御注文である。<BR>和田さんからは 「 学問的なとりあつかいをした論文に 」 というコメントがついていた。しかし, この仕事はもともと学問のベースで出発したものではなく, 今わたくしが仕事をしている農林統計協会の事業 ( 59年度農林水産省統計情報部の委託開発研究事業 ) の一つとして手がけているものであるから, なかなか学問的というわけにはいかない。どうするか考えているうちに大変に遅くなってしまった。ここに報文の形で御注文に応えたい。<BR>私も永年研究所で仕事をしていた習慣から, 事業にのせるだけではつまらない, という意識も働いている。この仕事を利用して私自身の問題として別な側面から考えを組み立ててみたいという気がないでもない。考えようによっては, この極めて具体的な問題を論理的な側面からとりあげるのも面白いのではないかと思われる。<BR>この問題を学問的にとりあげるとすれば, その依拠すべきパラダイムをどこに求めるべきであろうか。経済学あいは農業経済学というアプローチも可能であるが, それほど面白いものにはならないであろう。やはり, これは情報処理過程の問題なのでその側面からアプローチをする方が面白いであろう。それに, この接近法には, 未だにパラダイムとよべるものがないから, 既存の体系にわずらわされず自由に考えることができる。<BR>そこで, ここでは地域農業計画の策定を一つの情報処理過程としてとらえてみたい。このような情報処理過程の中で 「 農業集落カード 」 ( 1980年農林業センサス ) の利用システムをどのように位置づけて組み立てるか, という問題である。