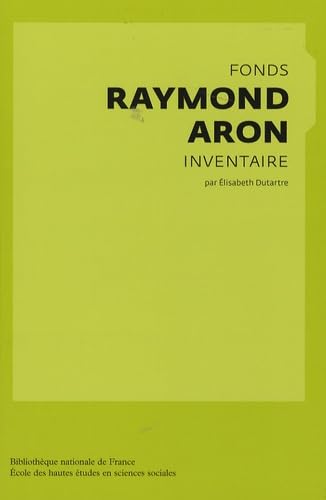2 0 0 0 共依存とアディクション:心理・家族・社会
- 著者
- 樫田 美雄
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.60-60, 2001
「共依存」は, 標準的には, 嗜癖者を可能にする, 正のフィードバック・システム (あるいはそのうちの1人の当事者) につけられた名前である。それは, 人間関係的には, 「嗜癖者-イネーブラー (嗜癖を可能にする者) 」両者間の「刺激-反応」連鎖の増幅システムであり, 子どもを「アダルト・チルドレン」にすることで, 世代間連鎖をなす永続的体系である。文化的には, 男性的な「自立・自律強制社会」において, 女性的な「依存・ケア的サブカルチャー」が, 非難される様式であり, 臨床的には, 「嗜癖者の配偶者 (しばしば女性) 」が, 「医療」的に「啓蒙・改善」の対象とされる際に, その「操作」の根拠となる「病名」である。わが国ではアメリカほど「大衆心理学化」された形では広がっていないが, すべての依存症 (薬物依存, 仕事依存, 愛情依存……) の基礎にこの「共依存」があると考えるなら, 裾野の広がりは巨大であるといえよう。<BR>本書はこのような多面性をもった「共依存」概念に関して, 臨床心理学・公衆衛生学・構築主義社会学・家族システム論等の各視点からの論考を集め, まとめたものである。実例と学史がバランスよく配置されているので, 「共依存」に関して, 現象としてのそれに関心をもつ社会学者にも, 諸議論の配置に関心のある家族心理学者にも有益な本になっている。また, アメリカの状況を集中的に紹介した章 (5章以下, とくに7章) と, 日本での実践を紹介した章 (3・4章) の両方があるため, 家族の日米比較に関心がある研究者にも読まれるべき本にもなっている。<BR>以下, 各論者の主張の簡単な紹介と評者からのコメントを行おう。<BR>まず, 序章から2章にかけては編者の清水新二が, 総括的な議論の整理をしている。「共依存」に関する近年の議論史は, 個人からシステムに関心の焦点が移動していったという点からは, 「精神分裂病」や「アルコール依存症者」に関する議論を基本的には後追いしていること, ギデンズが行ったような社会評論的な共依存論と個人を焦点とした臨床的共依存論は区別すべきこと, 治療が必要な共依存とそうでない共依存を仕分けるために, 共依存の文化社会的適合度などに基づいた「共依存スペクトラムモデル」に基づいた思考をすべきこと, などを主張している。判断の論拠はもっと知りたいが, 結論には実感的妥当さがあり, 理論と実践の架橋はこのような臨床的知によってなされるのだろうと思われた。3章と4章は, 臨床家の遠藤優子と猪野亜朗が, (「共依存物語」内的視点から) 共依存の実像と臨床的対処の実際を述べている。事例が興味深くかつ身にしみる。5章と6章は, 構築主義社会学の立場から, 上野加代子が「共依存」概念の語られ方を解析している。3・4章の議論がなぜ説得力をもつのか, の謎解きになっている。7章と8章は, V.クラークと本田恵子が, アメリカにおける文化的少数者に定位した対策の紹介と, 文献レビューを行っている。これからは, 日本の社会学者もこういうシステマティックな仕事の仕方に慣れていくべきだろう。「共依存」議論の多様さに接近するために有益な書として, 本書を広く推薦したい。
2 0 0 0 広背筋部痛を訴える野球肩の発生原因に対する一考察
- 著者
- 鵜飼 建志 山崎 雅美 笠井 勉 林 典雄 細居 雅敏 赤羽根 良和 中宿 伸哉 田中 幸彦 宿南 高則 近藤 照美 増田 一太
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.C0974, 2004
【はじめに】<BR> 野球肩の多くは、impingement syndromeやrotator interval損傷などの報告が多く、当院ではquadrilateral spaceでの腋窩神経由来と思われる肩後方部痛が多く認められる。これらは第2肩関節や臼蓋上腕関節での障害であり、肩甲胸郭関節での障害はあまり見られない。<BR> 今回、肩甲胸郭関節での障害と思われる広背筋部痛を訴えた野球肩を少数ではあるが経験した。その発生原因について、考察を加え報告する。<BR>【対象】<BR> 平成14年2月から15年10月までに、当院で野球肩と診断された60例のうち、広背筋部に疼痛を訴えた6例(10%)である。<BR>【理学的所見】<BR> 疼痛誘発投球相は信原分類のacceleration phase(以下A期)に全例認められた。圧痛部位は肩甲骨下角部周辺の内側~外側にかけてに位置する広背筋最上方線維部であった。また疼痛の出現の仕方は、脱力を伴うような鋭い痛みであった。3rd内旋可動域低下は全例に認められた。MMT3以下の僧帽筋筋力低下は中部線維が3例、下部線維が全例であった。投球フォームの特徴として肘下がりは2例と特に多いとは言えず、A期で肘が先行するタイプが4例と多かった。<BR>【考察】<BR> 信原は、「広背筋に攣縮が起きると肩甲骨の外転や肩関節外転・外旋が制限され、肘下がりなど投球動作に支障を来すもの」を広背筋症候群とし、rotator interval損傷やimpingementなどの二次的障害を惹起する可能性を指摘しているが広背筋部痛に対する詳細な説明はない。<BR> 広背筋の最上方線維は、肩甲骨下角部をpulleyのようにして外上方への急な走行変化を生じている。今回、広背筋部痛を訴えた選手は全例A期に疼痛が見られた。A期で肩甲骨が上方回旋する際に肩甲骨下角部で広背筋上方線維をfrictionし、筋挫傷を生じさせることが疼痛の原因と考えられた。今回の症例のほとんどが3rd内旋可動域の低下及び僧帽筋の筋力低下を認められたことから、A期において3rd内旋可動域低下が早期に過剰な上方回旋を、僧帽筋の筋力低下が肩甲骨上方回旋に伴う過剰なprotractionを引き起こしたものと思われる。そのため下角部の外上方移動が通常より大きくなり広背筋上方線維へのより大きなfrictionにつながったものと考えられた。<BR> 肩甲骨下角部周辺は広背筋以外にも大菱形筋、大円筋、前鋸筋などが存在し、疼痛は短時間で鋭く発生するため部位の特定がしづらく、当初は治療に難渋した。現在は、広背筋のリラクゼーション、僧帽筋の筋機能改善、肩下方軟部組織の伸張性獲得などを目的に治療を行い、良好に改善が認められている。
2 0 0 0 OA 大正期の社会科学と科学主義をめぐる思想史的研究
2 0 0 0 OA PUMPKIN (模擬原爆)の投下を当時の日本の報道機関はどう報じたか(二)
- 著者
- 菊池 良輝
- 出版者
- アジア文化研究所
- 雑誌
- アジア文化研究所研究年報 = Annual Journal of The Asian Cultures Research Institute (ISSN:18801714)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.15(206)-27(194), 2009
2 0 0 0 Fonds Raymond Aron : inventaire
2 0 0 0 IR 「行政庁」概念の位相
- 著者
- 小林 博志
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学会誌 (ISSN:05111951)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.p129-159, 1980
2 0 0 0 IR 行政組織法・行政作用法上の基礎カテゴリ-と「行政庁」概念
- 著者
- 小林 博志
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学会誌 (ISSN:05111951)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.p57-86, 1985
- 著者
- 川本 玲子
- 出版者
- 一橋大学大学院言語社会研究科
- 雑誌
- 言語社会
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.128-146, 2009-03
2 0 0 0 IR 物語のメタファーからみた心理療法
- 著者
- 高森 淳一
- 出版者
- 天理大学学術研究委員会
- 雑誌
- 天理大学学報 (ISSN:03874311)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.21-57, 2002
物語というメタファーから心理療法の諸相を顧みることが本稿の課題である。自己は物語的に展開する時間性と等価なものであり,心理療法の場で扱われる心理的問題も物語として理解されうることを示した。そして臨床場面でクライエントが治療者を聴き手として,自分自身を語ることが,いかに自己の主体性・能動性を恢復するよう寄与するかを論じた。一方,語りが孕む自己隠蔽性や自我防衛的側面を指摘し,語りのメタファーでは取りこぼされる,語り以前の体験や自己傾聴について合わせて論考した。また治療理論や文化・社会的文脈といった治療に作用する「物語」に関しても考察を加えた。
- 著者
- 松崎 憲三
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.141-168, 1988-03-30
Traditionally, folklorists have had a marked tendency to choose depopulated areas as their favorite field, because it was these remote places that seemed most likely to maintain folkways permitting them an efficient investigation. They never tried, however, to study seriously the problem of depopulation itself. In natural consequence, it has been rare for them to try methodological examinations, such as those aimed at discovering how to interpret depopulation and change in folkways.In accordance with these reflections, we tried to analyze the colony of Amagase in Nishihara Section, Kami-Kitayama Village, Yoshino District, Nara Prefecture. Three viewpoints, that are 1) the ecological viewpoint 2) the social viewpoint and 3) the religious view and consciousness structure, were defined as analysis indicators to be used in comprehension of the transformation of folkways.Nishihara is composed of five colonies of Amagase, Hiura, Izumi, Hosohara, Obara. The first two colonies are called ‟Amagase-gumi” (Amagase group), and the last three are called ‟Mikumi” (three groups). The Amagase and Mikumi groups were separated from each other by four kilometers, but the abolition, during the Meiji era, of the highway passing through the Amagase area left it abandoned far behind the main highway and urged some of inhabitants to move into the Mikumi area. The reparation works of the National 169 around 1970 made for a decisive urge to leave the Amagase area completely abandoned. Facilities for shopping and traffic communication as well as the human inclination for togetherness must have concentrated inhabitants' dwellings along the roads of Mikumi.However, even after they dispersed among the inhabitants of Mikumi, members of the Amagase group maintain their original unity performing their group duties in festivals or mutualaid association events and showing a greater attachment to the Kumi (group) than to the Daiji (section).In any case, it may be said that the Amagase group, in a way, overcame the danger of depopulation by moving to the Mikumi area and reorganizing their colonies. What made it possible was the their ownership of common forests and worship of a god as symbol of their unity. However, both the Amagase and Mikumi group show great attachment to the Kumi, and it is not so that the life of Nishihara area as a whole is reorganized. Depoputation of the Nishihara area as a whole is, as slow as it is, in progress. The area on the whole will face the need of some action in near future.
2 0 0 0 OA 北槎聞畧
- 巻号頁・発行日
- vol.壱,
2 0 0 0 OA 短書用文 : 絵本 頭書類語摘要
2 0 0 0 IR 東京「遷都」の政治過程
- 著者
- SASAKI S
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 人文學報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.41-64, 1990
2 0 0 0 レチノイドの表皮ランゲルハンス細胞に及ぼす影響について
- 著者
- 小林 勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.7, pp.763, 1983 (Released:2014-08-20)
レチノイド(etretinate)を CH3/He マウスに連日経口投与し,表皮ラングルハンス細胞(L細胞),ことにその分布密度と形態に及ぼす影響について検討した.L 細胞の分布密度は投与量(4mg/kg および 16mg/kg)と部位(耳,足脈,尾)により若干の差はあるが,ほぼ同様の傾向を示して変動した.すなわち,投与開始直後にL細胞は一過性に増加するが,以後は減少傾向を示し,2週後には最低値となる.しかし,その後投与を続けることにより回復傾向がみられた.このL細胞の分布密度の変動は表皮の厚さがレチノイド投与により変動する経過ときわめてよく一致た.一方,レチノイド投与により胞体が縮少し,樹枝状突起が細長く伸びた L 細胞が多数観察された.足蹠皮膚の垂直切片における観察では,投与2週日以後,基底層から真皮上層にla抗原陽性の樹枝状細胞がみられ,L細胞かあたかも真皮へ脱落しかけているような所見が得られた. 以上の実験を通じて,L 細胞は表皮内において抗原提示細胞としての機能を果すべく,角化細胞と密接な関連を保ちながら,その分布密度を調節し,恒常性を保ちつつあることか考えられた.
2 0 0 0 OA 実務としての条約締結手続
- 著者
- 松田 誠
- 出版者
- 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局
- 雑誌
- 新世代法政策学研究 (ISSN:1883342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.301-330, 2011-02
2 0 0 0 OA 草木鳥獣之圖
- 著者
- 後藤光生 [編]
- 出版者
- [後藤光生] [写]
- 巻号頁・発行日
- 1700
書名からは平凡なスケッチ集かと思われるが、じつは宋の王継先ほか撰の『[紹興校定]経史証類備急本草』(1159年成、略称『紹興本草』)の図の転写である。『紹興本草』は中国では早くに失われたが、日本には本資料のほか、当館の別10-56本、特1-477本、特1-518本、特1-601本など、かなりの数の写本が残る。本資料は植物図(257点)、ついで動物図(97点)の順に配列され、その全点が『紹興本草』からの転写である。植物図は抄写であるが、動物図は全図を転写している。著者の後藤梨春(名は光生[こうせい]、1697-1771)は江戸の町医で、晩年は幕医の多紀氏が創設した躋寿館(せいじゅかん:のち幕府医学館)で都講(教頭)を勤め、本草を講じた。本資料はその躋寿館への寄贈本であることが、末尾の書き込み「躋寿館都講 後藤光生寄附」からわかる。梨春の本草関係著作には、『随観写真』(123-29)や、『本草綱目補物品目録 前編』(104-306)、同後編(特1-946)、『採薬使記』(梨春編、特1-464、特7-128)などがある。(磯野直秀)
- 著者
- 江 衛 山下 清海
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.106, 2003
最近における華人社会をグローバルスケールでみた場合、その大きな特色の一つは、華人の「新移民」および「再移民」の増加である。華人社会研究においては、中国の改革・開放政策の進行以後の中国大陸出身の新しい移民や1997年の香港の中国返還を前にした移民ブームで海外に移住した香港人、さらには最近の台湾人移民などを「新移民」と呼んでいる。また、いったん東南アジアや南アメリカなどへ移住した華人(ベトナム系華人など)が、さらに他の地域へ移住して行く現象を「再移民」と呼んでいる。 従来の伝統的な華人社会は、新移民や再移民の増加によって、大きな変容を迫られている。アメリカやカナダでは、従来のチャイナタウン(オールドチャイナタウン)の中に新移民や再移民が流入する一方で、彼らによる新しいチャイナタウン(ニューチャイナタウン)も形成されている(山下,2000)。 今日および今後の華人社会を考察する上で、これら新移民と再移民の動向に注目する必要がある。在日華人社会に関する従来の研究においては、横浜・神戸・長崎の日本三大中華街や伝統的華人社会を対象にした研究が多く、最近における華人新移民に焦点を当てた研究は乏しい。 外国人登録者数に基づく『在留外国人統計』の中国人(中国籍保有者)の人口をみると、1982年末の中国人は59,122人であったが、20年後の2002年末現在の中国人は424,282人に膨らんでいる。本研究では、日本において増加する華人新移民の動態を明らかにするために、埼玉県川口市芝園団地における中国人ニューカマーズの集住化のプロセスとそこにおける彼らの生活実態を明らかにすることを目的とする。 なお、本研究が対象とする華人新移民のほとんどが中国大陸出身のニューカマーズであることから、本研究では、中国大陸出身(香港・台湾出身者を除く)の華人新移民という意味で中国人ニューカマーズという語を用いることにする。 一般に華人社会の研究においては、関連の統計の不足に加えて、華人の警戒心の強さなどから聞き取り調査やアンケート調査の実施は容易ではない。本研究では、共同研究者の一人が中国出身者すなわち「同胞」である点を生かして、研究対象者との信頼関係を徐々に築きながら、出身地・学歴・職業・来日時期などについて聞き取りおよびアンケート調査を実施し、芝園団地への集住化のプロセスについて考察し、芝園団地在住の中国人ニューカマーズの生活の実態について明らかにした。